身勝手な女性2
2012年09月25日
身勝手な女性2

もう一つ、知恵袋にこんな質問もあった。
「婿入りした弟の嫁(医者)が、我が家(弟の実家)へ来ると、お客さん気分で食べっぱなし、座りっぱなしで何もしようとしない。わたしは、他家へ嫁いでいる身だが、70歳になる実家の母親が食事の支度からなにから全部引き受けなければならないので、可哀そうでならない。
嫁にも手伝わせようとしたのだが、母親は嫁に遠慮してか、わたしに手伝うように言う。弟は婿養子とはいえ、長男である。長男の嫁なら、小姑であるわたしや、姑よりも先に台所へ立つのが当たり前だ。
嫁は医師なので年収もかなりあるが、それがお客さんでいていいという理由にはならないはずだ。
いつかガツンと言ってやろうと思うのだが、皆さんの意見を聞かせてもらいたい」
こういうお客さん気分の嫁も多いという。
「嫁は、誰よりも率先して働けというような時代ではない」
との回答も多かったが、反対の意見ももちろんあった。
でも、ベスト回答は、
「お嫁さんにガツンと言うよりも、あなたが嫌なら手伝わなければいいことで、お母さんもあなたが手伝わないことで、一人でどうしようもなくなれば、必然的にお嫁さんに頼まざるを得なくなるんじゃないですか?」
と、いうものであった。
それにしても、この質問者の家族は、本当に気の優しい人たちの集まりなんだと思う。
この医師の嫁も、本気であげ前据え膳が当然だと思っているのなら、やはり一言忠告しておくべきであろう。
「仕事が何だろうが、嫁は嫁。落ちた釣鐘みたいに座り込んでいるんじゃない!」
それが元で、没交渉になって、両親に孫の顔が見せられなくなるのは悲しいと思うのなら、我慢すればいいだろうが、どうせ孫とはいっても出孫である。
大人になれば、年に一度も来るかどうか・・・。
無駄なフラストレーションを溜めるくらいなら、ドカンとカミナリの一つも落としてみるのも良いのではないだろうか。
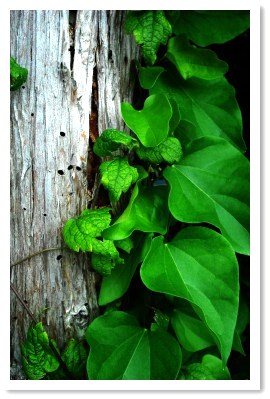
<今日のおまけ>
いじめ問題に取り組む教師の間違ったやり方に、「いじめられた子供と、いじめた子供をとにかく仲直りさせようとする」というものがあるという。
教師に仲直りするように言われれば、いじめた子供は、その場限りの良い子を作り仲直りしたかのように見せかけるし、いじめられた子供は、相手を許したような顔をしてそれに応じるが、双方、決して本心から仲直りなどしていないのが普通だそうだ。
双方を握手させて、教師だけが問題は解決したと自己満足しているに過ぎず、特にいじめられた子供は、仲直りを強要した教師も、結局いじめた方の子供の仲間なのだと位置づけ、一生その教師を恨むようになるという。
まあ、これは子供の社会だけの話ではなく、大人の社会にも同じことが言える。
とかく、問題を早期に解決したいと、双方を仲直りさせようと仲立ちする者がいるものだが、やった方はそれでいいかもしれないが、やられたと思う側は、そう単純に相手を許すことなど出来はしないものだ。
やられた側は、相手に対して同じかそれ以上の屈辱を味わわさねば納得は出来ないのが道理なのである。
また、いじめられた子供が学校を休みがちになった際、いじめた子供ではなく、別の子供を使者に立てて登校を促すような姑息な手段も教師はついとりがちなのだが、いじめられた子供にしてみれば、それも教師の逃げとしか受け取れないという。
もしも、教師がそんな仲立ちをしようとするのならば、いじめた子供をどのように処分したらいいかを、いじめられた子供やその親と十分話し合いを持った上で行なうべきである。
つまり、いじめられた子供側とのしっかりとした意思の疎通なくして、仲直りなど決してあり得ないというのが、教育評論家の意見であった。
いじめ問題に取り組む教師の間違ったやり方に、「いじめられた子供と、いじめた子供をとにかく仲直りさせようとする」というものがあるという。
教師に仲直りするように言われれば、いじめた子供は、その場限りの良い子を作り仲直りしたかのように見せかけるし、いじめられた子供は、相手を許したような顔をしてそれに応じるが、双方、決して本心から仲直りなどしていないのが普通だそうだ。
双方を握手させて、教師だけが問題は解決したと自己満足しているに過ぎず、特にいじめられた子供は、仲直りを強要した教師も、結局いじめた方の子供の仲間なのだと位置づけ、一生その教師を恨むようになるという。
まあ、これは子供の社会だけの話ではなく、大人の社会にも同じことが言える。
とかく、問題を早期に解決したいと、双方を仲直りさせようと仲立ちする者がいるものだが、やった方はそれでいいかもしれないが、やられたと思う側は、そう単純に相手を許すことなど出来はしないものだ。
やられた側は、相手に対して同じかそれ以上の屈辱を味わわさねば納得は出来ないのが道理なのである。
また、いじめられた子供が学校を休みがちになった際、いじめた子供ではなく、別の子供を使者に立てて登校を促すような姑息な手段も教師はついとりがちなのだが、いじめられた子供にしてみれば、それも教師の逃げとしか受け取れないという。
もしも、教師がそんな仲立ちをしようとするのならば、いじめた子供をどのように処分したらいいかを、いじめられた子供やその親と十分話し合いを持った上で行なうべきである。
つまり、いじめられた子供側とのしっかりとした意思の疎通なくして、仲直りなど決してあり得ないというのが、教育評論家の意見であった。
Posted by ちよみ at 11:44│Comments(2)
│ちょっと、一息 27
この記事へのコメント
仲直り 難しいですね。
銃剣で刺した方は忘れるが刺された方は永遠に忘れない と、国家間紛争での例えも有るくらいですから。
かといって、学校内で「ハムラビ法典」は採用できないですし。
銃剣で刺した方は忘れるが刺された方は永遠に忘れない と、国家間紛争での例えも有るくらいですから。
かといって、学校内で「ハムラビ法典」は採用できないですし。
Posted by DT33 at 2012年09月25日 13:39
at 2012年09月25日 13:39
 at 2012年09月25日 13:39
at 2012年09月25日 13:39DT33さまへ>
こんにちは。
かつての日本には、喧嘩両成敗という考え方がありましたが、ケンカといじめはそもそも違いますから、「仲直り」などという考え方も、実は根本から間違っているのです。仲直りとは、双方に落ち度がある場合にのみ採用される方法であり、いじめは一方的な攻撃ですから、この違いを混同している教師が実は意外に多いのです。
もしも、いじめに対する対処法として過去に倣えば、「仇討」が妥当でしょう。(仇討は、武士道のモラルの一種でしたから、親が殺された場合に限り、子にその権利が生まれ、その子が望むと望まざるとにかかわらず、藩から赦免状が出た場合は、本懐を遂げねばならないという過酷なものだったそうですが・・・)「ハムラビ法典」も、これに近いものがありますね。こちらは逆に、子供が殺された場合は、殺した相手の子供を殺すという方法のようですが。
しかしながら、現代の日本において、仇討もハムラビ法典も学校教育に持ちこむことは出来ませんね。表面化しにくいいじめが運よく発覚した場合でも、教師はとかく「いじめられている」と、騒ぎ立てる側を手っ取り早く黙らせようとするのですが、その焦りが姑息な「仲直り工作」に走らせるのでしょう。
そして、これが問題をますます泥沼化させる失策の入口なのだそうです。
いじめられている方は、「仲直りなどいらないから、とにかくいじめっ子を目の届かない所へやってくれ」と、言い続けるべきで、安易に仲直りに応じることは、むしろ危険だということのようです。
こんにちは。
かつての日本には、喧嘩両成敗という考え方がありましたが、ケンカといじめはそもそも違いますから、「仲直り」などという考え方も、実は根本から間違っているのです。仲直りとは、双方に落ち度がある場合にのみ採用される方法であり、いじめは一方的な攻撃ですから、この違いを混同している教師が実は意外に多いのです。
もしも、いじめに対する対処法として過去に倣えば、「仇討」が妥当でしょう。(仇討は、武士道のモラルの一種でしたから、親が殺された場合に限り、子にその権利が生まれ、その子が望むと望まざるとにかかわらず、藩から赦免状が出た場合は、本懐を遂げねばならないという過酷なものだったそうですが・・・)「ハムラビ法典」も、これに近いものがありますね。こちらは逆に、子供が殺された場合は、殺した相手の子供を殺すという方法のようですが。
しかしながら、現代の日本において、仇討もハムラビ法典も学校教育に持ちこむことは出来ませんね。表面化しにくいいじめが運よく発覚した場合でも、教師はとかく「いじめられている」と、騒ぎ立てる側を手っ取り早く黙らせようとするのですが、その焦りが姑息な「仲直り工作」に走らせるのでしょう。
そして、これが問題をますます泥沼化させる失策の入口なのだそうです。
いじめられている方は、「仲直りなどいらないから、とにかくいじめっ子を目の届かない所へやってくれ」と、言い続けるべきで、安易に仲直りに応じることは、むしろ危険だということのようです。
Posted by ちよみ at 2012年09月25日 15:42
at 2012年09月25日 15:42
 at 2012年09月25日 15:42
at 2012年09月25日 15:42※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。





