湯田中温泉ワークショップ楓・・・・・312
2010年01月02日
~ 今 日 の 雑 感 ~
湯田中温泉ワークショップ楓
湯田中温泉ににぎわいを取り戻そうと、有志が知恵を出し合い、湯田中駅の近くに、「おやすみ処楓」という名のワークショップを立ち上げてから、九ヶ月が経過した。
このメンバーは、42人。発足当時から二倍になったそうだが、実働出来る者は、15人ほどで、店番を務めてくれるのは6、
7人だということである。
この「おやすみ処楓」では、文字通り休憩のためにお茶を飲み、雑談をするために訪れる近所の人から、周辺の観光地などへの案内を頼む観光客への対応まで、毎週火曜日を除くすべての日を開所日として、幅広い活動を続けているが、それでも、未だに、肝心の町の人たちからの協力が思うように得られていないのが、現状であるという。
その理由の一つが、この「おやすみ処楓」を、開所する以前の、有志の人たちのPRの仕方に、問題があったのではないかと、考える人たちもいる。
そもそも、このワークショップを始める時のスローガンが、「街のにぎわいを取り戻すために、空き店舗のシャッターをこじ開けよう」と、いうようなものだったそうである。
ところが、街の人たちは、この「こじ開ける」と、いう言葉に、敏感に反応したようである。
「空き店舗だからって、かってに人の家をこじ開けられてたまるか。バールでも持ってきて鍵を壊す気か?」
「空き店舗の何処が悪いんだ。バカにしてもらっては困る」
「こっちは、ただのボランティアで店を貸すほど、篤志家じゃない。いくらか払ってくれるのなら、貸してやってもいいが、無料で使われてたまるか」
などなど、「こじ開ける」の一言で、街の人たちは、このブロジェクトに反感を持ってしまったというのが実態であるらしい。
無関心ならまだしも、マイナスのイメージを植え付けてしまったことが、この計画が最初から軌道に乗りにくくなっている原因なのである。
そうなれば、始めは、「おやすみ処楓」に期待し、感心があった女性たちも、「あんな所で寄り合っていれば、お父ちゃんに叱られる」とか、「行きたくても、誰かが見ているんじゃないかと思えば、行きづらいよね」などと、二の足を踏んでしまい、結局、未だに店を訪れることが出来ずにいると、いう訳なのである。
また、そういう女性たちも、本音を言えば、
「もしも、あの店に、安い野菜や果物や、お惣菜などが売られているのなら、買い物にかこつけて立ち寄ることも出来るのに、ちょっと、店内をのぞいたけれど、お土産品みたいなものばかりで、日常生活の足しにはなりそうもないから、行ってもしょうがないよ」
と、いうことでもあるらしい。
また、こういう意見もあった。
「いつも店が閉じめみたいに見えるし、店の中がうす暗いのがよくないね。それに、いつも扉が閉めっぱなしだから、何となく入りにくいんだよ。もっと、店の外まで品物が並べられていれば、それを見るようなふりをして、店内まで入ることも出来るんだけれどね」
どうやら、この店がイマイチ不人気の原因は、店内へ入りにくい印象を与えていたことにもあるらしいのだ。
男性が中心になってアイデアを出すことが、実は、かなりのデメリットを産んでいたのではないかとさえ思われる。人が集まる場所には、やはり、人が吸い寄せられるものである。店内の出入りを頻繁にして、人目を引くこともアイデアなのではないだろうか。
もしも、この店をもっと活用したいと思うのなら、店番の人たちに店内にばかり居させては意味がない。その店の周りに出て通行人に気さくに挨拶をするとか、(明確なビジョンを打ち出すことも結構だが)まずは、コミュニケーションの仕方から勉強した方がよいようにも思えるのである。
また、その店の中でお茶をふるまうだけではなく、近くの喫茶店から出前を取るようなことも出来るようにするなど、もっと臨機応変な対応を試みることで、違った展開が見えてくるような気もする。
昔からの老舗と呼ばれる店や古くからの住人が多く住む場所は、とかく、その地域のしきたりや独特のつながりがあり、新しいことには懐疑的なものである。
そのリスクは、もちろん承知の上で始められた「ワークショップ楓」のプロジェクトなのであるから、有志の人たちは、自分たちの目線だけではない、地元密着の視点で、対応することが今後の課題なのではないだろうか。

続きを読む
タグ :いろはす
物書きは、自己主張の塊・・・・・311
2010年01月01日
~ 今 日 の 雑 感 ~
物書きは、自己主張の塊
しばらく前だが、わたしの母校から、一通の手紙が届いた。
こちらとしては、もちろん断る理由もないので、電話で、了解の旨を伝えた。
ところが、その電話でのやり取りがどうにも不可思議で、わたしが、相手の女性の声があまりに若いので、「その図書館新聞に記事を書かれる生徒さんなんですか?」と、訊ねたところ、突然、、女性は気分を害したらしく、
「わたし、生徒じゃありません。図書館の司書をしている者です。そんなに、頼りないように思えたんですか?」
と、いきなりの喧嘩腰なのである。わたしは、おかしな人だと思いながらも、
「あまりお声が若いので、女子生徒さんなのかと思ったのです。すみませんでした」
と、詫びたところ、彼女は、生徒と間違われたことがよほど気に入らなかったのか、また、
「わたし、生徒なんかじゃないですから。それじゃ、書かせてもらいますから----」
まるで、こちらが書いてくれとでも頼んだような口ぶりで、電話を切ったのである。
その後、出来上がった図書館新聞が送られてきたが、そこには、「この小説を書いた人は、自己主張が強い」と、まったく本とは関係のないわたしの人物評までご丁寧に記されていたのであった。
直に会ったこともない、たった一度、電話で話しただけの人間を、よくもまあ、イメージだけで書いてくれたものだと呆れてしまった。それでも、一応は郵送してもらったお礼を手紙にしたためて送った。
しかし、どういう訳か、その後も、彼女は手紙をよこし、そこにも、自分の趣味や好きな漫画などについて事細かに並べ立て、読んでいたこちらは、
「なんで、あなたのプロフィールを教えてもらう必要があるの?」
と、首をかしげざるを得なかった。
彼女とは、もう二度と話をしたくないと思う気持ちから、わたしは、それに対しての返事は出さなかったが、この「自己主張」という一文には、未だに、納得がいかない。
だいいち、物書きというものは、素人だろうと玄人だろうと押し並べて「自己主張」の塊のようなものである。また、そうでなくては、自分の書いた文章を人様にお読みいただくなどという恐れ多いことが、臆面もなく出来る訳はないのだ。
それを取りたてて、「この人は自己主張が強い」などと、わざわざ記事に載せるその神経を疑ってしまう。要するに、彼女は、おそらく、わたしに記事掲載を頼む時から、既に、わたしに対して面白くないというマイナスの感情を持っていたのであろう。
何か、私生活で欲求不満なことでもあったのか?恋人に振られでもした後だったのか?
たとえ、どのような事情があったにせよ、こちらは何の関係もないのだ。感情のコントロールがうまく出来ない者が、学校の図書館司書などやっていていいのだろうか?
今もって考え出すと、腹が立つ過去のエピソードの一つである。

また、感情のコントロールが出来ないと言えば、かつて、こんな女性がいた。
ある有名な東京の出版社の編集員なのだが、わたしの原稿が読んでみたいと言うので送ったことがある。しかし、それに対する返事が全くないので、どうなったのかと電話で訊ねたところ、
「あなたね、書いていることがテレビの観過ぎなのよ!ぜんぜん陳腐で話にならないわ」
わたしは、これにブチ切れた。
「それ、誰に向かって言っているんですか?まさか、わたしじゃないですよね?わたしは、そちらに頼まれて原稿を送ったんですよ。文句を付けるなんて筋違いじゃないですか?あなたたちの方が原稿を選べるなんて思っているのなら大間違いですから!書いてくれる人がいなければ、何にも出来ないくせに、送った原稿と送料、返しなさい!」
しかし、そのバカ女は、原稿も送料も返しては来なかった。
自分はキャリアウーマンを気取っていて、男勝りに他人を威圧すれば一人前だと思っている勘違い女は、何処にでもいるものだが、絶対、彼女たちは、ヒステリーを起こしているだけのギスギス女に違いない。
こういう「世界は我が物症候群」の女自体が、世の有能な女性たちの社会進出を阻んでいる元凶なのである。

続きを読む
タグ :中野市は志賀高原の入り口ではない
良い嫁は、悪い嫁?・・・・・310
2009年12月31日
~ 今 日 の 雑 感 ~
良い嫁は、悪い嫁?
ご近所の若いお嫁さんがぼやいていた。
「お正月のおせち料理だけれど、家で作るよりもスーパーで出来あいの物を買おうと思う」と、言ったところ、お姑さんと口論になったというのである。
お姑さん曰く、「うちは、昔からおせちは自分の家で作ることに決まっているのだから、伊達巻もお煮しめも、煮豆も、栗きんとんも全部家で作る」と、のこと。
「そんなことをしているから、毎年、余計な分まで作って、不経済なことになる。水道代もバカにならないのだから、この際、習慣などにこだわっている場合じゃァないでしょう」
お嫁さんは、そう言ったのだが、お姑さんは、頑として聞かないのだという。どうやら、家の古くからのしきたり通りにやらないと、悪い嫁だと思われる-----そんな、義務感に取り付かれているようだと、彼女は話していた。
しかし、スーパーの出来あいで経済的に節約する嫁と、余計なお金をかけながらも、家のしきたり通りに努力を惜しまない嫁、いったいどちらがいい嫁なのであろうか?
「それじゃァ、何か一品だけ、家で作ったら?」
と、わたしが言ったが、どうも、そんな物では納まりそうもないようである。
「だったら、かまぼこも、酢ダコも、自分で海へ行って材料を獲って来いっていうんだ!」
彼女の怒りは、お正月まで鎮まりそうにもなかった。
また、もう一人のお嫁さんは、洗濯のことでお姑さんとバトルになったことがあるという。
お姑さんは、洗濯は毎日欠かさずやるものだと思っていた。しかし、そのお嫁さんは、結婚前の会社員時代からの習慣で、洗濯は、土曜日にまとめて一気に洗うものだと思っているようで、そのほかの日は、絶対に洗濯機を回さないのである。
まだ、ご主人との間には子供さんがいないので、そんなことでも済むのだろうが、子供が出来たら、そんなズボラは通用しないと、お姑さんに叱られても、「その時は、その時」と、まったく意に介さないそうである。
また、そのお嫁さんは、家では決して天ぷらや揚げ物をしないのだという。
油がはねて壁を汚したりすれば、掃除に手間も時間もとられるし、水道代もかかる。それを拭いたタオルも洗濯しなければならず、洗剤も余計に必要となる。
どう考えても、不経済だし、意味がないというのだ。そのため、お風呂も浴槽にお湯をためない。
お風呂掃除に無駄な労力を使いたくはないし、ここでも、水や洗剤が必要となる。だから、ご主人と二人、いつもシャワーだけで済ましているのだという。
しかし、シャワーだけではやはり疲れは取れない。ご主人は、時々、実のご両親のいる実家へ帰り、実家の内風呂を使っているとも、お姑さんの方は話していた。
最近は、こういう、よく言えば「経済的節約主婦」が増えてきているが、どういうものなのだろうか?
それも、これも、程度ものだと思うのだが、節約もやり過ぎれば単なる怠け者と思われても仕方がないのではないだろうか?
かつて、家柄や義理の父母に徹底的に絞られ、その家のしきたり通りに教育された嫁からすれば、今の若いお嫁さんたちは、容量ばかりがいい「悪い嫁」にも見えるのだろう。しかし、若いお嫁さんからしてみれば、昔のお嫁さんたちは、「経済観念0の、口やかましい悪い嫁」に見えるのかもしれない。
どちらが、「本当の意味の良い嫁」と、いえるのだろうか?
「良い嫁」「悪い嫁」の定義も、時代によって変わって行くのかもしれない。
 続きを読む
続きを読む医師は、スーパーマン症候群?・・・・・309
2009年12月30日
~ 今 日 の 雑 感 ~
医師は、スーパーマン症候群?
今日、とある医師のブログを読んでいたら、「医師たちは、スーパーマン症候群」にかかっているという記事があった。
これは、どういうことなのかと言うと、医師は、先輩医師からの教えもあって、決して人前で弱みを見せてはいけないと思い込んでいる人が多いのだそうだ。
自分が風邪をひいていても身体がだるくても、患者のために頑張らなくてはいけないと、強がってしまう傾向があるのだという。そして、自分は絶対にやれる、大丈夫だと、考えてしまうのだそうである。
そして、自分自身の体調が悪くても、あまり、他の医師に診察して欲しいとは思わず、自分で自分の診断を下し、薬で対処しようとするということであった。
それは、アンケート調査や統計的にも表われているそうで、
★ 同じ病院の医師に診察してもらうのは抵抗がある。
★ 出来れば、違う場所の医師に診てもらいたい。
★ 他の医師にかかること自体二の足を踏んでしまう。
と、いうような感想が多かったということである。
つまり、これは、医師が医師を頼るということが、医師の気持ちの何処かに、自分の職業的敗北につながるような気がするという意識があるためなのか?それとも、単に、同業者に診察されることに恥ずかしさを感じるという問題なのか?
それよりも、医者なのに、自分の体調も管理できないなど、恥だと感じる気持ちが強いのだろうか?
確かに、お医者様は、患者の前では、いつも元気な頼もしい存在であるはずだと、患者側も思いがちではある。
しかし、医師だって、普通の人間で、風邪もひけばお腹もこわす。時には、だるくて診察などしたくない時もあるはずなのだ。現在の医療崩壊の一端には、医師の過剰な頑張りも影響しているのかもしれない。
これは、以前、わたしが咳が止まらず診て頂いた当時70代のおばあちゃん医師のエピソードだが、そのおばあちゃん先生は、わたしの診察をしながら、その話の中で、ご自分が体調を崩し、子供がいるのに困惑したということを、本当に気軽に話して下さったのである。
そして、患者のわたしに対し、
「ねえ、最近、わたし、よく睡眠がとれないんだけれど、何か、いいアイデアないかしら?薬はあまり飲みたくないのよ」
と、何とも気さくに話しかけて下さるのである。そうやって、自分の弱みも明るく話して下さることで、わたしには、逆に医師と患者との距離も縮まるような気がした。
まあ、その日は、そのおばあちゃん先生から、わたしは、カニ缶一つを頂いて帰り、処方して下さった薬で咳もおさまった。
このおばあちゃん先生は、昨年、85歳で亡くなられたが、患者さんたちにもとても人気があり、真の地域医療の最前線で活躍されてきた名医だったと、未だに患者さんたちは話している。
「医師は、スーパーマンでなくてもいい。自分の本音を語ることも、患者の信頼感や親近感を高めるきっかけになる」
そんなことを、このおばあちゃん先生の診療方法から感じた次第である。

*** 写真は、ペプシ飲料のおまけに付いていた「ペリー提督」。他にも「真田幸村」や「直江兼続」「坂本龍馬」「土方歳三」などがあるそうですが、わたしは、「沖田総司」が欲しいなァ。
 続きを読む
続きを読むこういうのって、ありな訳?・・・・・305
2009年12月28日
~ 今 日 の 雑 感 ~
こういうのって、ありな訳?
★ 長野県には、誇れる日本一がたくさんあります。 長野県は、「行ってみたい」 「見てみたい」「住んでみたい」「経験してみたい」魅力にあふれています。
なお、原則としてコメントには返答をいたしませんので、ご了承ください。
回答を希望するご質問・ご要望は、以下よりお送りください(メールアドレスに間違いがないよう、ご注意ください。)
ご質問・お問い合せはこちらからどうぞ
(長野県企画部企画課)
最近、「長野県は日本一」というブログを発見しました。
どうやら、「長野県」が企画してアップしているブログのようなのですが、これって、少し不自然じゃありませんか?
だって、長野県が企画し、県の魅力を県内外アピールしたいと思って始めたブログならば、どうして、「原則としてコメントには返答いたしません」なのでしょうか?
メールをお送りくださいというのであれば、その送り手のメールアドレスや、設定の仕方によっては、名前までも明らかになる訳ですよね。
企画部企画課の方たちは、質問者のことを知ることが出来るのに、こちらは無防備。少し、不公平すぎるように思います。
それとも、自分たちは、お役所だから、素人のコメントにいちいち回答する必要などないと言われるのでしょうか?
そんな対応の仕方で、長野県が魅力的な県だと思ってもらえるのでしょうか?
もしも、企画課の方たちが本気で長野県の魅力を広報したいのならば、たとえどのような馬鹿げた質問がコメントで寄せられても、すべてに真摯に向き合い回答するべきなのではないかと考えます。
どうも、ブロガーの中で、自分たちだけは特別だと思っておられるように思えてなりません。
ブロガーのマナーは、コメント欄を設けたのなら、必ずコメントの返事を返す。そういうものです。
もしも、コメントに対して返事を書きたくないのなら、コメント欄は閉鎖しておくべきなのです。何処か、上から目線で他のブロガーたちを見ているように思えて残念です。
コメント欄への返事が頂けないということなので、自分のブログへ書かせて頂きましたが、承認後返事をする設定は、それでも結構ですから、真面目なコメントに対しては、誠意のある対応を望みたいものです。
★ ブロガーの中に、どうにも理解できない無節操な人物がいます。
自分は、そういう人たちとは付き合うつもりはないと言いながら、実は、裏ではしっかり交流があるのです。しかし、昔からよく言うじゃありませんか。「企みごとは、一人で行なえ」と-----。
つまり、共謀者が多くなればなるほど、上手の手から水が漏れるというものなのです。
面白いことに、そういう裏で色々と画策している者たちは、どうしても表だった場所で話をしたくなるものらしいのです。こっそりとメールやメッセージでやり取りすれば判らないものを、そういうやり方がまどろっこしくなったり、または、自分たちの仲のよさを他の人に見せびらかしたくなったりで、そのうちに必ずと言っていいほど、コメント欄上でそれにかかわる連絡を取り合ってしまうものなのです。
そういう行為が、そのあとで周囲から顰蹙を買うことは判っているのに、それが我慢できないのですね。
要するに、口が軽いというか、秘密の保持が出来ない人間が、確実に、策謀仲間の中から一人二人出てきてしまうのが常なのではないでしょうか。
それが、不思議なことに、わたしが偶然開けたブログに、そういうことが書き込まれている場合が多いのです。
いつもは、そんなブログを読む気などさらさらないのに、そういうコメントが書き込まれている時に限って、クリックしてしまうことがあるのです。これは、実に不思議なのですが、これこそ、「天網恢恢疎にして漏らさず」というものなのではないでしょうか。(笑)
堅牢も蟻の一穴から----。
つまりは、あなたの軽率な書き込みで、これまでの彼らの努力も水の泡ということですね。これだから、女は、ダメだといわれるのですよ!(爆)

続きを読む
弁護士が法廷で殴り合い!・・・・・304
2009年12月28日
~ 今 日 の 雑 感 ~
弁護士が法廷で殴り合い!(@д@;)
日本全国で裁判員裁判が始まり、法廷が劇場化しているという。
ある地域の裁判所では、暴力事件の裁判員裁判で、裁判員たちにその時の現場のリアルな状況を知ってもらおうと、被告の弁護人の男性二人が、法廷で実際に本当に殴り合ったそうだ。
 ガツッ!バシッ!ドスッ!という、本当に相手の顔や腹に思い切りパンチを食らわせるという傷害事件現場さながらの衝撃的な格闘劇に、裁判員たちはあっけにとられ、傍聴人は、震かんしたという。
ガツッ!バシッ!ドスッ!という、本当に相手の顔や腹に思い切りパンチを食らわせるという傷害事件現場さながらの衝撃的な格闘劇に、裁判員たちはあっけにとられ、傍聴人は、震かんしたという。いくら、事件の状況を間違いなく把握してもらいたいからといって、果たして、ここまでやる必要があるのだろうか?
また、裁判官は、その様子を見ていて、何も言わなかったのであろうか?
詳しいことは、わたしにも判らないので、何とも言えないが、もしも、この弁護人たちによるアクションドラマさながらの熱演が、判決に影響を与えたとしたら、これから、このようなリアルさを追求し、裁判員たちの視覚に訴えるという手法を取り入れる弁護士や検察官が、大勢出てくることであろう。
既に、検察官の中には、過剰なほどのパフォーマンスで、ハムレットの舞台劇でも演ずるかのように、大仰な身振り手振りを交えて、法廷で朗々と事件経過を説明した人もいるそうである。
このあまりの迫力に、裁判員の中には思わず苦笑する人もいたと聞く。
しかし、もしも、これからの裁判員裁判の法廷が、こういう調子で進められて行くのだとしたら、日本の裁判もアメリカ並みにエンターテイメント化して行くのも時間の問題だと思われる。
元裁判官の男性は、「法廷は、もはや、ディズニーランドも真っ青のアミューズメントパークだ」と、嘆いていた。
「そして、もうすぐ、裁判所の前には、劇場並みにその日の裁判の演目が書き出されることであろう」と、予想する。
たとえば、「今日の第〇号法廷は、アクション物で仁義なき抗争」とか、「第〇号法廷は、強姦致傷事件・若妻の嘆き」とか、そんな見出しが並ぶのだろうか?
そして、法廷では、検察官が東映・日活映画よろしく、当時の模様を演じ、女性弁護士が、男性弁護士を相手に、強姦シーンを臨場感たっぷりに演じるとでもいうのだろうか?
なんだか、すさまじい話である。(~_~;)
法律家も、演劇学校へ通う時代が来るのかもしれない。
傍聴人席には、映画館へ行くような気分の人々が詰めかけ、恰好のデートスポットになる可能性もあると、その元裁判官は危惧する。
いいや、もう、法廷内だけでは納まらず、裁判がホクト文化ホールなどで行なわれることだって考えられなくはないのだ。もちろん、そうなれば、テレビ中継も解禁となり、法廷専門チャンネルも確保されることだろう。
日本の裁判は、本当にこのままでいいのだろうか?
どうなる、裁判員裁判!?

続きを読む
タグ :ししゃも
それ、本心ですか?・・・・・303
2009年12月27日
~ 今 日 の 雑 感 ~
それ、本心ですか?
もしも、あなたが面白くないと思っている人間がいて、その人のことを恨んだり、憎んだりする気持ちを消し去ろうという思いから、こういう表現をすることはありませんか?
「大人になりきれない可哀そうな人だと思うことにした」
う~ん、こういう人に一度訊いてみたいのですが、あなたは、本当に、本心からそう思えるようになったのですか?
やせ我慢じゃァないのですか?
そんな風に思い込もうとしても、やっぱり、顔を合わせれば腹も立つのではないですか?嫌な気分になるのではないですか?それでは、自分は、大人だと言えますか?
そうじゃないでしょう?やはり、悔しいし、気に食わないものは気に食わないはずですよね。でも、自分は大人なのだと、無理やりに思い込むことで、そういう人を見下して気持ちを鎮めたいと思っているだけなのではないでしょうか?
あなたが、相手を子供だと思っているように、相手もあなたを気に入らない小生意気なガキだと思っているはずです。
人の気持ちなどというものは、そうそう意のままに変えられませんし、自分の気持ちだって簡単に変えることなど出来ないはずです。
あまり、大人ぶらない方がいいですよ。子供でいいじゃないですか。生物学的にも、人間が最も我慢が出来る年齢は、25歳ぐらいだと言いますから、我慢の持続や辛抱強さは、10歳も60歳もほとんど変わらないのです。
ですから、恰好つけは、最も恰好の悪いことなのです。
見苦しい見栄を張るよりも、自分に正直になることの方が、よほど人間らしいと思うのです。
本当に悔しかったら、相手に素直に気持ちをぶつけた方が楽になりますよ。
「もう、あんたたちと一緒にいるのは飽き飽きなんだよ!さっさと、消えてくれない!?」-----ってね。


ねえ、どうなのよ・・・・?
続きを読むタグ :オフ会の皮肉
そういうお前が元凶なんだ・・・・・301
2009年12月26日
~ 今 日 の 雑 感 ~
そういうお前が元凶なんだ
「人を傷つける奴は許さない」などと言う人がいる。
しかし、そう言っている自分自身はどうなんだろうか?
そういう人間は、「人を傷つけても無頓着な奴は、最低だ」とも言うが、では自分自身は、無頓着に他人を傷つけるようなことは絶対にしていないと、天地神明にかけて断言できるのか?
もしも、あなたが傷ついたと感じているのなら、それは、あなたが傷つけた人間からの仕返しにあっているだけである。
そのことに、どうして気が付かないのかと、わたしは言いたい。
自分が攻撃を受けたということは、必ず攻撃されるだけの理由があるのだ。
相手が拒絶したことを、自分をないがしろにしたと逆恨みし、その相手を攻撃した時から、相手の反撃が始まる訳で、自分の旗色が悪くなった時に、「人を傷つけるな」などと泣き言をほざいても、それは自業自得というものではないか。
大抵において、反撃は攻撃の数倍もの襲撃を受けるものと相場が決まっている。
先に喧嘩を売った方は、それを受ける覚悟で売るべきなのだ。(少なくともブログ上においては、わたしは、意見や反論は書かせて頂いたが、自分の方から喧嘩を売ったことは一度もないと断言できる!)
そうだ。誰かも言っていたではないか。「書くなら刺されるつもりで書け」と-----。
そう書いた本人も、もちろん、それなりの覚悟の上で書いたのだろう。つまり、自分も刺される覚悟があるという訳だ。そうでなければ、話のつじつまが合わない。
しかし、そんな恐ろしい覚悟を、よく決めることが出来るものだ。わたしには、到底考えられない。よほど、性根が座った人なのだろうな。大したものだ。見上げた根性の持ち主だ。(爆)
だから、人を非難する前に、まずは、わが身を省みて襟を正してから物申せと、言いたいのである。
「人を傷つける奴は許さない」と、言うのなら、お前自身も許すんじゃないぞ!
続きを読む
タグ :デートDV
保健室でご飯をもらう子供たち・・・・・299
2009年12月25日
~ 今 日 の 雑 感 ~
保健室でご飯をもらう子供たち
(奨学金が足りない)
(奨学金が足りない)
この記事では、わたしたちが、クリスマスケーキを食べ、チキンを焼き、シャンパンをグラスに注いでクリスマスパーティーだと浮かれている間も、一つのパンを食べることも出来ずに、ひもじさと闘っている子供たちが、この日本の中には大勢いるという現実を考えてみたいと思います。
今、日本全国の小学校、中学校、高校で、保健室へ来て、保健室担当の先生に「お腹が空いたので、ご飯をください」と、頼む子供たちが急増しているというニュースを観た。
小学生の男の子は、家では、母親が朝食も夕食も作ってくれず、学校で食べる給食が唯一の食事だというのである。
とはいっても、母親は、別に男の子を虐待したい訳ではない。お金がなくて、ご飯を食べさせてやれないのだという。しかも、男の子には小さな兄弟がいて、その兄弟に食べさせる食事を確保すると、男の子の分がなくなってしまうのだそうである。
その兄弟の分の食事も、茶碗一杯のご飯だけという、普通では考えられないほどの貧困なのである。父親は、会社をリストラされ、職を探してもみつからない。母親は、働きに出ているが、その稼ぎもアパートの家賃と光熱費で消えてしまうそうで、男の子はいつもお腹をすかせており、体格もかなり他の子供たちに比べて小さい。明らかな栄養失調である。
それに、虫歯が多く、痛くてもお金がないので歯医者さんへ行くことも出来ないと男の子は言う。
その日も保健室へ来た男の子は、先生の差し出したパンと牛乳を、むさぼるように食べていた。
もう一人の高校一年の女子生徒は、母親が貧困から仕方なく女子生徒を退学させ、今、女子生徒は、年齢を偽り、風俗店で働いている。母親からの仕送りなどは一切ないため、自分の食い扶持は自分で稼がなくてはならず、もう復学もあきらめたという。
そして、別のもう一人の女子高校生は、どうしても勉強が諦めきれずに、高校を夜間部へ移し、スーパーのアルバイトで学費を稼ぎながら大学進学を目指している。しかし、担任教師は、言う。
「やはり、親の協力がなければ、進学は難しいのが現実です。彼女の稼ぎだけでは、とても大学の学費は払いきれないでしょう」
わたしは、これを聞いたとき、奨学金制度があるのではないか?-----とも、思ったが、この奨学金制度も既に破綻をきたしているのだという。つまり、かつて奨学金を得て大学を卒業した人たちが就職し、奨学金を返済してくれればこそ、次の子供たちへ回るのである。しかし、この不況で、かつての奨学生たちの奨学金返済が滞り、まったく返す見込みのない人までもが急増しているというのである。
貧しい者は、より貧しく、勉強も就職も、食事さえも満足にできないこの現実を、いったいどのように考えればいいのであろうか!? 片や、親が子供のために一月1500万円も小遣いをくれるというとんでもなく裕福な家庭もある。
彼らは、そのお金の半分でも、そういう子供のために使おうと思わないのであろうか?政治をするには金がいる。-----それは判っている。しかし、今日の一口のご飯も食べられずにお腹をすかせて泣いている子供たちが何万人もいるのである。
それが、今の日本の現実なのである。
その子たちには、将来などよりも、今が大事なのだ。今を生きなければ、将来などあり得ない。
十年先、二十年先の日本も大事だが、今をしっかりと作ることが、未来を作ることなのではないだろうか?
この現実に、「悲しいよりも腹が立つ!」と、コメントした解説者の言葉が印象的だった。 続きを読む
タグ :壊し屋小沢幹事長
延命治療は、何処までやるべきか?・・・・・298
2009年12月24日
~ 今 日 の 雑 感 ~
延命治療は、何処までやるべきか?
末期がんなどで入院中の患者七人に対して、人工呼吸器をはずし、延命治療を中止して死亡させたとする、富山県射水(いずみ)市民病院の男性医師二名について、富山地検は、いずれも不起訴とする方針を決め、この医師たちの不起訴が確定した。
患者の死亡と人工呼吸器を外したこととの因果関係の立証が難しいうえ、遺族側が処罰を望んでいないということからも、不起訴となったものであった。
しかし、一方、川崎市の病院でこん睡状態の男性患者の人工呼吸器の気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与するなどして死なせたとされた女性医師には、殺人罪が適用され、懲役一年六カ月、執行猶予三年の有罪判決が確定した。
同じ末期患者を扱いながら、片や不起訴、片や有罪の違いは何なのだろうか?
一口に言えば、患者の家族が医師を恨んでいるかいないかという違いだけのように思えてならない。
前者の二人の男性医師の場合は、七人という死亡患者の人数が衝撃となり、大きな事件として扱われてはいたが、末期の患者の延命を続けることに疑問を持ち、それが、たとえ患者本人の意思でなかったとしても、家族の同意のもとに人工呼吸器を止めるという行為が、必ずしも犯罪とは認められないということであり、それは、これまで患者を診察して来た医師のみがなし得る決断だということを、地裁が認めたということなのであろう。
しかし、後者の女性医師の場合は、患者の意思がないままに、家族への説明も不十分で、適切な検査もせずに医師の独断により患者の呼吸器のチューブを抜いたということで、殺人罪が適用されているのである。
この富山と川崎のケースに、どれほど明確な違いがあるというのであろうか?
適切な検査とは言うが、末期の患者にどのような適切な検査ができるのだろう?呼吸器の気管内チューブを抜けば、必然的に患者が死ぬことは、正直説明などなくても、明確な事実であることは素人でも判るはずである。加えて、家族の要請があったにもかかわらず、患者の延命治療を継続しなかったことが問題視されるというのであれば、医師は、いったい何をきっかけに延命治療を終了できるのであろうか?
確かに、家族の立場に立ってみれば、一日でも一時間でも長く生きていて欲しいという気持ちはよく判る。
だが、病院側にも、やはり、都合というものがあり、回復の見込みのない患者にいつまでもベッドを占領してもらっていては迷惑なのであろう。治る見込みのある患者のために、ベッドを空けて欲しいと思う気持ちは当然のことだと思うのである。
わたしの家の近所の男性も、末期がんで入院し、意識不明のまま自発呼吸も出来なくなった時、医師が、家族に訊ねたそうである。
「延命処置を継続しますか?」
しかし、家族の答えははっきりしていたという。
「もういいよね。こんな面倒な親父のために、わたしたち、苦労させられて来たんだもん。ここまでやってもらえば充分だよ」
もちろん、訴訟などにはならなかったし、家族もさばさばしたものであったという。
富山県のケースは、病院側が真面目に警察へ通報したので、こういう問題にまで広がってしまったのだが、基本的には患者の命は、医師と患者本人が決めるということなので、患者にその意思表示がなかった場合は、医師が判断するしか方法はないのではないかと思うのである。
ましてや、患者の家族が、ごねればごね得と、医療訴訟を起こすことが形骸化されるようなことにでもなれば、反対に日本の医療がますます患者にとって不利益となることは間違いないのではないかと、危惧してやまない昨今である。
続きを読む
タグ :検索エンジン
それって、自惚れ?・・・・・296
2009年12月23日
~ 今 日 の 雑 感 ~
それって、自惚れ?
ブログを読ませて頂いていると、時々、首を傾げたくなるような記事を書かれているブロガーがおられる。
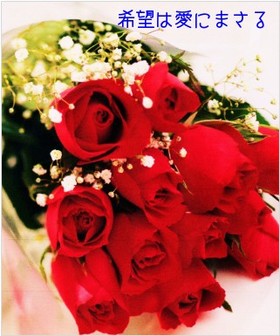 まあ、ブログというものは基本的には何を書いてもいいものだとは思うので、書き方はそのブロガーさんの自由なのだけれど、でも、それを最初にあなたが言ってしまっては、読み手はどう反応したらいいの?----と、考えてしまうような記事なのである。
まあ、ブログというものは基本的には何を書いてもいいものだとは思うので、書き方はそのブロガーさんの自由なのだけれど、でも、それを最初にあなたが言ってしまっては、読み手はどう反応したらいいの?----と、考えてしまうような記事なのである。そういうブログには、大体において、絵画やら写真やらの作品が掲載されており、その作品は、なかなか玄人はだしのそつのない佳作と評価されてもいいほどの出来栄えなのだ。
しかしながら、そういう作品を掲載しているブロガーが、そこに書き込んでいる文章は、
「この作品、自分で言うのもなんだけど、正直あまり好きじゃない。こういうのって、頭が痛くなる」
「また、こんな写真撮ってしまった。これじゃァ、いけないんだよね」
「こんな物作るのはあまり好きじゃないんだけれど、出来ちゃった」
こういうものが大半で、それじゃァ、どうしてブログに載せたんだ?と、言いたくなるような説明なのである。
でも、そう言いながら、何度も何度も作品をアップしてくる。結局、何のかんの言っても、自分の作品を自分でけなしながらも、実際本音のところでは、「わたしって、こんなに上手な写真を撮れるんだ」「わたしの描く絵って、素敵でしょう」と、自慢したいんだろうとしか思えない。
では、これを見せられた読者は、なんと反応したらよいのだろうか?
読み逃げするのは簡単だが、いつもコメントのやり取りをしている場合などは、実に厄介なことになる。
「そんなことないよ。とても素晴らしい作品だ。きみは天才だな」
なんて、褒め言葉を書けば無難なのだろうが、作品を作っている本人が、「うまく出来なかった」と、公言しているのだから、それに反論するのも申し訳ないというのが、常識なのではないだろうか?
わたしなら、そういう作者には、間違いなく、こうコメントを書き込むだろう。
「そうだね。きみが言うように、もう一つ工夫が足りないね。自分が納得できない作品は、あまり人目にさらさない方がいいと思うよ」
つまり、作者は、こういうコメントを待っているんだろう?そうでなくては、話が合わない。
「謙遜も、度を超すと嫌味になる」-----の典型だと思うのである。
せっかくブログに掲載するのである。もっと、堂々とアップしたらどうなのだろうか?
どれほど自分の作品をけなしても、ブログに載せている以上、それは、自慢の作品に違いないのだ。だったら、もっと素直に、「こんな写真撮りました。みなさんご覧ください」とか、「一生懸命作りました。渾身の作品です」とか、正直な気持ちを書けばいいのである。
そのほうが、よほど清々しい。
あまり、自己卑下が過ぎると、逆にこれ見よがしの自惚れに聞こえるものである。
だから、わたしは、そういうブロガーの記事を読むと、必ず心の中で鋭く突っ込みを入れている。
「だったら、そんな作品、載せるなよ!」と-----。 続きを読む
タグ :小笠原と稲葉
のだめカンタービレの意味は?・・・・・295
2009年12月23日
~ 今 日 の 雑 感 ~
のだめカンタービレの意味は?
皆さん、18日、19日と、二夜連続のテレビドラマ・スペシャル版(再放送)「のだめカンタービレ」ご覧になりましたか?
やっぱり、このドラマは、楽しいですよね~。

ところで、この「のだめカンタービレ」の意味ですが、皆さんはご存知でしたか?
音楽を演奏する時には、五線譜に音符が書かれている楽譜が必要ですよね。
この楽譜には、五線、音部記号、拍子記号、音符、休符、調号、臨時記号などが書き込まれています。つまり、これがないと、演奏が出来ないからです。
その他に、重要ではありますが、必要不可欠というほどのものではない記号に、「演奏記号」というものがあるのだそうです。
この「演奏記号」は、文字を用いて演奏者に示すものと、マークやシンボルを書いて示すものがあるのです。
この前者である「文字を用いて示す記号」の中には、「速度記号」や「発想記号」というものがあり、ひっくるめて「標語」と呼ぶそうです。
「速度記号」の例では、Adagio (アダージョ・ゆるやかに)とか、Andante (アンダンテ・歩くような速さで)とか、Vivo (ヴィーヴォ・活発に)などのものがあります。
そして、次の「発想記号」の中に、この「カンタービレ」があるのです。
cantadile ----- 「カンタービレ・歌うように」
つまり、「のだめカンタービレ」は、「のだめ、(ピアノで)歌って!」と、いう意味にでもなるのではないかと想像します。
「発想記号」のほかのものには、dolce (ドルチェ・柔和に柔らかく)とか、legato (レガート・滑らかに)とか、calmato (カルマート・静かに)などがあります。
これらのいわゆる「標語」は、基本的にイタリア語で書かれるそうで、おそらく、キリスト教のカトリックの総本山であるバチカンがイタリアにあり、そこで作られた宗教音楽が、すべての五線記譜法の楽譜の大元となっているためではないかと類推します。
それにしても、「のだめカンタービレ」は、面白いだけでなく、色々勉強にもなるドラマですね。
わたしは、原作の漫画をまだ読んだことがありませんが、上野樹里と玉木宏のコンビは、実に見事に役になりきっていると思います。
映画化で完結ということらしいのですが、その後の二人の活躍も観てみたいと思うのは、わたしだけではないでしょう。
 続きを読む
続きを読むタグ :生姜ブーム
別れさせ屋の悲劇・・・・・294
2009年12月22日
~ 今 日 の 雑 感 ~
別れさせ屋の悲劇
世の中に、「別れさせ屋」などという商売があるなんて、驚きました。
この職業は、文字通りに、依頼者が別れて欲しいと思う対象者を、さまざまな手段を駆使して別れさせ、報酬をもらうというものなのだそうですが、最も依頼が多いケースは、不倫中の独身女性からの、「彼と奥さんを別れさせて欲しい」と、いうものだそうです。
何だか、とんでもなく身勝手な依頼のようにも思えますが、そこは商売ですから、「別れさせ屋」は、奥さんの方に近付き、奥さんの気持ちを自分の方へ向けて、彼女にも自分との間に不倫の事実を作ることで、ご主人が別れやすくなるように仕向けるのだといいます。
この手口で、夫と離婚させるために奥さんに近付いた「別れさせ屋」が、なんと奥さんを本当に好きになってしまったことが、殺人にまで発展してしまった事件が最近起きました。
「別れさせ屋」の男性調査員の桑原武被告(31)は、2007年、栃木県のスーパーで五十嵐里恵さん(死亡時32)に、「チーズケーキのおいしい店を教えてください」と、声をかけ、自分は、本当は既婚者でありながら、独身でIT 関係会社勤務と彼女を騙し、夫との関係に悩んでいた里恵さんの気持ちに付け込んで、接近。
里恵さんは、新しい恋人が出来たことで夫との離婚に踏み切ったものの、今度は、「別れさせ屋」の桑原被告の方が彼女を本気で好きになってしまい、離婚成立後も、自分の身分を偽って里恵さんと交際を続けていたといいます。
しかし、今年の三月、里恵さんは、桑原被告が「別れさせ屋」であることを知り、また、妻がいることも知って、彼との交際を断とうとしたところ、既に、「別れさせ屋」の探偵会社を解雇されていた桑原被告によって、東京都中野区の里恵さんの自宅マンションで、絞殺されたのでした。
こうした事件が起きたこともあり、さらに、着手金が数十万円から百万円と高額なうえに、成功率も低いということもあり、依頼料が払えずに途中で依頼を取り消す客も多いといいます。
国民生活センターには、「別れさせ屋に着手金を支払ったのに何もしてくれない」と、いう相談が寄せられていることもあり、警視庁は、「(依頼者からの)苦情が多い業者には、報告を求め、立ち入り検査や指導をする。業法違反があれば厳正に対処する」と、説明し、探偵会社などで作る日本調査業協会も、「別れさせ行為は公序良俗に反する」と、自主規制を促しているという話です。
それにしても、こんな職業が商売として成り立っていたということが不思議でなりません。
不倫関係で、「奥さんと彼を別れさせて」などと頼む女性の心理は、判らなくもないですが、しかし、奥さんと別れるような男性は、たぶん、数年もしないうちに、その女性とも別れると思うのです。つまり、それが、そういう男性の癖なのですから。
わたしの家の近所にも、奥さんを離婚させてご主人と一緒になった女性がいますが、そういう女性がご主人の浮気癖を、近所の奥さま仲間にくどいても、奥さま仲間たちは、「あんただって、前の奥さんから旦那を奪ったんだから、浮気されても当然じゃない。大目にみてやりなさいよ」と、素知らぬ顔で笑われてしまうようです。
不倫の代償は、大きいものだと思いますよ。(爆)
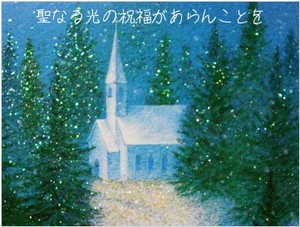
続きを読む
タグ :野球とベースボール
年越し派遣村民のその後・・・・・293
2009年12月21日
~ 今 日 の 雑 感 ~
年越し派遣村民のその後
NHKのクローズアップ現代で、昨年末の「年越し派遣村」で、ボランティアの炊き出しをもらう生活を余儀なくされていた人たちが、一年を経て、どのような暮しをしているかを取材した番組を放送した。
 49歳の男性は、17年間フォークリフトの専門職を続けてきたが、会社の業績の悪化で職を失い、日雇いの仕事を転々としたが、ついに、この不況でその日雇いの仕事もなくなり、昨年、年越し派遣村で年末年始を迎えることとなってしまった。
49歳の男性は、17年間フォークリフトの専門職を続けてきたが、会社の業績の悪化で職を失い、日雇いの仕事を転々としたが、ついに、この不況でその日雇いの仕事もなくなり、昨年、年越し派遣村で年末年始を迎えることとなってしまった。そして、その後、生活保護を受けながら、アパートにも住むことが出来、再就職のクチを探すため、50件もの会社を回り、面接も受けたが、すべてが、不採用の返事であったという。
その理由の一つに、男性が、派遣社員ではなく、正規雇用を望んでいるということがある。派遣は、いつまた離職という問題に直面するか判らないため、怖くて受け入れられないのだというのだ。しかも、職を得れば、これまでの生活保護が打ち切られてしまう。派遣社員を受け入れ、また、解雇という時になって、再び、生活保護が受けられる保証はないというのである。
さらに、そのほかにも、男性がこだわるものは、やはり、これまでの17年間で培ったフォークリフトの技術を生かした職に就きたいという願いなのである。
そんな折、男性に恰好ともいうべきフォークリフト操作の正社員の求人情報が舞い込んだ。
男性は、即座に、面接を受けたが、相手の会社の求人が、最初は正社員募集であったのが、面接後は、派遣ならば雇用するという物に変わってしまったのだという。
男性は、熟慮の末、この会社の申し出を断わった。
つまり、このような、雇用する側と、職を求める側との希望がかならずしも一致しないというミスマッチが多く、派遣村の元村民たちの就職がうまく運んでいないという現状が浮き彫りになっていると、番組は説明していた。
この男性は、それから、今度は手に職を付けようと、就職支援のための職業訓練校への入学を希望したのだが、やりたい職業訓練は、既に定員オーバーで、入学はかなわなかった。
では、こういう男性のようなケースは、どうしたら正社員としての就職が出来るのだろうか?
それは、あくまでも自分の希望の職種を押し通すのではなく、発想を転換させて、まったく新しい分野の職を見つけることだというのである。
しかし、これまでの年功序列で長年同じ会社へ勤めることが立派なことで、また、それが男としては当然の進路だと思い込まされて来た日本の男性たちの頭を、派遣や、別の職種へ切り替えさせるというのは、正に至難の業であるというのである。
かつて、国鉄からJRになった時にも、再雇用からあぶれた男性社員たちが、どうしても、元の運転士や車掌に復帰しなければ承知しないと、再就職先として会社が用意したパン屋さんや飲食店などの求人を蹴って、JRを相手に再雇用を迫り続け、ついに定年を迎えてしまったように、どうしても、過去の仕事への執着を捨てきれないというのが、就職ミスマッチの最大の要因ではないかということであった。
これを見る限り、彼らは、本当に背に腹は代えられないという状況ではないのではないかと、戦後の食糧難を死に物狂いで生きて来た、わたしの父親たち世代は、感じるようである。
父親たちの時代は、職にありつければ、何でも構わないという究極に切羽詰まった時代であったから、皆、不本意な職についても文句一つ言わずに勤め上げたのだという。
そういう意味からすると、確かに、不況で失業者が急増とはいっても、何処まで額面通りに受け取ってよいものやら判らないというのが今の失業率なのではないかと、思うのである。
この番組を観ていて、この49歳の男性が、いつまでもフォークリフトのオペレーターにこだわらず、介護の分野などにも目を向けてくれたなら、どんなにか社会のためにもなるのではなかろうかと、考えた次第である。 続きを読む
タグ :Tさんのクリスマスカード
何となくのボヤキ…Ⅲ・・・・・292
2009年12月20日
~ 今 日 の 雑 感 ~
何となくのボヤキ・・・Ⅲ
B型(ことに女性)という血液型は、どうしてこうもトラブルを起こすのであろうか?
一時間前に言ったことと、今とでは、まったく違うことを言っているのに、本人は、「そんなこと言ったかしら?」と、言うような態度なのだ。記憶力が鈍いのか、それとも、自分の言葉に責任などないと思っているのか、信頼度の低さといったら、そのほかの血液型の比ではない。
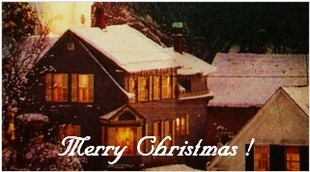
しかし、当人にとってみれば、「わたしは、自分の心に忠実に生きているだけよ」などと、ご都合主義もいいところの屁理屈をこねる。
「明日、夕食を一緒に食べない?近所のレストランを予約しておくから、付き合ってよ」
B型人間が誘ってきても、決して、その手に乗ってはいけない。その言葉を信じて、待っていたとしても、おそらく、その通りには絶対にことは運ばないのだから。
翌日になれば、すっかりと気が変わり、
「レストランの予約?そんなこと面倒くさいからしなかったわ。それよりも、これから、ラーメン食べに行かない?おいしいラーメン屋さん見つけたから」
などと言い出すのが関の山である。しょうがないと、諦めて、ラーメン屋行きを承知しても、自動車でその場所へ向かう間に、今度は、
「あっ、そうだ、テレビの録画し忘れたから、もう一度家へ戻ってもいい?」
なんてことになり、いったん家へ戻ると、
「ねえ、もう、外へ出るのやめない?あたしが夕飯作るから、食べて行ってよ」
なんてことになってしまうほどの、気まぐれな行き当たりばったりの気分屋が多いのである。そんなことを誰にでもしてしまうものだから、B型の周りからはいつしか友人がいなくるのだ。
しかも、昨日は笑顔で付き合ってくれたので、翌日もそのつもりで会いに行くと、「何で来たんだよ!帰れよ!」なんてことになってしまうので、それまで付き合いのあった者たちも、腹を立てて呆れかえり、皆離れて行ってしまうのだ。
「どうして、わたしは、友達は出来ないのだろう?あんなに親切にしてあげたのに、何故、みんなわたしを避けるのだろう?」
と、思うあなたは、そういう顰蹙をこれまで周囲に思う存分まき散らしてきたに違いない。そして、友人だけではなく、家族にも見捨てられ、最後は一人ぼっちになるのが相場と決まっている。
B型人間のあなた、世の中から総スカンを食らわされないうちに、自分の欠点には早く気付いた方がいいですよ。

最近、冤罪事件のやり直し裁判がやたらに増えて来た。
それだけ、昔の警察も検察も裁判官も、いい加減だったということなのだろうな。警察は、とにかく誰でもいいから犯人らしき人間を逮捕して、自白させればメンツが保ち、検察は、警察の仕事をうのみにして、裁判官は、自分で考えることなくマニュアル通りの判決を下す。
そんなずさんなやり方で、これまで犯人は作られて来ていたのかと思うと、そら恐ろしい気がする。
ということは、結果的に、何人もの真犯人が世間に野放し状態だったという訳だ。間違えて犯人にでっち上げられ、死刑になった人たちも多いのだろう。
犯罪者の検挙率が高いと世界に自慢していた日本警察が、実は犯人をねつ造していたのだとしたら、国民としても恥ずかしい限りである。
わたしは、まったくの一般庶民の第三者に事件に関してのいきさつを訊ねる警察官のしゃべり方を聞いたことがあるが、どうして、彼らは、犯人でもない協力者に対してまで、あのような無作法な言葉遣いをするのかが、気になった。
高圧的な上から目線の見下し口調で、いったい何様のつもりかと、言いたくなる。あのような敬語も使うことのない質問の仕方をすれば、腹立たしさの方が先に立ち、もしも、重要な何かを知っていても、訊かれた方は教える気になどなれないだろう。
冤罪は、こういう初歩的な言葉のやりとりという段階からも生まれるのではないだろうか?
脅しで屈服させるような原始的なやり方では、真実を見つけることは出来ないと思うのであるが、まさか、真実よりも成績の方が大事だなどと考えている訳ではないでしょうね・・・・?
 続きを読む
続きを読む女性は、なぜ長生きなのか?…・291
2009年12月19日
~ 今 日 の 雑 感 ~
女性は、何故長生きなのか?
*** これは、zukyさんへのコメントのレスに書いたものを、少し肉付けした記事です。

女性が男性よりも何故、平均寿命が長いのか?
もちろん、生物学的に考えれば、ホルモンの加減とか、内臓の機能とか、身体の大きさとか、まあ、色々と理由はあるのでしょうが、素人的発想からいわせて頂ければ、以下のような理由もあり得るのではないかと、考えます。
これは、わたしの推測なのですが、女性は、一か月のうちのほぼ二週間が、(男性を標準的な人間のレベルとすると)ほとんど活動を停止している状態になるためではないかと思います。
確かに、普通に息をして生活もしていますが、月経前症候群で約三日、その後生理で一週間、長い人では十日も、苦痛や煩わしさとも戦い、しかも、水泳なども出来ませんし、激しいスポーツも出来ません。中には、生理のたびに入院するという症状の重い人もいます。
それが、早い人では10歳ぐらいから始まるのです。男性よりも長生きをしたとしても、一年365日フル稼働が可能な男性が80歳まで生きるとして、女性が90歳まで生きても、活動停止中の期間を差っ引けば、決して長生きだということにはならないと思います。
しかも、若くて何でも出来る体力がある時は、この苦痛や出産で思うように自由が得られず、老人になってからどれほど時間があっても、若い時のような楽しみは、絶対に取り戻せやしません。
ですから、女性にも男性と同じような働きや遊びがしたいと思っても、出来ない現実がある限り、本当の男女平等ではないと思うのです。
そんな、女性の大変さを理解しない男性たちは、平気で「女はダメだ。使い物にならない」などと、陰で笑っているのです。 でも、考えて見て下さい。
もしも、この世の中が、女性の活動に合わせて機能するようになれば、男性だって住みやすく暮らしやすい社会になると思うのですけれどね。
男性は、これまで、男性が働くための最高難度のレベルの社会を築き上げ、体力や気力に物を言わせ、女性の存在を踏み台にして、もしくは、そんな存在が世の中にあることすらも気付かずに、走り続けてきたのが、現在の社会です。
でも、この社会の中で、男性の方たちは、本当に生きやすいと思いますか?
とても、そうは思っていないでしょうね。だからこそ、日本の年間の自殺者が三万人(男性が多い)などということになるのです。
この男性中心の社会ルールを見直し、女性の視点で作り直したとすれば、かなり、世の中は楽に生活できるようになるのではないでしょうか?もちろん、そのためには、他の国との技術開発競争に後れをとることは否めません。
しかし、それで、過労死や、うつ病や、事故、自殺が減れば、その方がいいのではないでしょうか?
こんな話があります。
ある文房具用品の会社が、ホチキスの新製品を作ることになりました。男性社員たちは、少し大きめのがっしりとしたタイプのホチキスを作りました。確かに、このホチキスは力も強く、かなり分厚い紙も一発で綴じることが出来ます。
一方、女性社員たちは、小さな女性の手の中にも納まるような、小ぶりでまるまるとした可愛いホチキスを開発し、色もパステルカラーを基調にした三色に決めました。
この二つのホチキスを、それとなくオフィスに置いておいたところ、頻繁に使われたのは、女性たちが開発したホチキスだったのです。しかも、ごつくて力のあるホチキスを開発した男性たちまでもが、その女性たちが作った可愛いホチキスを使い始めたのだそうです。
そして、電化製品も、家具も、キッチン用品も、食器も、歯ブラシも、自動車のデザインでさえ、女性用に開発されたものの方が、基本的に誰にも扱いやすいのです。
つまり、世の中の仕組みは、弱者に合わせた方がより暮らしやすくなるということに、これからの時代は気付く必要があるのではないでしょうか?
極端な話、将来クローン技術が発達していけば、生物学的な男性の役割の意味は、かなり狭められていくものと思います。事実、世間では、既に「草食系男子」なるものが存在し始め、特別、結婚などしなくても生きていける男女が増えて来ているのです。
自分の生活を大切にして、他人には必要以上に干渉しない。今後、少子化が進めば、この傾向はさらに顕著になると思います。男性の女性化は、もう、始まっているのかもしれません。
これからは、おそらく男性も、子供のために稼がねばならないというプレッシャーから解放されて、より長生きする世の中になるのかも知れませんね。
そうなると、ますます日本は、ご長寿大国になっていくことでしょう。
 続きを読む
続きを読むタグ :タイガー無期限出場停止
奇跡の起きる場所・・・・・290
2009年12月18日
~ 今 日 の 雑 感 ~
奇跡の起きる場所
子供と、お年寄りと、障害者が共に暮らす「共生型施設」が、今、日本中で増えているそうである。
そんな「共生施設」が起こしている数々の奇跡のような現象を、NHKの「クローズアップ現代」ではリポートしていた。
ある共生型施設では、産まれて間もなく母親が病気になり、その施設に預けられた三歳の男の子の存在が、ちょうど同じ頃、その施設に入居した高齢男性の認知症を改善させているという事実もあるのだという。
その高齢男性は、一人でいる時は、足腰も満足に動かすことができず、言葉もあまりに発することがないのに、その男の子が施設へ来ると、途端に、元気になり、まるで、その子の本当のおじいちゃんのように可愛がるのである。
「おじいちゃん、あそぼ」
男の子が誘うと、一人で満足に立つことが出来ない男性も、「よしよし----」と、笑いながら立ちあがり、施設のスタッフの人が、「〇〇君の鼻をかんでやって」と、男性にティッシュペーパーを渡すと、その弱い足で、階段を上り、二階で遊んでいる男の子のところまで行き、鼻を拭いてあげるのである。
男の子も嬉しそうに、おじいちゃんに顔をすりつけるようにしてニコニコ笑っている。
正に、奇跡のような光景だと、これを見た専門家も驚いていた。
また、別の共生型施設では、八十代の認知症の女性が、どうしても施設の洗濯機の使い方が判らず、ある男性の部屋まで行き、教えて欲しいと頼むと、出てきたのは、五十代の統合失調症の男性で、すぐに使い方を教えてやる。
八十代の女性は、男性のことを、「何か困ると、すぐにお願いしちゃうの」と、微笑んでいた。
さらに、別の施設では、自宅で転んだ拍子に頭をぶつけ、脳に傷を負って高度機能障害となり、感情のコントロールが出来なくなってしまった五十代の男性が、そこのお年寄りたちの前では、決して感情の起伏を見せず、まるで、一般のスタッフと同じようにお年寄りたちの面倒を見ているのである。
この男性のことを十年診てきているという医師は、この劇的な変化に対し、「介護される側にいた時は感じられなかった、責任感とかやりがいといったものが、大きく影響して回復を手伝っているのではないか」と、話していた。
人間には誰しも、本能的に、「人のために役に立ちたい」「何かをしてあげたことに対して、ありがとうと言ってもらいたい」という気持ちが大きく働いているものだという。それは、どれほど自分の体力的や気力が衰えているとしても、必ず備わっている欲求なのだそうである。
わたしも以前ブログにこれに似たことを書いたが、やはり、人は、人のために尽くすことで自分の存在意味を確認しているのではないだろうかと、思われるのである。
そういう自分の価値を確かめるためにも、社会の中で常に介護を受ける立場の人たちも、この「共生施設」の中では、しっかりとした役割を果たす存在であり続けられることが、このようなささやかな「奇跡」を生みだす原動力になっているものではないかと考えるのである。 続きを読む





