雪の夢を見た時は・・・
2011年12月16日
雪の夢を見た時は・・・

何だか、とんでもない吹雪になりましたね。
午後三時ごろまでは、風が冷たいくらいだったのですが、夕方頃からいきなりの吹雪です。
慌てて、家中の窓に寒さよけのビニールシートを貼りました。
では、こんな雪の夢を見た時は、そこにどんな意味が隠れているのでしょうか?
雪は、純粋、潔白、幸運などの象徴とされるものですから、雪の夢は、良いものとされることが多いそうです。
しかし、その降り方や状態によっては、孤独、寂しさなどを表わすこともあるので、雪の夢を見た時は、その雪景色がどのような状況にあったかを覚えておくといいそうです。
まず、単純に、雪がしんしんと降っている夢は、幸運が舞い込む印と捉えてよいようです。
特に、大雪の夢は、運が開けたり良いことが起きる前兆でもあるとか。
また、雪崩の夢も、思いがけないお金が転がり込んで来る暗示ともいわれます。
そして、雪が吹きだまっているような夢は、これもまた幸運に恵まれる予感だといわれるそうです。
ところが、大雪に埋もれて身動きが取れなくなってしまうような夢は、病気の兆しともいわれ、体調管理に十分気を付けた方がよいそうで、雪の中を薄着のまま寒さに凍えて歩いているような夢も、運勢の下降が予感されるとのことです。
さらに、猛吹雪の中を必死で歩いているような夢を見た場合は、今後、仕事やプライベートで何かしら困難な出来事が起きるかもしれないという暗示だそうで、とにかく、その逆境に立ち向かう勇気を持ちなさいという忠告と捉えた方が良いそうです。
ただただ、雪が降り積もるだけの情景は、あなたの中に、人に相談できないような心配事があるのかも・・・。
でも、新雪が朝日に輝いているようなシーンが出てきた時は、困難が克服され、未来に希望があふれる証しだともいわれます。
硬く凍りついたような雪面が夢に出てきた時は、恋人関係や夫婦関係に何かしらのトラブルが起き、あなた自身が心を閉ざしている可能性も・・・。
時間をかけてじっくり相手と話し合う必要があるのかもしれません。
続きを読む
我が子がイジメに遭ったら・・・
2011年12月15日
我が子がイジメに遭ったら・・・

ヤフーの知恵袋を読んでいたら、
「小学三年生の我が子が、クラス替えでこれまで仲の良かった友人たちのクラスではなく、別のクラスへ振り分けられたことが原因で、クラスメートから嫌がらせを受けるようになり、学校へ行きたくないと言い出した。子供は、どちらかといえば頑固な方で、クラス替えの後も、元の友人たちとばかり遊んでいたのも理由なのか、『臭い』と言われたり、無視されるなどのイジメに遭っているようなので、親としても腹が立ち、相手の子供の家へ怒鳴り込んでやろうとも思う。学級担任に相談しようにも、担任の性格からしてことを大問題にしてしまいそうなので、それは避けたい。どうしたら、クラスメートたちのイジメをやめさせることが出来るのか、教えて欲しい」
と、いう切実な投稿があった。
まだ、小学生ぐらいの子供に中には、本当に気心が知れた相手としか口をきかないという者も少なくない。
環境の変化にうまくついていけない子供もいて、ようやく保育園や幼稚園から小学生となったことに適応し始めた頃に、再びクラス替えでは、自分の身の置き場を見失ってしまうことも多々あるわけだ。
おそらく、この子供さんも、そういう性格なのだろうと思う。
しかし、他の順応性が高い子供たちの目から見れば、いつまで経っても前の友だちとばかり遊んでいる「変な子」ということになるのだろう。
そこで、自分たちとは相容れないその子供を、「臭い」などの言葉で敬遠し始めるというわけだ。
だから、その子供さんが本当に臭いわけではない。「臭い」「汚い」は、要するに、自分たちとは違う人間だと差別するための子供なりに発明した蔑視用語なのである。
しかし、この親御さんは、我が子のイジメを学級担任に話すことは避けたいと考えている。
出来れば、学校側の耳に入らないうちに解決したいのが本音のようだ。
とはいえ、回答者たちの投稿にもあったように、イジメている相手の子供の家へ怒鳴り込んでは、大事にならないはずがない。
となると、解決の方法は、やはり第三者の介入しかないように思う。
イジメについての講演を専門家に依頼し、クラス全員かもしくは学年全員を前に、イジメが如何にバカげたことかを語ってもらうという手もあるように考える。
海外の高校では、イジメ対策の一環として、クラスを便宜上イジメる側とイジメられ側に分けて教師がイジメる側ばかりをえこひいきするという学習指導をしているところもあると聞く。
そして、その際、イジメられる側に、いつもイジメに加担している子供たちを入れるのだという。
そして、イジメに遭うということが如何に辛いことかを認識させるのだそうだ。
日本の学校では、こうした指導はおそらく行き過ぎだと教育委員会も簡単には許可しないと思うのだが、こうした学習指導方法を参考に、第三者の外部講演者になら、もう少しゆるいイジメシミュレーションが可能なのではないかと思う。
たとえば、その子供さんを「臭い」と言ったいじめっ子のことを、第三者からわざと「きみ、臭いね」と言ってもらい、反対にいじめられている子供さんの方を、「きみ、とてもいい匂いがするね。お母さんがいつも清潔を考えてお洗濯してくれているからだね」と、言ってもらうなど、クラス内に思考の逆転を起こすという方法もあるわけだ。
自分たちの感性が間違っている場合もあると、子供たちに客観視させることで、周囲の見る目を一瞬にして変化させることも時には可能なのだ。
イジメを学校やPTAなどの小さな枠内で考えるだけではなく、時には、第三者の力も借りることで、新しい解決策への道も見えて来るのではないかと、素人ながら考える次第である。
続きを読む
自殺防止に、理容師が一役
2011年12月14日
自殺防止に、理容師が一役

長野市の理容師らで作る県理容生活衛生同業組合長野支部が、自殺予防のための講習会を「もんぜんぷら座」で開催したという新聞記事を読んだ。
理容師は、お客さんと一対一で会話をする機会が多い職業のため、お客さんの悩みや愚痴の聞き役になることも多いという。
そうしたことで、理容院が少しでもお客さんの心のはけ口となり、自殺願望を抑止する役割を担うことが出来るはずだという意図で、初めて企画された講習会だという。
確かに、年末には、毎年自殺者が増えるという統計もあり、精神科のある病院が悩みや寂しさから自殺願望を懐く人たちの主な駆け込み寺になることもしばしばだそうだ。
しかし、こうした自殺問題については、精神科医だけが取り組めばいいことではなく、自殺願望予備軍といわれるような、まだ救えるところにいる身近な人たちの悩みを気軽に聞いてくれる存在が、実はとても重要なのだという。
自殺を考え始めた人は、必ず、周囲の人たちにそのサインを出しているともいわれるが、ほとんどの人たちは、日々の生活の忙しさに追われて、それを見逃しているのだそうだ。
サインは、「ねえ、ちょっと、話を聞いてくれない?」などという簡単なものが大半で、こと改まって相談を持ちかけるという場合の方が珍しいともいわれる。
それには、世間話の延長で話を聞くことができる理容師や美容師といった職業が、もっともそうしたサインを汲みとりやすいのだろう。
これからは、理容師や美容師の人たちも、お客さんの悩み相談係として傾聴の勉強をする必要があるのかもしれない。
続きを読む
血圧計が壊れた
2011年12月13日
血圧計が壊れた

今日、ついに、血圧計が壊れました。
いや、この夏あたりからしょっちゅうエラーが出るので、おかしいとは思っていたのですが、それでも、何とか測れていたので使い続けていたのです。
ところが、今日の夕方、ついに----。
何処かから空気漏れしているような音がして、腕帯がまったくふくらまなくなってしまいました。
こうなると、修理に出さねばなりません。
確か、一年の保証期間があったはずだから、購入した家電量販店へ行けば、無料で修理や取り換えが出来るはずだと思い、慌てて以前のレシートを捜し出しました。
そして、購入日を見てみたところ、なんと、
2010年12月17日----!!

あと、4日(今日を入れれば5日だけれど)で切れるところでした。
一応、お店へ電話して確認すると、
「今なら、無料で修理できますよ~」
の返事。
善は急げと、そのまま、血圧計を箱に詰めて保証書と一緒に店舗へ持ち込みました。
すると、対応に出てきた女性スタッフが、その血圧計を箱から取り出すや、自分の腕に腕帯を巻いて操作。
「あ~~、やっぱり、何処かから空気が漏れているみたいですね」
壊れていることを確認してから、
「では、修理が出来しだい、お電話さし上げます」
と、約束。
これで、しばらくは、血圧測定が我が家では出来なくなりました。
別に乱暴に扱った訳ではないのですが、いや、むしろ、かなり丁寧な使い方をしていた方だと思います。
でも、機械って、案外容易く故障してしまうものなんですね~。
 続きを読む
続きを読む小、中学生のための剣道 昇級、昇段試験のコツ
2011年12月12日
小、中学生のための剣道
昇級、昇段試験のコツ
昇級、昇段試験のコツ
あくまでも、私見ですので、あしからず。
小学生や中学生の剣道は、とにかく『元気』が一番!
昇級試験や昇段試験の際も、礼儀と姿勢がしっかり出来ていれば、あとは勝つことよりも元気いっぱい果敢に打ち込むことが大切だと思います。
実技は、ほんの一分足らずの間にその審査を行ないます。
単純計算でも、面を打ち込む回数として、15本も打ち込めれば御の字ですよね。
そのわずかな時間の中で、間合いを考えて一本を取ることに集中するのは、大人でも至難の業です。
それならば、とにかく声を出して攻める!
前へ前へと進み、相手にぶつかることも厭わない勇気を出すことが先決です。
審査官たちも、子供に多くは望みません。
のびのびと全力投球こそが、好印象を与えるのではないでしょうか。
早い話が、大人の剣道をするな。子供の剣道をしろ----と、いうことですね。
では、健闘を祈ります。
元気いっぱい、頑張りましょう!

因みに、小手の臭いを防止するには、しっかりと手洗いをした後で剣道用の手袋をはめた上から小手をつけます。
これだけでも、かなり臭いは防げるはずです。
続きを読む
昨日の記事の続き
2011年12月12日
昨日の記事の続き

では、もしも「わたしって、~だから」と、自らのコンプレックスを連発する女性が本気でそう悩んでいるのだとしたら、それはどういうところから推察できるのでしょうか?
それは、その女性が、その「~~だから」の言葉だけで終わらせず、その後にもう一言付け加えているか否かで判るのだそうです。
つまり、
「わたしって、ブスだから。もっと、綺麗になる方法、教えてくれない?」
とか、
「わたしって、勉強不足なところがあるから、間違っていたら指摘してね」
と、いうような、相手に教えを請う言葉が続いているかどうかが、本気か否かの見極めには必要な点なのだそうです。
本気で自分の欠点に気付いている人は、欠点をそのまま放りっぱなしにはしたくないと思うものですよね。
ですから、自然と向上心が出て、そのための努力を惜しまなくなるわけです。
よって、「わたしって、バカだから・・・」だけで、その後に付け加える一言もない場合は、「でも、バカでもいいの。人から説教されるなんて、ウザいだけよ」と、開き直ってしまっているか、逆に、「それは口だけよ。本当のわたしは、バカじゃないもん」と、思っているかのいずれかなのです。
因みに、こういう反応しか見せられない人は、根が子供っぽい人だともいえるのだとか・・・。
褒められたら、褒められたことへのお礼は言っても、褒めてくれた相手への褒め返しが出来ない人も、また、子供っぽい思考の人だといいます。
たとえば、
「あなた、本当にいつも綺麗で羨ましいわ」
と、言われたとしましょう。
これに対して、
「そう?そんな風に言ってくれるなんて、お世辞でも、うれしいわ」
だけではなく、もう一言、
「あなただって、ファッションセンス抜群よね。いつもお手本にさせてもらっているのよ」
くらいを付け加えるだけでも、大人の会話が成り立つというものです。
でも、その際気を付けなくてはならないことは、相手にそれが単なる社交辞令だという誤解を与えないような言い方をすることです。
それには、日々の会話を浮ついた口調ばかりで済まさないことが肝心です。
会話の中に真意が見えないと、他人は、あなたの言葉の半分も信用してはくれなくなりますから・・・ね。

続きを読む
開き直りの常套句
2011年12月11日
開き直りの常套句

ヤフー知恵袋の質問に、「わたしって、ブスだから」というように、「~だから」を連発する人がいて、イライラするという投稿がありました。
確かに、こういう口癖の人はいますよね。
「わたしって、バカだから・・・」「わたしって、ドジだから・・・」
そんな言い方をすることで、自分が失敗したり物事を成し遂げられなかった時の世間の評価に対して、自己弁護のための予防線をはろうとしているわけです。
しかし、こういう人は、決して本心から自分のことをブスだとか、頭が悪いと思っているわけではありません。
むしろ、周囲は自分をそんな風に評価はしていないだろうと、高をくくっているからこそ、こうした軽口を叩くのです。
いつもテストで100点を取るほど頭の良い子供に限って、「テスト、ぜんぜんダメだった」とか、「勉強しなかったからな・・・」などというものですよね。
そういう子供ほど、内心は自信満々なことが多いものです。
あなたの周りに、「わたし、~だから」という開き直りの常套句を良く使う人がいたら、本心ではない可能性が大だと思っても間違いはないようです。
でも、そういう口癖の人に限って、実は、本当に残念な人の場合があるんですけれど・・・ね。
つまり、人は、自慢したいことがあると、わざと逆のことを口に出すことがよくあるのです。
「わたしって、ホント、バカよね」と、いう女性には、たいていの人は、「そんなことないわよ。あなた賢いじゃない」と、女性を擁護する声をかけるものですし、「わたしって、ブスだから」と、言われれば、「そんなことないわ。あなた、可愛いわよ」と、否定するのが普通です。
そういう厄介な女性は、その褒め言葉を待っているわけです。
正に、逆こそが真実----と、いう考え方からすると、何の前提もなくいきなり、「自分には理解ある大勢の仲間がいて幸せだ」というようなことを言いだした人には要注意です。
本心は、往々にして反対の意味の場合があるのですから。
続きを読む
体型から性格が判る
2011年12月08日
体型から性格が判る

体型と性格は、あまり関係ないと考えがちですが、やはり、ある程度の性格は体型で判断できるのだそうです。
★ 丸くてぽっちゃり型の人は、社交性もあり明るく楽しいタイプの人が多いですね。
また、こういう人は、親切で、積極的な温かみのある性格だともいわれます。
しかし、感情の起伏が大きくて、ものすごく喜んだかと思うと、突然、ささいなことで怒り出したりもします。
大したことでもないのにいきなり泣き出したり、落ち込んだりするなど、予測不能な感情の変化を見せるのも、こうした体型の人の特徴だそうです。
では、こういう体型の人との話は、どうやって進めればいいのでしょうか?
それは、話をする時、最初からテーマを一つに絞って、短時間で結論を出すような会話をすることです。
同じ話題に時間を取られたり、いくつもの話題を一気に持ち出すと、情緒的にややムラがあるため、途中で飽きてしまうこともしばしばです。
★ 次に、痩せ型の人ですが、基本的には生真面目で神経質タイプの人が多いようです。
自分の殻に閉じこもりがちで、社交性はあまりありません。
ちょっとした相手の言葉にも敏感に反応してしまうデリケートな面があるため、何かを決断するまでに、かなりの時間がかかることも・・・。
とはいえ、逆に相手の気持ちには無頓着で、「空気が読めない人」と、思われることがあるのも、このタイプだそうです。
こういう人と付き合う際は、ぽっちゃり型の人とは逆に焦りは禁物。時間をかけながらゆっくりとお互いの理解を深めて行くのが最良の手段だそうです。
★ では、筋肉質で骨太のスポーツマンタイプの体型の人は、どんな性格なのでしょうか?
そういう人は、几帳面でルールを重んじる集中力に富んだ人だといえるようです。
体力にも恵まれているため、一つのことを長時間続けても平気な規律人間だといえそうです。
礼儀正しく、正義感も旺盛。実に、頼りがいのある人なのですが、なかなか頑固な一面も持ち合わせていて、一度決めたことを簡単には翻さない堅物だと思われることが少なくないようです。
ですから、こういうタイプの人と親しくなるためには、とにかく時間を守ること。そして、本当に親しくなるまでは、敬語を崩さないことだそうです。
しかし、いったん気心が知れてしまうと、呼び捨てでも許してくれる気さくさをみせるのもこの体型の人です。
続きを読む
大丈夫はダメの裏返し
2011年12月08日
大丈夫はダメの裏返し

ある実験があったそうです。
有名な歌手のコンサートやスポーツ観戦のチケットを手に入れようと長蛇の列を作るファンの人たちに、心理学者がこう訊ねたのだとか。
「チケットは、手に入ると思いますか?」
すると、前の方に並んでいる人たちは、もちろん、チケットは買えると答えたのですが、中ほどに並ぶ人たちは、
「もしかしたら、売り切れてしまうかもしれない」
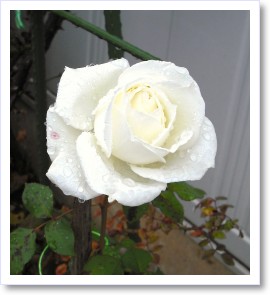
と、かなり弱気の発言が目立ったのだそうです。ところが、不思議なことに、もっと後方へ並ぶ人たちに同じ質問をしたところ、
「大丈夫!絶対に買える」
と、答えた人が多かったそうで、実に奇妙な心理の逆転現象が起きていたのだといいます。
これは、無意識のうちに自分自身が受けるかもしれないショックを和らげるための予防線をはる心理現象で、中ほどに並んでいた人たちは、本心では、「おそらくチケットは買えるだろう」と思っているのです。
「しかし、万が一買えない時も、がっかりすることはない」と、自らに言い聞かせるため、あえて「売り切れてしまうかもしれない」と、思い込もうとしていたというわけです。
これを心理学用語で、セルフ・ハンディキャッピングというのだそうです。
その反対に、ほとんどチケットは買えないと思われる後方の人たちは、自分の気持ちを奮い立たせるためにわざと、「大丈夫!」と言っていたのであって、決して本心からの発言ではなかったのです。
その心理学者は、これを「ギャンブラーの幻想」と呼び、彼らは真逆の発言で自らを縛り、現実を否定しているのだと説明します。
しかし、ある意味、これは危険な思考であり、こうした幻想を常に抱き続けることにより、人は等身大の自分を見失うことにもなり兼ねません。
「大丈夫!」とか「出来る」という言葉を安易に口に出す人は、むしろ、「ダメだ」「出来るわけがない」と、確信している人ということも往々にしてあるのです。
そのため、あまり立て続けに「大丈夫」「出来る」を連呼している人の言葉は、要注意と思ってよいようです。
これと似ているのですが、聞きもしないのに取り立てて自分の能力や人脈の広さを自慢する人も、この「ギャンブラーの幻想」にハマっている可能性があるようです。
つまり、自慢するようなことなどないという人に限って、わざと誇張した表現を使いたがる傾向にあるということのようですね。
続きを読む
靴の夢を見たら・・・
2011年12月07日
靴の夢を見たら・・・

「靴がなくなる夢を見たんですけれど、どんな意味があるのでしょうか・・・」
そんな声があったので、ちょっと調べてみました。
そんなことからも、もしも、夢の中であなたが履いて来たはずの靴が何処かへ行ってしまうようなシチュエーションがあった場合は、誰かに敵意を持たれていたり、陰で非難されているかもしれない----と、いう暗示だそうです。
つまり、あなたの気持ちの中に潜在的に反感を懐いている人がいて、
「きっと、そいつの仕業に違いない」
という思いが、夢にまで反映するからだとか。
あなたに恋人がいた場合は、その恋人があなたを裏切るのではないかという恐れが、そうした夢を見せることもあるそうです。
とはいえ、他人から敵意を持たれたり、恋人が裏切るかもしれないという原因は、むしろ、あなたの方にあることも・・・。
自らの言動を振り返り、人の気持ちを逆なでするようなことばかりをほのめかしてはいないか考えてみて下さい。
さらに、靴がボロボロだったり、片方しか見付からないような夢は、あなたの中に現状に対する不満が募っている証拠でもあります。
頑張っても、思い通りの結果が伴わないとか、必要なものが揃わないために、やりたいことがいつも中途半端になってしまう----などの苛立ちの表われだそうです。
中でも、ハイヒールの踵が折れたり、靴が壊れる夢は、さらなる危機の暗示だともいわれます。
何者かの妨害や思いがけないアクシデントにより、結婚がダメになるとか、ケガをする等の危険性も考えられるようで、より慎重な言動が求められると思われます。
また、靴屋へ行ったのだが、どうしてもお気に入りの靴が見付からない。気に入った靴があっても、値が張り過ぎて手が出ない----という夢もありますね。
これは、好きな人がいてもそのことを告白できないとか、自分には分不相応な恋愛感情を懐いているといった場合に見る夢のようです。
「もっと、積極的になりなさい」
との忠告だととらえると良いようです。
靴の夢には、思った以上に見ている人の本音が反映するようですね。
続きを読む
呆れた観光客
2011年12月06日
呆れた観光客

時々、「何が言いたいの、あなた?」と、思う人がいる。
おそらく、自分も頭の中が整理できていないのかもしれないが、それでも口に出さねば気が済まないようだ。
今日、我が家に一人の女性旅行者が飛び込んで来るなり、
「向こうの共同浴場だけれど、どうして、地元の人しか入れないの?」
と、早口でまくしたてる。
「どうしてって言われても、そういう決まりですから・・・」
こちらが答えると、その女性は実に不満そうに、
「外の汲み湯のところからは、お湯があふれているじゃない。もったいないと思わない?」
と、言うので、こちらもどう返事をしていいか判らず、
「もったいないと言われても、温泉なんてそういうものでしょう」
「あんな風に無暗にあふれさせているなら、誰が入ってもいいじゃない」
女性は、理屈にもならない不思議なことを言いだした。
だったら、その外の汲み湯のところで足でも洗えば----と、こちらも言いたくなる。
共同浴場を地元住民のみの利用としているのは、何も温泉の湯量が関係しているわけではない。浴場の広さや維持管理、犯罪防止など、もろもろの理由があってそういうことになっているのである。
そんな訳で、どうしてもその共同浴場へ入りたそうなその女性には、各旅館にも日帰りの入浴サービスがあるはずだと教えてあげた。
ところが、女性は、無料でお風呂へ入りたいそうで、外湯の鍵を貸して欲しいと言い出したのだが、それはきっぱりと断った。
こういうことをいい加減にすると、他の観光客にも示しがつかない。
女性は、何とも不満げな表情で帰って行ったが、その後、わたしが共同浴場へ行ったところ、何と、その女性が浴場から出て来たのだ。
女性は、わたしの顔を見るや仰天し、慌てて服を着て脱衣所から外へ飛び出して行った。
おそらく、地元の誰かから鍵を借りたに違いない。
本当に、呆れた話である。

続きを読む
心理テスト・クリスマスの夜
2011年12月05日
心理テスト・クリスマスの夜★
今夜は、クリスマス・イブです。
彼にクリスマス・ディナーに誘われたあなたは、ドレスアップをして予約してあるホテルの上層階のレストランへ行きました。
そこには、既に彼が待っていて、その前のテーブルには、可愛いクリスマス・ケーキともう一つの何かが置かれていました。
もしも、置かれていたら嬉しい何かを想像してみて下さい。
それは次のうちのどれですか?
A 大きな丸鳥のロースト。
B リボンがかけられた大きなプレゼントの箱
C 大きなバラの花束。
D リボンがかけられた小さな箱
これは、あなたが彼と結婚したのちに理想とする生活を暗示する心理テストです。
Aを選んだあなたは、とにかく食べるに困らない生活が理想です。彼の出世や住まいへの希望は二の次。毎日がおいしいものであふれていれば、それで満足な結婚生活を夢見ています。
Bを選んだあなたは、結婚生活に対して高望みや分不相応な背伸びはしません。とにかく、毎日が平凡でもそこそこに生きて行ければ幸せで、プレゼントにも、高級品をもらうよりも実用的な洗剤やタオルなどの日用品をもらうことを嬉しいと感じるタイプです。大きな箱の中身は、信州の冬に重宝する安価な厚手のストールだったかもしれませんね。
Cを選んだあなたは、とにかく華やかな雰囲気に弱いタイプです。結婚生活には子供も義父母も小姑もいらない。夫婦二人だけの生活が大切で、二人がいつも見詰めあって暮らせることが一番の幸せと思っています。しかし、バラの花はいつまでも咲いてはくれません。夫婦の関係も花がしおれるように、互いに飽きが来てしまったらあっさりと終わりになる予感がします。
Dを選んだあなたは、とにかく決まりごとに対して敏感です。結婚生活もきちんと手順を踏みたい方で、面白みがないと言われても、堅実こそが美徳だと信じています。あなたは、小さな箱に入っているのは、たぶん、婚約指輪だと想像しているはずです。マニュアル通りに物事が進まないと、不安に感じるタイプだといえるでしょう。
さあ、あなたの理想の結婚生活は、どれですか?
続きを読む
心理テスト・あなたの一番好きな人
2011年12月04日
心理テスト・あなたの一番好きな人

面白い心理テストがあったので紹介します。
★ 次の項目の〇〇の中に、あなたが入れたいと思う知人や友人の名前を考えて下さい。
あなたは、金づちです。
友人たちと山へハイキングに来たあなたは、森の向こうに美しい湖を見付け、自分が泳ぎが苦手なことを忘れて、つい水の中へ飛び込んでしまいました。
案の定、足がつかない辺りまで来て、あなたは溺れてしまいます。
でも、幸いなことに、偶然、近くを通りかかった森林警備員たちがそのことに気付き、あなたを救助してくれました。
そんなあなたに向かって、友人たちが声をかけて来ました。
A 「助かってよかった!すごく心配したんだよ」と、〇〇さんが声をかけました。
B 「なんて、無茶なことをするんだ!死にたいのか!?」と、〇〇さんが怒鳴りました。
C 「きみが悪いんじゃないよ。こんなに澄んだ湖を見れば誰だって泳ぎたくなるさ」と、〇〇さんが慰めました。
D 「・・・・・」〇〇さんは、ただ黙って自分の上着を脱ぎ、あなたにかけてくれました。
これは、あなたが〇〇に入れた知人や友人のことを、本当はどう思っているのか----を、探る心理テストです。
Aの〇〇に入れた名前の人を、あなたは、嫌いだと思っています。
Bの〇〇に入れた名前の人を、あなたは、尊敬しています。
Cの〇〇に入れた名前の人を、あなたは、面倒くさく思っています。
Dの〇〇に入れた名前の人を、あなたは大好きですし、一番の友だちだと思っています。
それが、あなたの本心だそうですよ。★
リンゴのホットケーキ
2011年12月04日
リンゴのホットケーキ

リンゴをたくさん頂いたので、リンゴのホットケーキを作りました。
ホットケーキとはいっても、ホットケーキの素を使うわけではありません。
とにかく、短時間で簡単に作りたいので、材料はいたってシンプルです。
まず、リンゴ2個の皮をむきます。
皮をむいたら四つ切にして芯を取り、それを一センチほどの幅に切ります。
切ったリンゴをボールへ入れたら砂糖をまぶしておきます。
別のボールへ小麦粉、卵一個、砂糖、塩、マーガリン、牛乳、水を入れて混ぜ合わせます。
その中へ、先ほど切っておいた砂糖まぶしのリンゴを一気に投入。
混ぜ合わせたら、サラダ油をひいたフライパンへ流し込みます。
ガスは中火にしてフライパンに蓋をし、片面が焼けたら、ひっくり返してもう片面を焼きます。
ひっり返す時は、かなり重いので気を付けて。
両面が焼けて、ある程度中に火が通ったと思ったところでフライパンから皿へ取り出して、次に電子レンジのあたためで一分ほどチン。
こんな具合のリンゴのホットケーキが出来上がります。
ちょっと、こげましたが、味はまあまあイケました。
所要時間20分弱で出来る、安上がりのズクなしレシピです。
熱々のところを召し上がれ。

続きを読む
聞きわけの良い患者はダメ患者
2011年12月03日
聞きわけの良い患者はダメ患者

「聞きわけの良い患者はダメ患者」----と、いう言葉があるという。
検査や治療の際に痛みや辛さを我慢してしまう患者は、医療関係者にとっては扱いやすい患者だといえるが、医療技術そのものの向上を妨げる元になる----と、いう意味らしい。
先日放送された『DOCTORS~最強の名医~』に、
「患者に嘘をつかれては、医師は病気を治せません」
と、いう台詞があったが、劇中では、これは、母子家庭の母親が、娘に内緒で不倫相手と東南アジアへ旅行していたせいでマラリアに感染していたのだが、娘の手前、そのことを担当医に話せなかった----との設定であった。
確かに、患者が自分の病歴や生活環境、もしくは体質について、医師に事実を話さないということはある程度の治療の妨げにはなるであろう。
しかし、認知症の人や口下手の人は、診察室での決まり切った時間内にそれらのことを何処まで医師に伝え切れるかは、疑問である。
いや、普段は弁が立つ健常者でも、病気にかかったいわゆるパニック状態の時に、自分のすべての病歴や生活について洗いざらい伝えきるのは至難の業といえよう。
だから、そういう患者の症状については、それこそ医療のプロが技術を駆使して見抜く必要があるし、また、それが出来るはずなのである。
ところが、検査や治療時の肉体的精神的苦痛は、人それぞれの感じ方があり、痛みに鈍感な人もいればかなり敏感に反応してしまう人もいる。
日本人は、人前で醜態を見せることを最も恥ずべきものと考える習慣のある国民性を持っているせいで、そうした場合の辛さを我慢してしまう傾向が顕著であるという。
そうなれば、医療関係者は患者の本当の苦痛を理解しにくくなり、医療技術の進歩も滞ることになり兼ねない。
たとえば、わたしの場合など嘔吐反射が他の人よりも激しいために、胃カメラの検査が出来ないのだが、胃カメラの欠点は、口、もしくは鼻から入れた内視鏡を、胃の方向へと喉の部分で動かすせいで激しい嘔吐反射を引き起こすことにある。
つまり、喉にあたる内視鏡部分を動かさずにいれば、さほどの嘔吐反射は起きないことになるのだ。
それには、喉のところの内視鏡は固定したままで、内視鏡の先のカメラ部分だけがそこから胃の方へ伸びるように改良すればいいのではないだろうか。
早い話が、二段階に伸びる内視鏡である。
しかし、胃カメラを苦もなく飲める患者ばかりだと、そうした技術開発も出来ないわけで、一部の飲めない患者たちがいつまでも迷惑を被ることになるのである。
『DOCTORS』では、再三にわたり、主人公の相良医師が、「ぼくは、良いお医者さんになりたいだけです」と、いう。
では、良いお医者さんとはどういう医師のことを指すのか?
おそらく、ほとんどの患者は、「ケガや病気を治し、以前と同じ健康体で社会復帰させてくれるお医者さん」と、答えるだろう。
しかし、わたしなら、そこにこう付け加えたい。
診察や検査、治療の際に患者に苦痛や苦労を与えず、恥をかかせないお医者さん----であると。
続きを読む
児童虐待を見抜く目
2011年12月02日
児童虐待を見抜く目

今日、お昼のワイドショーを観ていたら、11歳の少年に日常的に暴力を振るい、食事も満足に与えていなかった31歳の同居男性が、少年に対する傷害の容疑で逮捕されたという事件を取り上げていた。
この同居男性は、少年の母親の愛人で、少年が8歳の頃から殴る蹴るの暴力を加え、今回、少年に対し肝臓破裂の重傷を負わせたことで、ようやく虐待が明るみに出て逮捕となったのだという。
近所の人は、これまでも何度か子供の悲鳴などを聞いていたにもかかわらず、母親たちの「何でもありません」の言葉を鵜呑みにし、小学校や児童相談所も、身体測定の際、少年の身体中に殴られたようなアザがあることや、体重が年齢のわりには異常に少なく、身長も低いことに気付きながら、その都度、母親や少年が、
「ご飯もちゃんと食べさせています」
「身体のアザは、ぼくが自分で転んだんです」
などとごまかす言葉を信じて、適切な対処をしなかったのだそうだ。
少年の身体には、煙草の火を押し付けられたような火傷の痕まであったというのに、結局、その言い分を良いことに、少年を救う機会を逃したのであった。
警察の事情聴取に応じた母親は、自分の知らないところで同居男性が子供に暴力をふるっていたと、話しているそうだが、つまりは、同居男性と別れることが出来ず、男性が我が子へ加える虐待を黙認していたようである。
周囲の大人たちの見て見ぬふりにより、少年は三ヶ月の重傷を負う破目になってしまったのだが、一番始めに少年の低身長や痩せすぎに気付いた小学校の担任教師が、もう少し家族内に踏み込む姿勢が取れなかったものだろうかと、ゲストコメンテーターたちも悔しがっていた。
虐待を受けている子供たちは、必ず、その事実を否定するもので、どんなにひどい親でも、子供は親が世間から非難されることを最も恐れ、親を庇うものなのである。
つまり、虐待されている子供から話を聞き出す場合は、子供が嘘をつくことを前提にして、聞き取りをするべきだと、専門家は説明する。
また、家庭内の事情を話す親も虐待を認めるわけはないので、当然ながら嘘をつくのだ。
現に、この同居男性も、逮捕前の番組インタビューに対して、
「暴力を振るったことはない。三度のご飯もちゃんと食べさせていた」
と、平然と答えているのである。
ただ、その答え方はかなり不自然で、終始口ごもりながらという様子であったが・・・。
ならば、異常に虫歯が多いとか、着衣がいつも汚れているなども含めて、子供の生活態度や健康状態に疑念をもった大人は、その虐待を見抜くためにどうすればいいのか?----と、いうことになる。
おそらく、児童虐待における第一発見者は、学校の担任教師になる確率が高いと思われるため、小、中、高校の教諭たちが虐待を見抜くプロになるための教育を、大学の教職課程を履修する際に必修科目として受講するというのが理想だと思われる。
以前聞いた話だが、家でご飯を食べさせてもらえないのではないか----との疑念を懐かせるほど痩せた子供の担任教師が、その子にそのことをそれとなく訊ねたのだという。
しかし、案の定、子供は親から食事を与えられていないことを否定した。
すると、担任教師は、放課後その子供を保健室へ呼んで、予め持参した弁当を広げると、
「今日、先生、お腹が痛くてお弁当食べられなかったんだけれど、捨てるのももったいないんで、代わりに食べてくれないかな?」
と、言ったところ、子供はその弁当をむさぼるように空にしたのだという。
そして、ようやく、家でご飯をほとんど食べさせてもらっていないことを認めたのだそうである。
結局、その子供の家は、貧しい母子家庭であったために食費を節約しなければならず、子供に満足な食事を与えられなかったということで、虐待とまではいえなかったのだそうだが、このケースのように、身近にいる大人たちのささいな気付きや敏感さが、子供たちの大切な命を救うことにもなるのである。
続きを読む
寒い日・・・
2011年12月01日
寒い日・・・

今日から師走・・・。
さすがに、寒いです。
今日も病院へ行って来たのですが、途中の橋の上の気温は2度でした。
つまり、こちらは、それ以上に寒いというわけです。
晩秋の情緒にひたっている場合ではなくなりました。
世の中はクリスマスシーズン突入で、街のあちこちにチャカチャカのイルミネーションが輝く季節ですが、あの青色発光ダイオードの青が、その寒さをさらに後押しするようで滅入ります。
出来れば冬季のイルミネーションの色は、黄色や赤系統にして欲しいと思うのですが、青いLEDライトの方が安上がりなのでしょうか?
それにしても、クリスマスツリーの飾りや壁に下げるクリスマスグッズを、最近の言い方では、スワッグとかオーナメントとかガーランドなどというそうですね。
おしゃれな横文字言葉があふれるのも、この季節の特色です。
クリスマスグッズは、見るものすべて欲しくなってしまうほど夢いっぱいの美しさですが、買ってみたところで、結局は物置の肥やしになるのが毎年のお決まりなので、最近はほとんど購入しなくなりました。
以前は、手当たり次第に買っていたものですが、今やクリスマスパーティーも過去の話ですから・・・。
人間、年をとると、イベントに傾ける情熱も衰えて来るようです。
クリスマスツリーも、後片付けを考えると、「今年は、いいか・・・」と、なるわけです。
そんなことで、せめてブログの中だけでもクリスマスっぽい雰囲気を出してみたいと思います。
続きを読む
あるエッセイを読んで・・・
2011年11月30日
あるエッセイを読んで・・・

これまで特に気にすることもなかったのだが、近頃気付いたことがある。
まあ、ど~~でもいいと言えば、ど~~でもいいことなんだけれど・・・。
新聞や雑誌に掲載されているエッセイを読むと、どうして、こういう寄稿文の筆者には、これほど贅沢な生活をしている人が多いのか----と、いうことだ。
この間は、バリ島で夫婦ともども体調を崩したというエッセイを読んだのだが、そこには、バリ島の医師や看護師の献身的な治療について感激したとの筆者の心情が記されていた。
しかし、そのエッセイを読むにつけ、初っ端から驚いたのが、まずエッセイの舞台になっているのが薄給の一般庶民にとっては夢のリゾート地のバリ島だということである。
その旅でのエピソードが、特別気取ることもなく淡々と始まっているのだ。
まるで、バリ島などこれまでも何度も訪れた隣の県へ行くような感覚で、「別に驚くことでもないでしょう」とばかりに、その文章は書かれている。
そこで足の感染症を患い、駆け込んだ現地の病院での手厚い治療ぶりに感心したということに加え、帰国後に受診した皮膚科の医師までが東南アジアのリゾート通であったという記述にも、唖然であったし、そのあまりの世間一般の感覚とのズレに戸惑いすら覚えた。
しかし、次を読み進めると、その旅行の帰りの機内で腹痛を訴えた妻を、帰宅後に近所の内科医院へ連れて行ったところ、そこの医師が、
「現地で病気になるのは自己責任」
と、言ったとの一行に、ようやくホッとした気分になれた。
筆者の妻は、診察後、「バリのお医者さんとはずいぶんな違いよね」と、愚痴ったようだが、その近所の内科医の言葉は一般的な日本人の感覚そのものであろうと思う。
おそらくその内科医にも、外国旅行へ行き遊んできた人間が胃腸炎になったところで同情の余地なし、身のせいだという気持ちがあったに相違ない。
もしも、この妻が家計を節約するあまり、つい賞味期限切れの食材を食べて腹痛になったというのなら、医師もこうした厳しいもの言いはしなかったはずである。
そして、こうも思った。
バリ島の観光協会としては、日本人観光客は大のお得意先であるから、現地の医療施設に対しても外国人観光客には丁寧に接せよとの依頼をしているのかもしれない。
帰国後にかかった内科医のきつい発言は、そんな筆者夫婦の浮かれた生活に対する戒めだったに違いない----と。
続きを読む
不適切発言の裏側
2011年11月29日
不適切発言の裏側

一川保夫防衛相は29日夜、那覇市内での記者団との懇談会で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設に関する環境影響評価書の提出時期をめぐり、不適切な発言をしていたことが分かった沖縄防衛局の田中聡局長の更迭を決めた。(ヤフーニュース)
ある心理学の本を読んでいたら、ほとんどの不適切、または勘違い発言の裏には、それを言った人の無意識の思い込みが隠れている----と、書いてあった。
たとえば、ある自治体が作った「雪国はつらつ条例」なる言葉を、つい思い込みで、「雪国はつらいよ条例」と、書いてしまった人がいたそうだ。
その人は、「雪国は寒いので、きっと冬はかなり辛いに違いない」という先入観から、そんな書き間違いをしてしまったと思われる。
ある漫画には、一人の登山者が疲れのために早く何処かで休みたいと思うあまり、「もうすぐ頂上、ガンバロー」と書かれていた立て札を、「もうすぐ頂上、バンガロー」と、読んでしまった----との爆笑シーンが描かれていた。
田中局長の失言も、不適切という表現を使ってはいるが、そもそも本当に不適切だと思っていたら決して口から出るはずのない言葉である。
この発言が事実だとしたら、おそらく、彼は、常にこうした類の話を身の周りの人たちと交わしていたのではないかと思われる。
つまり、生活の中で、そうした類の話題が日常的に行なわれていたがために、たとえ非公式の場とはいえ、無意識のうちに発せられてしまったのではないだろうか。
まったく頭にない言葉が、つい口をついて出るなどということは普通の人間心理ではほぼあり得ない。
失言の裏側には、たいていにおいて、その人自身の本音が隠れているといっていいのである。

続きを読む
他人の健康が妬ましい
2011年11月29日
他人の健康が妬ましい

「人の不幸は蜜の味」
とは言うが、自分が大病を患っている人の中には、時にこうした感情が強くなる人もいる。
知り合いの高齢男性は、重大な病気を抱えているせいか、友人が大病で入院したなどと聞くと、途端に元気になり、
「あいつは、もう、長くないみたいだな」
などということを平気で口に出す。
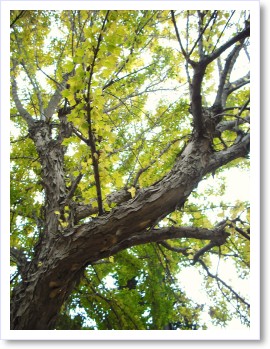
しかし、その入院した人が病気が回復してしまうと、その悔しがりようではないのだ。
また、ある男性は、自分が病気にかかると、友人たちも同じ病気にかかってくれないかと、日々望むようになったという。
そして、その男性の友人の一人が医師から検査をした方がいいと言われただけで、
「あいつは、おれと同じ病気だそうだ」
と、早合点して周囲に言いふらした。
ところが、検査結果は異常なし。
「まったく、脅かされたよ」
と、苦笑いする友人に向かって、
「そんなはずはない。絶対に異常個所があるはずだ」
と、無理やり疑ってみせ、不安感をあおり立てたのだそうだ。
そういう他人の不幸を望む傾向は、どうも高齢者に多いようだ。
若いうちは、病気になっても治る見込みがあるので健康な人をうらやむ気持ちは薄いのだが、高齢になると、完全回復の確率も必然的に下がるので、常に持病のことが頭から離れず、どうしても、同病の仲間が欲しくなるらしい。
今日、ワイドショーを観ていたら、昔、名子役と呼ばれた斉藤こず恵さんが出演していて、現在、彼女は甲状腺がんを患い、抗がん剤治療中だと話していた。
その際、斉藤さんがこんなことを言った。
「こういう病気になると、本当に気持ちを判りあえるのは、家族でも友人でも恋人でもない。同じ病気で苦しんでいる人たちなんですよ」
病気の人にとって、心から信頼し語り合えるのは、やはり、同じ病気と闘う患者同士しかいないというのである。
だから、上記の彼らもきっと、自分と同じ病に苦しむ人たちが身の回りに大勢いてくれることが安心であり、自分はまだ大丈夫だという確信のよりどころにもなるのだと思う。
病気になって心細いのは良く判る。
どうして、自分だけが・・・と、思う辛さも悔しさも当然のことだ。
だからといって、健康な人を妬むようなことは言って欲しくないし、そんな言葉を聞かされる側も快くはない。
どんなに人を妬んでも、現実の自分から逃げ出すことは出来ないのだから・・・。
病気とうまく付き合いながら、そこそこ生きていければそれでいい----そんな、ある意味前向きな諦めも悪くないのではないだろうかと、考える昨今である。
続きを読む





