違和感・・・
2013年09月08日
 違和感・・・
違和感・・・2020年の東京オリンピック開催が決定した。
昨夜は、テレビで東京招致委員のお歴々によるプレゼンテーションを観たが、あれを、「洗練されていて、素晴らしかった」と、評価する声が多いということに、やや違和感を覚えた。
そもそも日本人が外国語で話をする時、どうして腹話術人形のような奇妙な表情になってしまうのだろうか?
芝居がかっていて、何ともいえない恥ずかしさがあった。
長野冬季五輪招致の時は、それでも良かった。
日本の小さな片田舎の長野市が、西も東も判らぬまま一生懸命にオリンピックを引こうと頑張ったのだ。
心もとない英語を話そうが、レディーファーストにもたつこうが、失敗を重ねながら額に汗し、見栄も外聞もかなぐり捨てて突っ走った。
それがまた、微笑ましくさえあった。
が、東京は違う。言わば地球上にあるすべての意味において最上級レベルの巨大先進都市である。
芸術文化、産業はもとより、ファッションにおいても世界のリーダー的存在といっても過言ではない。
その東京が、福島第一原発での汚染水漏れに対して、
「状況はコントロールされている。決して東京にダメージを与えるようなことを許したりはしない」「東京は水、食物、空気についても非常に安全なレベル」「福島とは250キロ離れている」
この回答には、恐れ入った。
これでは、まるで「福島」を汚いもの扱いしているも同然の言い分である。
「福島県は、東京都とはまったく関係ない県なのです。あの県と一緒にしないでもらいたい」
そう言っているようにも聞こえた。
ある番組で一人の福島県民が、「我々は棄民(きみん・捨てられた民)のようだ」と、話していた。
今回の特別番組に出演していたタレントやアスリートなどのゲストコメンテーターたちが口々に東京のプレゼンを褒め千切る中、有森裕子さんだけが、
「物足りないところもあった」
と、答えていた。
おそらく彼女も、あまりに東京の素晴らしさばかりを強調するスピーチに、何処か不自然さを感じたのではないだろうか。
それよりも、
「今回の原発問題には、日本は国民の総力を挙げて取り組んでいる。福島は以前難しい局面を完全には払しょくしきれていないが、福島や東北被災地の子供たちも東京オリンピックを心待ちにしている。それが、彼らの未来を照らす大いなる希望の星にもなるのだ。
アスリートの皆さん、東京は最大限の努力をしてあなた方のパフォーマンスを応援する。だから、日本を怖がらないで欲しい。今の日本にはあなた方の勇気と元気がどうしても必要なのです」
ぐらいのことは、一言添えて欲しかったように思った。
続きを読む
運転中もスマホ・・・?
2013年09月07日
 運転中もスマホ・・・?
運転中もスマホ・・・?長野県内で車を運転中に携帯電話やスマホを操作する「道交法違反」の容疑で摘発されたドラーバーの人数が、ウナギ上りだそうだ。
運転中に携帯電話を使い、通話をしたり画面を操作する違反ドライバーは減少傾向なのだそうだが、今度はスマホの普及が原因で、再び摘発件数が上昇に転じたらしい。
スマホは、専用アプリを導入すれば無料通話や道路案内などさまざまな機能が使えるために、運転中も手放せないというドライバーが多いのだとか。
「運転中は、電話には出ないようにはしているのだが、友だちからのラインが入ると、どうしても読まざるを得なくなる」
と、いうドライバーも。
そういえば、知恵袋にもラインへの返事が遅れたということで、ママ友から、
「付き合い悪いよ」
と、嫌みを言われ悩んでいる主婦の投稿があった。
運転中にラインをするなどもっての外だと思うのだが、そういう常識さえもラインにのめり込んでいる利用者には通用しないらしい。
運転中の携帯やスマホの使用は、ドライバーの注意力を低下させることから画面を見るのもNGのはずだ。
返信が出来ない旨が設定されている携帯やスマホに連絡を入れると、「ただ今、運転中<(_ _)>ゴメン」のような文字が自動的に相手に送信されるようなシステムはないのだろうか?
24時間携帯やスマホに縛られているのでは、行動を監視されているのも同然である。
互いに監視し合うような文字対話は、もういい加減にしたらどうかと言いたい。
続きを読む
久々に感動!
2013年09月06日
 久々に感動!
久々に感動!昨夜の『アンビリバボー』では、長野市にある中央タクシーの感動エピソードをドラマ仕立てで放送していた。
久々にいい話だなァ・・・と思い、ちょうど録画もしてあったので、二度観してしまったほどだ。
一つめは、若い母親が、保育園に通っている娘が体調を崩しているとの園からの連絡を受け、中央タクシーで駆けつけたという話。
母親は保育園で保育士さんから娘を引き取ると、待たせていたタクシーに再び乗車し、今度は病院まで行って欲しいと頼んだのだが、何故か財布がなくなっていることに気付いた。
これでは乗車賃が払えない。
焦る母親だったが、タクシー運転手の厚意で何とか娘を受診させることが出来た。
すると、そこへ先ほどのタクシー運転手がやって来て、「財布が見付かりましたよ」と、母親に財布を手渡したのだという。
運転手は母親と娘を病院前で降ろしたのち、近くの空き地までタクシーを走らせると、そこで車内のシートまで取り外して財布が落ちていないかを確認したのだが、やはり何処にも見当たらない。
次に彼は、元来た保育園まで戻り、園庭の遊具の間に財布が落ちていることを発見したのだった。
二つめは、中央タクシーの運転手が老夫婦を助けたというエピソード。
老夫婦は羽田空港から北海道へ飛ぶ飛行機に乗るため、タクシーに乗車した。
ところが、道路が渋滞を起こしていて、とてもそのままでは飛行機の出発時間に間に合わない。
慌てた夫婦は途中でタクシーを降りると、電車で東京まで向かうことにしたのだが、駅へ入って行く夫婦の後ろ姿を見ていたタクシー運転手は何となく不安を覚えた。
そこで駅の中まで入ってみると、案の定そこには切符の買い方が分からず途方にくれる夫婦の姿が・・・。
運転手は、「自分が一緒に電車に乗って羽田まで行きますから、心配しないで下さい」と、申し出た。
「そこまでして頂いては・・・」と、恐縮する老夫婦だったが、運転手は「お客さまを目的地までお送りするのがタクシー運転手の仕事ですから・・・」と、二人を無事羽田空港まで送り届けたのだという。
そして、三つめは、大事な知人の結婚式に出席するために東京からやって来た若い母親と二歳になる息子の話。
東京の気温を頭に入れていた母親は、長野駅に到着した時、市内のあまりの寒さに驚いた。
11月とはいっても長野市には早くも雪が降り、幼い息子に薄着をさせて来てしまったことを後悔した。
そこで、母親は乗車した中央タクシーの運転手に、「子供の厚手の靴下を買いたいので、何処かのお店で停めて下さい」と、頼んだのだが、まだ早朝ということもあり、店は一軒も開いていない。
仕方なくそのまま結婚式場となっているレストランまで行き、寒がる息子とともに披露宴に出席していた。
と、そこへ式場のスタッフがやって来て、母親に紙袋を手渡した。
訳が分からないままに彼女が紙袋を開けると、中には子供用の厚手の靴下が一足入ってた。
驚く母親に、スタッフは、
「タクシーの運転手さんが、お子さんにと・・・」
と、説明。母親は、運転手に感謝しながら息子に靴下を履かせ、風邪をひかすことなく東京へ帰ることが出来たのだという。
実は、この運転手にもちょうど二歳になる子供さんがいて、とても人ごととは思えなかったので、会社へ引き返す途中に開いている洋品店を見付け、靴下を購入。
その後、式場まで戻り、スタッフにそれを託したのだった。
中央タクシーには、そんなタクシー運転手たちの「神対応」に対する利用客からのお礼状が後を絶たないという。
運転手の一人は、インタビューに答えて、「普通のことをしているだけ」と、話す。
会社側も、運転手の独自の判断で一時間ぐらいの勤務外時間を利用者のために使ったところで、そんなものは大した損ではないという姿勢だ。
それよりも大事なのは、地域の皆さんの足としての信頼を、決して損ねないことだそうである。
そのため1998年の長野冬季五輪の際も、中央タクシーだけが乗車率減も覚悟で県外客を断わり、「いつも利用して下さる地元のお客さまを優先したい」との理由から利用者を県内客のみにしぼったのだとか。
一見、中央タクシーの宣伝番組か----とも疑われそうな内容だったが、それでもここに登場した運転手たちの自発的行動は、誰もがそう容易く真似出来るものではない。
ここまで親身になって利用者のためを思えるということは、やはり運転手一人一人の人間的資質が素晴らしいからに違いないと、久しぶりに温かな気持ちに浸ることが出来た。
スタートレックと半沢直樹
2013年09月05日
 スタートレックと半沢直樹
スタートレックと半沢直樹映画『スタートレック』が公開されているとか・・・。
テレビCMで観たキャプテン・カークが若くてビックリ!

かつてのテレビ版『宇宙大作戦(再放送)』ではまってしまったわたしなんぞは、その後小説(文庫本)を買いあさり、東京スターフリートベースの隊員にまでなってしまった過去がある。(笑)
後にニュージェネレーション版(ピカード艦長バージョン)も観たが、やはり最初のシリーズには勝てなかった。
「映画になると、どういう訳か自分たちのスタートレックではなくなってしまう・・・」
と、かつて語っていたのは初代ミスター・スポック役のレナード・ニモイ氏だっただろうか。
果たして、今度の映画は旧エンタープライズ乗組員たちを満足させることが出来たのだろうか?
近頃は、アメリカ映画にも新しいヒーローを生み出すバイタリティーが衰え、スパイダーマンやスーパーマン、そしてこのスタートレックなどのリメーク版を次々打ち出すことで、古き良きアメリカへの回帰願望が見て取れるようになってきた。
そして、日本もまた同じような傾向にある。
今、巷の話題を独占しているテレビドラマ『半沢直樹』を、先日初めて観てみたが、リアリティー感も薄く、わたし的にはのめり込むほどの面白さは感じなかった。
ただ、世間ではこのドラマを「勧善懲悪の時代劇と同じ」と、見る向きもあるやに聞くが、確かに作り方が『水戸黄門』に近いものがあるように思う。
疑問と矛盾、理不尽だらけの閉塞的な世の中を「十倍返しだ!」と、スッパリ切って捨ててくれる主人公の台詞に胸のすく思いを懐く視聴者も多いのだろう。
長寿ドラマの最高峰に君臨していた『水戸黄門』が終了したために、視聴者は新しい世直しヒーローの登場を欲していたのかもしれない。
しかし、この『半沢直樹シリーズ』が新たな『水戸黄門』になれるかと問えば、それはまた別問題。
おそらく、そう容易なことではないように思われる。
続きを読む
不景気ネタ
2013年09月04日
 不景気ネタ
不景気ネタ毎度の不景気ネタだが、今日、取引のある問屋さんから驚きの不景気ネタを聞いた。
「昨年まで毎年夏になると40台以上の観光バスを連ねて小布施へ来ていたツアーが、今年は景気の不透明さから客が集まらずキャンセルになった」
と、いうのである。
同地の観光業者たちも、あまりの景気の落ち込みに驚愕の色を隠せないそうだ。
そういえば、近頃目立つ旅行者の車内泊。
道の駅にキャンピングカーや自家用車を駐車して車内泊し、旅館やホテルを利用しないという人も多いそうだ。
道の駅ならば、食べ物は売店で買えるし、水道もトイレも自由に使える。
そういう格安旅行を計画する人たちの中には、足湯のそばに車を止めて、無料で温泉気分も味わってしまおうという達人も・・・。
散歩の途中で見たのだが、そうした足湯に飼い犬連れで来るなり、犬までお湯の中へ入れるという不衛生極まりない行為を平然と行なっている人もいて、いったい何処まで図々しいのかと、開いた口がふさがらなかった。
まさか、その様子を写真に撮って、ネット上へ投稿しているのではないだろうな・・・と、疑いたくもなった。
「人出はあるが、金は落とさない」
これが今までの観光地の姿だったが、これからは、
「人も来ないし、金も落とさない」
と、いうことになるのかもしれない。
先日の新聞には、富士山が世界遺産登録されたことで、山梨県側からの登山者が激減しているという記事も載っていた。
静岡県側からの登山者が増えたことで、必然的に山梨県が割を食う破目になってしまっているらしい。
つまり、登山者の人数が爆発的に増えたわけではなく、これまで山梨県側から登っていた人たちが、世界遺産としての景観を楽しむために静岡側に移動してしまったということなのだ。
世界遺産効果で観光客が増えたと思うのは、大きな間違いのようである。
このところ、街にはほとんど観光客の影がない。
街中がやけに静かで、子供たちの声が響くこと・・・。
十年ほど前までは連日ひっきりなしに通っていた大型観光バスも、近頃はとんと見なくなった。
続きを読む
蒸し暑い日
2013年09月03日
 蒸し暑い日
蒸し暑い日今日は、とにかく蒸し暑かった。
散歩をしていても、汗がほとんど蒸発せず、ベタベタして気持ちが悪かった。
この異常気象が原因で、埼玉県ではF2クラスの竜巻が発生したという。
竜巻に壊された家々をテレビで観たが、二階部分はほぼ全壊状態。
一階部分もガラスや家具が散乱して、とても住める状態ではない。
ケガをした人も大勢いるとのことで、とにかく自治体の迅速な応急対応が求められる。
竜巻被害の理不尽で悲惨なところは、自分の家は全壊しているのに、数メートル離れた隣の家には一つも被害がないという不公平さだという。
台風や大雨、洪水などの場合は、被害が同じ地区全域に及ぶものだが、竜巻は幸運と不運をあまりに明確に分けることから、被災住民の心のケアも重要なのだそうだ。
被害に遭ったある女性は、「窓ガラスがほとんど割れてしまったので、昨夜は網戸を釘で打ちつけて休んだが、誰か入って来るのではないかという不安から、一睡もできなかった」と、語っていた。
また、ある男性も、「こんなところで夜を過ごすことは出来ないから、何処かへ避難したいのだが、家財道具や貴重品も散乱状態なので、盗まれる危険もある。自宅から目が離せない」と、困惑していた。
日本の木造住宅は竜巻には脆いし、地下室がある家など日本には稀有だ。
今後も温暖化が進む以上、日本国内でも竜巻は珍しい気象現象ではなくなるらしい。
被害に遭った人たちが早急に元の暮らしを取り戻せるよう、県や市町村の徹底した助勢を期待したいものである。
国民が真面目に税金を納めているのは、こういう不足の事態に陥った時、国や自治体に手厚いフォローをしてもらうためである。
それを忘れてもらっては困る!!
続きを読む
今日は、暑かった・・・
2013年08月31日
今日は、暑かった・・・

今日は一日風もなく、暑かった・・・。

ところで、昨夜放送していた『貞子 3D』----何だか、貞子が怪獣のようになってしまっていて、ホラーというよりも怪奇アクションムービーの色が強く、あまり怖いとは思えなかった。
特に、あの長い髪の毛がわんさと噴き出すようなシーンは、以前観た『チャーリーとチョコレート工場』の中に出て来る、チョコレート工場の従業員ウンパルンパの一人が、試作品を食べて毛むくじゃらになっている場面を思い出し、つい笑いがこみあげて来てしまった。
まあ、お子さま向けホラーと思えばいいのだろうが、初期の同名作品の続編としては、かなり物足りない出来になっていた。
今度また、新作が映画公開されるそうだが、こちらは初期の要素を取り入れた日本人好みのじわじわ怖さがやって来るストーリーになっているとのこと。
『13日の金曜日』のジェイソンではないが、貞子も作品を追うごとにパワーが強化されているようで、何処まで強くなるのか興味津津である。
それにしても、『貞子』という名前の女性たちは、どんな気持ちでこの映画を観ているのだろうか?
わたしの中学時代の同級生にも、実は漢字も同じ『貞子』さんがいる。
ものすごく頭が良くて、学級委員長をやっていた女の子だったが、その後は教師になったとか・・・。
聡明な女性に多い名前なのかもしれないな。
続きを読む
真夜中の呼吸音
2013年08月30日
 真夜中の呼吸音
真夜中の呼吸音あまりに暑いので安眠のためにと、夜11時を過ぎた頃、アイス枕を冷蔵庫まで取りに台所へ行った。
台所の照明をつけて、冷凍庫で冷やしてあるアイス枕を取り出し、部屋へ戻ろうとした時である。
何処からともなく、奇妙な音が聞こえて来た。
「スー、ハー、スー、ハー・・・」
まるで、誰かが寝息を立てているような音だった。
どうやら、音は、今来た台所の方から聞こえて来る。
耳を澄ますと、台所の隣にある洗面所の天井あたりからしているようなので、もしや、また猫か何かが天井裏へ入り込んだのかと思い、じっと息を殺して天井付近へ意識を集中する。
すると、しばらくして音はピタリと止まった。
もしかしたら、外の虫の音か何かを息づかいと勘違いしたのかもしれないと思い直し、その時は部屋へ戻ったのだが、さらに一時間ほどして、もう一度確かめておこうと、台所へ向かった。
と、また、あの音がしている。
「スー、ハー、スー、ハー・・・」
今度は先ほどよりも音が近くで聞こえる。
その時、目の前にある台所と洗面所を区切るアコーディオンカーテンが、ゆらゆら揺れていることに気が付いた。
そして、そのアコーディオンカーテンのすそにどういう訳かガムテープの切れ端がくっついていて、それがカーテンが揺れるのと同時に床にこすれていたのである。
「シャー、サー、シャー、サー・・・」
無意識のうちに、わたしが手を触れていたせいで、カーテンが揺れ、つられてガムテープが音を立てていたのだった。
幽霊の正体見たり、枯れ尾花----。
マジに冷や汗をかいた。

もう、これ以上面倒くさいことが起きるのは勘弁して欲しいと思っていたので、呼吸音の正体が分かってホッとした。

続きを読む
また、暑さが戻った
2013年08月29日
 また、暑さが戻った
また、暑さが戻った今日は、また夏の暑さが戻ってきた。
で、髪をカットしに・・・。
節約のために、しばらく自己流で切ってはいたのだが、やはりだんだん格好が付かなくなり、やむなくプロにお任せすることにした。
いつも行きつけの理容院へ電話をしたのだが、お休みのようだったので、別の美容院へ----。
ベリーショートに近い感じにサッパリと切ってもらい、スッキリした。

そこで聴いたラジオ放送で、今は女流競技麻雀士なる職業の人がいることを知った。
二階堂さんという美人麻雀士なのだそうだが、最初、この世界へ入ると決めた時はかなり抵抗があったとか。
「マージャンは、男性の仕事というダーティーなイメージがあったので、初めは躊躇した」
と、言う。
しかし、実家が雀荘を経営していたこともあり、妹さんが高校生の時にプロの競技麻雀士になると宣言。
妹さん一人をそんな危険な世界へ飛び込ませるわけにはいかないと思い、保護者感覚で自分も入ったのだそうだ。
今では、妹さんよりもマージャンの腕は上になり、G1と呼ばれる最高レベルの試合を制した押しも押されぬ女流プロになったのだという。
マージャンのマの字も知らないわたしなんぞは、パーソナリティーたちと二階堂さんの会話に出て来るマージャンのルールなどはまったくチンプンカンプンだったが、彼女には多くの男性ファンもいるということで、世の中にはさまざまな業界があるものだと感心した。
因みに、彼女の話によれば、マージャンを日本に紹介したのはかの明治の文豪・夏目漱石だったとか・・・。(注・夏目漱石が日本に麻雀を紹介した明治42年と同年に日本上陸第1号の麻雀牌を もたらしたのは日本語と英語の教師として中国四川省に赴任していた名川彦作という 人物である)
かつてのマージャンは庶民の娯楽というよりも、上流階級の知的遊戯としての要素が大きかったようである。
続きを読む
声なき声は賛成とみなされる
2013年08月28日
 声なき声は賛成とみなされる
声なき声は賛成とみなされる信濃毎日新聞の「山ろく清談」に、前中国大使の丹羽宇一郎さんの談話が掲載されていた。
「(中国大使を務めて)2年半ぶりに日本へ帰って来たら、知的空気が非常に悪い。本当の自分の意見を言うと、疎外感を感じてしまうという意味です。政権側に反対する意見を言うと弾かれるというような。例えば、政権内にいろんな会議、協議会が立ち上がっていますが、ほとんどが賛成者の集まりになっています。これでは、本当の意味の改革になかなかならない。右傾化していると海外でも言われていますよ。----
尖閣諸島購入計画について、私は英紙のインタビューで、『もし計画が実行されれば、日中関係に深刻な危機をもたらす』と発言し、日本国内からさまざまな批判を浴びました。おかしいんですよ。私は賛成も反対も言っていない。大変なことになりますよと言っただけ。(私の発言に)賛成だという人も結構いたんです。じゃあ、言ったらどうですかと、私が言っても、(公には)言わないんですね。声なき声は賛成になってしまいます。選挙の投票に行かないのも同じ。民主主義社会の中で全員が一致するというのは、気持ち悪いことです。異常な社会ですよ。
第二次大戦前の日本とそれほど大きな差がないんじゃないですか。危ないですねえ。軍部に反対すると嫌がらせを受けるとか、殺されるとか、そういうのが怖いからみんな黙っている。そういう空気で対戦に入って行ったのではないですか。-----」
政権内に生まれつつある疑問や矛盾を直に見て来た人物による、何とも実感がこもった談話だと思う。
消費増税についての有識者会議も、一応賛成派、反対派の双方を招いているそうだが、これは、国民の中にアベノミクス効果が未だ浸透しきれていないため、政府としても来年度からの引き上げを強引に推し進めようとしている訳ではないとのパフォーマンスだという説もある。
テレビ番組の街頭インタビューでは、もちろん消費増税に反対する声が大きかったが、中には、
「将来の国民に大きな負担を背負わせるのは困るので、増税には賛成」
と、言う女性店員もいた。が、その女性でさえ、増税で客が減るのは痛いと付け加える。
おそらく、本音は反対なのだろう。
マイクの前では本音が言えないような雰囲気が、既にじわじわと広まりつつあるのではないかとの不気味ささえ覚えた。
TPP交渉の詳細も、国民には一切知らされていない。
噂では、結局日本はかなり大幅な譲歩をせざるを得ない状況になりつつあるのではないかと、いうことである。
ある消費増税反対派の政治評論家が皮肉をこめて話していた。
「来年から、1%ずつ上げることになるかもしれません。最初は国民もそれなりに抵抗するでしょうけれど、そのうちに慣れてしまいますからね」
でも、確実に生活保護受給者は増加するだろうな。
続きを読む
コメントにも書いたが・・・
2013年08月25日
 コメントにも書いたが・・・
コメントにも書いたが・・・コメントにも書いたのだが、インターネットが普及したせいで、即断即決即答ばかりが求められ、熟慮出来ない人たちが増えているという。
メールやラインはもとより、フェイスブックやツイッターでも、相手の相談や質問に対して即座に反応しなければならないという癖がついているために、一昔前ならば、一日二日、いや、問題によっては一週間も熟考した上で答えを出していたことを、ものの五分も経たないうちに即応しなければならないのが現実である。
そのせいで、物事を極めて軽薄に考える習慣が常態化しているのが、今のネット文化といっても過言ではないようだ。
たとえば、昔の学生たちは一つの疑問が浮かぶと、図書館に通ったり、教師を追いかけ質問責めにし、徹底的に自ら疑問と格闘して答えを導き出していた。
ところが、今はネット検索するだけで、信じられないほど楽に答えが手に入る。
知恵袋のようなネット上の質問コーナーへ投稿すれば、あらゆる人が一瞬にして回答を寄せてくれる。
つまり、自分の頭でじっくりと思考する必要のない時代になってしまったわけだ。
そのため、自分のこれまでの人生で培ってきた経験のみを正しいと信じる者も少なくなく、一方的な見方しか出来ない若者が増えていることで、例の「風立ちぬ」の喫煙シーン問題のように、時代背景を無視するような意見が公然と発表されたりするのであろう。
今日、たまたまそうした若者たちの思考の浅さが話題に上り、ある女性が、
「やっぱり、昔の文豪たちが書いた小説や評論をたくさん読むべきだね」
と、語っていた。
さすれば、携帯電話がなかった時代の人々の暮らしぶりも想像できるし、ネット世代とネットが存在しなかった頃に教育を受けた世代との物事の捉え方の違いも、察することが可能になるのではないかというのである。
現代社会は、ある意味、まったく異なる二つの世界の空気を呼吸する人たちが共存している時代だといえる。
生活にネットのあるのが当たり前と思う世代と、ネットなどなくても十分暮らしていけると考える世代だ。
これは、かつて一度として人類が体現し得なかった、実に稀有な現象なのだそうだ。
もしも、日本の自治体の中にネットや携帯電話がつながらない、もしくは必要としないながらも、日常生活にはまったく困らないという、古き良き日本そのものといった地域があったならば、手に入る情報量は本や新聞、ケーブルテレビ、ラジオ等からに限られるものの、そこに暮らす子供たちの想像力や知識、思考レベルは驚異的に発達するだろうという人もいる。
このネット社会がどんどん成長し続ければ、今度はすぐにキレやすいネット高適応者だけが社会の中枢を握ることのできる時代がやって来るかもしれない。
そして、ある水準以下しかネットを使いこなせず、思考も浅い低適応者たちは、彼ら高適応者の支配下に甘んじなければ生きていけない未来が来ないとも限らないのである。
それもまた、今以上に格差のある生きにくい世界なのではないだろうか。
続きを読む
東日本大震災にまつわる不思議なエピソード
2013年08月24日
 東日本大震災にまつわる
東日本大震災にまつわる不思議なエピソード
昨日の大雨も上がり、秋風が感じられる涼しい一日だった。
昨夜のNHK総合では、東日本大震災で肉親を亡くしたそれぞれの家族の悲痛な思いを特集していたが、中でも印象に残ったのが、「不思議な白い花」の話だった。
大好きな父親を、まだ54歳という若さで津波に奪われた女性が語っていた。
「震災後、ようやく父親の遺体が見付かったので、急いで遺体安置所へ向かったのだが、遺体に触れることが許されなかった。どうしても、最後に一度だけでも触りたかったのだが、ただ眺めるしか出来なかった。
その時、気付いた。お棺に納められている父親の胸に、見覚えのある真っ白な花が一輪置かれていることに・・・。
で、思い出した。
自分の職場のげた箱は、ロッカーのように鍵がかかるタイプで、そのげた箱に靴を脱いで入れると、いつもちゃんと鍵をかけていたのだが、ある日、帰り際にげた箱から靴を出して履こうと片方に足を入れたら、足に何かが触った。
ひんやりと冷たくて、やわらかい感触・・・。靴下の上からでも、それがはっきりと分かった。
何だろうと靴の中を見ると、まるで今摘み取って来たかのようなみずみずしさを保った真っ白な花が一輪入っていた。
遺体安置所の父親の上に置かれていた花が、正にその花だった。
ああ、きっと、父の遺体に触れたとしたら、あの花の感触と同じだったんだろうな・・・。あの日の白い花の感触は、父親の肌そのものだったに違いない」
本当に不思議な体験談だった。
これを語った女性は、今、大震災の記憶を原稿にまとめているそうだ。
他にも、保育園に通っていた息子を津波で亡くした母親は、最近、自宅の仏壇の前に座ってニコニコ微笑んでいる息子の夢を見たといい、やはり、津波で奥さん、11カ月の長男、生後間もない次男を亡くした男性は、背が伸びてお兄ちゃんらしくなった長男と次男が着物姿の見知らぬ女の子と手をつないで夢に現われたと、話していた。
男性は、
「二人の息子がすぐそばにいることが分かるんです。だから、いつまでも悲しんでばかりいられない。息子たちに恥ずかしくない父親になります」
と、前向きな決意を言葉にしていた。
あの日、思いもかけない悲劇に襲われた人々は、皆、何とかして愛する肉親の死を納得し受け入れようともがいている。
「どうして、彼らは死ななければならなかったのか・・・。運命などという陳腐な一言で片付けて欲しくはない」
しかし、その答えが出ない以上、おそらく遺族は一生それを納得することは出来ないであろう。
ならば、せめて、彼らの想いを自分の想いとして心の中にその存在を感じていたい----その気持ちがこれからの人生を前向きに生きるための支えともなる----そう番組は伝えたかったのではないかと思いながら視聴した。
ネットでの反論は攻撃と認識される
2013年08月23日
 ネットでの反論は攻撃と認識される
ネットでの反論は攻撃と認識される先日の新聞記事に、インターネットとの向き合い方について、フェリス女学院大学の高田明典教授の見解が掲載されていた。
現在のネット社会を、実に的確に分析している。
ネットが社会に与える影響として、
「まず、感情の過剰反応を促している」
と、教授は語る。
人間は、生身の対面型コミュニケーションを前提に進化し、社会も発達してきたのだが、そこに文字だけのコミュニケーションが登場したことで、これが生身のコミュニケーション能力が備わっていない若者層に急速に広まってしまったがために、自分と違う意見を攻撃とみなして、頭に血をのぼらせて激しく反論したり、また、逆に殻に閉じこもってしまう者も出て来たというのである。
実際に顔を合わせて話をすれば、相手の微妙な声や表情なども分かるために、それほど険悪にならないことでも、文字だけのやり取りでは、極めてダイレクトにしか内容が伝わらず、時には、読み手の感情を必要以上に刺激し、『孤独』や『悪意』までも増幅させることになり兼ねない。
そして、この『孤独』や『憎悪』は、ネット利用者に悪意のよろいを身につけさせることともなり、時には、自分と同じような感情を懐く仲間を広げる手助けもしてしまうのである。
しかも、残念なことに、一度こうしたよろいを身につけた者たちが改心することはほとんどないし、良心や寛大さが増幅されることもまずない---と、教授は語る。
そして、そうした悪意の攻撃に遭った場合、現実社会の常識的感性で生きている人たちは、ネット社会では太刀打ちできない。何故ならば、良心は悪意に反撃することが出来ないから----と、説くのである。
さらに、
「ネットは増幅装置であり、出来ないことを出来るようにするわけではなく、能力や技術をより強化、拡大することが出来るという装置であるため、実際ネット社会の中では、『格差』が拡大しつつある。高度な技術を獲得するものは、さらに高度な技術を獲得し、ネット社会の中で力のある者と落ちこぼれ組との落差が、どんどん開いているのが現実だ」
ということなのである。
教授は、ネット社会のもう一つの特徴として、『群化』があるという。
傷付くことを恐れる人たちが、同じ意見を持つコミュニティーの中でだけおしゃべりをする。そして、自分たちの意見のみが正しいと思い込んでしまう。
これもかなり怖いことだが、思い当たる節のある人も多いだろう。
または、そうしたコミュニティーからのけものにされたくなくて、反論が書き込めないという人も少なくないはずである。
自分はネットの『高適応軍』だと思っている人ほど、実は適応できていないというケースが多々あるのも事実。
つまり、教授は、ネット社会の中ほど、利用者の対話能力が必要となる----と、諭したいのではないかと思われる。
しかし、そこへ至るまでには、自ら右往左往しながらネットを活用し、なおかつ良きにつけ悪しきにつけさまざまな体験を経る必要がありそうだ。
続きを読む
ナトリウム量と食塩量って、どう違うの?
2013年08月22日
 ナトリウム量と食塩量って、どう違うの?
ナトリウム量と食塩量って、どう違うの?今日は内科の診察日だった。
「夏はたくさん汗をかくので、腎臓のためにも水分を多めに摂って下さい」
と、担当医の先生からアドバイスを頂いた。
診察のあとは、久しぶりに栄養指導室へ-----。
そこで、栄養士さんから興味深い話を聞いた。
皆さんは、よく食品のパッケージなどに表示されている、「ナトリウム」という言葉を見たことがあるだろう。
「ナトリウム」とは、もちろん塩分のことなのだが、実は、これ、いわゆる食塩量とはまったく違うのだそうだ。
たとえば、カップラーメンの栄養表示に「ナトリウム 2.5g」とあったとする。
これを単純に、「食塩2.5gだから、大したことないわね」などと思ったら、大間違い。
ナトリウム量(mg)×2.54が食塩量の概算になるのだそうだ。
つまり、2500mg×2.54となり、食塩量に直すと6350mg----これを1000で割ることで、本来の食塩量がはじき出され、カップラーメンをつゆまで飲み干せば、食塩を一気に6.35gも摂ってしまったことになるのだという。
早い話が、ナトリウム400mgは、食塩1gと考えれば、おおよその食塩相当量が分かるのだそうである。
食品メーカーは、消費者の錯覚(無知)を利用して、如何にも少ない食塩量を使用しているように見せてはいるが、そこには実に巧妙な販売戦略が隠されていることを知っておく必要があるようだ。
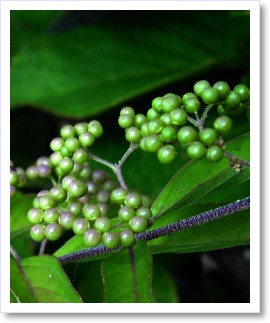
続きを読む
こんなことってあるの?
2013年08月21日
 こんなことってあるの?
こんなことってあるの?長野・松本市の私立の小中一貫校「才教学園」で、免許のない職員が授業していたことがわかり、警察は21日、教員免許法違反の疑いが強まったとして、学校を家宅捜索した。
才教学園は20日、2005年の開校当初から、免許のない補助の職員が授業をしたり、中学校の教科の免許しかない教員が、小学校で担任をしていたことを明らかにし、謝罪したうえで、「事務長の認識不足によるもので、組織的に行ったものではない」と説明していた。
警察は、免許のない者が教員となったり、教員として雇用することを罰する、教育職員免許法違反の疑いが強まったとして、21日、学校を家宅捜索した。(YAHOO!ニュース)
こんなことって、本当にあるのだろうか?
教員免許がどういう種類に分けられているかなど、素人にだって判りそうなものだ。
それを、教育のプロが、「認識不足でした」とは、にわかには信じがたい。
さらに信じがたいのは、免許を持っていない者を採用した学校側の意識はもちろんだが、採用された側が、採用試験面接や免許コピー提出の時点で、「実は、わたしは小学校教諭免許は持っていないのですが・・・」と、何故、自己申告しなかったのか----ということである。
それとも、小学校教員免許を持っていないことが判っていながら、「いずれにしても補助教員なんだから、そんなに四角四面に考える必要はないのでは?」とでも、双方が深く考えていなかったのだろうか。
公立校ならばいざ知らず、私立はある程度の自由裁量が容認されてしかるべき----と、甘く考えていたのかもしれない。
学校教諭に採用されたくても試験ではじかれ続けている者は多い。
いや、万が一採用試験に合格しても、各学校に実際に雇用してもらえるかは、また別問題なのだ。
せっかく採用試験が通っても、雇用校が見付からなければ採用資格は失効してしまう。
やはりそこはある程度の人脈や縁がなくては就職もままならないことは、採用試験を受けたことがある者ならば自明の理だ。
個人の素質や成績だけではいかんともしがたい現実があるのは、いつの時代も同じなのだ。
しかし、もしも、無資格のまま児童や生徒を教えることが出来る現状がまかり通れば、これまで歴とした資格を持ち、なおかつ教員になりたいという長年の夢、情熱、実力がありながらも、コネがないばかりに悔し涙を飲んで来た誠実な不採用者たちに、県教育委員会はどう説明をつけるつもりなのだろうか?
また、そうした無資格者の授業を受けた子供たちの単元履修は、果たして認められるのだろうか?
認められるというのならば、何も教員資格を持たなくても小、中、高の教師は誰にでも出来るという前例を作ることになる。
この前代未聞の不始末----県は何処に落とし所を見付けるのか、県民は冷ややかな視線で今後の成り行きを見詰めている。
続きを読む
やっぱり夏はこれでしょ!
2013年08月19日
 やっぱり夏はこれでしょ!
やっぱり夏はこれでしょ!「ほんとにあった怖い話 夏の特別編2013」----夏といえば、やっぱり、これでしょう。
鈴木福くん主演の引っ越した家の二階に幽霊が住んでいるというエピソードも、なかなか怖いものがあった。
子供の純粋な感性故に見えてしまう幽霊たち。
でも、大人は信じてくれない。
幽霊も怖かったが、母親が「うちにはお化けがいる」と、いう子供の声にまったく聞く耳持たずの方が、何だか不気味な感じがして・・・。
もしや、あの家の二階が幽霊たちの通り道になっているのではないかと、想像してしまった。
研修医が病院で奇怪な体験をするという「Xホスピタル」は、恐怖体験の定番といえるが、やはり、夜の病棟は気味が悪いもの。
ただ、夜の病院ほど実は騒がしい空間もないので、ああいう体験は、実際にはあまりないのではないかと思われる。
誰が押すともしれない無人のストレッチャーに追いかけられるようなことがあっても、入院病棟は患者であふれているし、ナースステーションも24時間煌々と明かりをつけて稼働している。
廊下だって、看護師さんたちが何度もラウンドに回るし、トイレへ起きる患者が何人も行きかう。
必ず誰かに気付かれるはずだ。
あの研修医さんは、日々の激務でよほど疲れていたのだろうなァ・・・と、思わずにはいられない。
中でも奇妙だったのが、学校でのエピソード。
女子校という設定だけに、ああいう集団恐怖体験のようなものはあり得るだろうな・・・と、思った。
校舎の屋上から飛び降りる女子高生の姿を、大勢の生徒が目撃する。
しかし、その少女の身体は飛び降りた途端に消えてしまう。
それが何度も何度も繰り返される。
錯覚が共有されるという摩訶不思議な現象だった。
黒い影が入って行った家に不幸が起きる----という話は、その影の正体の説明がなかったのがちょっと残念。
主人公の女性と彼女の祖父だけに見えるという怪現象。
幽霊というよりも、彼女自身の霊感の強さがそうした奇異なものを見せてしまうという超能力的お話。
最後は、アンティークショップで手に入れた木彫りの兵隊人形が、買った女性の周辺に災いをもたらすという話。
せっかく出来た彼氏が人形の呪いに脅かされて彼女の元から去り、彼女の友人も怖い体験をする。
女性は、人形にまがまがしい恐ろしさを感じ、ついには捨ててしまうのだが、人形はボロボロになりながらも彼女の元へ戻って来てしまう・・・という都市伝説的ほん怖。
今回の「ほん怖」は、昨年ほどのインパクトはなかったものの、夜一人で観るにはちょうどいい感じの怖さだった。
ユーチューブ投稿映像などで怖がらせる番組が最近増えて来たが、こういうドラマ仕立ての納涼物も正に背筋が寒くなる・・・という意味では絶品。
ぜひこれからも続けて頂きたいものである。
続きを読む
不景気きわまれり
2013年08月17日
 不景気きわまれり
不景気きわまれりお盆休みといえば、例年は近所で子供連れの里帰り家族などが大勢いて、浴衣を着た子供たちが夏祭りに出かける風景がよく見られたのだが、今年は、なんと、一人も目にしなかった。

共同浴場もこの時季は里帰り家族が入るので、時間帯によっては大変な込み具合で、近所の人たちは空いている時間を見計らって入浴するのが常なのだが、今年はそうしたこともまったくといってなかった。
街中を散策する観光客の姿もまばらで、車中泊をしたり食事もコンビニを利用して済ませてしまうらしく、「いったい、今年の夏はどうなっているの?」と、皆首を傾げるばかりだ。

各商店や旅館に品物を卸す問屋さんも、「今年のお盆は、小布施、志賀高原、渋温泉、湯田中温泉、北志賀・・・何処からも注文がない」と、焦りの色を隠せない。
聞けば、お中元を贈るのを控えたり、安価なものに抑えるという家庭も多かったそうで、交通費やガソリン代等の経済的理由から今年は里帰り自体を諦めたという若夫婦もいるとか。
春先に、過度なアベノミクス効果が期待されていたせいもあり、その時点でボーナスや給料が上がることを前提に出費をしてしまったことが仇になり、ぬかよろこびをした分のツケが、ここへ来て大きく響いているのではないかということである。
このまま消費税アップが現実のものとなれば、今後は財布のひもをさらに締めなければやっていけないという懸念が、既に国民の間にじわじわと広まりつつあるのではないだろうか。
続きを読む
そうめんの食べ方
2013年08月16日
 そうめんの食べ方
そうめんの食べ方このところ、我が家の食卓には毎日のように「そうめん」が登場している。
普通に麺つゆをつけて、みょうがや大根おろし、オオバ、わさびなどを薬味に食べるのも確かにおいしいが、麺つゆにはトマトが意外に合うことに気が付いた。
少し大きめの器に麺つゆ、砂糖少々、レモン汁を入れ、さらに1センチ角ぐらいに切ったトマトを散らす。
それらの中に茹でて冷やしたそうめんを入れたら、良く混ぜて食べる。
好みでマヨネーズや黒コショウなどをかけてもイケると思う。
ちょっと、趣の違うエスニック風味のそうめんになって、飽きずに食べられるような気がする。
そういえば、昨夜の「県民ショー」で、佐久地方には味噌汁にレタスを入れる食文化があると聞いた。
戦後、佐久地方に駐留していたアメリカの進駐軍が、「レタスが食べたい」と言い出したことをきっかけに、佐久でレタス栽培が盛んになったのだとか。
現在では全国一位の生産高を誇るそうである。
味噌汁に入れるだけではなく、レタスをしゃぶしゃぶにして食べるお宅もあるらしい。
わたしも、カレーなどの具としてレタスを使うことがあるが、歯ごたえはそれなりにシャキシャキと残ってはいるものの、しんなりとして甘みが出る。
佐久地域の長寿の秘訣は、レタス食にあるのかもしれない。
続きを読む
今日もまた暑い・・・
2013年08月15日
 今日もまた暑い・・・
今日もまた暑い・・・
家の中でじっとしていても、汗が噴き出す・・・暑さ。
節電のために風を入れたいのだが、窓を開けると何かと人工的騒音が入って来てしまうので、気が散ってイラつく。
観光地なのだから、ある程度の人の声や下駄の音は仕方がないのだが、宿泊客をホテルや旅館の中だけで過ごさせ、街ではお金を使わせず活性化に反するようなやり方をしている宿泊業者には、
「人迷惑だから、宿泊客に大声を出しながら道を歩かせるな----と、言いたい」
との近隣住民の声も多い。
殊に、夜のうるささは我慢が出来ないと、一般住宅の人たちは憤る。
かつては、観光客の落とすお金が街全体を潤していたために、街中の住民も協力を惜しまなかったが、今はそういう状況にない。
ホテルや旅館が宿泊客を囲い込んでしまうがために、蚊帳の外に置かれている一般住民は必然的に活性化には無関心となってしまっているのだ。
景気は回復しつつあり、内閣府の調査でも国民の70パーセントが今の生活に満足しているとの結果が出たそうだが、この調査結果、どうにも胡散臭い。
いったい、何処で誰を調査すれば、そんな脳天気な答えが出て来るのか・・・。
ただただ消費税アップのための布石を打つのが目的ではないかと、疑ってしまう。
お盆だというのに、日中も夜間も街中は閑散としていて例年のような活気やにぎわいはない。
「渋温泉もモンハンで人はそれなりに歩いているけれど、売り上げは全然ダメ」
と、某旅館の従業員はこぼしていた。
続きを読む





