時間に几帳面な人は・・・
2012年05月24日
時間に几帳面な人は・・・

あなたは、待ち合わせ時間をしっかりと守る方だろうか?
そういう人は、得てして時間にルーズな人を嫌うものである。
待ち合わせ時間に五分遅れただけでも、烈火のごとく怒る人もいるが、こういう人は、何も相手が五分遅れたことだけに怒っている訳ではないのだそうだ。
こういう時間に対して異常に几帳面な人というのは、自分の思い通りに物事が進まないと、身の周りにあるすべての物事に対して、怒りを覚えるという人なのだそうである。
自分は道路をまっすぐ歩きたいのに、正面から太った女性が歩いて来て、道を譲らなければならないとなると、それも腹が立つ。
待ち合わせ時間までに、まだ少し間があるので、途中で喫茶店へ入ったが、自分のところへ注文のコーヒーが来るのが少し遅れただけで、我慢がならない。
会社で自分が取ろうと思っていた得意先からの電話を、同僚が先に取っただけでも怒髪天突きとなる。
そんな風に、すべてのことが気に入らない人なのだそうだ。
つまり、それは、その人物が、時間にルーズな奴が嫌いなのではなく、自分の人生そのものが気に入らないということなので、希望通りの道を歩んでいないという証拠でもあるのだと、心理学者は言う。
人は、本当に好きなことをしている時は、むしろ、時間などない方が良いとさえ考えるもので、待ち合わせに相手が遅れたとしても、必ず来ることさえ判っていれば気長に待ち続けられるのだそうだ。
そういえば、わたしも昔は相手が待ち合わせ時間に一分遅れたというだけで、帰ってしまったことがあったほどのイラチだったのだが、自分の身体があまり自由に言うことをきかなくなってからというものは、少しは悠長に構えられるようになったかもしれないな。

続きを読む
夫 源 病
2012年05月23日
夫 源 病

夫源病(ふげんびょう)とは、「たけしの家庭の医学」という番組に出演していた、心療内科医(男性更年期専門医)の先生が命名した病名だそうだが、これは、文字通り夫が原因で起きる妻のストレス病なのだという。
長年、ひどいめまいや激しい頭痛に苦しめられてきたある主婦が、少し早い更年期との診断でホルモン治療などをしていたのだが、一向に症状が改善しないので医師を替えたところ、「もしかしたら、ストレスが原因かもしれない」と、言われ、この心療内科医を訪ねた。

すると、詳しい問診により、原因不明の頭痛やめまいの元凶が、実は夫への不満や苛立ちだったことが判明したのだそうである。
その不満や苛立ちの理由の一つ一つは、実にささいなことなのだが、それが積もり積もってそうした症状を引き起こしていたのだそうだ。
たとえば、主婦が几帳面にたたんでタンスに仕舞っておいた衣類を、夫が妻の手を煩わせまいとして自分で取り出し、せっかく整理されているタンスの中をぐちゃぐちゃにしてしまうとか、主婦が、風呂へ入る際に服やズボンは脱ぎっぱなしにしないで欲しいと、いくら頼んでも、夫がそれを無視するとか、そんな日常の小さなことなのである。
しかし、しっかり者の主婦にとって、そうした夫の行為は、決して見過ごせるものではなく、主婦の気持ちにまったく気付こうとせず、むしろ自分は妻のためにしてやっているというような、まったくの思い違いをしている鈍感さに、彼女の神経はついに我慢の限界点を超えてしまったのであった。
こういうことは、普通の家庭にも良くある話で、自ら進んで妻の買い物について来るくせに、買い物時間が長くなると「早く帰ろう」と、急かせる夫などにも、そうした夫源病の病因があるという。
この病気にかかりやすい妻を見極めるには、日ごろからの夫の言動をチェックすればよいという。
★ 妻に何かをしてもらったら、素直に「ありがとう」が言える夫か?
★ 妻がヘアスタイルなどを替えた時、それに気付ける夫か?
★ 妻の誕生日や自分たちの結婚記念日などを覚えている夫か?
これらを確かめるだけでも、気配りが出来る夫か否かが判るのだとか・・・。
二つ以上に☓がつくと、妻が夫源病になる確率はかなり高くなるのだという。
まあ、頭痛や肩こり、不眠、めまい、動悸などの症状もかなり辛いものがあるが、もっと重大な病気になる可能性もあるわけで、無関心や鈍感な夫には、時にヒステリックだと思われても構わないから、言いたいことはしっかりと伝えておくことが大事なのではないだろうか。
続きを読む
東京スカイツリーの功罪
2012年05月22日
東京スカイツリーの功罪

東京スカイツリー(とうきょうスカイツリー、Tokyo Skytree)は東京都墨田区押上にある電波塔(送信所)である。2008年7月14日に着工し、2012年2月29日に竣工した。ツリーに隣接する関連商業施設・オフィスビルの開発も行われており、ツリーを含めたこれらの開発街区を東京スカイツリータウンと称する。2012年5月22日に開業。
-----だそうですね。
ということは、今日が開業日ということなのかな?
あまり関心がないので、ピンと来ないのですが、この東京スカイツリーが学校のPTAなどでも問題視されているのだそうです。
長野県の小学生は修学旅行先に東京を選ぶ場合が多いそうで、今年の修学旅行も東京と決まった北信のある小学校では、子供たちにこの出来たばかりの東京スカイツリーを見学させようと、入場券の申し込みをしたそうなのですが、抽選に外れてしまったというのです。
 ところが、スカイツリーのある地元の子供たちは招待されて入場出来るということで、地方と東京都で子供に差を付けるとは不公平だ----との不満が親御さんたちから上がっているのだとか。
ところが、スカイツリーのある地元の子供たちは招待されて入場出来るということで、地方と東京都で子供に差を付けるとは不公平だ----との不満が親御さんたちから上がっているのだとか。確かに、東京在住の子供たちは、これからいつでもスカイツリーには上ることが出来ますが、地方の子供たちにとっては、もしかしたらこれが最初で最後の東京旅行なのかもしれないのです。
大人もわざわざ今上らなくても、いつでも好きな時に入場できるのですから、何もこの開業時目がけて入場券を手に入れる必要などないはずです。
わたしも、スカイツリーの開業時には、まず全国の小学生や中学生に入場券を配るべきであり、一般見学者はその後で入場を許可するという方法は取れなかったのだろうか・・・と、思いました。
その北信の小学校では、もしかしたらスカイツリーを見学できるかもしれないと期待していた子供たちは、かなりがっかりしているそうです。
また、これは、ワイドショー番組で取り上げていたのですが、スカイツリーのそばの住民たちが、今大変な目に遭っているのだそうです。
スカイツリーを観るためにやって来る観光客たちが、昼夜関係なく住宅街で大声を出したり走り回ったり、花壇の花を引きちぎったり、スカイツリー周辺にはトイレがないので、路上で用を足したりと、やりたい放題なのだとか・・・。
街は汚され、安眠妨害までされて、もう我慢がならないと住民たちは怒っているそうです。
スカイツリーの経済効果は確かに相当なものがあると思いますが、そのせいで近くに住む人たちが体調を崩すなどの被害を受けては困ります。
わたしも夜中の騒音で悩むことがあるものですから、それは切実に感じます。
この対策としては、住民や警察官によるパトロールを強化したり、監視カメラも70台以上を設置して、不心得者の監視にあたっていると番組はレポートしていましたが、今のところあまり効果は見られないそうです。
東京スカイツリーの開業で浮足立っている日本列島ですが、問題点も色々と浮上しているのが事実のようですね。
続きを読む
田宮五郎降板のわけ
2012年05月21日
田宮五郎降板のわけ

映画「白い巨塔」や「クイズタイムショック」の司会などで知られる俳優の故田宮二郎さんの次男で、俳優の田宮五郎(45)が4月12日、都内の自宅でくも膜下出血で倒れて緊急搬送され、8時間に及ぶ手術を受けていたことが20日、分かった。4日間、意識が戻らずに生死のはざまをさまよったが、現在はリハビリを開始するまでに回復。このため、出演していた東海テレビ制作のフジテレビ系昼ドラ「七人の敵がいる!」(月~金曜、後1・30)は降板した。
兄で俳優の柴田光太郎(46)によると、田宮は4月12日、自宅で役作りのため筋力トレーニングをしている最中に倒れ、すぐに救急車で病院に運ばれた。くも膜下出血と診断され、13日午前2時から8時間に及ぶ大手術。それから4日間、こん睡状態が続き生死の境をさまよったが、奇跡的に一命を取り留めたという。
(中略)
なお「七人の‐」の田宮の代役として、冨家規政(50)が21日放送分から出演する。(YAHOO!ニュース)
今日、「七人の敵がいる」を観ていて、有森也実さんの夫役が、いつもの田宮五郎さんから冨家規政さんにいきなり代わっていたので奇妙に感じた。
そして、こういう事情があったことを知り、本当に驚いた。
田宮五郎さんは、俳優・故田宮二郎さんの次男ということで、彼が出演するシーンを楽しみにしていたのだが、とても残念な気持ちだ。
兄の柴田光太郎さんは、医師から「救命のため、手術で脳の圧迫を抑える必要がある」と説明を受け、手術後も「しゃべれるかわからない、歩くのも夢かもしれない」といわれ、
「死刑宣告みたいだった」
と振り返ったそうである。
田宮五郎さんはもともと、腎臓病を抱えており、高血圧のため降圧剤を飲んでいたという。
田宮さんは、39歳で俳優デビューをした遅咲き。
出演中の「七人の敵がいる」は、彼がこん睡状態の間にも収録があったため、柴田さんが関係者にすぐさま降板を告げたそうだ。
4日間も眠っていたとは知らなかった田宮さんは、降板を知ると、うつ状態になるほど落ち込んだということで、病的に神経質な区会議員の夫役を絶妙な仕草と味で演じていただけに、その役を降りなければならなかったのは自らも相当に無念だったものと思う。
(YAHOO!ニュース)を読む限りでは、現在は頭痛と声の違和感を残すものの、入院中の病院から車イスで外出できるまでに回復しているという。
リハビリ生活は、3カ月はかかるといわれているそうで、ドラマ後に予定されていた映画やラジオ出演は、今後の状況をみて判断。
「奇跡の生還」から約1カ月がたち、精神的にも前向きになったという田宮さんは、俳優復帰に向けて「頑張る」と柴田さんに語りかけているとのことであった。
「七人の敵がいる」の今日の放送分から役は冨家さんにバトンタッチしたが、田宮さんがやっていたあの眼鏡を指で上げる独特の仕草は、冨家さんも続けている。
田宮さんの父親・田宮二郎さんは1978年12月28日に43歳の若さで亡くなっている。
天国のお父さんが、「まだ、こっちへ来るのは早いぞ!」と、愛する息子を生還させてくれたのかもしれないな。

続きを読む
いつも早いねェ~♨
2012年05月20日
いつも早いねェ~♨
共同浴場へ行くと、必ずといっていいほど近所のおばさんたちから声をかけられる。
「いつも、上がるの早いねェ~」

そうなのだ。
わたしは、折り紙つきのカラスの行水である。
入浴時間は、身体や髪を洗う時間を入れても、せいぜい10分ぐらい。
15分も入っていれば、浴場の湯気だけでのぼせてしまうくらいなのだ。
でも、おばさんたちは共同浴場を一種の社交場としているので、お互いに背中などを流しっこしながらいつまでもおしゃべりを続ける。
洗髪しては入浴し、洗顔しては入浴し、身体を洗っては入浴する。
見ているだけで疲れてしまいそうだ。
温泉場育ちは、皆おしなべて入浴時間が短い。
どんなにゆっくり入っても、20分が限度だろう。
つまり、長々と入っている人たちは、たいていが別の土地からこちらへ嫁いできた女性たちである。
そういえば、わたしの祖母も入浴時間が長かったようで、一時間ぐらい平気で入っていたそうだ。
温泉場育ちの母親は、いつまで待っても上がって来ない祖母を心配して、何度も外湯をのぞきに行ったくらいであった。
しかし、わたしのような温泉場育ちにとっては、入浴で時間を使うほどもったいないことはないのである。
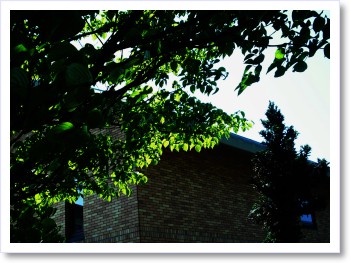
続きを読む
何じゃ、そりゃ?3
2012年05月20日
何じゃ、そりゃ?3

ヤフーの知恵袋を読んでいたら、またまた、「何じゃ、そりゃ?」の質問があった。
若い夫(28歳)からの人生相談で、年上妻(40歳 9歳の連れ子あり)の誕生日にプレゼントしようと、器用な夫が手編みのチュニックを製作し始めたのだが、仕事が忙しかったり、途中で編み方を間違えるなどのアクシデントが発生し、誕生日までに間に合わなかったというのである。
すると、妻は、「誕生日にプレゼントされなけりゃ意味がない」と怒り、夫は妻の機嫌を取るために、その後一生懸命編み続けて、何とか渡すことが出来たのだそうだ。
しかし、プレゼントが誕生日に間に合わなかったからといって、あれほど怒られる必要があるのか疑問だ----と、夫は悩んでいるようである。
因みに、チュニック(tunic)というのは、細い筒状の腰から膝ほどの丈の上着のことで、語源はラテン語のトゥニカ(下着・皮などの意)から来ているファッション用語らしい。
この夫は、妻からもらう小遣いも少なく、毛糸を買うのがせいぜいだったので、プレゼントを手作りにしようと思いたったのだそうだが、そんな風に考えてくれるだけでもその年上妻は果報者だと思うのだが、誕生日にプレゼントが遅れたからといって、どうしてそこまで目くじらを立てる必要があるのか不思議だった。
誕生日プレゼントなど、「いつも、ありがとう」の言葉一つで十分ではないか。
いや、誕生日を覚えていてくれただけでも、その夫はかなり妻思いの出来た男といえる。
年配者夫婦などには、妻の名前さえうろ覚えという夫だって少なくないのだ。
わたしの知り合いの男性など、自分の妻の名前をず~っと「〇〇え」だと思っていたと話していた。
実際は、「〇〇こ」だったのに三十年も気が付かなかったのだ。
それが、プレゼントが用意できなかっただけで、そんなに機嫌を損ねられては、夫の立つ瀬がない。
まあ、この夫婦はかなりの年の差結婚だから、妻の方に何かと夫の愛情を確かめなければ気が済まないような依存傾向があるのかもしれないが、それにしても変な話である。
しかし、それに対するベストアンサーが、また奇妙だった。
「夫は、妻の誕生日が判っているのだから、それまでに準備をするのが当然」
と、いうものだった。
この回答にも、「何じゃ、そりゃ?」である。(ーー;)
東日本大震災で多くの人命が失われ、家族が生きているだけでも幸せと思うべきだとの認識を新たにしたこの日本で、何をほざいているのかと、呆れ返った。
だいいち、不惑(40歳)にもなったら自分の誕生日など、もうど~でもいいではないか。
いつまで、子供じみたことを言っているのかと、アホらしくて思わずため息が出てしまった。(-_-;)
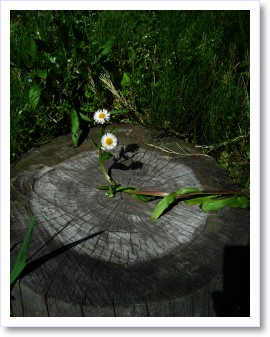
続きを読む
『平清盛』が観にくいわけ
2012年05月19日
『平清盛』が観にくいわけ

1月に始まったNHK大河ドラマ「平清盛」の視聴率低迷が続いている。開始早々、清盛ゆかりの兵庫県の井戸敏三知事が「画面が汚い」と批判したのがケチのつき始め。このままでは“大河史上最低”の危機も迫っており、NHKではてこ入れに躍起だが、外野からは「躍起なのは“犯人捜し”なのでは」と心配する声も聞こえてくる。
(中略)
NHKにも60代の視聴者を中心に「見づらい」との声が寄せられており、画面のコントラスト調整や、難解な人間関係を分かりやすくするための人物に関するテロップ挿入など、てこ入れに躍起。松本正之会長も5月の定例会見で、「2部、3部になると、義経や弁慶など内容もポピュラーになっていくし、話もシンプルになって面白くなると期待している」とフォローする(YAHOO!ニュース)
大河ドラマ『平清盛』の視聴率が相変わらず超低空飛行を続けているようだ。
ドラマ開始早々の兵庫県知事の「画面が汚い」発言がケチの付き始めだとはいうものの、この画面の薄汚れ色あせた感じが、どうしても殊に高齢者の好みに合わないというのが一番の問題なのだろう。
そこで、今回は、この視聴率低迷の理由を、「色」という視点から考えてみようと思う。
では、60代以上の人が好む色というものはどういうものなのか?

比較的若い年齢層の人は、ストーンウォッシュ加工やケミカルウォッシュ加工などのどちらかといえば洗いざらし汚れた感じの洋服なども格好いいとか、素敵だと思う色彩感覚を持っているのだが、団塊の世代と呼ばれる年齢以上の人たちの中にあるイメージは、
暗い、汚い、貧乏くさい、ダサい、寂しい
などのマイナスのものばかりなのである。
昭和30年ごろまでは、家庭照明といっても、部屋の中に裸電球がポツンとあるだけのもので、暗さはイコール貧しさと結びついていたわけなのだ。
暗い場所には楽しさがないし、兄弟が多くて食べたい物も食べられなかった辛さばかりが記憶されている。
しかも、年をとると視力が落ちるのはもとより、眼球の水晶体が濁って来るので、物がかすんで見えたりぼやけて見えたりするものだ。
高齢者の中には、白内障を発症している人も少なくないため、風景が黄色や茶色のフィルターを通して見ているような状態になるのだという。
如何に地デジ放送になったとはいえ、色の薄い白茶けた画面では演じる俳優たちの顔もはっきりとしなくなるのが普通である。
そこで、高齢者の目でもはっきりと物や俳優の顔が判るようにするためには、基本的に明暗をくっきりとさせて、彩度の差を付けるのが良いとされている。
これに当てはめて考えると、今回の大河ドラマは実に高齢者の目には優しくない色が映像に採用されてしまったといえるのである。
あまり馴染みのない平安時代を取り上げたストーリー展開や、人間関係の複雑さ、登場人物のやたら似通った名前など、視聴者は色々と覚えることだけでも大変で、素直に内容にのめり込めないだけではなく、加えて画面の色までもが判りづらいとなれば、ドラマ自体を敬遠したくなるのも当然なのだ。
そもそもドラマとは、嘘を作るものである。
視聴者は、平清盛の実直で朴訥な人間性よりも、謀略と裏切りに満ちた朝廷と武家の怨念めいた確執や、それを取り巻く宮中の女性たちの雅な恋愛模様や絢爛豪華な平安絵巻が観たいのだ。
それがあのようなボロボロの着物をまとった砂ぼこりまみれの男たちばかりが登場したのでは、視聴者の興味も失せるのは仕方がないといえよう。
とはいえ、これからいきなり画面を色彩豊かに変えることも出来ないだろうから、徐々に画面の彩度を上げて行くとか、女性の十二単をもっと重厚で豪華な物に替えるなどして、まずは観た目から変化させて行くことが大事なのではないかと思われる。
しかし、俳優たちの迫真の演技はなかなか見応えがあるし、台詞も最初の頃に比べるとかなり今風になって来たようにも感じる。(最初の頃をあまり観てはいないのだが・・・)
脚本にエピソードを詰め込み過ぎているのも、物語を判りにくくしている一因のようにも思われるので、あまりあれもこれも描こうと欲張らず、誰の視点を一話一話の軸に据えるのかということを、明確にしておいた方が視聴者にも判りやすいのではないかと思われた。
続きを読む
今は、いません。---?
2012年05月19日
今は、いません。---?

お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、一部で報じられたTBSの田中みな実アナウンサーとの熱愛をツイッターで否定した。
藤森は19日午前中、熱愛についてのフォロワーからの質問に「あの子、実はマジメでかたいからな~。仲はうぃーけど!無理だろなー!」と返答。チャラ男キャラとしてジョークを交えつつも、正式に報道を否定した。
田中アナは番組制作会社社員とのデートが報じられ、「みなさまに誤解を招きご心配をおかけしてしまってごめんなさい」と18日にブログで謝罪したばかり。藤森との熱愛が報じられたことで、二股交際なのではないかとネット上で話題になっていた。(YAHOO!ニュース)
こんな記事があったけれど、この田中みな実アナウンサーって、例のぶりっこキャラで最近ブレイクしている女子アナだよね。
先日観た、和尚さんたちに悩みを聞いてもらうというバラエティー番組では最後に登場して、やたらに「彼氏は、今はいません。TBSのために頑張ろうと思います!」を連発していた。
この時の彼女の表情を観ていて思ったんだけれど、彼女はかなり気の強い女性のようだ。
自分を一つのキャラで統一して注目を集めようという意図は判るのだが、その薄皮一枚下には、「わたしは、そんな軽い女じゃないわよ!」という素が強く透けて見えている。
これは、藤森くんがチャラ男を武器にブレイクしているのと一見同じなように思えるのだが、実は二人の戦略はまったく真逆なのだと思う。
藤森くんの方は、悪ぶっているが根は真面目な好青年。
比べて、彼女の方はお馬鹿でカワイ子ぶっているが、根は人生設計も男などには頼らない、正に鉄の女なのである。
しかも、彼女の言葉の最後には常に、「~~だと思います」が付く。
決して断定的な言い方はしないところに、「言ったことに対しての責任は取らないわよ」との保身が、しっかりと働いているのである。
つまり、かなり賢い女性でなのある。
そして、この「彼氏、今はいません」という言い方にも、その一端が垣間見れるのだが、「彼氏、いるの?」という質問に対して、「今はいません」とか「どう思います?」のような含みのある言い方をする場合は、十中八九真実を隠していると思ってもいいのだそうだ。
おそらく、彼女の中には意中の男性が既にいるのだろう。
ただ、相手の男性が彼女を意中の女性だと思っているかは、また別問題なのだが。
藤森くん、さすがに女性観察眼はしっかりしているようだ。(^_-)
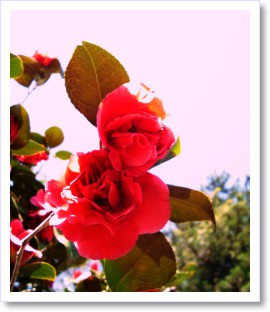
続きを読む
謙遜する女性の心理
2012年05月18日
謙遜する女性の心理

「あたしって、全然可愛くないし・・・」
「スタイル悪いし、こんなんじゃ彼氏なんか出来ませんよ~」
このように、如何にも悩んでいるような謙遜をする女性は、意外に多いものだ。
ただ、こういうことを言う女性に本当に可愛くなかったり、スタイルの悪い女性はあまりいないのも事実である。
では、彼女たちはどうしてこんな自らを卑下するような言葉を平然と吐くのか?
それは、彼女たちが、本心からそう思っているわけではないから言える言葉なのである。
明らかに太り過ぎだと思われるような女性は、決して自分のことを、「あたしって、太っているからモテないのよね」などということは言わない。
何故なら、彼女にとって「太る」という言葉は、自らに課した絶対的禁句なのだから・・・。
昔、わたしがかなりぽっちゃり気味の友人女性と買い物をしている時、別にさほど気にも留めずにわたしが放った一言に、その友人は俄然噛みついたことがあった。
「こんな細身のジーパン、あたしたちには穿けないよね」
わたしが言った途端、友人の顔色が変わり、
「わたしたちって、あたしも入っているわけ?」
と、言うのだ。
当然だろう----と、わたしは思ったが、どう見ても彼女はわたしよりも太っているにもかかわらず、同じ種類の人間とは思われたくなかったようなのである。
これが本当に自分にコンプレックスがある人の反応なのだ。
では、さほど見た目も悪くないにもかかわらず、あえて謙遜する女性心理とはどういうものなのか?
つまりは、彼女たちはそういう言葉を投げかけることによって、相手が、
「そんなことないでしょ。全然、スタイル良いじゃない」
と、言ってくれることを期待しているのである。
そう言ってもらうことで、安心感を得ようと謙遜という餌を投げているに過ぎないのだ。
たとえば、160センチの女性が体重55キロになったからといって、「あたし、太っちゃった」なんて言ってもそんな言葉は別に取るに足りない『謙遜の餌』と思えばいい。
その女性が80キロにもなったら、ようやくその謙遜にも現実的な深刻さが見えて来るというものである。
続きを読む
湯けむりドクター
2012年05月18日
湯けむりドクター

山ノ内町や中野市を舞台に繰り広げられるミステリー・ドラマ『湯けむりドクター 華岡万里子の温泉事件簿』のロケが、今、山ノ内町内で行なわれているそうです。
ドラマは、テレビ東京の水曜ミステリー9として放送され、これが六作目だとのこと。
わたしも、このシリーズは大好きで、毎回録画して観ています。
外科医・華岡万里子(かたせ梨乃さん)は、娘の持病療養のため、都会の病院を離れて田舎の診療所の医師として娘とともに赴任したという設定で、昔ながらの古き良き風習が伝わる村内で起きる数々の事件の犯人を、医師としての鋭い観察眼で暴いて行くというストーリーです。
頼りがいのある「華岡診療所」のベテラン看護師・青田富士子役の三林京子さんや長野県警の刑事・犬丸剛役の渡辺哲さんもストーリーに安定感を持たせていて好感が持てますが、殊に万里子先生のことが大好きな村長・志村仙吉役の石井愃一さんの演技がとても楽しいです。
この作品には、山ノ内町の町民が大勢エキストラ出演するほか、町内にある建物や町周辺の自治体の風景などもふんだんに撮影されているので、とても親近感が湧くドラマなのです。
今回のロケでは、リンゴの花が満開の菅(すげ)地区の樹園地を使い、奥信濃村長選の遊説シーンなども撮影されているそうです。
番組の放送予定は、首都圏が7月で、長野地方の放送は8月から9月を予定しているそうです。
(写真は、北信ローカル紙から)
続きを読む
自慢こそが自己防衛
2012年05月17日
自慢こそが自己防衛

「わたしは、何でも出来る」
「あれも、これも持っている」
「何もかも知っている」
こんな言動を癖にしている友人が、あなたの周りにも一人や二人いるはずです。
「ああ~、また、例の自慢話が始まったよ」
そう周囲がうんざり顔で聞いていることに気付きながらも、どうしてその人は自慢話をやめないのでしょうか?
それは、その人にとって、自慢話が自己防衛手段の一つだからなのだそうです。
周りにつけ込むすきを与えてはならない。
自分を周囲の攻撃対象にはさせない。
そんな過剰な防衛本能が、こうした自慢をさせることになるのだそうで、そういう人ほど実は自らの弱点を熟知している可能性が大なのです。
自分の内面の弱さを相手に見せまいとすることで、こうした必要以上の自己主張に走ってしまうことは良くある話で、そのことがさらに敵を作るはめになることに気が付かないのだとか・・・。
こういう自己防衛本能の強い人は、自分というものに自信がないために物や他人の威光を己の身にまとう形で、安心感を得ようともするのだそうです。
でも、こういう考え方って、かなり侘しいものですよね。
要は、寄りかかる物がなければ自立出来ないことを暴露しているようなものですから。
ぜ----という語尾が意味するもの
2012年05月16日
ぜ----という語尾が意味するもの

男性が時々使う「ぜ」という語尾には、どういう意味が含まれているのだろうか?
「今度、飲みに行こうぜ」
「よかったら相談に乗るぜ」
近頃はお笑いピン芸人のスギちゃんも、この「~だぜェ」を連発している。
「ワイルドだぜェ~。最終回の登板が残っているのに阪神ファンが、どんどん席を立って行ったぜェ~」
(スギちゃんは、プロ顔負けのマジックの腕前を持っているのに、どうしてこんな芸で人気を集めているのか不思議なのだが・・・)
どうやら、この「~ぜェ」には、相手に対する男性特有の優越感や寛大さを見せるという意味があるようで、下目に見ている相手にほど、使いたくなってしまう語尾なのだそうだ。
つまり、スギちゃんの芸が可笑しいのは、スギちゃんというどう見てもうだつの上がらなそうな滑稽な風体の男性が、その事実に気付かないまま、観客に向かってさも自分の方が立派な人間なのだとアピールするところにあるのだが、その効果を倍増しているのが、この「~だぜェ」なのである。
しかも、この「~ぜ」には、相手に対して「きみだけなんだ」という切迫感がない。
「きみの相談は受けてやるよ。でも、こっちもそう必死になって相談に乗るわけじゃないからな」
と、いう気持ちがやんわり透けるのが、この「~ぜ」なのである。
こういう語尾を頻繁に使う男性の性格は、どちらかというと親分肌の兄貴風を吹かすタイプだから、こういう男性の気を惹きたいと思うのならば、逆に、
「自分にとっては、あなたこそ特別な人です」
的な態度や言葉使いをすることで、好感度は上がるそうである。
因みに、この間の「(笑)の考察」に補足するのだが、この(笑)には、本心をカムフラージュするという役割があるのだが、冗談ぽい事柄のあとに(笑)が来ていた時は要注意である。
たとえば、「きみに対して良からぬ気持ちなんか持たないから。(笑)」のような場合は、「持つかもしれないぞ~」という気持ちが十分に隠れていると思った方が無難だとのことである。
続きを読む
ブログの読者の増やし方
2012年05月16日
ブログの読者の増やし方

今日の信濃毎日新聞に「ブログひと工夫 愛読者増やそう」という記事があった。
記事には、ブログをアップする時間帯を、読者層をある程度絞り込むことで出来るだけ定時にするとか、文字に大小を付けたりカラーにするなどして読者の目を惹こうなどの、ブログのアクセス数を増やすうえでの効果的な方法が書かれていた。
この記事にアドバイスしているのは、ナガブロガーさんだそうだが、確かにどのような記事が読者の興味に応えることが出来るのかを見極めるのは容易な作業ではない。
ブログは、ほぼ毎日書くものだから、アクセス数を稼ぐことばかりを目的にしてもブロガー自身が疲れてしまうこともある。
やはり、アクセス数も大事だが、ブロガーが無理なく楽しく書けるような、自身にとって興味のある話題や書き方をするのも長く続けるための秘訣ではないかと思われる。
わたしの書く記事は、以前、「読んでいて疲れる」と言われたこともあるほど理屈っぽいし、かといってカラー文字を多用することもない、いわゆる「文字ブログ」の類なのだが、やはり自分にはこういう書き方が一番合っているようにも思うのだ。
ブログには、写真で魅せるブログもあれば、文章力や情報量で読者の興味を惹くものもある。
また、きわどい表現を多用することで、記事その物ではなく、書き手のブロガー自身に興味を覚えさせるという新手を駆使するブロガーもいる。
まあ、ブログの書き方は多種多様だが、わたし個人の希望としては、もっと自身の考え方や思いを反映させた文章で読ませるブロガーさんが多く出て来て欲しいと思うのだが・・・。
皆さんは、如何だろうか?
続きを読む
日本語は難しい
2012年05月15日
日本語は難しい

日本語というものは、何とも難しいものだ。
先のブログ記事に「人気のない志賀高原が好き」というのを書いたのだが、あとでタイトルを読み返してみて「こりゃ、いかん!」と、慌てた。

この「人気」という漢字、読み方を間違えればまったく意味が変わってしまうことに気付いたからだ。
そこで、「人気(ひとけ)」と、ふり仮名を付けることにした。
以前、どーもオリゴ糖さんが教えて下さった「関ヶ原で戦死したのは何人?」のクイズのようになってしまった。
これも、「何人?」を「なにじん?」と、読むことで正解が判るというものだった。
もちろん、答えは、「日本人」だ。

ところで、あなたは自分自身が親離れで来ていると思っているだろうか?
「もちろん、親離れしているわ。だって、わたし結婚しているもの」
と、いう人がいても、それが本当の親離れなのかは怪しいという。
要は、親の代わりが配偶者になっただけのことではないのか?
ある心理学者は、親離れの意味をこう説明している。
「親に対する依存心をなくした時が、親離れである。依存心をなくした時とは、自分が親から可愛がられようと思わなくなった時ということだ。つまりは、親の機嫌をとる必要を感じなくなった時ということである」
しかし、それは何も親や配偶者に対する日常の無意識化とは違う。
これを当てはめると、配偶者の機嫌を気にするうちは、完全な意味での親離れとはいえないようである。
続きを読む
ゆきつぼさんの記事
2012年05月15日
ゆきつぼさんの記事

五月十二日(土)の長野市民新聞にナガブロガーのゆきつぼさんの記事が掲載されました。(上の記事です)
栄村出身のゆきつぼさんが、栄村をもっと知ってもらいたいと、昨年三月十二日の長野県北部地震で被災した同村の文化伝統を発信する企画展を、長野市長門町のカフェ『マゼコゼ』さんで開いているという内容です。
同企画展は十九日までで、入場無料とのことです。
栄村の方たちは、今、懸命に復興への足がかりを模索しています。
わたしの知り合いの栄村出身の方も、「とにかく、まず村がどういうところなのか知って欲しい」と、話していました。
ゆきつぼさんの企画展は、きっと皆さんにそんな栄村を身近に感じてもらえる一助となることでしょう。
豪雪と歴史とぬくもりの里・栄村をもっと知りたいと思われる方は、ぜひ開催期間中に足を運んでみては如何でしょうか?
続きを読む
イエス、ノーの見分け方
2012年05月14日
イエス、ノーの見分け方

人と話をしている時、「この人、わたしの意見に賛成なのかな?それとも、反対なのかな?」と、気になって仕方がない時ってありますよね。
そんな時は、相手の手の仕草を見ていると、意外にその本音を知ることが出来るんだそうですよ。
たとえば、相手が自分の顎に片手を添えてあなたの話に頷いている時や、テーブルの上に両の手のひらを開いたまま載せているとか、テーブルの上にある湯呑み茶碗などを手で横へよけたりする時は、たいてい、あなたの話をもっと聞きたいと思っている証拠だそうです。
顎に片手を添えて頷くということは、神経を集中しているということであり、手のひらを開いたままテーブルに載せているということは、あなたに対して気持ちを開いているという証拠なのだとか・・・。
また、テーブルの上の湯呑茶碗などを横へ片付けているということもまた、あなたとの間に垣根を作りたくないと思っている無意識の行動なのだそうです。
ところが、その逆に、相手が、顎の前で握りこぶしを作るとか、両手を頭の後ろで組む、両手で顎を支える、テーブルの上を指でコツコツ鳴らす、テーブルの上の湯呑茶碗やペンケースなどを頻繁に手で移動させる、指先で額の真中を押すなどの仕草をしているような時は、あなたの話に否を唱えたいと思っている証拠なのだそうです。
顎の前で握りこぶしを作ったり、顎を両手で支えるなどの仕草の場合は、あなたに対する防御姿勢であり、両手を頭の後ろで組むというのは、既にあなたの話に飽きている証拠。
テーブルの上でコツコツ指を鳴らすのは、あなたの話が長いのでイライラしている意味であり、テーブルの上の湯呑茶碗やペンケースなどを頻繁に移動するのは、あなたの意見に反論したいという気持ちの表われであり、額の真中を指先で押している時は、あなたのアイデアには無理があると言いたいような場合だということのようです。
脚の組み方や置き方にも人の気持ちは大きく表われますが、手の仕草からもやはり同じように気持ちの動きは見えるもののようですね。
続きを読む
人気(ひとけ)のない志賀高原が好き
2012年05月14日
人気(ひとけ)のない志賀高原が好き

先日、あるバスツアーでこちらを訪れたという観光客の中年女性が、散歩途中のわたしに道を訊ねたついでに、こんなことを言っていた。
「実は、ツアーに申し込んだら、あたしと友人だけ、泊るホテルが志賀高原のホテルになってしまったんですよ。他の人たちは麓の旅館やホテルに割り当てられたんだけれど・・・。
そうしたら、今の季節の志賀高原て本当に誰もいないのよね。スーパーがあるわけじゃないし、遊ぶところもなくて、あんまり寂しいから路線バスで山から下りて来ちゃった。
でも、予定ではもう一泊することになっているから、また戻らなきゃならないんだけれど・・・」
そりゃァ、そうだろう。
この時季の志賀高原といえば、山へ入るのはたいていが山菜採りの地元住民ぐらいだから、ホテルでの宿泊客などほとんどいないのが相場だ。
きっと、ホテルの中もガラ~ンとしていて、人の気配もないんじゃないかな?
女性の話を聞くと、ミステリー・ツアーの類の旅行のようだから、目的地は観光業者任せで自分たちは何処へ行くのか判らなかったらしい。
それにしても、ホテルがちょうど時季外れの志賀高原とは、それだけでも十分ミステリーだ。

そういえば、昔、わたしも良く冬季のスキー以外でも志賀高原のホテルに泊まったことがあったが、そういう時は、やはりいつも6月ぐらいの梅雨寒むい頃であった。
でも、わたしは、何故かその時分の志賀高原の閑散とした空気が好きだった。
友人と一緒に人気のないハイキング道を歩くのも好きだったし、他には宿泊客の影さえないような広々としたホテルの中も何となくワクワクしたものである。
晴れた日よりも、どんよりと曇った空に薄墨を溶かしたような霧が流れ、それが青黒い山肌を覆うさまがまた何とも言えず、無性に創作のイマジネーションを掻き立てられたものである。
まあ、こんな風に感じる人は、あまりいないんだろうな。
最近は、志賀高原へも行っていないが、こんな季節になるとあの頃の神秘的な光景が思い起こされて、ちょっと楽しい気持ちになるものだ。
 続きを読む
続きを読む本心を隠す人
2012年05月13日
本心を隠す人

大人になると子供の頃と違って、簡単には本音で欲求が表現できなくなるものだ。
たとえば、先の料理研究家・園山真希絵さんの例もそうだが、彼女は本心では塩谷瞬が大好きで仕方がないのだが、それを口に出すのは照れくさいし、子供っぽい女性だと軽んじられても面白くないと思うあまり、
「わたしをお嫁さんにして下さい!」
という、直接表現が出来ずにいたのではないかと思われる。
つまり、彼女は、単に自分本位の暗黙の了解のうちに、彼の妻になったような錯覚を懐いていたのだと推察される。
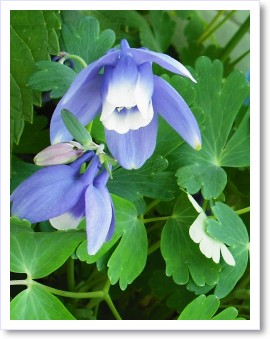
ところが、当の塩谷瞬は園山さんはあくまでもごく親しい友人の一人だという認識だったわけで(たぶん)、内心では薄々、「彼女、もしかしておれと結婚したいなんて思っているのかな?」との思いはあったにせよ、園山さんが自らの意思をはっきりと口に出さないために、なあなあの関係を続けるしか仕方がなかったのではないかと思われる。
ところが、二股問題が浮上した途端、園山さんは自分が塩谷の本命ではなかったと知り、その醜態を払拭するために、色々な言い訳を用意する破目になったのである。
「最初から、バカでアホな男だと知っていた」「私しかこの人を再生させるのは無理」などの言葉を並べたて、あくまでも自分は彼のことが見捨てられなかったわけで、彼に惚れていたわけではないと自身も周囲も納得させようとしているのである。
しかし、それが彼女の本心ではないため、そんな言葉を百万遍重ねたところで、彼女の気持ちは納まらないはずなのだ。
たった一言、「わたしは塩谷に騙された!本当は大好きだったのに、どうして、結婚相手がわたしじゃなかったの?」と、言えるならば、園山さんの気持ちもかなりすっきりするだろうに・・・と、番組視聴者は思いながら観ていたに違いない。
これもまた、神経症の一種といえるようである。
「ママ、あれ買って!」「パパ、あそこへ連れてって!」
子供ならば、駄々をこねても周囲は許してくれるが、大人がそんなことは恥ずかしすぎて口が裂けても言えない。
だから、自分の気持ちを納得させるための理屈を必死になって考える。
「きみが前から欲しいと言っていたから買おうっていうんだ」「子供たちが行きたいって言うから仕方なしに行くんだよ」
ところが、それを聞いた周囲や家族がそれに理解を示さず、
「別に、わたしは欲しくないわ」「ぼくたち、勉強があるから行きたくない」
などと言おうものなら、言い出した本人は引っ込みが付かなくなってしまい、「おれがこんなに親切に言っているのに、何だその態度は!」ということになってしまうのである。
ただ一言、「本当はおれが欲しいんだよ」とか「おれが行きたいんだよ」と、素直に言えれば人生も楽なのだが、子供の頃から優等生の我慢強い子などという評価をもらって生きて来た人には、この本音がどうしても言えず、結果自分を偽り続けることになってしまうのだそうである。
続きを読む
狭い世界しか見えない人
2012年05月13日
狭い世界しか見えない人

人は、自分が生まれ育った環境だけが現実であるかのような錯覚をしがちである。
まったく異なる環境に生きて来た人の話を聞いても、架空の出来事を聞かされているようにしか受け取れないという者は多い。
これが芸能人とか政治家のように、一般人とはかけ離れている世界の人間の話なら、「そういうこともあるだろう」と、いう開放的な視野を持つことも出来るのだが、こと相手が自分とさほど変わらない境遇にいると思い込んでいる人間だった場合は、その想像力がほとんど働かなくなってしまうことがあるのだ。
たとえば、数十年前まで自分の家の近くに住んでいた人の情報が新聞に掲載され、それが何と大会社の新社長に就任したというような内容だったとする。
こんな時、人はまず、「そんなバカなことがあるわけがない。あんな奴が大会社の社長になんかなれるものか」と、考える。
そこで、「きっと同姓同名の似たような誰かに決まっている」と、思い込もうとさえするのである。
この他にも、こんな例もある。
普通に家業を継いで小さな商店の経営者に納まった男性には、絵画などの芸術は決して日常的に身近にあるものではなかった。そのため、彼には絵の価値というものがさっぱり判らない。
ある日、そんな彼の店へ、道を訊ねるために偶然にも有名な日本画家が立ち寄った。
画家はある画廊へ自分の描いた絵を持って行くところだったので、道を訊く間その絵をそばの壁に立てかけておいた。すると、その店の主人はそれを見て、「おじさん、そんなところへ絵ぼっこ立てかけないでくれないか。邪魔でしょうがない」と、言ったのである。
つまり、自分が生きて来た狭い世界しか知らない商店主にしてみれば、絵画などというものはどんな有名な画家が描いた作品でも、単なる「絵ぼっこ」にしか見えなかったのである。
人は、とかく物事を自分だけの目線や尺度で考えたがるものだが、それがとんでもなく失礼なことであるという場合も多いのだ。
ほとんど本を読まない人にとっては、作家などという仕事は子供のお話作り遊び程度にしか思えないだろうし、クラシック音楽など聴いたこともないという人にとっては、日本を代表するような名作曲家だってただの暇人としか認識し得ないのかもしれない。
そういえばかつて、こんなエピソードを聞いたことがある。
ある有名な時代劇の大スターが夜中に酔っぱらって自宅マンションの近くで大声をあげた。
すると、突如、近くの安アパートの窓が開いたかと思うと、男性が一人顔を出して叫んだのだそうだ。
「バカ野郎!いったい今何時だと思っているんだ?こっちは、お前みたいに毎日遊び呆けているわけじゃないんだ。睡眠妨害するんじゃねェ」
その大スターはこれを聞いて思ったそうである。
「おれの仕事など、テレビドラマや映画に興味のない人にしてみれば、単なる遊びに見えるんだろうな・・・」
続きを読む
園山真希絵さんの言い分
2012年05月12日
園山真希絵さんの言い分

昨夜、珍しく『中居正広の金曜日のスマたちへ』を観ていると、あの二股騒動の当事者である料理研究家の園山真希絵さんが出演していた。
園山さんは、例の俳優・塩谷瞬との破局にいたる一連の騒動について、克明かつ正直に打ち明けていた。
彼女の塩谷瞬に対する気持ちの中心には、常に、「わたし以外にこの人を再生させるのは無理」というフレーズがあったようである。
園山さんと塩谷瞬の出会いは、彼女の経営する割烹料理屋に彼が食事をしに訪れたことから始まったようだが、再現VTRを観ながら、おそらく、一目ぼれしてしまったのは彼女の方なんだろうな・・・と、思った。
何故なら、園山さんが「最初に彼と会った時の印象はあまり良くなかった」と、語っていたからである。
最初にあまり良くない印象を与えられた方が、そのあとに好印象を得ると、相手に対する好感度が急上昇するというのは、心理学において当然のセオリーだからである。
しかも、相手は人気上昇中のイケメン俳優である。
たぶん、園山さんは、そのあとで食事をしている際の塩谷が本当においしそうに自分の料理を口に運んでくれる姿に、一気にノックアウトされてしまったに違いない。
しかし、彼女の中のプライドが自身が塩谷に懐いている想いを『恋愛感情』と、決めつけることを許さなかった。
そこで彼女が無意識のうちに編み出した方法が、「彼にはわたしが付いていなければダメ」という母性本能をカムフラージュに使った言い訳だったように思われる。
では、塩谷瞬の方には彼女に対する恋愛感情があったのか?----と、考えると、あの再現VTRを見る限り、ほとんどなかったのではないかと想像されるのだ。
何故なら、彼は、最初の頃に既に彼女が差し入れてくれていた高級弁当をあまり食べてはいなかったからである。
本当ならば、園山さんは、この時点で彼の愛情がそれほど自分にはないことに気付くべきだったと思うのだが、「ここで彼を手放したくない」という感情の方が先行してしまったが故に、「彼を放っておけない」という正義感へと気持ちを無理やり置き換えて、彼の押しかけ彼女に徹することになったのではなかろうか。
しかも、VTR中に塩谷の口から彼女の料理をほめる言葉は出て来ても、彼女自身をほめる言葉が一度も聞こえて来なかったのも、気になるところであった。
園山さんは、彼を教育していたと言うが、それは正に教師と生徒の関係であり、いつしか塩谷にとっての彼女は、要は食べたい時においしい料理を作ってくれる「都合の良い年上の家政婦」となってしまっていたのかもしれない。
家政婦に対して「愛している」とか「好きだ」というような言葉を言う男性はいない。
加えて、気弱な性格の塩谷が、園山さんに本心を伝えることを恐れるがために、ますます彼女の誤解に拍車をかけてしまい、ついには親戚に彼を結婚相手と紹介して回る婚前旅行にまでエスカレートしてしまったのだろうと考える。
そもそも最初から塩谷瞬には園山さんと結婚したいなどという気持ちは、さらさらなかったのではないだろうか。
そして、「園山さんなら、ぼくが他の女性を結婚相手として紹介しても、最後には許して受け入れてくれるにちがいない」との甘えがあったものと想像される。
一方、塩谷瞬の冨永愛さんへの気持ちは、間違いなくそこそこの恋愛感情だったのではないかと思われる。
だからこそ、プロポーズもしたのだろう。
どうも、色々なテレビ番組に出演するタレントや歌手などのこの問題に関する発言を聞いていると、塩谷瞬という男性は気弱に見える半面、なかなか打算的な側面もあるようだ。
冨永さんへの愛情も、きっと彼女が世界的に有名なモデルで女優だということから、彼女と一緒になれば俳優としての地位も盤石なものになるはず----という打算がなかったとはいえないだろう。
著名な若手料理研究家の夫というよりも、ずっと箔が付くに違いない。----未だ俳優としての足固めを模索しつつある塩谷にとって、そんなイメージが働いたとしても何ら不思議ではない。
とはいえ、この園山さんのような、「いわゆる思い込み恋愛」のケースは、一歩間違えればストーカーにもなり兼ねないパターンでもある。
だが、彼女の場合は、自身が有名人であったということが救いでもあった。
塩谷瞬の二股が発覚して以来、連日マスコミが大騒ぎしたことと、冨永さんが実に割り切った対応をしたおかげで、園山さんの中にもある程度の整理が付いたものと思われる。
しかし、司会の中居正広が番組の最後に指摘していたように、園山さんの中には、まだ塩谷に対する憎からぬ思いが少なからず残っているのも事実のようだ。
一年ぐらい経ってから、園山さんと塩谷瞬の間に改めて恋愛関係が芽生えないとも限らない。
こういう園山さんのような女性は意外に情が深いので、また今後塩谷瞬がひょっこり彼女の料理屋を訪れるようなことがあれば、そのままずるずると----というようなことになる可能性もなくはないのだ。
ただし、そうなった時は、園山さん自身も塩谷の前で大人ぶったお釈迦様の真似ばかりしていないで、時にはやきもちを焼くくらいのわがままな一面を見せるなどした方が良いと思う。
でも、おそらく尊厳に生きる彼女には、そういう自分の弱点を見せるような恥ずかしいことは、決して出来ないだろうけれど・・・。

続きを読む





