あまり年とったから・・・
2012年03月30日
あまり年とったから・・・

高齢者にとって気になる言葉は、色々あると思いますが、ある女性は、
「あまり年とったから、判らなかった・・・」
と、言われたことがショックだと言います。
この女性は、いつも髪の毛を染めて綺麗にしてたのですが、このところ風邪が長引いていたせいもあり、髪を染めるのがおっくうで、しばらく白髪を放置していたところ、久しぶりに会った50代の知り合い女性から、
「やだ、〇〇さんじゃない。あまり年とったから、判らなかった。白髪染めないと、誰だか判らないよ」
と、言われたのだそうです。
髪など染めても染めなくても年は相応にとっているんだから、ああいう言い方は失礼だと、高齢女性は話します。
若い人が今までの長い髪を切ってショートヘアにしたからといって、あまり年とったから----などとは言われないはずですよね。
月日が経てば年は誰もがとるものですから、もしも、高齢女性が誰だか判らなくても、「年とったから」は、必要のない言葉ではないかと思います。
「髪、染めていないから、見違えちゃった・・・」
ぐらいなら、たぶんその女性もさほど傷付かずに済んだのではないでしょうか。
まだ、50代ぐらいの若さの人は、老人の気持ちが判らないためにとかく配慮に欠けた言い方をしてしまいがちですが、
「今のうちに見ておいた方が・・・」とか「今度~~することが出来るかどうか判らないよ」などという言葉は、高齢者には実にショックな言い方なのです。
「冥土の土産に」などということを高齢者はおどけて口に出すことがありますが、これは本心から言っている言葉ではないと考えるべきです。
ましてや、若い人が口に出すのは極力控えるべき一言だともいえるのです。
今日は、良いお天気でした。
2012年03月29日
今日は、良いお天気でした。

やっと、春らしい良いお天気になりましたね。
散歩中は、むしろ日差しが暑いくらいで、上着を着ているのが煩わしく思えたほどです。
こんな天気が長続きしてくれるといいのですが、また、一気に寒さが戻るのでしょうか?
それにしても、ガソリン、値上がりしましたよね。
父親曰く、「バイクのガソリンなんて500円あれば足りていたのに、今日は610円もした」

どうりで、お昼のワイドショーでもにガソリン値上げがもたらす影響について特集を組んでいました。
市販の弁当一つとっても、パックは石油から作るものだし、おかず類もビニールハウス栽培の野菜を使えば暖房が石油だということで結局値上がりになるそうで、いくら米や小麦の値段が下がっても配達コストがかかれば更に意味がないのだといいます。
原油の値上がりは電気料金の値上げにもつながりますから、電気炊飯器でご飯を炊いている飲食店などにももろに影響が出ますし、必然的に提供する料理を50円ほど値上げしなければやっていけないと、ある飲食店主は悩んでいました。
毎回の食事が50円上がるというのは、家計にもかなり響きます。
この春は、正に値上げの春ともいえそうです。

そんな訳で、コンビニにある比較的安価な自社製品は助かりますね。
今日は、一袋に4パック入ったチャーハンの素を買ったのですが、さっそく冷やご飯で作ってみたところ、これがメーカー物に引けを取らないくらいおいしかったです。

今日は、あまり書くことがないので、この辺で・・・。
ネット依存症
2012年03月28日
ネット依存症

インターネットなしでは生きて行けないというほどの、いわゆるネット依存症に罹患する日本人が急増中だそうだ。
あえて罹患と書いたのは、韓国など海外では既にこの症状を病気と認定し、精神科医やカウンセラーなどが患者の診療に当たっているというテレビニュースを観たからである。
ある女子高生の一日をグラフにしてみると、なんと、二十四時間のほとんどを携帯電話片手に過ごしていて、夜眠る時間までもが削られていた。
教室でも友人たちとおしゃべりしながら携帯をいじる。
家へ帰り食事をしながら、やはり携帯を見ている。
その後、自室へ入りテレビを観ながら携帯で友人とメール。
彼女の手が携帯から離れることは、ほとんどない状態だ。
今、こうした携帯電話やスマートフォンを手から離せないという若者やビジネスマンが急増しているのだそうである。
また、ネット依存症は携帯電話に限らず、パソコンでも起きることがある。
何十時間もネットカフェでチャットなどをしていた男性が、座りっぱなしのためのエコノミー症候群で急死したというような事例も報告されているらしい。
ネットゲームにはまり、昼夜の感覚がなくなったという若者も多く、家の中でご主人が携帯ゲームに熱中するあまり家族間の会話が激減したと嘆く女性もいる。
海外では、こうしたネット依存症は、アルコール中毒や薬物中毒などと同じく病気であると認識されていて、多くの患者が精神科医やカウンセラーを受診しているそうである。
このネット依存症を治すために一番手っ取り早い方法は、インターネットがつながらない環境に患者を置くことだとか。
そのため、韓国ではネット依存症の子供たちを集め、携帯電話もパソコンもない場所で長期間の合宿生活を送らせるのだそうだ。
そこでは生身の友だち同士で体験できるキャンプや力仕事をして、インターネットよりも楽しいことが世の中にはあることを知ってもらうのだそうだ。
インターネットの世界だけが唯一の自己表現の場だと思い込んでいる人は、逆に生身の人間の方が信じられないという傾向が強いのだという。
ネット依存症を克服するには、こうした意識を変えさせるのが最も重要なのだそうだ。
しかしながら、自分または子供が本当にネット依存症なのか、それとも単なるネット好きなのか、その境界が判らないというのがこの病気を発見するうえで難しい問題なのだともいう。
ブロガーの中にも他のブロガーと毎日コメントのやり取りが出来ないと不安で寂しいとか、自分だけが仲間外れにされているような気がするなどという人が時々いるが、これもある意味ネット依存症の予備軍と考えられるそうである。
あなたは、仕事の合間でも携帯電話が気になることはないだろうか?
ブロガー同士のコメント会話に入れずに悩んだことはないだろうか?
仕事で使用しているわけでもないのに、気が付いたらパソコンの前から何時間も動いていなかった・・・などということはないだろうか?
もしかしたら自分はネット依存症なのでは・・・?
そんな風に感じた時は、一度携帯電話やパソコンから徹底的に離れる生活を送ってみるのも一つの方法だと思う。
続きを読む
救急隊員も大変です。
2012年03月28日
救急隊員も大変です。

近所に救急車が止まった。
ところが、いつになってもその救急車が発車する気配がない。
急患の受け入れ病院が見付からず困っているのかと思いきや、そうではなかった。
どうも、救急車を呼んだ方が、いざ到着した途端に乗るのを渋り始めたようなのだ。
その乗車を渋る男性を相手に、救急隊員たちは事情を聞いたり搬送するための説得をしているらしいのだが、男性はそれを拒否し続けている。
「余計なことするな!」
「関係ねェ!」
と、いうような声も聞こえてきた。
どうやら、酔っ払っていたようだ。
救急車を呼んだ人物と急患は別の人間だったのか?
男性は結局最後まで乗車するのを拒否。
仲間らしき人物が運転する車に乗って、その場からいなくなってしまった。
かなりの時間を説得に要したのち、救急車も急患を搬送することなく、その場から去って行った。
まあ、そんな一部始終を見ていたわたしも、暇っちゃァ暇なんだが・・・。(~_~;)正直、野次馬です。
それにしても、急いで駆けつけてきたうえに相手に怒鳴られては、救急隊員もたまったものではない。
でも、おそらく、彼らにとってはそんなことは別に取り立てていうほどのこともなく、こんな経験はしょっちゅうなんだろうなァ・・・と、思う。
悪態をつく男性に対しても、実に冷静な対応だった。
とはいえ、ふと考えた。
もしも、こんなことにかかわっている間に、本当に一分一秒を争う急患の搬送要請が来た時はどうするのだろうか・・・と。
おそらく、今回救急出動を要請した人は、その男性の泥酔ぶりに手を焼いて思わず119番通報してしまったのだろう。
だが、こういう時に通報するべきは、消防署ではなく警察なのでは?
詳しいことは判らないが、春先ともなると色々なお騒がせ人間が出没し始めるようだ。

続きを読む
今日は、暖かかった。
2012年03月27日
今日は、暖かかった。

今日は、暖かかったですね。
やっと、春らしいお天気になりました。
でも、また明日は雨模様になりそうですが・・・。
こんなに寒い日が続いたのだから、今年の夏はあまり気温が上がらないのでは?----と、思いきや、夏はそれなりに平年並みの暑さになるそうですね。
冬は寒すぎて暖房費がかさみ、夏は夏で暑すぎて冷房費がかさむ・・・。
考えてみれば、長野県は本当に大変な気温差の地域に位置するところだといえるようです。
「よくこんなところに住んでいるよね」
県外から来た観光客には、道を訊ねられたついでなどに時々言われます。
確かに、観光で二、三日滞在するにはいいところなのかもしれませんが、生活するには過酷な地域なのでしょうね。
ところで、昨夜は不思議な夢を見ました。
夢の中に「金色」の物が出て来る夢というのは、あまりないそうなのですが、夢の中にその「金色」のカットばさみが出て来たのです。
金色というのは、神秘性や英知、崇高さ、パワー、エネルギーなどを示す色なのだとか。
それがカットばさみですから、髪を切るものですよね。
つまり、気持ちに区切りがついて、新た気分で再出発出来る---という暗示だそうです。
夢の暗示のように、何かいいことがあるといいのですが。
この冬は体調面といい、とにかくひどかったですから・・・。
で、話はまた変わりますが、猫ひろしさん、ロンドン五輪マラソンのカンボジア代表に決まったそうですね。
この代表選考にはカンボジアや日本でも賛否両論あるようですが、何はともあれ代表になったのですから全力で頑張って欲しいものです。
写真は、かつて長野マラソンを走っていた猫さんです。
いったい、誰!?
2012年03月26日
いったい、誰!?

先日、某スーパーで、偶然知り合いの主婦に会いました。
「ねえ、聞いてよ。この間さァ・・・」(゜o゜)
その主婦が話すには、
「独りで外湯に入っていた時に変なことがあってね。お風呂の入口のドアの鍵が開けられるブザー音がしたのに、いつまで経っても誰一人入って来ないのよ。そうしたら、また、何度か音がして・・・。それでも、誰も入って来ないから、気味が悪くてね・・・」(-_-;)
「何なんですか、それ?悪戯ですか?」(・_・)
わたしが訊ねると、
「こっちも、そうかもしれないと思って急いで湯船から上がって、身体を洗うのもそこそこに脱衣所へ出たのよ。もう、気持ち悪いから、誰か男の人でも入って来たら嫌だと思って急いで服を着てね。そうしたら、入口の外の方で、大勢の人のしゃべり声までするじゃない。ますます、気味が悪くなってさ・・・」(・_・;)
主婦は、外の人たちに顔を見られないようにしようと、頭からバスタオルをかぶって外湯を出たのだそうです。
すると、そこにいたのは数人のテレビ番組のロケ隊で、彼女はカメラ撮影でもされたら嫌だと思い、大急ぎでその場から走り去ったのだと言いました。
「それは、災難でしたね。外湯は誰が入って来るか判らないですから、ブザーが鳴るばかりで誰も入って来なければ、何があったんだろうと気が気じゃないですよね」(ー_ー)!!
わたしが言うと、主婦は本当に不愉快そうな表情で話します。
「嫌だよね~~。ロケをするなら、いついつやりますから、その時間は入浴しないでください----ぐらいの連絡をしておいて欲しいもんだわよ。もう、あのあと一日変な気分だったわ」(>_<)
「お風呂上がりなんて、人に見られたくないですよね。顔、撮られちゃいましたかね?」(・_・)
「バスタオルをかぶっていたから大丈夫だと思うけど・・・」(T_T)
確かに、話を聞けば気の毒としか言いようがありません。
入浴中の女性を驚かすようなことは、たとえテレビ局でも遠慮して欲しいと主婦は語っていました。
わたしだったら、たぶん大爆発だな。(ーー;)
続きを読む
『相棒ten』最終回
2012年03月25日
『相棒ten』最終回

『相棒ten』の最終回は、クローン人間誕生か?----という話でしたね。
二人目相棒の神戸尊もこれで警察庁官房付きとなり、特命係を去りました。
神戸役の及川くんに関しては、ようやく彼らしい演技が観られたような気もしました。
あの切羽詰まった演技を観てしまうと、もう少し続けて欲しかった・・・とも思ってしまうのですが。
これまでの間に、どうしてああした彼の演技力を引き出すシナリオが書けなかったのかなァと、残念です。
ミステリーのトリックやプロットにこだわり過ぎたせいで、俳優の演技への演出面がおろそかになっていたのかもしれませんね。
それにしても、「クローンとは、遅れて生まれて来る双子の一人」という杉下右京の説明で、なるほどと思いました。
ただ、クローンとして生まれて来るということは、クローン胚性幹細胞組織は体細胞提供者の年齢ということなので、誕生の瞬間既に0歳ではないということになるという話を聞いたことがあります。
つまり、それだけ短命だということなのかな?
また、クローンには世間の風当たりもさることながら、その他色々な障害をもつ可能性もあるのだとか・・・。
そう考えると、確かにそうなることが最初から100パーセント判りながら、人間として誕生させるのは酷なような気もします。
物語では、結局最後は生まれなかったという形になりましたが、ただ、これが『相棒』という特異な刑事ドラマのストーリー上よかったのかどうか・・・。
案外、制作スタッフの間でも意見が分かれたのではないでしょうか。
今後、杉下右京の新しい相棒が誰になるのかも興味がありますが、こうした一般人ではあまり知ることが出来ない職業や業界の人間を犯人にするようなストーリー構成を期待したいと思います。
日照不足が・・・
2012年03月24日
日照不足が・・・

天気が悪いと、気分的に調子が出ない人は多いですよね。
わたしも、モロこのタイプです。
しかも、ここに寒さが加わったらもうダメですね。
思考回路まで停滞して、ほとんどうつ状態に近くなってしまいます。
北日本では西日本にくらべて自殺者が多いというのも、案外そういう日照不足や寒冷が大きな原因なのかもしれません。
先日のテレビ番組でも、この太陽光が不景気と密接な関連性があるということを伝えていました。
過去にも太陽の力が弱くなった時期と、世界恐慌などが起きた時期がしっかりと重なるのだとか。
以前、当ブログに現在の太陽で磁場を構成する黒点の数が減少しているということを書きましたが、黒点が少ないということは、すなわち太陽の力が弱まっていることを意味するのだそうです。
太陽の力が弱くなると太陽が自力で周りに張り巡らせているバリアーの威力も弱まるということで、宇宙放射線がまともに地球へ降り注いでしまうのだといいます。
降り注ぐ宇宙放射線は、地球の上空にたくさんの雲を生みだすため、地球上は必然的に日照不足に陥るのだそうです。
すると、太陽光が雲によって遮られることで地球は寒冷化し、これらが連動することで人間の脳内物質に影響が及び、うつ状態を引き起こすため、やる気や楽観という気分が阻害されて人々の生産力や購買力が低下、景気にも悪影響を及ぼすことになるのだというのです。
しかも、この脳内物質への悪影響は、殊に女性に強く出ることで少子化を加速する原因にもなるそうです。
わたしの好きな映画に「デイ・アフター・トゥモロー」という地球に氷河期が訪れるというSF作品がありますが、今は正にこんな状況の始まりなのかもしれないという説もあるのだとか・・・。
そう考えると、今年の寒冷化も自然と人々の気持ちを消沈させる要因となっているわけで、もう一つ世の中が活性化しない理由なのかもしれません。
人の気持ちをウキウキさせてやる気を起こさせるためにも、早く春が来て暖かい日光が降り注ぐ必要があるのでしょうね。
景気を左右する力が太陽光にあるのだとしたら、この不景気を吹き飛ばす秘策は光にあるのかもしれません。
しかしながら、今の日本は昨年の大震災の影響で節電意識が支配していますから、安易に電気照明に頼ることは出来ません。
では、どうしたらいいのか?
これを打開する方法は、「色」にあるという専門家もいます。
太陽光や照明に頼れない場合でも、街に出来るだけ多くのカラフルな色彩を生み出すことが出来れば気持ちの活性化率も上がるのではないでしょうか。
ビタミンカラーと呼ばれる赤やオレンジ、黄色などのライト・トーナス値の大きい色をファッションに取り入れることで気分も明るくなれるのだと思います。
それにつけても、早く本格的な春が来ることを祈りたいものですね。
靴がはけた!
2012年03月23日
靴がはけた!

以前もブログに書いたのだが、足が極度に浮腫んでからというもの、それまではいていた靴が尽くはけなくなってしまった。
その靴が最近になって、またはけるようになった。
わたしは靴が大好きで、過去には何足も買っていたのだが、足が浮腫んでからはそれらが一足もはけず、流行遅れでもあるので、もう捨ててしまおうかと思っていたのだ。
しかし、先日、どうせ捨てるのならと思い、そんな古い靴の中でもやや大きめの物を試しにはいてみたところ、これが何と足がすんなりと入ったのである。
「おお、ラッキー!!」

流行遅れでも何でも構わない。
はけるとなれば、捨てるのは惜しい。
まだ、何度もはいていたわけでもない靴なので、見たところは新品も同然なのだ。
もしかしたら、他の靴もはけるのではないかと思い、二、三足試してみたところ、やはりはくことが出来た。
早速、その靴をはいて散歩に出ると、意外に歩きやすい。
そういえば、身体がガタガタになりつつあった頃、もしかしたら靴が悪くて足が痛むのかと勘違いしていて、次から次へと靴を買い替えた。
結局、原因は靴ではなかったのだが、考えればとんだ散財をしてしまったものである。
手術のあとは両足が異常に浮腫んだので、もう、かつての靴ははけないものだと思い込んでいたのだが、捨てずにいてよかった。
流行遅れの靴ばかりだが、これからは気にせずはこうと思う。
普通にお気に入りのおしゃれ靴がはけて歩けるということは本当にすごいことなんだと、今更ながら実感する。
皆さんは、階段の上り下りや日々の歩行を何の気なしに行なっていることと思うが、これって奇跡的なことなんですよ。
足が萎えてしまうと、たった10センチの段差も人の支えなしには上れなくなるのだ。
そんなバカな・・・と、思うかもしれないが、百歳を実体験したわたしにははっきり言える。
また、今日は、ゆっくりだが階段を手すりにつかまることなしに下りることが出来た。

こんな感覚は、十年ぶりぐらいだな。
歌詞の意味が判らない
2012年03月23日
歌詞の意味が判らない

近頃の歌謡曲の歌詞は、理解不能なものが多くて、作者は何が言いたいのか良く判らないことが度々あります。
この原因は、曲が先に出来ていて、そこへ歌詞をあとからあてはめるという近年の曲作りの主流である「曲先」の手法にあるのだと思うのですが、それにしてもこういう疑問を持つのは、わたしだけではないようです。
インターネット上にも、歌詞の意味が判らないという苦情が意外にあることに気が付きました。
その中でも、特に判らないと皆さんが首を傾げるものが、巷では「名曲」と呼ばれている一青窈さんの「ハナミズキ」。
空を押し上げて
手を伸ばす君 五月のこと
どうか来てほしい 水際まで来てほしい
つぼみ をあげよう 庭のハナミズキ
「水際まで来て欲しい」の「水際」は、おそらく何かの比喩的に使われているのだと想像出来ますが、具体的には何を指すのかは定かでありません。
でも、この辺りまでならば、何とか理解しようと思えば出来ないこともありません。
問題は、この後です。
薄紅色の可愛い君のね
果てない夢がちゃんと 終わります ように
君と好きな人が 百年続きますように
「薄紅色の」----が、いったい何処へつながるのか?「可愛い君」ですか?それとも、「果てない夢」へつながるのでしょうか?
さらに「果てない夢」とは何でしょうか?それが「終わる」とは?最終的に好きな人と結ばれることを意味するのでしょうか?
夢が終わってしまったのに、「好きな人と百年続きますように」とは、どういうことなのでしょう?
考えれば考えるほど意味不明です。
一説には、この歌は結婚適齢期を迎えた娘へ贈る父親の心情を歌ったものだということですが、せっかくの父親の気持ちが、これでは娘に伝わりませんよね。
ところが、一箇所歌詞を替えてみると、案外判りやすくなるのです。
「果てない夢がちゃんと終わりますように」を、「果てない夢がちゃんと叶いますように」と替えてみただけで、どうでしょうか?
俄然、意味がすんなり通って来るように思うのですが・・・。
まだ、あの頃幼かったきみが、五月の空へ思い切り手を伸ばす。
ハナミズキの枝が欲しかったんだよね。
ほら、頑張ってこっち(池のほとり?)まで来てごらん。
ハナミズキのつぼみのついた枝をあげるよ。
薄紅色のほっぺたをしていた可愛いきみ。
そのきみが手を伸ばして欲しがったハナミズキのつぼみのように、今は彼との恋を手に入れたいと願っている。
そんな果てない夢がちゃんとかないますように・・・。
ぼくはいつも祈っているよ。
きみとその彼の愛がこれからもずっと長く続いて行くことを、いつまでも。
歌詞の一番だけを解釈すると、ざっとこんな感じになるのではないでしょうか?
これならば、娘の成長を喜びつつも何となく一抹の寂しさも拭えない父親の心情が理解できるような気がします。
もちろん、作者の本当の意図がどういうものなのかは判りませんが、第三者が何とか頑張って内容を忖度(そんたく)すれば、こんなところが妥当でしょう。
歌詞の意味を考える時、この一言をこう替えたらもっと判りやすいのになァ・・・と、思うことって良くありますよね。
それに比べて「おひさま」の主題歌は、本当に気持ちにすんなりと入り込んで来ます。
最後の、「それだけでいいのよ。それだけがいいのよ」は、正に名文だと思いました。
続きを読む
金縛りに遭う夢を見たら・・・
2012年03月22日
金縛りに遭う夢を見たら・・・

夢の中で、突然身動きが取れなくなったことがある。

そんな経験のある人は、いませんか?
動こうと思っても、何故だか身体がピクリともしない。
身体が重くて苦しい。息が出来ない。

胸の上に手を載せて眠っていたからだとか、布団が顔にかかっていたからだとか、色々理由はあるようですが、どうもそういう物理的な要因ばかりではないようです。
夢の中で金縛りに遭う----と、いうのは、心の中に大きな葛藤や不安がある場合に起きやすいことなのだとか。
「こうしたいのに実際は出来ない」「こんなことにはなって欲しくないが、もしかしたら・・・」「あの人と会いたくないなァ・・・」
などのジレンマや恐れが心理的に反映して起きる可能性が大なのだそうです。
さらに、夢の中でも眠っていて、あまりの苦しさに目を開けたが、それがまだ夢の中の出来事で、しかもその夢の中では目が覚めているにもかかわらず、どうしても身動きが出来ない----と、いうような場合は、この不安や恐怖心がかなり大きいことを意味するのだそうです。
また、こうした夢を見る時は、心理的な疲労ばかりではなく、肉体的な疲労が蓄積している場合もあるので、ゆっくりと休養をとることも必要です。
特に、その金縛りの夢を見る際に、常に身体の同じ部分が痛いとか重い、苦しいなどという場合は、その部分に何らかの病気が隠れていることも考えられるそうですから、あまり頻繁に身体の同じ箇所が辛くなる夢の時は、一度病院で検査を受けてみることも必要かもしれません。
たとえば、夜中に横っ腹の痛みを伴う金縛りの夢を良く見たという人が、実は腎結石を患っていた----などということもあったり、 息苦しさを覚える金縛りの夢が、睡眠時無呼吸症のせいだったなどということもあるそうです。
あなたは、夢の中で金縛りに遭ったことはありませんか?
最近、良くそんな夢を見てうなされる----などという人は、一度静かな場所でじっくりと自分の心身の状態に耳を澄ませてみる必要があるのかもしれません。
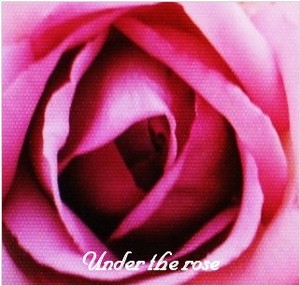 続きを読む
続きを読む腹の立つしゃべり方
2012年03月21日
腹の立つしゃべり方

会話をしていると、とかく腹の立つしゃべり方ばかりする人って、いますよね。
何かにつけて上げ足をとるとか、相手の話についてはほとんど上の空でまともに聞いている試しがないとか、皮肉ばかり言うとか、やたらに「嘘~」を連発するとか、などなど。
また、何かを教えてあげた時、「そうなんだ」という返事を返す人もウザいという意見が多いです。
教えてもらったのならば、返事は「そうなのか」が礼儀ですよね。
「そうなんだ」というのは、「だいたい判っていたけれど、やっぱりそういうことなんだ」という意味で、初めて聞いたという素直な驚きがそこにはないのですから、教えた方にしてみれば、「何だよ!せっかく話してやったのに」ということにもなるわけです。
これに似ている反応の仕方に、
「そんなの決まっているじゃない」
と、いうものがあります。
自分が発見したことや初めて知ったことを他人に話したいという気持ちは、誰もが持っている衝動ですよね。
ある人が何か珍しい物を見て、そのことを友人などに教えてやった時、
「へ~~、そんな物があるんだね」
と、素直に驚いてくれれば話した方も話がいがあるというものです。ところが、相手がそういう珍しい物を知るはずがないにも関わらず、
「そりゃ、そうだろうね。そんなもんだよ」
などという如何にも知ったかぶった返事を返して来たら、やはり話した方としては面白くないと思うのは当然です。
でも、何を言われてもそういう返事しか返せないという癖を持った人も時にいるようで、どんな話題に対しても、すべて自分の想定内だと主張するのです。
これは、相手よりも自分の方がものを知っているとか、バカにされたくないという虚栄心の表われなのですが、あまり頻繁に使うがために、いつの間にか無意識下でそういう反応をしてしまっている場合があるようなのです。
しかし、やはりこういう返事を聞いた方は、「そんなに物事に詳しいのなら、もう何も教えてやらない!」と、腹を立てるのは当たり前で、そうした癖を続ける人は、知らず知らずのうちに友人や味方を失って行くものなのです。
高齢者になった時、誰も話し相手がいないと嘆く人の中には、若い時分常にこうした「知ったかぶり」をしていた人が少なくないとか。
あなたの周囲にも、「そんなの決まっているじゃない」「そんなことも知らないの?」というような口癖の人はいませんか?
実は、わたしの身近にもそういう人が何人かいます。
でも、不思議なことに、そういう口癖の人は、同じ口癖の人のことが大嫌いなんですよね。自分にもそっくりな癖があることにまったく気が付いていないのです。
知らないことまでも「知っている」というあの見栄っ張り根性は、何処から生まれるのでしょうか?
知らないことを知るということは、楽しいことだと思うのですが、そういう人たちはおそらく新しいことを知るのが怖いのだと思います。
知らないことを知って驚くことが、自分の無知をさらけ出すことだとでも思い込んでいるのでしょう。
つまり、そういう人ほど、実は何も知らない人なのです。
続きを読む
最近の夢は・・・
2012年03月20日
最近の夢は・・・

皆さんは、夢の中に「お寺」が出て来ることってありますか?
わたしの場合、このお寺の夢がとても多いんですよね。
前世は、お坊さんだったのかも?----なんて、最近は思うくらいです。
高校時代は善光寺の境内が通学路だったようなものでしたから、そんな記憶が潜在意識の中にあるのでしょうか?
でも、いつも夢に出て来るお寺は、善光寺とはまったく違うものです。
そのお寺の風景はほとんどいつも同じで、お寺のある場所や本堂などの配置もかなり具体的なのです。
お寺自体はそれほど古いということはなく、山門から本堂までは階段が何カ所かあって少し薄暗い感じです。
その中の一室は広間のような畳敷きで、濡れ縁の手すり越しに見える中庭のような場所に鐘つき堂があります。
お寺の近くにはバス停もあって、以前もこの辺りへ来たことがあるなァ・・・と、思う場所なんですよね。
これほど頻繁にお寺の夢を見るということは、何かにすがりたいという深層心理の証なのでしょうか?
日々、煩悩だらけだからなァ・・・。

それと、部屋の夢も良く見ますね。
そこがホテルなのかアパートなのかも判りませんが、とにかく幾室もの部屋が並び、その部屋には昔の知り合いや知り合いではないにせよ何故か親しいと思い込んでいる見知らぬ人物などが住んでいるのです。
夢というものは、実にユニークなシチュエーションを演出してくれるものです。
そんな夢の中に、この間久しぶりに例の人が現われました。
また、何かこちらに伝えたいメッセージがあるのかもしれませんね。


続きを読む
ほめ言葉の裏側は?
2012年03月20日
ほめ言葉の裏側は?

「ほめ言葉には裏がある」
「ほめ言葉を真に受ける利口もん」
昔の人は、こんなことを言って、他人からほめられた自分が有頂天になることを戒めていたそうですね。
「利口もん」とは、信州の方言で「バカ者」という意味です。
ほめられたのなら素直に喜んでいればいいのに・・・と、現代人ならば思いますが、「褒め殺し」という言葉もあるように、人が人をほめるということの裏側には、必ずほめる人の打算があると、昔の人は考えたのだと思います。
特に商人がお得意さんをほめる時などは、正しくこの打算が働いていると思って間違いないでしょう。
「本当に、お宅さまのお嬢さまはお美しくて・・・」
商売の足しになるからこそ、こんなお上手も言えるわけですよね。
しかし、人が人をほめる時は何も打算が働いている場合だけではありません。
心理学的に見ると、「無理なく他人をほめることが出来る人は、自分が相手よりも優位に立っていると感じている場合の確率が高い」ということだそうで、ほめ言葉とは心に余裕がある人が発しやすいものだともいえるようです。
女性の心理を研究している人に言わせると、「あの子、可愛いわね~」と、素直に言える女性は、その女性よりも少なくとも自分の方が美しいはずだと認識している場合が多いとか・・・。(なんか、判る気がする)

以前このブログにも書いたことですが、友だちが真の友人か否かを判断する時も、こうしたほめ言葉が重要なファクターとなることがあるそうで、もしも、あなたに嬉しいことが起きた場合、友だちがそれに対して、
「おめでとう!」「よかったね」「やっぱり、大したもんだよ」

などの称賛を、率直に言ってくれるかどうかでおおよそ知ることが出来るのだそうです。
つまり、「ありがとう」という言葉は簡単に口から出せても、「あめでとう」は、相手に対してコンプレックスや嫉妬心を抱えている人ほど言い出しにくい言葉なのだといえるのだと思います。
では、もしもそのほめ言葉が誰かを仲介しての伝聞であった場合はどうでしょうか?
その場合は、その伝聞の仲介者が誰かということが大事なのだとか。
もしも、その仲介者があなたと利害関係がある人や親しい知り合いの場合は、その言葉はあまり信用できないということのようです。
何故なら、その仲介者自身があなたから良く思われたいという心理が働くために、内容を誇張して伝えている可能性が大きいからだそうです。
まあ、少しばかり割り引いて受け止めておいた方が無難なのかもしれませんね。
続きを読む
ほめる人は、ほめられたい人
2012年03月19日
ほめる人は、ほめられたい人

人は、何故他人をほめるのか?
それは、もちろん、ほめた相手からのほめ返しを期待するからです。
もしくは、ほめたことへのお礼の言葉をもらいたいがためです。
「そんなこと考えてほめていない」
そう思っているあなたも、ほめた相手がいつもほめられっぱなしで、あなたにお礼の言葉一つなければ、絶対に快いはずはありません。
かつて、わたしが十三代須坂藩主堀直虎を主人公にした歴史小説を出版した時、大学時代の同級生が感想を述べてくれました。
「主人公の恋人女性が殺されるシーン、感動的で泣いた」
すると、その同級生もしばらくして文庫本でミステリー小説を出版しました。
もちろん、わたしもお礼の感想を伝えました。
ただ、彼女はその時まだ自動車免許を持っていなかったので、主人公が自動車を運転する場面の描写がイマイチだったのですが、それでも推理展開はなかなかで面白かったと伝えました。
人が他人をほめる時、少なくともそこには自分も相手から評価して欲しいという気持ちが働くものです。
それを暗黙のうちに了解して、相手の欲するように動くのが大人の世渡りというものでしょう。
しかし、時に自分の主張はするものの、相手の意向をまったく汲もうとしない人がいます。
自分がして欲しことは相手に要求しても、相手が要求することは尽く無視するのです。
まるで、最初から聞いていないかのように。
「今度、〇〇して下さい」と、頼んでも、次の返事にはその答えの部分だけは完全にノータッチ。
そのうえ、自分の要求だけはまた繰り返し行なうのです。
要するに、自分に都合が悪いことには一切耳を貸さないという態度を徹底させているわけで、こういう人にはどんなに協力や助力をしても、決して見返りは期待できません。
「無償の愛」を注げるほどに、相手が尊敬出来る人物でもあれば、また話は違うのでしょうが、そんな漫画の主人公のような人物が世の中に存在するはずはないのです。
相手をほめ返すことが出来ない人は、結局、ほめられる資格さえない人だと言っても過言ではないでしょう。
あなたの周りにも、他人をほめられない人や他人の好意は受けても、自分からの好意は一切返さない非常識人間はいませんか?
「最近、良く同じ人からほめられるなァ?」
そんな風に感じたら、それはその人自身があなたからの何らかのほめ言葉を待っている証拠なのです。
大人ならば、それに気付いてあげましょう。
続きを読む
即席ピクルスを作る
2012年03月19日
即席ピクルスを作る

塩分を極力控えるように言われているわたしは、漬物が食べたいなァ・・・と、思うと、即席ピクルスを作ります。
まずは、玉ねぎ、キャベツ、ニンジンなどを適当に切って鍋へ入れ、少しの水で野菜がグッタリしないていどに軽くゆでます。
この時、ナベ蓋をすると案外早く軽い蒸し煮状態になります。
その後、この野菜を別の陶器(酢を入れても大丈夫な素材)の器に取り出して、そこに熱を加えない大根とキュウリの薄切りを加えたら、すし酢、砂糖、レモン汁を混ぜ合わせたものをたっぷりとかけ、まんべんなく和えます。
砂糖はやや多めに入れて味をみるのが良いでしょう。
塩を入れる場合は、本当に少々。アクセント程度にふって下さい。
塩味が好きな人は、もう少し多めでもいいと思います。
ラップをしてから冷蔵庫へ入れて1、2時間ほど冷やせば完成です。
お好みで粒コショウを入れてもおいしいです。
一度にたくさん作っておけば、食事のつど食べられて便利です。
大根とキュウリだけは火を通さないので、しゃきしゃき感が残ったままでサラダ感覚も味わえます。
コツは、あくまでも野菜を煮過ぎないこと。
漬ける時間が短縮出来て、すぐに食べたい時にもお勧めです。
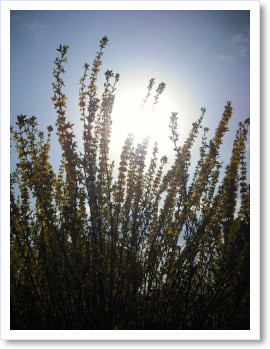 続きを読む
続きを読むファッション今昔
2012年03月18日
ファッション今昔

これは世界共通のことなのだろうか?
ファッション感覚がある時代から、あまり動かなくなったように感じる。
たとえば、わたしの父親世代が若い頃身につけていた背広やネクタイは、わたしの弟の世代はファッションセンス的にも違いがあり過ぎて、とても身につけることは出来なかった。
まあ、父親が若い時代の背広などのスーツといえば、ほとんどがオーダーメードで、テーラー仕立てだったからなのだが。
ところが、弟の息子たちは、父親である弟がかつて着ていた服を今でも平気で着ることができる。
まったく、違和感がない。
ジャケットにしてもネクタイにしてもTシャツにしても、無理なく共有できているのだ。
もちろん、弟と甥っ子はほとんど体格差がないので、このようなことが可能なのかもしれないが、それにしてもセンスという意味からすれば、ほぼ共通である。
しかし、わたしの父親が若い時に着ていた服を弟が着たとしたら、正に昭和時代の芝居用衣装か?----と、思われてしまうに違いない。
では、現代の若者のファッションは果たしてどうだろうか?
今の若者世代が親となり、その子供たちが二十歳以上になった時、親が若い頃に着ていた洋服をタンスの奥から引っ張り出し、何の抵抗もなく着られるものであろうか?
う~~ん、それを考えるとかなり大きな疑問符がつく気がする。
そんな風にファッションを考えると、若者たちは自分に子供が出来た時のことを想像してあまり冒険はせずに洋服やバッグを選んだ方が、ある意味経済的だといえるのかもしれない。
続きを読む
嘘をつくという心理
2012年03月17日
嘘をつくという心理

あなたがつい嘘をついてしまうという場合は、どんなことを考えている時でしょうか?
おそらく、相手に自分を良く見せたいとか、相手に嫌われたくない----そんな打算が瞬時に働いた時ではないでしょうか?
相手があなたのことを嫌おうがどうしようが勝手にすればいい、自分には関係ない----と、思う気持ちがあれば、たとえ相手が激怒しようが傷付こうが真実を話そうとするはずですよね。
まれに、相手のことを思い、わざと嘘をつくということもあると思いますが、こういう場合はごく限られています。
しかし、そうした「ついはずみで」という嘘は、案外簡単にばれてしまうもの。
最初の嘘を正当化するために、また新たな嘘の上塗りをしなければならなくなるからです。
まあ、中には自分が嘘をついたことをケロリと忘れて、かつて「付き合っていない」と、公言していた人と食事をしたとか一緒に買い物に行ったなどという事実を、自らしゃべってしまうお気楽者もいるようですが、こういう人は正直言って客商売には向きません。
客から聞いた秘密まで無意識のうちに誰かれなしに暴露してしまう可能性があるからです。
あなたの周囲にも、そんな人はいるのでは?
では、つい嘘をついてしまう心理の元になっているのは、一体何なのでしょうか?
それは、子供の頃の親のしつけに大きな原因があるのだそうです。
子供が初めて嘘をつくのは、「親に嫌われたくない」と、考えた時だとか。つまり、子供は親から良い子だと思われたい、親の嫌がることを隠したいという本能から嘘をつき始めるのだというのです。
ここに、ある五十代後半の女性の例があります。
彼女は、幼いころから親から「あの親戚のおじさんには、こういうことは言っちゃダメ」「あの親戚のおばさんには、あれは言っちゃダメ」と、言葉や気持ちを常に制限されて生きてきたせいで、親戚のおじさんやおばさんに連れて行ってもらいたい所や買ってもらいたい物があっても、必死で我慢して来ました。
両親が共働きで忙しかった彼女は、行きたい所や買いたい物があっても両親に言えず、いつも自分を窮屈な殻の中に閉じ込めて来たのでした。
そのせいで、大人になっても未だに親の目が気になり、何処か行きたいところがある時は、自分から友人を誘っているにもかかわらず、親の前ではつつましやかな女性を演じ続けなければならないために、
「友人から誘われて、仕方なく行くことになった」
と、その都度嘘をつくわけです。しかし、友人はそんなことは知りません。ある時、彼女の親から、
「あまり、うちの娘を買い物に連れ出さないでくれる?」
と、苦言を呈され、何で自分が誘ったことになっているのかと、激怒したというのです。
もちろん、その友人は二度と彼女と買い物に行くことはなくなったそうです。
しかし、嘘をついたことを後悔する人はまだ救いがあります。が、「別に、良いじゃないの嘘ぐらい」と、開き直り始めたとしたら、これは相当の重傷です。
こういう人が犯罪に進む確率は、かなり高まるのだとか。
嘘つきの芽は、実は子供の頃から育ち始めるのです。それも親に嘘をつかなくては嫌われるかもしれないという恐怖心が引き金になっていることが大半なのです。
「嘘をついちゃダメ」と叱るのなら、「ママ、嘘つきは嫌いよ。何があっても本当のことを話してくれる子が大好き」と、言う方がよほど子供の気持ちを楽にするのだそうです。
そして、もしも子供が真実を話した際も決して頭ごなしに叱らないことです。
子供の視点からすれば、どうしてこんなことで大人は怒るのか判らないということが多いものです。
スーパーで万引きをしたある幼い少女は、補導された際にこんなことを言いました。
「あたし、弟にご飯を食べさせてやりたくて盗んだんだけれど、弟をお腹いっぱいにしてやることの何処が悪いの?あたし、いつも一生懸命おうちの手伝いしているよ。だから、叱らないで!」
世間一般の価値観や常識さえも判らなくなってしまうことがあるのです。
続きを読む
視点の違い
2012年03月16日
視点の違い

今日、共同浴場で、時々入浴時間が一緒になる近くの主婦と話をした。
話題は、先日町内で自動車に轢かれて亡くなった幼い子供さんのこと。
わたしは、まだ小さな子供さんが気の毒で、何と痛ましいことかと気持ちを話したところ、相手の主婦の感じ方は、わたしとは、まったく逆だった。
「子供さんは確かに可哀そうだけれど、それよりも車で轢いてしまった人の方がもっと気の毒だ」
と、言うのである。
突然、路上へ飛び出されたのでは、ドライバーが急に車を止められるはずがない----と、いうのがその理由だった。
「誰も子供さんを轢きたくて運転しているわけではない。偶然にもそういう場面に遭遇してしまったことが可哀そう」
と、いうのである。
こういう事故があった時、どちらの立場に視点を置いて考えるかで、その物の見方が180度変わってしまうのだ。
幼い子供さんを持っている親御さんならば、間違いなく亡くなった子供の視点やその親の視点で事故を総括するだろう。
しかし、もしも轢いたのが自分の夫や子供だったらと考える、六十代以上の女性たちの場合は、今度は逆の見方になるのである。
先に記した福島の瓦礫問題についても、これと同じことが言える。
福島県民や被災地の人たちの気持ちになるか、それとも自分の子供や孫の気持ちになるかで、引き受けるか否かの選択は180度変わるのだ。
「『瓦礫を引き受けても構わない』と、言う人は、たいていが中高年で幼い子供や孫がいない人だ」と、話す人もいる。
自分自身がどちらの視点を持つかで、考え方は真逆にもなるのである。
つまり、世の中の認識に正解、不正解は必ずしもないのかもしれないし、確信的な正義ですら時代によって変化する。
ただ、そこには、「失われた命は二度と戻らない」という動かすことの出来ない現実があるばかりなのだ。
 続きを読む
続きを読む今日は、朝から・・・
2012年03月16日
今日は、朝から・・・

今日は、朝から色々なことがあり過ぎました。
まずは、知り合いの方の訃報。
つい先日まで元気で我が家へ来て下さっていたのに、旅行先で急死されたそうです。
両親もわたしも弟も、ショックで言葉を失いました。
本当に、人の一生は判りません。
父親もご家族の気持ちを思うと、それ以上は聞けなかったそうです。
これは、わたしの担当医の先生が下さった年賀状に書かれていた言葉です。
「平凡、普通が如何に貴重なことか・・・」
こういう突然の出来事に直面すると、心から実感出来ます。
実は、昨年も長野電鉄に勤めていた親戚の男性が小布施駅舎内で急死しました。
心筋梗塞だったそうですが、こういうことが重なると、人間が生きているということはどれほどの奇跡に値するのだろうか?----と、考えてしまいます。
そして、午後は買い出しへ。
例の如く家にばかりこもっているので、またまた生活必需品が底をつきました。
今日は、かなり暖かくて上着がいらないほどでしたから、外出しやすかったです。
その買い物中にもさまざまあったのですが、ここでは割愛します。
それにしても昨年の大震災以降、何か人々が知らず知らずの間に異常なストレスにさらされているのではないかとさえ疑ってしまいます。
続きを読む






