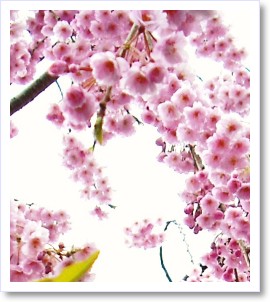「気付く」力
2012年03月15日
「気付く」力

昔、元NHKアナウンサーが出版した「気配りのすすめ」という本がありましたが、最近の人たちはとかく「気付く力」が弱いと言われます。
たとえば、隣で困っている人がいても、何に困っているのかだけではなく、困っていること自体に気付かないという人が増えているのです。
また、ある人が何かを欲しがっていて、その物が自分の目の前にあるにもかかわらず、それに気付こうとしないと、いう人も多いのです。
「気配り」とは、ある意味、実に能動的で、常に周囲にアンテナを張り巡らせている必要もあるので、そういう緊張感が苦手な人も多いでしょう。
しかし、いわゆる「気付き」には、そこまでの注意深さは必要ありません。
自然体に近い形でいいのだと思います。
ところが、自分の中に相手の気持ちを想像したり、思いやる意識がないと、この「気付き」がまったく出来ないのです。
要するに、こういう人を称して「鈍感」とか「無神経」と、世間では言います。
「空気が読めない人」という言い方も出来るかもしれません。
では、どうしてこういう人が世の中に増殖してしまうのかというと、そこには一口で言って「謙虚さの欠如」があるともいわれます。
つまりは、開き直り人間が多くなったということでしょう。
「誰に何を言われても構わない」「これが私なんだから・・・」「別に、好きに生きたっていいじゃない」
こういう人が他人の気持ちを理解することは簡単ではありません。周囲に不快感を与えていることにさえ気付かないからです。
早い話が精神的に大人になりきれないということなのですね。
こういう人は、とかく「奥ゆかしさ」と「おしとやか」を混同したり、「でしゃばり」を「活発」と間違えて認識してしまう傾向があるようで、自分のことは後回しに考える癖のある人でも活発で積極的な人は大勢いるのです。
何も相手を立てることが、「おしとやか」という意味ではありません。
自分だけの思いのレールを突っ走ることならば子供にでも出来ます。
大人ならば、「気付く力」を大いに養って、自分の言葉や態度で相手がどんな気持ちになるかを想像しながら、日常生活をすることを心がけたいものですね。

続きを読む
共同浴場でのルール
2012年03月14日
共同浴場でのルール

皆さんは、共同浴場へ入る時、先に入浴している人たちに対してちゃんと挨拶をしていますか?
わたしの地元では、挨拶は当たり前のことで、これをしないと、
「礼儀知らず」
と、いうレッテルを貼られてしまいます。
しかも、この挨拶には一定のルールのようなものがありまして、昼間のうちに入浴する時は、
「こんにちは」
ですが、午後五時以降は、
「こんばんは」
と、なります。
ところが、共同浴場をあとにする時は、たいていの人が時間に関係なく、
「おやすみなさい」
と、なるのです。
でも、これに違和感を覚える場合は、
「おしずかに」とか「ごゆっくり」または「お先に」
などと、言う人もいます。
ですから、この挨拶がない場合は、たいていが観光客か初めて入浴する人だということが判るのです。
しかも、挨拶は必ずあとから入っていった方が先にしなければなりません。
既に入浴している人の方が先に挨拶した時は、
「挨拶ぐらいしなさいよ」
と、半ば呆れられていると思っていいでしょう。
これが地元の共同浴場での暗黙のルールなのです。

続きを読む
武道必修化について
2012年03月14日
武道必修化について

学習指導要領の改定により、四月から中学一年、二年生の体育で、男女問わず武道が必修科目となるようですね。
この武道は、原則として「柔道」「剣道」「相撲」から学校側が独自に選ぶということのようですが、地域性により、「なぎなた」「弓道」「空手」なども選べるそうです。
そうはいっても、やはり資金面とも相談しなければならず、防具費や土俵などの整備費が必要となる「剣道」「相撲」を選ぶ学校は少数で、ほとんどの学校は用具費が少なくてすむ「柔道」を選択するようです。
でも、「柔道」の稽古中の事故は長野県内でも1964年以降少なくとも5例もあるとのこと。
硬膜下血腫や脊椎損傷で、亡くなったり障害が残った子供がいるということでした。
また、何度も頭を振られることで脳を支える血管が切れて起きる急性硬膜下血腫の危険性も少なくないということです。
こうした危険性が伴うことの要因の一つに、柔道を教える指導員の技量不足があげられるといいます。
まず生徒が技を覚える前に、柔道の基本である受け身を完全にマスターしているかを見極める技量が、指導者にあるのかということですが、これについても「自信がない」と、回答する教師が多いとか。
あるニュース番組で取り上げていたのですが、フランスでは指導者を目指す場合、子供たちに柔道を教えることができる資格を持つまでには、徹底した指導者資格取得のための講習を数カ月にも渡って受けなければならないのだそうですが、日本にはそうした明確なルールはないのだそうです。
有段者であれば、三時間ほどの講義を受けるだけで指導者認定が可能になると聞いたこともあります。
子供の能力は千差万別です。
本来ならば、この三つの武道を子供たちに選択させてしかるべきなのではないでしょうか。
しかし、その前に何故、今、武道なのでしょう?
その理由が良く判りません。
礼儀作法を身につけたり精神力を鍛えるなど、日本古来の武術に触れることで日本人たる誇りを子供たちの中に喚起させるためなのでしょうか?
それならば、茶道や華道、書道でもいいのでは?
文科省の考えに何か裏があるのでは?----と、勘繰りたくもなります。
指導適格者がいない場合は、必ずしも四月開始にこだわらず、十分な準備期間を取ってもらいたいと思います。
番組の取材によれば、フランスでは柔道の稽古中に事故が起きたなどという話は聞いたことがないそうで、日本はいったいどういう指導をしているのか逆に不思議だということでした。
因みに「剣道」では、全国的に見ても、指導者が不在の稽古後に子供たちが勝手にふざけ合っていてケガをしたような話は過去に聞いたことがありますが、稽古中にそうした事故に結びついたようなケースはほどんどないそうです。
とにかく、やると決まってしまったのなら、事故やけがをしないような万全の態勢で武道必修化を進めてもらいたいものです。
続きを読む
「思いやり」と「もてなし」
2012年03月13日
「思いやり」と「もてなし」

テレビコマーシャルで「『もてなし』とは、相手をリスペクトすることである」という台詞が出て来るものがあります。
これは、実にその通りだと思います。
相手のことを心から思いやり尊敬すれば、人の態度や言葉は自然と奥ゆかしさを持ち、相手に嫌われたくないという心情がにじみ出るものなのです。
しかし、相手を自分よりも地位の低い奴だとか、貧乏人だとか----そんな下目に見る気持ちがもてなす側にある時は、決して真の「もてなし」など出来ません。
そういう相手を蔑む気持ちは、本人は隠したつもりでも必ず何らかの形で表に現れるものなのです。
たとえば、言葉一つにしても、
「うちは、お客さまを買い物のため外へお出ししている」
などと平然と言う旅館経営者などがいますが、とんでもなく失礼な言い方ですよね。
つまり、この言い方では、主導権は旅館側にあり、客を泊めてやっているんだと言わんばかりの態度が見え見えです。
でも、もしもこの経営者に客に対するリスペクトの念があれば、
「お客さまに外で買い物をして頂いている」
と、言えるはずなのです。
もちろん、旅館やホテルの中にも売店はあります。客が外で買い物をするなどということは、経営者にしてみればあまり面白くないことなのでしょうが、主賓はあくまでも客側なのです。
客が楽しいと思うことを、旅館側も喜ぶべきなのです。
そういうところで、もてなし側の本気度が知れるのではないでしょうか。
長野県は、これからさらに観光客誘致に力を注ぐ方針だとか。
本気で「もてなし」を考えるのならば、まずは客を下目に見るようなもてなし側の心根から立て直す必要があるように思います。
福島の瓦礫(がれき)は・・・
2012年03月12日
福島の瓦礫(がれき)は・・・

また、雪景色になってしまいましたね。
しかも、吹雪です。
これが、本当に三月か----と、思ってしまう光景ですね。
今日も朝から国会中継を放送していますが、やはり、復興のさまたげとなっている福島の瓦礫問題は大きいようです。
一年前の大震災後は、「日本は一つ」「ぼくたちがいる」「絆プロジェクト」「つながろう日本」などと、テレビでもタレントや市民が連日連夜叫んでいたはずなのに、
「少しでも瓦礫を引き受けて下さい」
と、国が言い出した途端に、それとこれとは別----とばかりに、全国の自治体が弱腰になりました。
総論賛成、各論反対の理屈ですね。
農林水産省は、国有林への瓦礫の一時保管を認める姿勢のようですが、環境省としては、それは放射能の影響がない場所の瓦礫のことだと言います。
国の姿勢も一貫してはいないようです。
各自治体は岩手、宮城両県の震災ゴミを受け入れることにも躊躇いがあるようで、一番のネックは、「子供たちの健康に悪影響が出ないか?」ということなのでしょう。
これに関しては、誰も「でません!」と確約できないのが二の足を踏ませている原因なのだと思います。
長野県内の住民でも、大震災当初、放射能の恐怖感から他県へ逃げ出したという人もいたくらいですから、放射能汚染のことを考えると、今も吐き気がしたり気分が悪くなるという極度の不安症を患っている人もいるそうです。
受け入れはしたものの、受け入れ側の住民たちが神経を病んでは意味がありませんし、これは本当に困った問題だと思います。
昨日の大震災特別番組の中で、被災地の男性住民がこんなことを話していました。
「阪神大震災の時は、あっというまに復興ができた。都会には国民も関心があるが、やはり田舎は見捨てられているのだと思う」
本当に、人ごとではありません。
近頃は、テレビのワイド番組でもやらたに「首都圏に直下型の大地震が来るかもしれない」と、特集を組んでいますが、どうしてそんなに東京のことばかり取り上げるのでしょうか?
長野県民にとっては、正直、東京も一地方にすぎません。
やはり、都会のおごりが見え隠れして、あまり良い気持ちはしないというのが本音です。
続きを読む
一年前の今日は・・・
2012年03月11日
一年前の今日は・・・

一年前の大地震発生時、あなたは何処で何をしていましたか?
わたしは、いつもと変わらず家でテレビを観ていました。
しかし、地震が来ても突然の大報道にはならず、そのことが逆に不気味でした。
阪神大震災の時もそうでしたが、災害の規模が大きければ大きいほど、報道らしい報道がないのです。
それは、災害を伝える人々や設備が機能不全に陥っている証拠でもあるのです。
復旧を急ぐうちは気持ちにも緊張があり生きることに前向きですが、問題はこの一年が過ぎてからの被災者の心のケアだといいます。
一番怖いのは、「取り残され感」だそうです。
テレビの東日本大震災特集番組で被災地の三十代の女性は、
「最初のうちは悲しみを共有していた者同士が、一人また一人と仕事を見付けたり、新しい生活を始めたりと、自分から離れて行くようで、気が付けば自分だけが悲しみや不安感から抜け出せないでいることに異常な焦りを感じ始めている」
と、話していました。
「震災に限らず、子供を亡くした母親の会に参加して気持ちを話すことで、何となく一人ではないのだと思うと心が軽くなるような気がする」
と、語っていた若い母親も、しかし、やはり一人になるとどうしても前に進むことが出来ない自分がいると、激しい孤独感に襲われる心情を吐露していました。
被災した高齢者の寂しさを伝える報道は頻繁にされますが、若い人たちの「異様な焦り」に焦点を当てた報道はあまりありません。
若い被災者たちの中には、これから何かをしなければならないことは判るが何をしたらいいのか?まだまだ生きて行かなければならないのにどうやって夢や希望を見付けたらいいのか?との先の見えない恐怖感に苛まれる人が実に多いそうです。
「何か楽しいことをしたり、考えたりしよう」と、励ます声は良く耳にするものの、楽しことをするにしても結局お金がかかるじゃない----との現実問題が突き付けられてしまい、何も出来ないのが現状なのだと思います。
医師から気分転換を勧められて内職を始めた女性もいましたが、やはり、気持ちは晴れないそうです。
今後、お年寄りに加えて若者たちの心のケアがより重要になってくるだろうと、ある心療内科医は語っていました。
わたしも、自分の身体が動かなかった時は、一日中カーテンを閉め切った部屋で過ごしていました。
外界との接触が焦りにつながり、ますます落ち込んでしまうからです。
そんな時、「そうだ、五年を一年と考えよう」と、時間の観念を切り替えると、かなり気持ちが楽になりました。
何も、急ぐ必要などないのです。
被災地の合い言葉も、これからは、「復旧復興を急ごう」ではなく、「焦らずゆっくり生きて行こう」の精神が大切になるのだと思います。
続きを読む
共同浴場で・・・
2012年03月11日
共同浴場で・・・♨
昨日から、どうにも腹立たしさが消えない。
昨日は、こちらの共同浴場の湯はらい日で、せっかくお湯が新しく入れ替えられて綺麗になったというのに、わたしが夕方行ってみたら、近所の女性が親戚の子供を連れてきていて、出湯を止め、溜まり湯にして入っていたのだ。
当然のことながら、湯船のお湯は濁り、まるでプールかと思うほどに冷めていた。
こちらは急いで入りたいので、「出湯を出してくれない?」と、頼んだところ、その女性は、「すみません」と、一応謝りはしたものの、子供に向かって、
「ほら、早く入らないと、お湯が熱くなっちゃうよ」
と、何とも嫌みたらしい口をきく。
この女性、時々外湯で一緒になるのだが、自分一人の際も必ず出湯を止めて、湯船の中でスクワットをしたり足踏みをしたりと、マナーの悪さこのうえなしなのである。
しかも、女性にしては身体が大きいので、動くたびにお湯が揺れて、一緒に浸かっている時など危うく溺れそうになるくらいだ。
そして、出湯を止めたら止めっぱなしで家へ帰ってしまう。
そこで、今回は仕方なく注意をしたのだが、一緒に来ていた女性の母親が、彼女に輪をかけて嫌みの言いたい放題であった。
今、女性の父親が介護施設で植物状態だという噂もあるので、こちらもあまり強いことは言わなかったのだが、そうやって近所の人たちが気を遣うことに味をしめ、近頃はますます勝手な振る舞いが目立つようになってきた。
さすがに、今日そのことを別の近所の主婦にくどいたところ、
「ああ、あの人たちだよね、判る判る。家庭風呂じゃないんだから、いい加減にしてもらいたいよね」
と、言っていた。
どうやら、わたしの知らないところで、皆困っていたようだ。
だから、今日は、あの女性が入らない時間に、ゆっくりと綺麗なお湯に入って来たいと思います。
芸能界という伏魔殿
2012年03月09日
芸能界という伏魔殿

芸能界というところは、つくづく「伏魔殿」だなァ・・・と、感じる。
以前、「ちやほや----持ち上げて落とす」などというテレビCMがあったけれど、最初のうちはこれでもかというくらいタレントや俳優を持ち上げて視聴者の目を引いたあとで、今度はどうでもいいような話題に引っかかり、思いっきり落としめてまた視聴率を稼ぐ。
今日、亡くなった山口美江さんが芸能界を引退した時も、正にこの状態だったように思う。
当時も普通の女性ならば話題にも上らないようなほどの体重増を、「激太り」などとマスコミが取り上げ、彼女が「芸能界って、なんて、くだらない世界なの」と、呆れた気持ちがわたしにはよく判った。
しかも、ごく最近の番組でも彼女を「あの人は今・・・」的な取り上げ方をして、「この辺りを山口美江さんが徘徊しているというのですが・・・」などと、実に失礼なナレーションを加えていた。
この言葉にはさすがに彼女自身も、「徘徊なんて、失礼ね!」と、立腹していたので、観ているこちらもあまり良い気持ちがしなかった。
かつて山口さんはニュースキャスターなどもしていたようだが、わたしの記憶に残っている彼女のそれは、やはり二時間サスペンスドラマに出ていた女優としての姿だ。
あの頃の女優さんたちは、確かに皆美しかったが、山口さんの聡明な美しさは群を抜いていたように思える。
おしゃれで、頭が良くて、バイリンガルとなれば、男性はもちろんのこと女性たちにとっても憧れの的であった。
少々気が強い面もあったが、お嬢さまタレントにはそれも似合っていた。
今日、テレビニュースで彼女の訃報を聞いた時は、とても驚いたし、残念だった。
まだ、51歳の若さである。
その先日の「あの人は今・・・」というような番組に登場した際も、少し顔が浮腫んでいるように見受けられ、心臓か腎臓が悪いのでは?----と、思ったものである。
頻繁に通院もされていたようなので、やはり体調が思わしくなかったのであろう。
たぶん彼女のような凛とした人生観を貫く気骨のあるお嬢さまタレントは、芸能界にもしばらくは出てこないのではないだろうか。
本当に、残念である。
続きを読む
占いにはまる人の性格とは
2012年03月08日
占いにはまる人の性格とは

先日、テレビを観ていたら「占いにはまりやすい人の性格」という話題を取り上げていた。
どうやら、巷で話題になっている女性お笑いタレントが、占い師の女性に依存して仕事を放り出してしまったということから発展した性格分析らしい。
たとえば、自分を見失うほどに占いに依存してしまうと、食事に何を食べたらいいのか、またどんな順番で食べたらいいのかさえも自分自身では決められなくなるという。
そんなことになったら、日常生活のすべてを占いに従って行動しなければにっちもさっちも行かなくなるというものだ。
しかし、テレビ番組でも占いすべてを否定しているわけではなく、人生の参考にする程度の占いなら信じてみるのも、案外気分転換的にいいのかもしれない。
かの野田総理も毎日の朝のワイドショーで放送される占いコーナーがお好きなようだし、もしも観忘れた時などは秘書に「今日の運勢はどうだった?」と、訊くそうである。
まあ、総理大臣はかなり孤独だというから、占いを頼りたくなる気持ちも判らなくはないが・・・。
下駄占いなどで、破れかぶれにTPP参加や消費税アップを焦るようなことだけはして欲しくはないものである。
で、その占いにはまりやすいか、そうでないかは、こんな性格診断でもわかるのだとか。
★ 時間にルーズである。
★ 自分はちゃらんぽらん人間だ。
★ 日記などつけたことがない。
★ 人の話を最後まで聞かない。
★ 現金以外は信用しない。
★ 相談出来る友人が多い。
★ 打算的で合理主義者だ。
★ 多趣味である。
★ 将来や未来の話をするのが嫌い。
こんな人は、簡単に占い依存にはなりにくいのだという。
つまり裏を返せば、ごく普通の神経の人は、ほとんど占いにはまりやすい要素を持っているということだろう。
まあ、昔から占いというものは当たるも八卦当たらぬも八卦----と、いうくらいなのだから、のめり込むことなく、娯楽の一部ぐらいの感覚で利用した方がいいのだと思う。
因みに、わたしも時々は星座占いなどを見たりもしますが、良い兆候しか信じません。

救急車が・・・
2012年03月02日
救急車が・・・

昨夜の0時過ぎに、近所に救急車が停まった。
あまりに近くだったので慌てて外へ出てみると、近所の主婦が搬送されて行くところだった。
ご主人の話では、犬の散歩をしていた時に転んで頭を打ったとのこと。
何とか自力で家まではたどりついたものの、頭が痛むので救急車を呼んだということだった。
夜の犬の散歩はよほど気を付けないと、通行人も少ないのでアクシデントがあった時に即座の対応が出来ないこともある。
しかも、一頃よりは暖かくなってきたとはいえ、まだ道路のあちこちには凍った場所もあるから危険だ。
そういえば、昨夜はどういう訳か救急車のサイレンが何度も聞こえていた。
真冬は皆気を付けて外へ出るのを極力自粛しているが、少し暖かくなってきた今時分が、人々が徐々に活動的にもなりもっとも転倒事故が多い時期なのかもしれない。
冬の運動不足で足腰も弱くなっているのだから、一度気に身体を酷使するような運動は避けたいものだ。
主婦は、病院での検査の結果、特別悪いところもないということで夜中のうちに自宅へ戻って来たそうだが、大事に至らず幸いだった。
ところで、『秘密のケンミンSHOW』は今回は諏訪湖周辺の長野県民の秘密だったが、なかなか面白かった。
他の都府県では、母校の校歌を覚えている卒業生があまりいないというのは驚きだ。
わたしは、小、中、高、大と、校歌はすべて歌える。
それって、普通だと思っていたのだが、これも県民性なのだろうか?
ところで、長野県の方言で「~~やらず」「~~へ行かず」という否定語が実は肯定語というのも、一つの秘密なのではないかと思う。
これは、戦国時代の名残で、敵に意思を逆に伝えるための信州人の知恵だったと聞いたことがあるのだが・・・。
「さて、畑へでも行かず」と言いながら、鍬を持って畑へ行くお年寄り、あなたの周りにもいるのではないだろうか?
では、また。