美人に独身が多い理由は?ほか
2012年11月09日
美人に独身が多い理由は?ほか

10月29日、松本幸四郎(70才)の長女・松本紀保(41才)と『相棒』の伊丹憲一役で知られる川原和久(50才)の結婚披露宴が開かれ、媒酌人を務めた水谷豊(60才)のほか、及川光博(43才)・檀れい(41才)夫妻、成宮寛貴(30才)、岸部一徳(65才)、六角精児(50才)ら、『相棒』のキャストが顔を揃えたが、約9年間も水谷とパートナーを組んでいた初代“相棒”の寺脇康文(50才)の姿はなかったそうだ。
ヤフーニュースの記事によれば、亀山薫役の寺脇康文が「相棒」を降板した理由は、「相棒」が長年高視聴率をキープし続けていることへの貢献は、自分にも少なからずあるはずという思いから、寺脇が番組に対して独自のアイデアを主張し始め、制作スタッフや杉下右京役の水谷豊との間に溝が生まれたことによるものらしい。
「相棒」の主役は確かに二人の刑事だが、メインはやはり水谷。その水谷以上に寺脇が目立つことをスタッフは快く思わなかったようである。
そのため、俳優同士が自発的に行なっていたリハーサル前の打ち合わせもなくなり、次第に寺脇の意見が通らなくなったことで、寺脇は自ら降板を願い出たのだという。
裏話を読めば、なるほどと思いあたるシーンもあったなァ・・・。
「美人に独身が多い理由は?」
高根の花だと敬遠されて、あまり男性からアプローチされた経験がないという理由は大きいだろうが、逆にアプローチされ過ぎて、女性自身が、
「男なんて、みんなこんなもの----」
と、男性に魅力を感じなくなってしまっているという場合もあるのだそうだ。
何故なら、美人は、子供のころから「可愛いね」とか「なんて、綺麗な子なんだろう」などの褒め言葉を山のように聞いて育っているわけで、合コンなどの席で、
「きみ、素敵だね。きみみたいな綺麗な子、初めて見たよ」
なんて、男性たちから通り一遍の褒め言葉を聞かされても、そんなの耳タコよ---ぐらいな反応しか返せないのだ。
「あ~~、どうして、もっとわたしの内面を褒めてくれる人がいないのかしら?」
なんて、溜息つきまくりの人生があっという間に過ぎてしまい、気が付いたら----なんてことは、美人にはざらにある。
美人に生まれたら、自ら積極的にひょうきんな面やドジな自分をアピールでもしない限り、内面まで見てくれる男性はかなり少なくなるはずだ。
「お高くとまっている」「格好つけている」「冷たそう」「近寄りがたい」「三日見れば飽きる」と、あまり良いイメージを持たれにくいが故に、損をしている面が多々ある美人さんたち。
そんな彼女たちを振り向かせたいのなら、外見を褒めても、ほとんど徒労に終わるはず。
むしろ、褒めるべきは、彼女たちの性格や特技である---という、暇つぶしのお話。
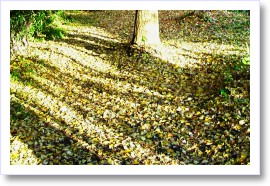
続きを読む
剣道少年の悩み
2012年11月09日
剣道少年の悩み

どうやら、昨日あたりから検索エンジンがかかったようだ。
読者が閲覧している訳ではない。
一年に二回ほど、こういうことがあるんだよね。
見分けるのは簡単。
短時間の間に、一気に訪問アクセス数が上がる。

でも、PVの方はあまり関係がない。これが、特徴かな?
ヤフー知恵袋に、男子中学生からの投稿があった。
「ぼくは、剣道が大好きで、二つの剣道教室に通っています。一つの方は、大人の有段者が多い教室なのですが、ぼくが稽古を始めると、大人の人たちが笑います。面を打っても、胴を入れても、とにかく笑う笑う。とても、不愉快です。
もう一つの教室では、今度は、みんなから、『格好つけてんのか?』というような言葉を浴びせられ、せっかく大好きな剣道が嫌いになりそうです。ぼくの何が悪いのでしょうか?」
これに対するベスト回答は、
「わたしは、過去に剣道を経験し、再び30代で剣道を始めた主婦ですが、自分の中学生時代のことを思い出すと、基本よりも試合に勝つことばかりに熱心だったように思います。
大人の有段者から見ると、あなたの剣道は基本がなっていないということで、笑いの対象にされてしまっているのではないでしょうか。
格好ばかりつけていると思われるのも、そのせいだと思います。剣道は奥が深く、選手権大会に出場するわけでもないのなら、段が上がれば上がるほど、勝ち負けよりも基本を重視するようになるもので、大人の人たちは、あなたのその基本の未熟さを笑っているのではないでしょうか?
もしも、自分の剣道が笑われたら、『自分の何処がおかしいのでしょうか?教えて下さい』と、訊ねてみるといいと思います」
と、いうものだった。
しかし、この投稿者は、まだ中学生である。基本は確かに大事だが、既に試合で勝つことを放棄した一般の大人が彼の剣道を笑うとは、逆に笑止千万。
構えが変だと思うのなら、笑ったり、茶化したりせずに、真面目に最初から教えてやればいいのである。
中学、高校の頃は、勝つための剣道をするのが常識である。それがないのなら、剣道などやる意味さえないくらいだ。
勝つ楽しさを知らずして、剣道の何を勉強せよというのか?ただ大人しい綺麗な剣道ばかりをしている子供に、どんな魅力があるのだろう。
格好つけて何が悪いのか?モチベーションを上げるために、格好から入ることは、決して間違っている訳ではないと思う。
そのカッコつけ剣道で、試合に負け続けるというのであれば、どうしたら勝つことが出来るかを、また勉強し直せばいいのだ。少年時代の剣道は、とにかく元気が一番。
剣道は楽しいと、子供たちに思わせるためにどうするか?----それを考えるのが大人の有段者の役目なのではないだろうか。
中学生がどんな剣道をしようが、笑うなどもってのほか。たとえ、その姿が可愛らしいから笑っていたとしても、そんなことは理由にはならない。
投稿者も、試合もせずに、過去の栄光よもう一度と、防具をつけることだけをステータスのように考えているおじさんやおばさんたちの無礼な態度に、委縮する必要など決してないのである。
続きを読む
頭の体操
2012年11月08日
頭の体操

久しぶりにコンビニでチャーハンを買った。
餃子二個のおまけ付き。
何だか、以前よりおいしくなっているような気がする。

深夜のテレビ番組を観ていたら、ちょっとトンチの利いた面白いクイズ番組を放送していた。
あなたは、このクイズ、解けるだろうか?
★ 誰もが一度は聞いたことがある「一年生になったら」という歌だが、この歌詞を聞いていた子供が、突然、
「この歌、変だよ」
と、言い出した。子供は、この歌の何が変だと思ったのだろうか?
一年生になったら一年生になったら
ともだち100人できるかな
100人で 食べたいな
富士山の上で おにぎりを パックン パックン パックンと
一年生になったら一年生になっ たら
ともだち100人できるかな
100人で かけたいな
日本中を ひとまわり ドッシン ドッシン ドッシンと
★ メアリーさんの父親には、五人の娘がいる。
長女の名前は、「ナナ」 次女の名前は「ネネ」
三女の名前は「ニニ」 四女の名前は「ノノ」
では、五女の名前は、何と言うのだろうか?
さあ、この答え、お判りだろうか?
最初の答えは、富士山の頂上に100人は登れない?----いやいや、そうではない。
ともだちが100人出来るということは、自分も入れれば101人なのだが、この歌詞は「おにぎりを100人で食べたい」となっているのが変だということなのである。
歌詞を正しく直すならば、「100人と食べたいな」にするべきなのだ。二番も同じ理屈である。
二問目の答えは、もしや、「ヌヌ」と答えてしまった人も多いのでは?が、それは間違い。
五女の名前は、「メアリー」----メアリーさんの父親には----という問題に注目すると良い。
 続きを読む
続きを読む注目されたい女
2012年11月08日
注目されたい女

「ザ・世界が仰天スペシャル」で、とにかく自分が注目されたくて仕方がない女が犯してしまった事件を、ドラマ仕立てで取り上げていた。
被害者は、その女とルームシェアをしていた女性たちなのだが、どうしても注目の的になりたい願望が抑えきれなかったその女は、最終的に自分を被害者に仕立てた自作自演の事件をでっち上げ、それが警察の捜査対象となったために、すべてがバレたという顛末であった。
このドラマを観たあとで、番組ゲストの一人だった女優の遠野なぎこは、
「こういう女性、わたしたちの業界にもいますよね。いつも、話は自分の自慢ばかり。誰も褒めてくれないので、自分で自分を誇示するしかないのだと思う。すごく寂しい人なんだと思いますね」
と、いうように語っていた。
そういえば、かつてのヒッチコック劇場にも、これに似たような物語があった。
ニュース番組の男性キャスターが視聴率を上げて自分の知名度をさらにアップさせたいがために、自ら連続女子高生殺人事件を起こし、それを自身がレポートするというストーリーである。
他人から常に注視されていないと、自分の存在が世間から忘れ去られているのではないかと不安になり落ち着かない---という人はいるが、口を開けば自分の自慢話ばかりとなると、これは既に心を病んでいるといえるのかもしれない。
そういう人は、そのうち、身近な人たちからだけの注目では飽き足らなくなり、大勢の人の関心を集めなくては気が済まなくなるといわれる。
それがいつしか犯罪にまで手を染めることにもなり兼ねないのだそうだ。
また、自分自身には自慢できることがあまりない人が、自分に近しい人の自慢をすることで、結局は遠回しに自分はそういう人の友人なのだ、みんなわたしを尊敬しろ---と、訴えるケースもある。
番組中で、遠野は、こうも語る。
「そういう人は、(みんなに飽きられることを警戒して)自慢話をしているように思わせないような話し方をすることもあるけれど、やはり、それだって自慢話に違いがないんですよね」
どんなに婉曲的な話し方をしても、注目されたい願望が強い人は、尊敬されるどころか、結局は周囲から疎まれる存在になるのだということを、肝に銘じておいた方が良いだろう。
続きを読む
同じ匂いがする・・・って、ど~よ?
2012年11月07日
同じ匂いがする・・・って、ど~よ?

昔は、女性を惹き付けたり、自分の術中にはめる際の常套句には、
「何処かで、お会いしたことありましたっけ?」
が、一般的だったが、近頃は、
「あなたとわたし、同じ匂いがするわね」
だそうだ。犬じゃないんだから、同じ匂いか否かなど判るわけがないのだが、人は、この言葉に何故かグッと親近感を懐いてしまう。
わたしなら、「え?わたし、香水なんかつけていませんけれど」と、まぜっかえすところだが、今の女性たちはとにかく親しい友人に飢えているようで、「同じ匂い」----つまりは、似た経験者同士とか似た境遇同士とかに、コロっとやられてしまうようだ。
似非宗教家や自称メンタルアドバイザーなどの中にも、こうした言葉で巧みに、文字通り他人の懐へ入り込む者も少なくないという。
まあ、メンタルな分野の資格は、ほとんどが民間認定なので、どんなに肩書を詐称しても罪には問われないという理由もあるのだろうが、近頃は、誰にでも臨床心理士まがいの行為が許されているので、こうした言い方で巧みに近付く人には、要注意だという話である。
しかし、冷静になって考えてみると、そうそう世の中に自分と同じような生活環境や経歴を持つ人間などいるはずもない。
たとえば、同病相哀れむとはいうものの、同様の病気を患った者同士とはいっても、既婚者か、独身か、子供はいるかはもちろん、学歴、職歴、経済状態など突き詰めれば、結局は相違点ばかりで、「同じ匂い」などするべくもないことは一目瞭然なのである。
そういえば、奇しくも先日テレビで放送した映画「ナイト&デイ」の劇中、トム・クルーズが図らずも事件に巻き込んでしまった女性に言う、こんな台詞がある。
「安心して下さいとか、安全は保証しますという奴には気を付けろ」
実に、今の時代を言い当てている一言だと思った。
続きを読む
パンを買う夢を見た
2012年11月06日
パンを買う夢を見た

この間、とてもリアルにパンを買う夢を見た。
夢の中では、パンの種類までもしっかりと判り、パン屋さんの店内は、わたしの他にも大勢のお客さんで繁盛していた。
わたしは、たくさんの焼き立てのパンを前に、トレーとトングを手にしてウキウキだ。
中でもふわふわの大きな茶色いパンを二つトレーへ載せた。これは、ミルクパンだと思う。
次に、カステラパンをトングで挟み、取ろうとするが、あまりに軟らか過ぎてパンくずが落ちてしまって少し取りにくい。が、これも何とかゲット。
そのうちに近くまで来た男性客が、ビニールに包まれたカレーパンを手にして何やら言いがかりを付けたそうな気配だが、こちらが一喝したら退散した。
やがて、会計を済ませて店を出たところで、目が覚めた。

このような、パンを買う夢を見た場合の暗示は何なのか?
パンは、豊かさや生活状況を意味するのだそうで、パンを買う夢は、信頼できるパートナーや味方になってくれる目上の人を得られる予感ということだそうだ。
また、ふっくらとしたパンを買う夢ならば、順調な仕事や日常生活、嬉しい知らせが届く予感という暗示。
パンくずが印象的な夢は、思いがけない幸運が舞い込むかも・・・ということのようである。
自分でパンを焼く夢は、充実した結婚生活が送れているという意味と、まだ独身の人ならば、そういう未来が待っているという暗示。
たくさんのパンを抱えている夢は、金運上昇の印で、くじに当たるなど棚ぼた的幸運が訪れるかもしれないという意味だそうだ。
そして、パンを食べている夢は、健康に恵まれている証だとか・・・。夢の中で物を食べると風邪をひく---と、いうような迷信があるが、パンはそうでもないらしい。
しかし、硬いパンやカビの生えたパンの夢は、運勢が下降気味ということを知らせているものらしく、何らかの障害が現われる兆しとか・・・。
食べてみたら、やけに甘いパンの夢は、身体の変調を暗示している可能性もあるそうだ。
そして、パン職人がパンを焼いている夢を見た時は、やがて何か大事な知らせが届くということを暗示しているので、見逃さないように気を付けた方がいいらしい。
だいたいにおいて、パンの夢は、幸運の知らせということのようだ。
まあ、実際にこんな幸運がやってくればいいのだが、期待せず気長に待つとしようか・・・。(^_^;)
続きを読む
「セカンドオピニオン」の落とし穴
2012年11月06日
「セカンドオピニオン」の落とし穴

某ブログに、「セカンドオピニオン」についての記述があったので、コメントを書き込もうとしたが、会員以外のコメントは受け付けられないということなので、ここに書くことにした。
そのブログでは、
「自分に下された診断結果に疑問がある時、担当医に『別の先生にも診察して頂きたいのですが、紹介状を書いて下さい』と、頼むことが出来る『セカンドオピニオン』を受ける権利は、当然患者誰もが持っているものなのだから、頼まれた医師は、嫌な顔をしたり、『もう自分の知ったことじゃない』などと言って、患者に心理的ストレスを与えてはいけない」
ということが書かれてあったが、この文章には、もう一つ、患者側からの視点が抜け落ちていた。
つまり、この文章は、「セカンドオピニオン」を受けたいと思う患者が、自力で何処へでも行けるという前提に立った話なのである。
たとえ、担当医が「セカンドオピニオン」を承諾し、紹介状を書いてくれたとしても、世の中の患者が、皆、遠くの病院まで行けるわけではないということにまで、記事は触れてはいなかった。
そこで、わたしが書き込もうとしたコメントは、以下の通りである。
「セカンドオピニオン」に関するご説明は、確かにその通りだと思います。
しかしながら、一方で、そういう患者の頼みにケチを付ける医師がいる病院へしか診察を頼めない患者が大勢いることも事実です。
医療関係者の方々は、簡単に「別の病院へ行って下さい」と言われますが、独り暮らしのお年寄りや、経済的な理由で移動にお金がかけられない人、子供がいても気兼ねをして同行を頼めない人、移動するだけの体力がない人は、どうしたらいいのでしょうか?
現在、がん治療の拠点を信州大学病院へ集約するという構想も進んでいるようですが、北信地方から松本のがんセンターまで通院出来るはずがない---と、心配するお年寄りも少なくありません。
正に、「医療は誰のものか?」---医療関係者にこそ、そうした患者のための移動手段までもを念頭に入れて、真剣に検討、議論して頂きたいものと、切に希望します。
わたし自身も、まったく身体が動かず、しかも誰にも通院の付き添いが頼めずに、「別の病院で治療してもらって下さい」と言われても、一度も行けなかった経験がある。
医師は、簡単に「〇〇病院ならば治せる」と言うが、患者はそれぞれの経済状態や生活環境により、そこまで行けないことの方が多いのだ。
足が悪いので駅までの行き来が出来ず、タクシーを利用するしかない状況下で、通院だけで一年間に100万円も使ってしまい、「いっそ死んでしまいたい」と、嘆いている女性患者がいるというニュースを観たこともある。
健康な人には判らないだろうが、身体に病気を抱える身には、体力もともなわず、遠方への移動は物理的にほとんど不可能なのである。
医療関係者の視点は、そうした患者にとってもっとも不可欠な部分がいつも抜け落ちているのだ。
「セカンドオピニオン」が重要なことなど、今は、医師も患者も皆周知の事実である。
医療とは、ただ上っ面だけの専門知識を並べれば事足りる分野ではない。
傾聴や心理に携わる専門家ならば、問題の本質は、むしろ、その先にあることに気付いて頂きたいものである。

続きを読む
独りが好きな人
2012年11月05日
独りが好きな人

「黒バラ」というバラエティー番組で、SMAPの中居くんが、面白いことを言っていた。
「おれは、彼女が出来ても三日一緒にいられない。相手に気を使い過ぎて、疲れてしまう。とにかく、独りが好きなんだ。結婚すれば、どうしても同じ家に住まなくてはならなくなるので、とてもそんな状況に耐えられない。
結婚した後も、別々の家に住むことが出来ればいいんだけれど・・・」
こういう考えの男性って、案外多いような気がする。

いや、男性だけじゃない。女性だって、四六時中、夫とべったりなんて、面倒くさいと思う人は少なくないんじゃないだろうか?
中居くんのように、自分だけの自由な生活を40年以上も続けていれば、他人を自分のテリトリーへ入れようなどという気持ちは薄れて来るものだ。
彼女に愛情はある。確かにある。
しかし、他人に気を使う生活はしたくない。結婚相手なんだから気を使う必要なんてないだろう----と、傍はいうだろうが、気を使う使わないは、その人の性格なんだから、どうしようもない。
いくら大好きな夫とはいえ、一緒に生活することで緊張のし過ぎになり、円形脱毛症になった女性もいるくらいだ。
好きならば好きなほど、相手に格好悪い自分を見せたくなくて、トイレに行くことも夫が会社へ行っている間だけと決めて、膀胱炎を起こした妻もいるという。
愛情と、気苦労は、別物なのである。
もしかしたら、中居くんもこうした感受性の強いタイプなのかもしれない。
妻のやることが、いちいち気に障って、洗濯から掃除まですべてやり直さなければ気が済まなくなり、過労で離婚した男性もいるそうだ。
つまり、人には、絶対に共同生活に向かない性格の人もいるのだ。
そして、そういう性格の人が、今の時代確実に増えている。
かつて、ある薬剤師の女性が、意中の外科医の先生に、「先生は、ご結婚されないんですか?」と、訊ねたそうだ。
外科医の言葉は、一言、「しない!」だった。
彼も、自分だけの時間を大切にしたい人だったようだと、女性薬剤師は残念がっていた。
続きを読む
歩く夢を見たら・・・
2012年11月05日
歩く夢を見たら・・・

ほとんど歩けなかった時は、よく夢の中で歩いたり走ったりする夢を見た。
何だ、歩けるじゃない・・・と、感動しながら目を覚ますと、現実に戻って落ち込む---という日々の繰り返し。
そうかと思うと、まったく逆の夢を見た時も・・・。
どんなに頑張って歩いても、ぬかるみに足を取られて、まったく前進出来ないとか、階段が急すぎて上れないとか、足が重くて一歩一歩が汗だくという夢も見た。
そんな時は、やはり夢の中に現実が入り込んでいるのだと辟易したものだが、担当医の先生に電話をかけると、「階段の上り下りは、どうですか?」と、すぐ訊ね返して下さり、そんな気遣いも励みになって、毎日必死に歩く練習をしていたせいか、今では階段の上り下りもさほど苦労ではなくなった。
人間、何でもなせばなる---である。
で、そんな歩くという行為が夢に出て来た場合の意味を考えてみた。
歩くという夢は、人生の歩み自体を意味するものだそうである。
そして、夢の中の歩き方で、その意味も変わってくるそうだ。
さっそうと歩いている夢は、目標に向かって順調に進めるという暗示であり、成功や達成が手に入るという兆しを意味するものだが、歩き疲れてふらふらしていたり、時々躓いたりする夢は、もっとしっかり前を向いて行きなさいという忠告だそうだ。
また、歩き疲れている夢は、心身ともに疲れが溜まっている証拠。現実では、ゆっくりと休養をとることが必要という意味だという。
一歩一歩確実に歩みを進めている夢は、地道な努力を続ければ、頑張っただけの成果が得られるだろうということで、歩いている間に目的地が見えて来たら、恋のチャンスが巡って来る兆し。
しかし、いつまでたっても目的地が見えない場合は、自分が内心、そんなチャンスは到来しないかも・・・と、弱気になっている証拠だということのようである。
あてもなくさまよい歩くのは、現実でも、この先自分はどうしたらいいのか判らず、精神的に不安定な証しであり、何処かに寄り道をしてしまう夢は、一度立ち止まってよく考えよ、という注意の意味があるらしい。
夢の中の歩き方には、現実の体調や心理状態が反映されやすいそうで、迷いや不安があると夢の中でもうまく歩けないのだとか。
もしも、そんな歩きにくい夢を見た時は、実生活をじっくりと振り返り、見詰め直すことが大事だということのようである。

続きを読む
人を説得する方法
2012年11月04日
人を説得する方法

一日ごとに寒さが増して行く。
ついに、もう一台の石油ストーブも稼働させた。
昨年は、買った灯油に水が混入していて、すぐに火が消えてしまったのだが(もちろん弁償してもらった)、今年は間違いのない物を売ってもらった。-----はずである。
今のところ、調子よく燃えている。

ところで、人に何かを納得させたい時には、二つのやり方があるといわれる。
一つは、納得させたい物事の良い所だけを並べて、「・・・だから、そうしましょう」と、説得するやり方である。これを「片面説得」という。
もう一つは、納得させたい物事の良い面と悪い面を両方上げて、「・・・だから、こちらの方が良いと思いますよ」と、説得するやり方である。これを「両面説得」という。
それぞれの説得方法は、相手によって、その効果が多少異なるのだという。
「片面説得」が効果を表わすのは、主に低学歴の人たちを対象とした時といわれ、高等教育を受ける機会のなかった時代の人たちには、この説得方法が功を奏したそうである。
しかし、現代は、ほぼすべての国民が義務教育以上の学歴を有するため、こうした「片面説得」は、あまり向かないということであった。
つまり、AとBがあれば、両方の長所と短所を知った上でなければ、相手の説明を納得出来ない人が多いという実験結果も出ているそうである。
そのため、たとえば医療の分野においても、昔は医師が一方的に、
「この薬を飲んで下さい」
と、言えば患者はそれを何の疑いもなく飲んでいたが、今は、薬の長所である効能や短所である副作用までも、しっかりと説明しなければ、患者は安心して服用しなくなっているという。
また、小売業者に言わせても、売る側のベタ褒め賞品は、消費者が胡散臭がって、簡単には手を出さないそうである。
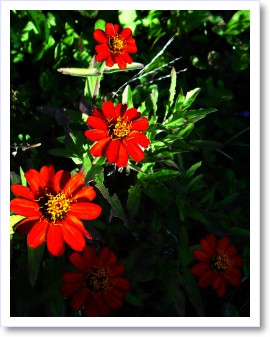
続きを読む
絵を描く
2012年11月04日
絵を描く

わたしは、小説やエッセイも書くが、たま~~に絵も描く。

店内が殺風景なので、風景画でも描いてくれと父親に頼まれ、久々に絵筆をとったのだが、これがさっぱりいつもの勘がもどらない。
何枚描いても、納得のいく絵が描けずに自己嫌悪だ。
それでも小さな物なら何とかマシになって来たので、額に入れて飾ってみた。
こうして置いておくと、ありがたいことに時々お買い上げいただくことがある。
それにしても、病気をしてからは体力の都合上、一日一枚描くのが限度になってしまった。
絵を描く時は、基本立ったままなので、作業に時間制限があるのだ。二時間を過ぎると、カラータイマーが作動し始める。
何とも、情けない・・・。

近頃は、40歳を過ぎても独身を通している男女が実に増えた。
一人の時間が快適だと思うようになると、結婚をしてお互いに気を使い合う生活などまっぴらだと思う人が多いためだ。
人間は、年を重ねると、自分だけの空間を大切にしたくなるもので、他人の干渉を鬱陶しく思うようにもなる。
まだ20代の頃、クリスマス・パーティーの席で、ある既婚女性に言われた。
「年をとって独身は辛いと思うよ。やっぱり、頼れる人と一緒にいた方が楽しいし、安心出来るから・・・」
年をとってから一人は辛い----果たしてそうなのだろうか?
むしろ、辛いのは、一度二人の幸せな生活を知ってしまった人の方ではないのだろうか?
チョコレートの味を知らない人は、チョコレートが食べられなくて辛いとは思わないだろうが、一度その味を知ってしまった人は、また食べたいと思い辛くなる。
人生だって同じことだと言った人もいる。
わたしに、「年をとってから辛いと思うよ・・・」と言ったその女性は、既に夫が他界し、子供は親元を離れ、今は結局一人暮らしだという。
おそらく、病気で大変なわたしなどよりも、ずっと孤独で辛い日々を送っているに違いない。
人の一生など、若い時にどうこう決めつけられるものではない。
それこそ、死ぬまで結論などは出ないものなのである。

続きを読む
巷の話題いろいろ
2012年11月03日
巷の話題いろいろ

先月、父親(70代)を肺がんで亡くした女性が、父親が肺がんを発症した時の様子を語ってくれた。
初めの兆候としては、軽い空咳のようなものがかなり長く続いたという。
本人は、風邪だろうと思い、病院へも行こうとしなかったが、さすがに一ヶ月を超えても治らないので心配になって、ついに病院へ行ったのだが、その時は、異常を発見できなかったのだそうだ。
それでも空咳は続くので、やはり心配になり人間ドックへかかったところ、痰の培養検査で、ようやく肺がんと判ったのだという。
それから約二年、治療のために入退院を繰り返していたのだが、最後は脳へも転移して、先月眠るように亡くなったのだという。
「父親は、煙草も吸わず、どちらかといえば健康にも気を使う几帳面な性格だったので、まさか、肺がんとは驚いた。職場の環境が悪かったのか・・・。肺がんの中には、レントゲンなどでは発見しづらいものもあるそうで、もっと早いうちに詳しい検査をしてもらえば良かったと思うが、個人的には原因になることが思い当たらないこともあり、父親が肺がんになるなど、未だに信じられない」
女性は、そう語っていた。
確かに、咳以外には特別な症状もなければ、風邪と勘違いして、病院へ行くこともつい一日伸ばしになってしまうかもしれない。
「気付くのがもう少し早かったら・・・」
女性は、今もそれが悔やまれるという。
もう一人、ある女性の話。
この女性(60代)は、つい最近、ご主人が重いがんを患っていることが判った。
抗がん剤などの治療費がかさむので、一時期勤めていた職場へ再び復帰した。
ところが、この復帰には、高いハードルがあったという。
実は、この女性、以前その職場の経営者と大げんかをして、自ら仕事をやめた経緯があったのだ。
その後も、経営者からは、何度か思いなおして戻ってきて欲しいと頼まれたのだそうだが、その時の憤懣が気持ちの中で尾を引いていて、
「二度と勤めてなんかやるもんか!」
と、断わり続けて来たのだそうだ。
しかし、ご主人の病気にお金が必要で、もはや意地を張っている場合ではないと、今度は自分からその経営者に頭を下げて、パートに復帰させてもらうことになったのだという。
午前中3時間、午後3時間の計6時間のパートだが、ご主人の入院費の足しにしているそうだ。
「一度けんかしてやめた職場だから、戻るのは気後れしたけれど、今はそんな自分のプライド云々を持ち出している場合じゃないから」
と、女性は苦笑する。
お金のためなら、自尊心さえもかなぐり捨てねばならないという話に、世の中の厳しさを実感せずにはいられなかった。
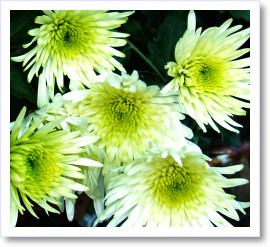
続きを読む
何故、人は従属したがるのか?
2012年11月03日
何故、人は従属したがるのか?

最近は、家族や友人から嫌われることを極端に恐れるが故に、相手に盲目的に従属してしまうという人々が何故か増えているという。
誰に何を言われようと、自分は自分だ。これだけは譲れない----という芯が欠如している人が多いのだそうだ。

日本人には、とかく「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の性格の人たちが多く、「赤信号、みんなは止まれ、おれ渡る」という覚悟の者が少ないと言われるが、これは、常に、誰かが自分の味方でないと安心して生活が出来ないという心理から来ているともいわれるようである。
あまり内容を詳しくは知らないが、連日報道されている角田被告の絶対君主的暴力と支配に抗えず、命令のままに身内の殺戮を繰り返した人たちも、正に、この恐怖支配から逃れられず、盲目的従属に甘んじた者たちということが出来ると思う。
恐怖支配下においては、そこから逃げ出そうと思えば逃げられる状況にありながらも、支配される側の人間の中に、何故か支配者に気に入られたいという思いが生まれるという状況が起こることが往々にしてあるらしい。
一連の事件の際、親戚から金を借りて来るように命じられたある夫婦が、裸にされたまま道を歩き、親戚宅まで出かけた時も、そのまま逃げ出して警察へ駆け込むなりすることは可能だったはずなのだが、それをせず、親戚に金銭を用立ててもらうと、再び角田被告の待つ家へと取って返したというのであるから、この夫婦も既にそうした心理状態に陥っていたものと思われる。
こうした恐怖支配に対する盲目的従属は、何もこのような大事件に限ったことではない。
身近なところでは、近所の主婦同士のささやかなつるみあいなどにも、同様の兆候は見て取れる。
少しばかり他の主婦よりも強引な性格の主婦がいつの間にか主婦同士のリーダー役となり、いつしか彼女の決断や指示なしでは、他の主婦たちは何一つ自分の気持ちで物事を決められなくなってしまうということもあり得るのだ。
そのリーダー的存在の主婦が夫の転勤か何かでその土地を離れたとして、残された主婦たちに、
「どうして、あんな女性の言いなりに行動していたのか?」
と、訊ねたとする。すると、その答えは、おそらく、
「何故だか判らない。彼女に反対して、仲間外れにされることが怖かったからかしら・・・」
というものになるだろう。仲間外れにされることが怖いとは、具体的にいえば、ご近所付き合いや情報交換の外に置かれるのが不安だったということなのだろうが、ご近所付き合いとはそもそも何なのか?身近な情報が入らなくなることが心配ならば、自ら自治体や地区役員に問いただせば済む話ではないだろうか。
自らが率先して動けば、何も仲間外れの状況におびえることなど何処にもないことに気付くはずである。
つまり、自分に自信がない者ほど従属を望みたがるわけで、逆に自信がある者は、支配者の呪縛さえ見えないというのが真のところであろう。
続きを読む
日々のたわごと 3
2012年11月02日
日々のたわごと 3

今日は、またグッと冷えましたね~。(>_<)
巷では、近頃、アミューズメントパークが大繁盛のようです。
東京ディズニーランドとかディズニーシー、ユニバーサルスタジオ・ジャパンなどなどには、連日家族連れが詰めかけ、大賑わいだそうで、そのあおりを受けたのが、デパート業界だということでした。
物を買うよりも、思い出を残そう---という、いわゆる節約、倹約生活へと、家族のあり方がシフトし始めた証拠なのでしょう。
アミューズメントパークは、三世代でも楽しむことが出来、若夫婦は、祖父母の財布を当てにできるというメリットも。
食事もレストランなどで食べるよりは格安だそうで、これからは、ますますこうした娯楽が主流になりそうだということでした。
でも、三世代とはいうものの、その実は、奥さまの実家の両親との家族単位が多いようで、旦那さまは付き人状態。
これって、厳密にいえば本当の三世代とはいえないと思うんですけれどね。
沖縄では、夜間外出禁止令を破った米兵が、民家に無断で侵入し、中学生の男の子を殴ったとか。
理性というものを知らない海兵隊員には、モラルとか規律などというものは通用しないようですね。
外出禁止令に違反した場合は、沖縄県警に身柄を渡す---とでもいう懲罰を科さなければ、本気で命令に従うつもりなど彼らにはないでしょうね。
でも、その米兵が、侵入した家の三階のベランダから飛び降りてケガをしたところを、どうして住民も取り抑えなかったのかも疑問の残るところ。
中学生が一人で留守番でもしていたというのなら、それも難しいかもしれませんが、ニュースを聞いた限りでは、近所の人たちに助けを求めて身柄を確保し、警察に引き渡せば良かったのに・・・と、思ってしまいます。
犯人の米兵に基地内の病院へ入院されてしまったのでは、沖縄県警は簡単には手が出せないでしょうから----。
どれほど、沖縄県が多発する不祥事の再発防止を厳命しても、アメリカ軍には本気で取り組む気はないようですからね。
となれば、沖縄県民は、家にいても安心出来ない生活を強いられているのですから、他の都道府県とは別に、一歩踏み込んだ自主防衛策を講じる必要があるようです。
続きを読む
学芸会は頭が痛い
2012年11月01日
学芸会は頭が痛い

ヤフー知恵袋に、「漫画やドラマでは、小学校や保育園などの学芸会で、時々笑いをとるためなのか木の役をやる子供が出て来ますが、こういう役は、本当にあるのでしょうか?」
と、いう投稿があった。
おそらく、今の時代は、我が子がこんな役を押し付けられたら、モンスターペアレントが黙ってはいないだろうが、昔は、確かにあったと思う。
回答の中にも、「木の役の子供は、舞台上で15分ぐらい黙って立ち続けていた」と、答える投稿があった。
因みに、わたしは、大蛇に破壊される堤防の一個の石の役をやったことがある。もちろん台詞はなし。ドミノ倒しに倒れるところが、それなりに難しく、何度も練習した。
そんな学芸会にまつわる質問で、ある母親が、「小4の娘が学芸会のある役のオーディションに臨み、落とされたのだが、その選考方法に納得がいかない」との投稿もあった。
「娘は、オーディションに臨むために、一生懸命練習した。オーディションは、学級担任の発案で公正な選考を行なうため、人気投票にならないように配慮され、候補者の女子児童たちとさほど接点のない男子児童四人の投票で選ぶことになった。
結果は、その役を射止めた女子が3票、娘が1票、もう一人が0票だった。その後、クラス全員でその配役で良かったかを話し合い、オーディションに落ちた二人の理由も述べられたという。
娘は、その時は涙を我慢していたが、帰宅後に悔しいと大泣き。わたしも、その話を聞いて、選考方法があまりに理不尽だと思い、どうしても納得がいかない。別に、モンスターペアレントという訳ではないので、学校へ文句を言いに行くつもりはないが、皆さんの意見をお聞きしたい」
と、のこと。
それにしても、今の小学校はすごい!
オーディションって、正にプチタレント養成塾だな。
しかも、審査内容までクラスメート全員の前で発表されるとは、よほど根性が据わっていなければ、心理的に這い上がれないほどのダメージを受けることにもなり兼ねない。
まあ、ゆとり世代の「みんなで主役」よりはマシかもしれないが、この投稿者も自分の娘がまるでクラス中のさらしものにされたように思ったのかもしれない。
いずれにせよ、子供のやる劇である。役を競うならば、それをやりたい子供全員でジャンケンでもすればいいんじゃないだろうか?
その方が、よほど公正公平になるように思うのだが・・・。
回答者たちの意見は、こういう選考方法も「あり」だということだが、役をもらえなかった子供にとっては、一生のトラウマになりそうな気がする。
熾烈なオーディション競争だったとはいえ、その子はまだ1票でも入ったのだから救いだが、0票だった子の気持ちを考えると、教師も酷なことをしたものだと眉をひそめずにはいられない。
続きを読む
こんな女性はモテない・・・かも 3
2012年11月01日
こんな女性はモテない・・・かも 3

「でっかいメガネ。顔の大きさをごまかせるけど、このアイテム使ってること自体が嫌だからプラマイゼロ」
「トレンカ? ってやつのよさがわからん。あれ野球部じゃん」
「カチューシャやカチューム。服装や顔の雰囲気に対してカチューシャが浮いてる人が多い気が」
「ネイルは家事していないイメージがつく。実際に(料理や洗い物をするとネイルが)取れるかどうかじゃなくて、何も知らんこっちからすると見た目でなんか不衛生なんだよなあ」
「でっかいピアス。あれが好きな男は見たことない」
などなどの意見もあるそうな。
因みに、「トレンカ」とは、足の土踏まずの所にひっかけるようにして穿くレギンスやタイツ、もしくはスパッツのようなものだとか・・・。
昔のスキーズボンを知っている人なら、あの形で脚にピッタリしている物----と、言った方が判りやすいかもしれない。
野球好き男子には、野球のユニフォームのストッキングを連想させるので、こういう答えになったものと思われる。
ただ、意外なのが、カチューシャが男性には案外不評だということ。
女性ならば、カチューシャは子供の頃から定番のヘアアクセサリーなので、ショートヘアのわたしでさえ、一つや二つは持っている。
おそらく、カチューシャの似合う女性の顔というのが、男性たちのイメージと違う場合に、NGということになるのだろう。
女らしい可憐な乙女顔ならば、カチューシャもカチュームもOKなのかもしれない。
が、これは、男性に「野球帽が似合わない人は被るな」といっているようなもの。モテない女性の理由にはならないと思うのだが・・・。
そして、極めつけは、やはりネイル。これは、男性のほとんど誰もが、「妻や彼女にはやって欲しくない」と、敬遠するファッションらしい。訳は、言わずもがな。
でっかいピアス----に関しては、南国系を連想させるからなのか、日本人の平面顔にはあまり似合わないと言いたいのだろう。
日本の男性は、好きな女性には出来るだけファッションも控えめな物を期待する傾向が大きいようだ。
総じて、見た目が派手な女性は、どうしても苦手にならざるを得ないようである。
やはり、清潔感のあるちょっと控えめな、性格の可愛い女性がモテる女性といえそうだ。
続きを読む
読者に親切な文章とは
2012年10月31日
読者に親切な文章とは

かつて、古谷綱正というニュースキャスターがいた。
若い人たちは知らないだろうが、テレビ黎明期の有名なキャスターである。
巷では、「滝川クリステルの語り口が、古谷さんに良く似ている」と言われているそうで、とにかく言葉の一音一句を丁寧に発音し、内容を常に視聴者の立場に立ち、判りやすく解説することをモットーとしたアナウンサーでもあった。
たとえば、珠算を取り上げたニュースでは、
「珠算----たまざん、そろばんのことですね」

というように、どの年代の人が聞いても納得のいく話し方で、ニュースを読み進めたものである。
こうしたことは、話し方だけではなく、文章を書く上にも必要な配慮であると思われるが、今の若い文筆家やフリーライターと呼ばれる人たちの書く文章は、何処か自己満足の要素が強く、各年齢層の読者のニーズにマッチしていないように懸念されてならない。
やたらと横文字を並べれば、知的な文章に見えるような錯覚を起こしているようにも感じられ、何の下知識もない読者には、極めて不親切なものとなっている。
せめて、横文字のあとに意味や解説なりが書き加えられていればまだしも、そのような説明もなく、「知っているのが当たり前」という姿勢では、本物の文筆家とはいえないのではないだろうか。
また、とんでもなく難しい漢字や熟語をこれ見よがしに使ったあとに、突如として今風の言葉が共存するなど、文脈もデコボコとしていて、文章全体に規則的な流れがないのも、そういう人たちの特徴のような気がする。
人間の脳は、普通、書き手の癖に慣れながら次の行を読み進めて行くように出来ているのだが、あまりにぎくしゃくした文章が続けば、途中で疲れてしまうし飽きてしまうものである。
とかく文を書く習慣があまりない人や、文章を書く機会はあっても知識が先走り過ぎる人は、難しい語彙や言い回しを多用することが、うまい文章のように考えがちだが、これは大いなる誤解だと思う。
良い文章とは、如何に読み手に判りやすく書けるかで決まると言っても過言ではない。
児童文学が大人向けの小説などよりも書くのが何倍も難しいといわれるのは、こういう理由からなのである。
幼稚や貧弱にならず、かといって難解過ぎることもなく、その上自分本位のご都合主義を排除した文章とは、どのようなものなのか?
かく言うわたしも、未だ毎日が模索の連続ではあるのだが・・・。(~_~;)
続きを読む
こんな女性はモテない・・・かも 2
2012年10月31日
こんな女性はモテない・・・かも 2

どうやら、男性に言わせると、モテない女性は何かを勘違いしている節があるようだ。
女性が考えるモテ女と、男性が考えるモテ女とでは、かなりイメージに差があるらしい。
★ 「食べないで痩せる女の子がかわいいみたいに思ってるガリガリのヤツ。ちゃんとした生活をして肉付いた子の方がいい」
これは、確かに女性の勘違い。
細ければ綺麗に見えるはず----との思い込みは、まったくのナンセンス。男性でなくても、ガリガリ女性は勘弁と言いたい。貧乏症にも見えてしまうので、とても家庭的な温かみのある雰囲気が感じられない。
特に、顧客とのコミュニケーションにおいて、癒しや安心を提供する小売、宿泊、飲食などの接客業には不向き。
★ 「エステ通いはあまり費用対効果が高くない気が。いまいちその違いが分からない」
これは女性の目から見てもそう思う。エステは、80パーセントが自己満足意の世界。見た目も変わるほどの美しさをエステで得ようとするのは少々無理があるように感じる。まあ、人の手に触れてもらうことでのリラックス効果もあるし、日々の忙しさから一時逃れ、ストレス解消の気分転換が出来るというメリットの方が大きいのではないだろうか?
また、エステへ行こうと思うような人は、もともとが自分に対する美意識の高い人なので、してもしなくてもさほどの違いはないのではないだろうか。それよりも、男性目線では「金のかかる女」というイメージの方が先行しがちのようである。
★ 「犬猫を見かけるとすぐに『かわいい』といって駆け寄るのは嫌。うそっぽく聞こえる」
これって、テレビCMでも観る。ペットの子ブタに向かって、「かわいい~~
 」と言いながら、カメラを向ける女性のCMだ。たぶん、プリンターの宣伝なのだろうが、わたしの母親はこのCMが大嫌いである。
」と言いながら、カメラを向ける女性のCMだ。たぶん、プリンターの宣伝なのだろうが、わたしの母親はこのCMが大嫌いである。「『かわいい~~』と、言いながら、その実、そう言っている自分を可愛く見せようとしているだけだ。女のせこさが見え見えだ」
という理由らしいが、男性たちの意見もそんなところなのだろう。これも敬遠されがちな「ぶりっこ」の部類に入るのだろうな。
★ 「会ってすぐのボディタッチ。肩から肘のあたりをなでるように触れられると、あざとすぎて引いてしまう」
中には、「モテテク」としてではなく無意識に行っている女性もいるかと思うが、それを見て男性は「ああいうモテテクは嫌だなあ」と逆に勘違いしているかもしれない。上のような行動をする場合は要注意----だそうだ。
そんな積極的な「モテテク」を使う女性がいるということにも唖然だが、気色悪いとしか言いようがない。
無意識で行なう女性というのは、おそらくつい職業病が出てしまう人なのかも・・・。男性でなくても、確かに引く。
続きを読む
こんな女性はモテない・・・かも
2012年10月30日
こんな女性はモテない・・・かも

男性があまり好感が持てないという女性の言葉使いや仕草には、次のようなものがあるという。
★ 「一人称が自分の名前。または『うち』という人。許されるのは20歳まで」
確かに、こういう女性は意外に多いもの。
学生気分が抜けないのか、子供の頃に名前で自分を呼ぶのを親がやめさせなかった名残なのか、とても大人の女性とは認めてもらえない気がする。
自分を「うち」というのは、別に京都生まれというわけでもないのだろうが、そういう言い方をする女子は、わたしの高校時代にもいたので、世代は関係ないんだなァ・・・と、ある意味驚いた次第である。
★ 「メシ食った時に頭フルフルさせる女。あれかわいいと思ってんのか?」
これは、わたしも一度見かけたことがあるが、実に不思議な仕草である。
ある喫茶店で、女性同士がお茶をしている様子をたまたま目撃したのだが、そのうちの一人が、ケーキを一口食べるたびにやたらと頭をグラグラさせるので、「大丈夫か?」と、思ってしまった。
物を食べるというある意味恥ずかしい行為の照れ隠しに行なっているのだろうが、良い年をした大人の女性が、子供のように頭をグラグラさせる方がよほど奇妙に見えた。
★ 「おちょぼ口で食べる子。おいしそうにガツガツ食べる女子が好きな男は多いと思う」
女は、他人の前で大口を開けるものではない。はしたないことだと教えられている女性は多いはずだ。教えられてはいなくとも、女性には、大口は本能的にみっともないことだというブレーキが働くものである。
そこで、自然とおちょぼ口になってしまうのだろうが、特定の男性とお互いに気心が知れればガツガツ食べることもいとわなくなるだろう。初対面では、女性のおちょぼ口はある意味致し方のないことと、男性も心得よ。
★ 「定番だけどぶりっこ。女に幻想抱いてるようなキモい男しか引っ掛からないし、逆に『必死な女』に見える」
この「ぶりっこ」は、確かに女性の目から見ても、あまり頂けない。
その「ぶりっこ」いつまで続けるのか?----と、聞きたくなる。まさか、40過ぎまでやるわけじゃァないとは思うが、どうせいつか化けの皮がはがれるのなら、早いうちからはがしてしまった方が、女性自身ものちのち楽じゃないのだろうか。
作りものの自分を演じ続けるには、限界があるものだ。
続きを読む
日々のたわごと 2
2012年10月30日
日々のたわごと 2

NHK長野局の堀越将伸(ほりこしまさのぶ)アナウンサー、久しぶりにテレビニュースで観た。
やっぱり、あのソフトな声、良いなァと思う。話し方もとても視聴者が聞きやすいように工夫されている。
一般の人にインタビューする時も、自然体の問いかけで、素人にも応えやすい雰囲気を作り出していて、うまいなァと感心する。
新潟県からの観光客が話すことには、十年ぐらい前から新潟県内にも天然温泉施設が増えたので、わざわざ信州の温泉へ旅行する必要がなくなったのだという。
「日本中、一キロメートルもボーリングすれば、至る所から温泉が湧き出す。だから、新潟県民も他県へ行くより、県内の近場で温泉旅行を済ませてしまうようになったんだ」
と、いうのである。
つまり、温泉地の希少価値が、昔ほど大きくはなくなったということなのだろう。
趣味も多様化してきているので、みんなが同じものを見て楽しむという時代ではない。
温泉とグルメ----それだけでは、観光客の興味を引くのはかなり難しい。しかも、今の人たちは、出来るだけお金を使わずに旅をしたいというのが本音であるから、インターネットで無料のサービスばかりを調べ出し、低料金旅に役立てるという観光客も少なくない。
何とも、世知辛い世の中になったものである。
ところで、磨きあげ過ぎた美人は、男性にモテないという話を読んだ。
昔はモテたのに、何で最近は男性に敬遠されるんだろう----と、思った女性は、案外、この状態なのかもしれないという。
頭のてっぺんから足のつま先まで、隙のないおしゃれでバッチリ決めているような女性は、男性から見て、
「高い化粧品使うんだろうな。結婚したら、エステやら何やらで金も手もかかりそうだな・・・」
と、想像させてしまうらしい。
また、人工的な美を好まない男性は多いという。
うぶ毛だらけだった学生時代の方が、男子受けは良かった----と、いう心当たりのある女性は、男子のそんな本音にマッチしていたからなのかもしれない。
宗教の本を買って欲しいという人がやって来た。
こちらが「いりません」と言っても、あれこれと説明をしてすぐには引き下がらない。
こういう人たちは、こちらの言うことに決して、「そうじゃありませんよ」ということは言わない。
あくまでもこちらの意見に同意しながら、「そうなんですよね。その通りです。だから、こういう本が必要なんです」と、持ちかける。
でも、その言い方が、なおさら胡散臭く思える。
「余計なことに使うお金がないので」と、言って、お引き取り願った。
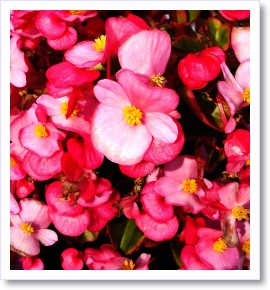
続きを読む





