親のエゴは子供の敵
2012年04月30日
親のエゴは子供の敵

この間、知り合いの女性と、いわゆる「ママ友バトル」の話題になった。
同じような年齢の子供を持つ親同士は、一見結束が固いようだが、その結束の仕方には従順型、しもべ型、友情型など色々なパターンがあるという。
そして、こうした団結は、えてして外敵である外集団を作ることでより強まるのが普通である。
これを内集団の団結と心理学では言うらしい。
しかし、こうした内集団VS外集団の対決で真に犠牲になるのは、常に子供たちである。
親は、我が子可愛さのために気の合う親同士で結束するのだが、子供の世界は親のそれとはまったく異なり、外集団の親を持つ子供たちも内集団の親を持つ子供たちと友だちであることには変わりないのだ。
そして、もちろん子供たちはその地域で大人になって行く。
学校を卒業していざ就職となった時、子供の頃の親同士の確執が原因で、いがみ合った相手の親が関わっている職業に就きたくても就けないなどということも十分にあり得るのである。
その時になって、「どうして、昔、〇〇くんのお母さんとケンカなんかしたんだよ」と、子供に責められてもあとの祭りなのだ。
親は、何があっても決して子供の将来の選択肢を減らしてはいけない。
そのためには、親同士はお互いに自身のエゴを捨てることが大事なのだと、知り合いの女性は話す。
バトルをしている本人たちはそれでもいいのかもしれないが、その犠牲になる子供はたまったものではない。
これは一例だが、かつて母親同士が争っていたことで、その一方の母親の夫が勤めている会社に相手側の子供が就職試験を受けに来たが、その夫が不快感を示して面接で落とされたというケースもあったそうだ。
子供は将来どんな道を歩むことになるか、それは誰にも判らない。
だから、親は自分の思いはさておいても、子供の未来を阻むことになるかもしれない可能性は、出来るだけ排除しておいてやるべきなのではなかろうか。

続きを読む
お節介な人は子供っぽい人
2012年04月29日
お節介な人は子供っぽい人

「あの人、あたしがいなけりゃ何も出来ないのよ」
「も~、何してんのよ。こうしなけりゃダメじゃない」
「いいから、わたしに貸してみなさいよ」
そんなことを頻繁に言う人が、あなたの身近にもいるのではないだろうか?
いわゆる、「お節介な人」である。
困っている人を見ると、どうしても手を貸さずにはいられないといった、世話役タイプといえばいいのだろうか・・・。
しかし、こういう人は、得てして疎んじられることがある。
「いつもいつも、手伝ってくれるのはありがたいんだけれど、たまにはこっちの意見も聞いて欲しいもんだ」
そんな相手の声が、そのお節介な人には必ずしも通じないのだ。
つまり、お節介な人は、自分の中のイライラをコントロール出来ずに、つい相手のやり方にケチを付けてしまうという癖があるわけで、根は子供っぽい人だということになるらしい。
同じ手を貸すにしても大人の対応はこれとは多少異なり、相手が何を欲しているのか、いつ欲しているのか等のデータを客観的に分析した上で、助け船を出すことが出来るのだという。
手当たり次第に手助けをしようとする人は、結果的に相手の気持ちを無視しているといっても過言ではない。
そして、自分には荷が重すぎる仕事が回ってきたり、相手がお礼を言い忘れたりすると、途端に不機嫌になるのである。
ボランティアを買って出る人たちの中にも、時々こうした自己満足的な目的のために活動するお節介な人がいるそうだ。
真に相手のことを思うのなら、時には何の手助けもしないという選択肢もあるということを忘れてはならないということである。

続きを読む
キャベツダイエット
2012年04月29日
キャベツダイエット

皆さん、キャベツは好きですか?
わたしは----というよりも、我が家はキャベツ大好き家族です。
特にわたし自身は、タンパク質を控えめに摂取しなければなりませんので、毎食キャベツは欠かせません。
 早い話が、キャベツでお腹をいっぱいにするとういうことですね。
早い話が、キャベツでお腹をいっぱいにするとういうことですね。でも、ただ普通にキャベツを千切りにして食べたのでは、その満腹感があまりないことに気がつきまして、ある秘策を思いつきました。
それは、キャベツ一玉を四つ切りにしたら、食べにくい芯を取り、その大きなひとかたまりのまま器に入れ、インスタントラーメンのスープの素やコンソメなどを少々振りかけたら、ラップをして電子レンジで軟らかくなるまでチンするのです。
スープの素やコンソメは、味が濃い方が好きな方は、大目に振りかけてもいいと思います。
要は、これだけです。
食べる時は、この大きなキャベツの葉っぱをそのまま噛むために、とにかく食べごたえがあるのです。
殊に、今の時季スーパーなどで売っている春キャベツは格別にこの食べごたえがあります。
すべて食べ切る頃には顎が疲れるほどで、途中でギブアップしたくなるほどですが、熱はしっかり通っているので消化は悪くないように思います。
栄養士さんにこれを話したところ、なかなかいいアイデアだとの評価を頂きました。
また、スープの素などを振りかけずに、ただのゆでキャベツ状態にチンしたところへ、マヨネーズ、砂糖少々、ポッカレモンなどを加えてまぜサラダ風にあえると、また違ったおいしさが味わえます。
この時、玉ねぎのスライスをキャベツと一緒にチンしてもおいしいです。
正にキャベツは万能選手です。
とはいえ、キャベツダイエットとはいっても、別にこれだけで一日過ごそうというわけではありませんので、ちゃんと主食も食べて下さいね。 続きを読む
何故、人は傷付くのか?
2012年04月28日
何故、人は傷付くのか?

人の心というものは、ほんのささいな一言で傷付くものである。
ある裕福な家の専業主婦が、パートをしている隣の家の主婦にこんなことを言ったとする。
「あなた、お勤めに出ているんですってね」
裕福な家の専業主婦は、特別な意図もなく隣の家の主婦の事実を言ったに過ぎない。
しかし、隣の家の主婦は、この一言にひどく傷付いた。
「うちが貧乏だからパート勤めに出ているんでしょうと、こちらをバカにしているんだ」
つまり、これは相手のせいで自分が不快な気分になったのではなく、自分自身が不快な気分を作り上げたことに他ならないのだという。
このブログでも以前書いたのだが、自分が入院したのに見舞いにも来なかった人に対して、「どうして見舞いに来なかった」と、問い詰めても、相手は「そんなささいなことで・・・」と、呆れ返ったという話も、これと同じことが考えられる。
要は、見舞いに行かなかった人にとってはごく小さな問題でも、入院した本人にとっては大問題という感覚の違いなのである。
でも、ここで一度立ち止まって考えてみると、相手は入院した人の病気をささいな問題と思ったから見舞いに来なかったわけで、これが重大な病気だと思っていれば必ず見舞いに来たはずなのである。
要は、裏を返せば、「自分の病気はそれほど大したものではない」と、いう証拠だということになる。
上記の例にしても、裕福な家の主婦は何でもないささいな日常会話だと思っていたからこそ、そんな話をしたのであって、もしも、本当に隣家の主婦を哀れんでいるのなら気の毒に思って声すらかけないはずなのである。
よほど、隣家の主婦との間に険悪な関係でもあるのならば、嫌みということも考えられるが、そうでないのなら隣家の主婦があえて気にすることはないのではないだろうか。
ささいなことだからこそ相手は口に出したのであり、特段傷付くほどの意味もないというのが心理学者の分析でもあるようだ。
もう少し言えば、自己評価が高く健全な自尊心を持っている人は、そんなことでは簡単に傷付いたりはしないのだそうである。
ところが、その反対に神経症的な自尊心にとらわれている自己評価の低い人ほど、相手のどうでもいい一言で容易く傷付いてしまうのだという。
つまり、もしもこの隣家の主婦が、「パートって楽しい。職場の友だちも出来て、今、とても充実しているわ」と、思っていたのなら、むしろ専業主婦をしている裕福な家庭の主婦を逆に、「働く喜びも知らないなんて、可哀そうな人だわね」と、哀れむことさえ出来るのである。
続きを読む
無視されていると悩むのは?
2012年04月28日
無視されていると悩むのは?

イジメの悩み相談で良くあるパターンに「無視されている」というものがある。
何故、人は「無視されているのはつらい」と、感じてしまうのか?
それは、そう思う人の中に、周囲の人たちに対する過度の「甘え」があるからだといわれる。
「甘え」とはすなわち、「依存」である。
つまり、自分に何かをして欲しいとか、相手は自分の思い通りに行動したり思考してくれないとつまらないという、いわば自分勝手な期待のことでもあるのだ。
この「甘え」があるからこそ、自分の思い通りにならない周囲に対して、「彼らはわたしを無視している」といって、悩むわけである。
では、もともと周囲に何の期待も希望も懐いていない場合は、どうだろうか?
たとえば、いつも道ですれ違うだけの見知らぬ赤の他人に対して、人は「あの人、わたしを無視している」とは思わないはずである。
いや、むしろ、面倒な挨拶を交わす必要もないので、無視してくれてありがたいとさえ思うのではないだろうか。
もしも、あなたの中に、「自分は皆から仲間外れにされている」などの「無視系」の悩みがある時は、あなた自身が周囲の人間たちに、「自分を認めて欲しい」というような過度の期待をかけないことで、その悩みは大半が解決するものなのだ。
「どうせ、一生付き合う相手じゃないし・・・」
そう思うだけでも、かなりの範囲で気持ちの平安は保てるものなのである。
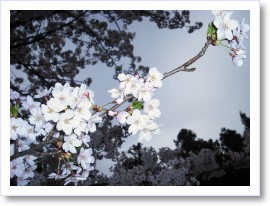
続きを読む
赤裸々女とは・・・?
2012年04月27日
赤裸々女とは・・・?

聞くところによると、赤裸々女とは、自分自身のことを何もかも正直にぶちまけて悦に入っている女性を指す言葉だという。
人が眉をひそめるような、良く言えば波瀾万丈な人生を、むしろ勲章のように考えているのかもしれない。
いや、そういう羞恥や卑下にあたるようなことを臆面もなく言ったり書いたりすることで、他人を驚かせたり引かせたりして喜んでいるのだから、ある意味劇場型性格とも呼べなくもない。
そういう癖のある女性は、自己陶酔型に多いそうだ。
そして、彼女たちには悩みや不安と呼べる感性が欠落しているのも特徴の一つである。
たとえば、自分の容姿容貌に、それが良いか悪いかは別問題でも、何故か人一倍の自信があったりして、どうしても誰かに見て欲しくてたまらないというような突出的性格も持ち合わせているものらしい。
だから、そういう女性は、ほんの一時は、そういう女性になりたくても理性や世間体が邪魔をしてどうしてもなれない女性たちの憧れの的となるが、結局最後は「変わり者」扱いされて歴史の表舞台を降りる運命を避けられないのである。
芸術家のような奇行さえもが利益を呼ぶ職業にでも就いているのならば、それもありなのだろう。
しかし、そんな才能を有する人間はそう多くはないはずだ。
赤裸々女----一見、コケティッシュで小悪魔的魅力をまとっているようにも思えるが、生まれて来る子供の将来なども考えるならば、おそらく結婚相手としては最も適さない人種なのかもしれない。
続きを読む
小学校の思い出は・・・?
2012年04月27日
小学校の思い出は・・・?

皆さんは、小学生当時の思い出にどんなものがありますか?
わたしがいたクラスは、担任の先生が六年間一度も替わらなかったので、それで良いこともあれば、もちろん弊害もありましたが、一口に言ってなかなかユニークなクラスだったような気がします。
もちろん、どんな小学校にも付き物のイジメや仲間外れ現象なども人並みにありましたし、身体が大きく学力のある子供が、音楽会や運動会などの学校行事などでは常に主役の座につくというような個人偏重もありました。
でも、今になって考えてみれば、短い時間の中でさまざまなカリキュラムを消化しなければならない教師の立場では、歌詞や台詞覚えの悪い子供に大役を任せて教育する余裕もなかったのだと思います。
そうなると、やはり、そこは出来る子に頼むということになってしまうのでしょうね。
とはいえ、出来ない子もそれなりに色々と知恵を巡らせます。

こんなことがありました。学校が子供に配布した授業参観のお知らせの手紙が入った封筒を、そのままポストに入れたらどういうことになるのか、確かめずにはいられない男子たち数人が、下校途中にその封筒を郵便局のポストへ投函してしまったのです。
封筒には学校名と住所が書かれていますから、翌日、封筒はすべて学校へ逆戻り。郵送料も学校側が支払わなくてはならなくなったのでした。(そのあとで、各児童の親が郵便料金を学校側へ支払ったのか否かは、わたしは知りませんが・・・)
担任の先生は男子たちを呼んでこう言ったそうです。
「どうだ。これで、郵便がどうやって配達されるのか、仕組みが判っただろう」
まあ、あの時代はそんなものです。今なら、PTAの大問題になるのでしょうね。
また、こんなこともありました。
一人の女子児童が一時間目の授業を終えたあと学校からいなくなったのです。そこで、授業そっちのけでクラス全員が学校の近辺を捜索し、山の中のお堂の石段で泣いている女子児童を発見しました。
いなくなった理由は良く判りませんでしたが、何かイジメらしきものが関係していたのかもしれません。
まるで、ドラマのような話です。大らかな時代でした。
しかし、このところ大阪維新の会が中心になって制定した大阪府の教育基本条例では、知事が教育委員を罷免したり、不適格教員をやめさせることが出来る規定が盛り込まれたそうで、また、橋下徹大阪市長は、学力が基準に達しない小中学生を留年させる考えも打ち出しています。
確かに、学力向上のための教育は不可欠かもしれませんが、小学校という人生の土台となる教育課程には、勉強よりももっと大事なものがあるような気がするのです。
大人には考えられないようなバカげたことでも、自ら体験してみる自由があるのは子供の頃だけです。
イチゴミルクを作ろうという家庭科の調理実習で、イチゴではなくミカンとミルクを合わせればどんなものが出来るか、先に教師が、「そういうことは授業の趣旨に反しますからやってはいけません」と、禁じてしまうことは簡単ですが、出来上がったものがカリキュラムの趣旨とはまったく違う物でも、子供はそれで一つ学ぶことが出来るように思うのです。
子供たちの心の成長の芽を、大人の都合で摘んでしまうことのないような小学校教育を望みたいものです。
続きを読む
またまた、通院日でした。
2012年04月26日
またまた、通院日でした。

今月は、これで二度目の通院日だ。
今日は、泌尿器科。
待合所では、おばあさんと先生が押し問答。
先生 「身長は何センチですか?」
おばあさん 「150センチだよ」
先生 「そんなに大きくないでしょ」
おばあさん 「昔はそうだった」
先生 「今の身長だよ。145センチぐらいでいい?」
おばあさん 「そんなに小さくないよ」
先生 「そのくらいだよ。それでいいね」
おばあさん 「・・・・・(不満そう)」
でも、わたしが見たところ、おばあさんはもっと小さいかもしれないな・・・。
年をとっても身長には見栄があるようで、もっとも高かった20歳ぐらいの時のことが忘れられないんだろうと思う。
でもね、高齢になると相当に縮むよ。
わたしなんか、この病気になって10センチ以上低くなった。
ま、今はそれでも5センチぐらいは戻ったかな?
一気に10センチも低くなると毎日のように世界が変わって行く。
元気だった頃は家の洗面所の鏡に胸の辺りまで映っていたはずなのに、退院後見たら首から上がやっと映っているだけだった時は、さすがにビックリだったけれどね。
それまでは身体中が痛くて鏡など見る気にもならなかったから、自分の身長がどんどん低くなっていることに気付かなかったんだけれど・・・。
だから、実際、背の高い人が羨ましい。
あのおばあさんの気持ち、ちょっと判る気がする・・・な。(~_~;)

続きを読む
やっと、桜が咲いた・・・
2012年04月25日
やっと、桜が咲いた・・・

やっと桜が咲きましたね。
今日は、本当に気持ちの良い一日でした。
西日本では、真夏のような暑さだそうですが、北信濃は快適です。
冬が長かった分だけ、春も長いことを期待したいですね。
ところで、CSI:マイアミを観ていて気付いたのですが、女性鑑識捜査官のカリーのヘアスタイルが、毎回変化しているんですよね。
これだけに注目していても意外に面白いんです。
わたしは、やはり真ん中のストレートシャギー・ヘアが真面目でちょっぴり勝気なカリーらしくていいと思うんですが・・・。
あなたは、どう思いますか?(^^♪
続きを読む
京都で事故相次ぐ
2012年04月23日
京都で事故相次ぐ

23日朝、京都府亀岡市で、登校中の小学生の列に軽自動車が突っ込んで10人がけがをした事故で、新たに妊娠中の26歳の女性も意識不明の重体になり、重体は合わせて4人となりました。
女性のお腹の赤ちゃんは助かりませんでした。
警察は運転していた18歳の少年を逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。
23日午前8時前、亀岡市篠町の府道で、安詳小学校の児童らが集団登校する列に軽自動車が突っ込みました。
この事故で、小学校1年生から5年生の女の子8人と男の子1人、それに保護者の26歳の女性1人の合わせて10人がけがをしました。
警察や病院によりますと、このうち3年生と2年生の女の子、1年生の男の子、それに26歳の女性の合わせて4人が意識不明の重体です。
女性は妊娠7か月くらいでしたが、お腹の赤ちゃんは助かりませんでした。
また、このほか3人が重傷だということです。
この事故で、警察は軽自動車を運転していた亀岡市の18歳の少年を自動車運転過失傷害の疑いで逮捕しました。
少年は無免許運転で、調べに対して「子どもたちに当たったのは間違いないです」と話しているということです。(NHKニュースより)
京都市東山区(祇園)で4月12日に起きた自動車の暴走死亡事故に続いて、またもや同府亀岡市で小学校への登校途中の児童と付き添いの保護者をはねる大事故が発生した。
午後のニュースによると、重体だった4人のうち同小2年、小谷真緒さん(7)と、負傷者の保護者で妊娠中だった松村幸姫(ゆきひ)さん(26)の死亡が確認されたそうである。
病院へ駆け付けた松村さんの妹さん(24)によれば、「先日、祇園で起きた交通死亡事故について姉と話をしたばかり」だったという。
今日の事故の報道を取り上げたワイドショーのコメンテーターの一人は、「事故現場に散乱している黄色い新入生帽子を見ると、希望に胸を膨らませて元気に登校していた子供たちの姿が目に浮かぶ。可哀そうというよりも、怒りが先に立つ」と、声を震わせていた。
テレビで亀岡市の事故現場の映像を観る限り、特別見通しが悪い道ではないし、道幅もさして狭いとは思えない。
事故を起こした車の運転手は、18歳の少年で無免許だったそうだが、同乗していた2人の友人とは夜通し遊び歩いてのちの事故だったらしい。
それにしても、どうしてこうも立て続けに大勢の人間を巻き込む交通死亡事故が起きるのであろうか?
今回の事故などは、保護者が児童を引率していることもあり、普通に考えれば起きるはずもない状況だといえる。
加害者少年が運転する車がちゃんと左側通行をしていれば、同じ方向へ進む児童の列に突っ込むことなどないのである。
近所の住民の話では、かつては道路脇にあった側溝にふたをして、道路幅を広げてからスピードを出して通り過ぎる車も増えたという。それまでは、狭い道だったので、車同士お互いに譲り合いながら走ることもあり、事故は起きていなかったのだそうだ。
しかし、この事故に関しては、道路幅を広げたことはあまり関係がないのではないかとも思える。
事故を起こした車は、児童の列の後方からノーブレーキで突っ込んで行っているわけであり、無免許とはいえそれまでは事故を起こさずに走行してきているのだ。
しかも、どうせ突っ込むならば児童の列ではなく、そこまでの間にいくらでも場所はあったはずである。それを、あえて児童の列をめがけるように飛び込んでいるということであるから、そこに運転手側の何らかの意図が感じられなくもない。
単なるハンドルの操作ミスとか居眠り運転などでは説明が付かない事態が想定されても不思議ではない。
「どうせ、突っ込むならば、そばの塀にでも激突すればよかったのに!」
ニュースを聞いて、あまりの悲惨さに怒りが治まらない主婦の一人は吐き捨てるように言った。
京都府警による徹底的な事故原因の究明が求められる。
ほっ・・・が危ない。
2012年04月22日
ほっ・・・が危ない。

雨の日にバスや電車の車内に傘を忘れたこと、ありませんか?
網棚に置いたバッグを忘れて降りてしまったこととか・・・。
わたしは、電車の中に大きなうさぎの縫いぐるみを忘れたことがあります。(>_<)
どうして、あんな大きな縫いぐるみを忘れるのか、自分でもかなり不思議だったんですが、バスや電車の車内には、人間が陥りやすい「ほっ----とスポット」があるようです。
人がいつ物を忘れるのかというと、それは、緊張状態が解けた瞬間だといわれます。
たとえば、朝、奥さんから「この手紙は大事な手紙だから、絶対に忘れないでポストへ投函しておいてね」などと念を押されて出勤したご主人が、すっかりそのことを忘れて夕方帰宅してしまった----という時など、正に、この「ほっ----とスポット」が働いてしまったからに他ならないのです。
ご主人は、奥さんから大事な手紙の投函を頼まれたことで一種の緊張状態にあったわけですが、途中でその手紙がちゃんとカバンの中へ入っているかを確かめた瞬間、彼の心の中にあった緊張が解けてしまったわけです。
「ああ、ちゃんと手紙はあるな」
これでほっとしたために、今度はそれをポストへ入れなければならないという気持ちが吹き飛んでしまったというわけなのです。
これと同じ論理で、雨の日のバスや電車内の傘の忘れ物が発生するのだそうです。
雨を避けてようやくバスや電車へ乗りこめたことで、そこに「ほっ---とスポット」が生まれるのです。しかも、下車する際になり既に雨が小降りだったりすれば、もう忘れるための条件はバッチリです。
わたしも、ひと抱えもある大きな縫いぐるみを電車の中まで運びこめたという安心感で、一気に緊張が解けて、ケロリとそれを車内へ置き忘れてしまったわけですね。
そんなわけで、皆さんも「ほっ---とスポット」にはくれぐれも注意して下さいね。


続きを読む
世界フィギュアスケート国別対抗戦
2012年04月21日
世界フィギュアスケート国別対抗戦

世界フィギュアスケート国別対抗戦2012(World Team Trophy Figure Skating Championship 2012)が20日、東京で2日目が行われ、男子シングル・フリースケーティング(FS)で高橋大輔(Daisuke Takahashi)が、カナダのパトリック・チャン(Patrick Chan)を2シーズンぶりに破った。
2010年の世界フィギュアスケート選手権(ISU World Figure Skating Championships 2010)王者で、初日に男子ショートプログラム(SP)の歴代最高得点94.00点を記録し、チャンに4.19点差をつけていた高橋は、エディ・ルイス(Eddie Louis)の「ブルース・フォー・クローク(Blues for Klook)」に合わせ、ミスの無い演技を披露した。
バンクーバー冬季五輪銅メダリストの高橋は、冒頭の4回転トウループに成功し、続けてトリプルアクセル(3回転半)と3回転サルコウも決めると、ステップとスピンで最高難度のレベル4を獲得し、自己ベストとなる合計276.72点を記録した。
演技終了後に高橋は、「大きなミスなく最後まで滑れて気持ち良かった。到底届かない思っていたチャンとの差を縮めたことは自信になる。これに満足せず、もっと練習に励みたい」と語った。【4月21日 AFP】
高橋大輔選手、素晴らしい活躍ですよね。
いや、高橋選手だけではありません。他の日本選手もそれぞれにベスト演技をのびのびと行っています。
ところが、男子シングルSPで高橋選手に次いで2位につけていたカナダのパトリック・チャン選手は、フリーでは2回目の4回転ジャンプに失敗し、合計260.46点で2位に終わりました。
まだ21歳のチャン選手は、
「勝つときもあれば、負けるときもある。最近2年間は素晴らしいシーズンを過ごせた。来シーズンもまた良いシーズンを送れる自信はある」
と語っていたそうですが、2014年ソチ冬季五輪で五輪初出場を果たす予定の彼は、お祭りのような会場の雰囲気に集中力を欠いていたことを明らかにしたそうです。
今大会は、2011~12シーズンの成績上位6か国の中で選抜された男女シングル各2名、ペア1組、アイスダンス1組による団体戦形式で行われたため、選手が演技後に得点発表を待つキス・アンド・クライの後方には各国の応援席が設置されています。
チャン選手は、
「これまでとは全然違う環境や形式で行われた大会だった。他国の選手全員から視線を感じる状況では普通の気持ちで滑れないし、威圧感を感じた。その心境が結果に出てしまった」
と話したといいます。
ところが、日本選手たちは、このような団体戦で選手同士が大声で励ましたり褒め合ったりしながら、一丸となって戦う試合方式に自然と馴染んでいるように見受けられます。
昨日行われたペアSPでは、64.92点を記録した日本の高橋成美/マービン・トラン組が首位に立ちましたが、小さな体に底知れない爆発力を秘めた慶応大学生の高橋成美選手の応援団長ぶりも板について、日本勢はますます追い風に乗った試合展開を見せています。
個人個人の真剣勝負は勝負として、最大限のチーム力を発揮するという戦い方は、日本で生まれた駅伝競技から踏襲されている精神なのかもしれませんが、それがフィギュアスケートにも生かされるというのは面白い発見ですね。
対戦各国の選手たちも、チームの総合力で競い合うという試合方法を楽しんでいるように思えます。
体操競技にも団体総合というものがあるのですから、こうした戦い方が公式のフィギュアスケート競技でも採用されるとなれば、もっと大勢の選手たちがオリンピックなどへ出場が可能になるのではないでしょうか?
団体総合専門の選手育成も各国で盛んになることでしょう。
そんなことを考えながら、今回の世界フィギュアスケート国別対抗戦を観ています。
続きを読む
男と女は価値観が違う
2012年04月20日
 男と女は価値観が違う
男と女は価値観が違う
「結婚するなら、価値観が同じ人が良いわ・・・」
女性が結婚相手に望む条件の一つが、これだそうですね。
同じ風景を見て、それを同じように「美しい」と感じられる人----それが価値観が同じということなのでしょう。
しかし、こと相手への期待感ということになると、男性と女性とではその期待の方向性がかなり違うといわれます。
男性のあなたに質問ですが、あなたは恋人が出来た時、彼女の何が一番気がかりでしたか?
逆に、女性のあなたは、彼氏の何が一番気がかりでしたか?
男性は、おそらく、「彼女が過去にどんな男性と付き合ったことがあったのか?もしくは、なかったのか?」が気になったはずなのです。
しかし、女性は、「彼がわたしと付き合う前に他の女性を好きだったことなんて、あって当たり前。それよりも、わたしの関心事は、今後彼がどうやってわたしのことを幸せにしてくれるか?----ということ」の方が、気になってならないはずなのです。
たぶん・・・。
でも、本来は、男性の方が未来のことが気になるもので、女性は、今の現実の方を気にするものなのでは・・・?
だから、恋人同士の会話でも男性はやたらに将来の出世などを話題に持ち出すのに比べて、女性は、そんな向こうのことよりも目の前の結婚式場の予約の方が大事でしょう----なんて、やきもきするというパターンが一般的なんじゃないのかな?
つまり、付き合い始めた頃と、既に結婚を前提とする段階の互いの立場とでは、価値観も逆転するというわけなのです。
となれば、もうお判りの通り、付き合い始めたばかりの男女間の会話は、もしも女性に合わせるとしたならば、出来るだけ楽しい将来を夢見るような内容を語り合うべきで、間違っても過去をほじくり返すような方向へは持って行かないこと。
思い切り夢のある会話をたくさんする方が、二人の恋愛感情を確実なものにしやすいのだそうです。
ただ、女性の中には、たまに自分の過去を男性に話したくてたまらないというような人もいますから、そういう場合は黙って聞いてあげることも必要かも・・・。
ただし、そういう女性は大概において自分の過去を必要以上に美化する傾向があるので、いざ結婚してから話が違うと驚かないようにしましょう。(~_~;)
 続きを読む
続きを読む良き指導者とは・・・
2012年04月20日
良き指導者とは・・・

「名選手、名監督にあらず」
スポーツ界では、こんな言葉を良く聞きますよね。
野球やサッカー、水泳などなど・・・各種スポーツで名選手と呼ばれた人が監督やコーチに就任しても、指導者としては必ずしも優秀とは言い難い----そんなジンクスから生まれたフレーズですよね。
どうして、そういうことが実際に起きやすいのかといえば、理由の一つに名選手と言われるような人は、もともと親から受け継いだ天性の体質や素質があるために、ある一定のレベルまでは特別な訓練や頑張りなしにたどり着けてしまうこともあり、努力して上達する一般の選手の気持ちや必要な練習過程について勉強不足であるとの難点があるからだそうです。
また、それに加えて、名選手と呼ばれる人の中には、人の何十倍もの過剰な訓練を自らに課すという練習オタクのような性格の人間も少なくないため、自分に出来ることが教え子たちに出来ないはずはない----との自分本位の指導の仕方を強要する癖があるともいわれています。
そして、最も問題なのが、そうした過去に名選手としての名声を得たことのある指導者は、教え子を指導する傍らで、自分自身もさらに競技者として成長しようとの貪欲さを捨てきれない----ということだといいます。
「教え子とともに自分も成長することの何が悪いのか?」
と、いう反論もあるでしょうが、指導者自身が成長するのは、あくまでも精神的な面に留めるべきであり、競技者として自分の成績を上げようという意欲が捨てきれない人に、心から教え子たちのことを考えることは出来ないというのがその理由なのです。
そういう自らの競技者としての成長を諦めきれない指導者の中には、時に、日々腕をあげる教え子に嫉妬する人も少なくありません。
ですから、自分は指導者になろうと決めた時から、本来監督やコーチは競技者としての将来をすべて諦める必要があるのだそうです。
そして、教え子が自分の指導者としての能力を凌駕する域に達した場合は、自分以上に力量のある指導者に教え子を託す度量を兼ね備えるべきなのです。
もちろん、名選手の中には名指導者になる人もいます。
しかし、そういう人に共通していることは、やはり自分が選手だった頃の過去の栄光をいつまでも引きずらずに、今目の前にいる選手の力量を正確に把握して、それに合った指導方針を構築出来るという心の柔軟性を有しているということのようです。
もしもあなたが何らかの指導者を頼まれ、でも未だに自分自身の成長に未練があるのだとしたら、指導者を引き受けるのは一考した方がよいかもしれませんね。
続きを読む
女性が占い好きなわけ
2012年04月19日
女性が占い好きなわけ

この間、ニュース番組の中の特集で、「何故、女性は占いにはまりやすいのか?」と、いう話題を取り上げていました。
番組には占い師の女性も何人か登場していて、一人の女性占い師が説明することには、
「占いは、ある意味女性にとって心のサプリメントのようなものなんですよ」
と、語っていたのが印象的でした。
確かに、そうなのかもしれませんね。
占いは、それを信じる人にとっても、決してはっきりと効き目が判る医薬品のようなものではなく、飲んでいると安心出来るとか、ちょっと調子が良いような気がする----と、いった具合の、あくまで個人の微妙な感覚で評価出来る程度の心の栄養剤なのかもしれません。
「〇月が誕生月のあなたの今日の運勢は、何事にも前向きに取り組むことで交友関係も好転し、仕事も順調に進むでしょう」
たとえば朝のテレビ番組の占いコーナーでこんな結果が出たとしたら、何とはなしに、
「よし、今日も一日前向きに頑張ろう」
という気合いも入りますよね。
それにしても、どうして男性に比べて女性の方が占いを信じやすいのでしょうか?
いや、頭から信じないにしても、占いが好きな人が女性には多いように思います。
それは心理学的に考えても、男性よりも女性の方が物事を受け身に捉える人が多いことと関係があるようです。
また、女性はたとえ男性と職場が同じでも、事務職や専門職などで働く割合が高いために、日々限られた人同士の交友関係しか体験できず、世間が狭いということにも理由があるようで、さらに、家庭の主婦ともなると、家族以外の他人との接触はますます少なくなるはずです。
となると、単調な毎日の退屈さを紛らわせるもっとも手っ取り早い方法が、いわゆる「空想」とか「想像」の類です。
人は、「もしも----が起きたら・・・」と、空想や想像といった仮想世界を思い描くことで明日への活力を養おうとする生き物ですから、結局は「希望」とか「夢」というものも、この未来の仮想世界に向かって歩もうという意志の表われと考えるべきなのです。
つまり、占いは、そうした仮想世界を思い描くための入口を示してくれる道しるべの役目を果たすものだといえるわけで、毎日の仕事で目の前の現実と向き合う必要に迫られる男性よりも、女性の方がより空想を巡らせる時間が多いということに、主な理由があるのかもしれません。
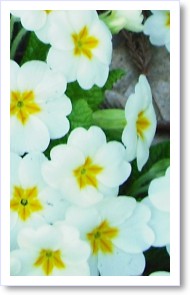
続きを読む
ママ友はママライバル
2012年04月18日
 ママ友はママライバル
ママ友はママライバル
ママ友はママライバル----。
これって、子供を持っている母親にとって永遠の命題のようですね。
殊に同じ学年同士の子供を持つ母親にしてみれば、自分の子供と相手の子供をどうしても比べずにはいられないようです。
それでも、同学年同士とはいっても、まだ男女の違いがあれば少しはその対抗意識も薄れるのかもしれませんが、同学年でしかも同性同士となれば、お互い黙っていても自然とそうした気持ちが母親同士の間で芽生えて来てしまうもののようです。
最近、始まったお昼の連続ドラマでも、そんなママ友同士のライバル心のあり方を問題視したPTA物がありますよね。
まあ、PTAなどでは子供の成績の良し悪しがそのまま親の評価につながるような奇妙な現象を生む場合も無きにしも非ずだそうですから、必然的に親同士間に派閥が出来てしまうのかもしれません。
でも、思うんですけれど、特に小学生の間の成績なんて人間の出来不出来にさして影響を与えるものではないんじゃないかと・・・。
わたしの経験からいえば、地方のド田舎の小学校出でも、大都会の有名私立小学校をお受験合格した人間でも、結局入学した大学は同じ----などということって良くある現実なんですよね。
子供の成長にはそれぞれ個性があります。
早くから知能が発達して勉強も運動もそれなりに器用にこなす子供もいれば、それこそ高校生になってから一気に目が覚めたように成績が伸び始める子供だっています。
中学卒業までは勉強もスポーツも負け知らずだった子が、高校生になった途端、自分よりも成績が良いクラスメートに囲まれてしまい、これまで負けるということを知らなかったばかりにその打たれ弱さ故に挫折感を払しょくしきれず、ついには登校拒否になってしまうなどということだってあるのです。
親である大人は、子供が小学生ぐらいの時は、自分の子供の成績や順位を伸ばすことを考えるよりも、その子にどんな才能や興味があるのかを見極めるといった程度の関わり方で良いのではないかと思うのです。
わたしは、甥っ子の一人が小学生の時、身体が小さくスポーツの成績があがらないことを悩んでいたので、こんなアドバイスをしました。
「サッカーの中村俊輔選手だって、高校生になるまでは背が低く身体が小さいためにサッカーのテクニックだけでは通用せず、チームメートにドリブルで追い抜かれたり当たり負けしていて悩んでいたけれど、身体が大きくなった頃から更に才能が開花した。子供はいつか必ず大人になるから、今は、じっくりと基本に取り組む時期で、強くなるのはもっと後でいいんだよ」
その甥っ子も高校生の今では身長175センチになりました。
たぶん、まだ伸びるでしょう。
体力もつき、スポーツの成績も十分人並です。
親御さんたちに言いたいことは、「とにかく焦らない」ということです。そして、自分の子供を他人の子供と無暗に比較しないということ。
もしも、どうしても比較することがやめられず、悩んでしまう時は、こう思って下さい。
「いいの、うちの子供は大器晩成型なんだから。勝負は、二十歳すぎてからよ!」

と----。

続きを読む
押し付け教育を続けると・・・
2012年04月17日
押し付け教育を続けると・・・

あれをしなさい。
これをしなさい。
何で、やらないの?
そんなんだからダメなのよ!
どうして出来ないの?
早くしなさい!
そんな押し付け教育ばかりをされていた子供は、大人になるにつれていわゆる「クローズド人間」になるといわれています。
「クローズド人間」とは、外界との接触を極端に拒み、表情は常に硬く、他人を受け入れにくい性格の人間ということだそうです。
押し付け教育は、必然的に子供へ与える情報量も膨大になりがちです。
親自身も子供がちゃんと出来るまで根気良く付き合うことが苦手な人ほど、こうした押し付けに走りがちなものですから、そうした多くの要求を早く片づけなければならないと考える子供には、一つの問題に対して長時間かけて考えるという癖がつきにくいのです。
つまり、相手の話を親身になって聞き、受け入れるという情報を収集するための器が浅いということになるのです。
そこで、子供は相手からの情報を出来るだけ短時間で処理しようとします。
そのためにはいちいち敬語などを使ってしゃべることを嫌いますし、相手の目を見ながら何かを説明するなどという手間をかけることも面倒に思い、会話も一方通行になりがちです。
たとえば、誰かに道を訊ねられても、その場に立ち止まることなく、手だけで、「あっち----」と、伝えるだけ、などという話し方しか出来ない大人になる可能性もあるそうです。
自分の関心ごとは口角泡を飛ばして語り尽くすのに、人の話はいつも上の空----と、いう人も、こうした押し付け教育を受けて育った「クローズド人間」に多いタイプだとか。
自分に必要のない情報は徹底的に排除しますから、知り合いと道で会っても挨拶しないことなどしょっちゅうですし、責任は尽く回避したがる性格ですから、何か気に障ることがあれば、すべて相手のせいだと思い込みます。
他人とトラブルが起きても、自分からは相手と接触することは極力避け、仲介者を立てて交渉にあたるのも、こうしたクローズド人間の特徴だそうです。
子供の頃から何か困りごとがあれば、すべて親が何とかしてくれたという経験があるため、自分自身の力で物事を解決しようという能力が欠けているということなのでしょうね。
子供の頭で考えられる処理能力には限界があります。
この処理能力の許容範囲を超えるような大量の情報を押し付ける教育は、逆に子供の判断力や思考力を鈍化させると考えた方が良いようですね。

続きを読む
花壇が消える・・・
2012年04月16日
花壇が消える・・・

二、三年前から感じていたことなのですが、街の中の花壇が少なくなったなァ・・・と。
十年ほど前までは、各家の前には必ずというほどプランターが並び、季節の花々がところせましと咲き誇っていたものです。
しかし、花を育てる人たちが次第に高齢になり、花の苗を植える体力がなくなって来ているせいか、これまで丹精込めて自慢の花壇の花を育ててきた人たちが、次々と花作りをやめてしまっているようなのです。
一頃、ガーデニングを楽しむという趣味が主婦の間で流行したこともありましたが、それも現在は、リーマンショック以降の不況でかなり下火になってしまいました。
花を育てるという趣味には、必然的にお金がかかります。
園芸雑誌、肥料、苗などを購入するにしてもお金も手間もかかりますし、根気も必要です。
そして、ガーデニングを趣味にしている人たちの情報交換のための集まりに費やす食事代などもバカにならないのではないでしょうか。
昨年の東日本大震災がそんな不況に追い打ちをかけたがために、趣味に回せる家計の余裕もなくなり、花壇の手入れが出来なくなったという人も多いのだと思います。
街中を散歩して歩くと如実に判るのですが、一昨年まではスイセンやパンジーを美しく咲かせていた家の花壇が、今年は跡形もなく壊されている----などということも少なくないのです。
既に庶民の暮らしが、花をめでるという余裕さえ失い始めているという証拠ではないでしょうか。
しかも、この長期に渡った厳冬が、人々の気持ちにある種のうつ状態をもたらしているようにさえ思われます。
街から花壇が消えるということは、それだけ街が高齢化しているということに加えて、社会経済や人々の精神をも疲弊させつつあるということの証拠なのではないかと・・・そんな一抹の危惧感に襲われるこの頃です。

続きを読む
気持ちは脚に表われる
2012年04月15日
気持ちは脚に表われる

では、質問です。
あなたは、会社の上司の指示で得意先へ新製品の売り込みに向かいました。
商談の席へ現われた得意先の社長とは初対面でしたが、彼はしっかりと脚を組んであなたの説明に何度も頷きながら耳を傾けてくれていました。
さて、この後、商談は成立したのでしょうか?それとも、失敗だったのでしょうか?
答えとしては、たぶん商談成立は厳しかったと見るのが妥当なようです。
あまり親しくない相手の気持ちを読む時、最も手っ取り早いのが相手の脚がどのような置かれ方をしているかに注目することだといわれます。
まずは、つま先の向いている方向に注目して下さい。
あなたに関心や興味がある場合は、相手のつま先はほぼあなたの方を向いているそうです。
たとえ顔があなたの方へ向いていても、つま先があさっての方向を向いているような場合は、あまり相手に期待しない方が良いということだとか・・・。
これに似たようなことで、脚の置き方でも同じようなことが判るのだそうです。
もしも、相手が脚を軽く開いてリラックスして腰かけていたり、または軽く組んでいたような場合は、相手にあなたを受け入れて話を聞こうという意欲があると考えてよいそうです。
しかし、同じ脚の組み方でもしっかりと組んでいたり、もしくは両脚をかたく閉じて腰かけていたような場合は、相手があなたに対して警戒心を懐いているという証でもあるそうで、自己防衛のポーズともいわれるのだとか・・・。
こういう脚の組み方をしている人は、甘えん坊の気があったり、簡単には本心を見せないタイプだと思えるので、案外交渉事は難航する可能性が大だそうです。
ですから、商談などに入る時は、まず相手の気持ちを解きほぐすような、当たりさわりのない世間話などから始めた方が良いかもしれません。
では、良く男の人に見受けられがちな脚の置き方で、大きく膝を開いて座っていたり、両脚を投げ出すように椅子に腰かけているような人は、どのような性格だといえるのでしょうか?
こういう人の性格は一口で言って乱暴で雑、自己中心的といってよいようです。
つまり、横柄な態度で相手を見下すか威嚇しているとも考えられるので、交渉相手としては難しいタイプだといえそうです。
また、中にはたいそう格好付けた脚の組み方で腰かけるような人もいますが、こういう人は、自分を印象付けてあなたに認められたいと考えている場合があるようです。
相手の自尊心をうまくくすぐることで、商談もうまく運ぶかもしれません。
初めての人と会う際などは、ちょっと相手の脚の置き方にも気を付けてみると、意外に面白い発見が出来るかもしれませんね。

続きを読む
心理テストをやってみた。
2012年04月14日
心理テストをやってみた。

☆ 森のポストにあなた宛ての手紙が入っているとします。
手紙は何通ありますか?
「1通」----自分の悩みの数だそうです。
☆ その手紙の一通は、友達、親、恋人、職場や仕事関係者の誰からですか?
「友達」----友達が自分に隠し事をしているのではないかなど、不信感を持っているそうです。
☆ その手紙は、あなたにとってあまり嬉しいものではありませんでした。あなたは、その手紙をどうしますか?
破り捨てる、何度も読み返す、返事を書く、ポストへ戻す----のうちのどれですか?
「返事を書く」
<心理診断結果>
友達との間にトラブルがあっても、積極的に立ち向かう性格。あなたにとってはトラブルもゲームのうち。出した返事が吉と出ようが凶と出ようが、結局、最後に正しいのは自分だ----と、いう結論で満足する人である。
う~~ん、納得かも~。(^_^;)
★ 因みに、「親」を選ぶと、両親の老後のことが心配。「恋人」を選ぶと、恋人が浮気でもしているんじゃないかと、そればかりが気がかり。「職場や仕事関係者」を選ぶと、今の仕事や職場の人間関係に行き詰まりを感じている----ということだそうです。
★ そして、「破り捨てる」を選ぶと、不安を拒絶するタイプで、嫌なことは見ない知らないに限ると考える性格だそうです。
「何度も読み返す」を選ぶと、問題が起きると一人で悶々と思い悩むタイプ。誰かに相談してみるとか、問題から少し離れることも大事。
「ポストへ戻す」を選ぶと、問題を後回しにしてしまうタイプ。「あとで考えよう」と、思っているうちに結局忘れてしまうお気楽な人だそうです。
続きを読む






