これって、偶然?・・・・・97
2009年07月16日
< 不 思 議 な 話 >
これって、偶然?
わたしは、小学生の頃、いくつもの塾に通っていました。
あの時分は、お稽古事が一種のはやりで、子供たちは様々な塾通いをしていたものですが、わたしの場合は、「そろばん塾」に「ピアノ」「英会話」「書道教室」などへ行っていたため、一週間のほとんど毎日が、学校、自宅、塾の三点セットでした。
しかし、当のわたしは、いずれも特別身を入れて学んでいた訳ではないため、日々の忙しさに疲れ、あわよくば塾を休みたいと、そんなことばかりを考えていました。
そんなある日のこと、英会話教室へ出かけたところ、建物の正面の扉に、「今日の英会話教室は、お休みです」の張り紙。ラッキーだと、内心ほっとしながら家へ帰ると、その日の夜、同じく英会話教室へ通っている同級生の母親から、わたしの家へ電話があり、英会話教室を開いていた若い女の先生が、亡くなったとのこと。

驚いた母が、詳しく理由を訊ねると、その相手の母親曰く、
「実はね、先生、自殺なさったらしいのよ。自宅の自分の部屋にガムテープで目張りをして、ガス自殺をしたんですって」
自殺の理由は、判らなかったのですが、その先生の死で、英会話教室は終了となってしまったのです。
しかし、わたしには、まだ他のお稽古事があります。英会話がなくなって、少し生活にも余裕が出て来ましたが、それでも、正直、書道教室には、閉口していました。
書道教室は、近所の薬師堂で、当時、三十代の庵主さんが教えて下さっていたのですが、この庵主さんがかなり厳しい先生で、相手が子供たちといえども、徹底的に時間をかけて教えるのです。
その間、ずっと正座ですから、足がしびれて、途中からは書道どころではありません。気が散っていると、いつまでもOKが出ず、何枚も書き直しをさせられます。
「もう、書道、行きたくない」
と、うんざりしていた矢先、薬師堂から電話が入り、「本日のお教室は、お休みになりました」との連絡。
その電話の直後、今度は、薬師堂のすぐ近くに住む、わたしの家の親戚から電話が来て、
「庵主さん先生、今朝、亡くなったんだよ」
との話。わたしの母親が、詳しく事情を訊ねると、薬師堂の自室で首を吊って自殺したとのことでした。こちらもまた、自殺の原因は、判らなかったようです。
ところが、こっちは、すぐに変わりの先生が来られて、書道教室は続けられることになりました。しかも、次に来た先生は、六十代のお坊さんで、これまでの先生に輪をかけて厳しい教え方で、あだ名は、「いま、一枚」。
何枚書いても、「いま、一枚」と言って、書き続けさせるのです。
これなら、前の庵主さん先生の方がよかったなァ----と、がっかりしたことを覚えています。
それにしても、二人の塾の先生の立て続けの自殺。このことは、未だに不思議でなりません。
こんな偶然て、あるものなんですねェ。
 続きを読む
続きを読む軍靴(ぐんか)の音・・・・・95
2009年07月15日
< 不 思 議 な 話 >
軍靴(ぐんか)の音
昭和十七年、わたしの父方の伯父は、ビルマ(今のミャンマー)で戦死しました。
まだ、二十三歳という若さでした。戦死といっても、最後はマラリアが悪化しての病死でしたが、当時、日本兵の中で、敵弾にあたって亡くなったという兵士は、ほとんどなく、大半の人は戦地の汚染された水を飲んだり、食糧が尽きたりしたための病死や餓死だったといわれています。
祖父母は、その上の伯父も、戦地へ送り出していたものですから、息子たちの戦死は覚悟の上だったそうですが、若い方の息子が先に亡くなることになるとは思わず、かなり悲嘆にくれたといいます。
特に、亡くなった伯父は、子供の頃から身体も大きく、わたしは、伯父の顔を写真でしか見ていませんが、なかなかの好青年で、地元の農商学校(現在の高校)では成績も優秀で常に級長(クラス委員)をしていたのでした。
しかし、家が貧しかったこともあり、進学は諦め、卒業と同時に働きに出ましたが、まじめな性格でとにかく祖父母にとっては自慢の次男だったのです。徴兵されて軍隊(松本連隊)へ入ったあとも、数々の試験をクリアして、一兵卒から軍曹にまでなりました。
そして、戦死による二階級特進で、伯父は少尉となって勲章と共に帰って来たのです。
その、伯父の戦死報告が連隊から届く少し前のことです。ある夜、家には祖母と、まだ中学生のわたしの父、父の姉たちが茶の間で夕飯を食べていました。
すると、家の外をかすかに軍靴の歩く音がして、その音は、次第に大きくなり、家の方へと向かって来たのだそうです。
軍靴とは、陸軍の軍人が履く靴のことで、靴の裏には、たくさんの鋲が付いています。ですから、歩くたびにガチャガチャと、音を立てるのです。その音が、家の前まで来たかと思うと、突然ぴたりと止まりました。
父が、「誰か、兵隊さんが来たみたいだよ」と、祖母に言うと、その直後、玄関の引き戸がものすごい音をたててガラッ!と、開いたのだといいます。父は、祖母に、誰か来たから見て来てくれと、言われたので、茶の間から玄関へと行ってみたのですが、引き戸はいっぱいに開けられているものの、そこには誰の姿もありません。開けられた戸の向こうには、真っ暗な夜の畑が広がっているばかりだったのです。
その後、数日たって、伯父が戦地で病死したという報告が、村役場から届き、父たちは、もしかしたら、あの時の軍靴は、伯父の魂が自宅へ戻って来た音だったのではないだろうかと、思ったそうです。
戦後、もう一人の上の伯父は、長いシベリア抑留を経て、餓死寸前の栄養失調状態で、それでも何とか復員(日本へ帰って来ること)して来ました。
祖母は、その後、戦死した伯父の話はほとんどしませんでしたが、八十三歳で亡くなる時、最後に言い残した言葉が、その伯父の名前だったのでした。
続きを読む
一本松の幽霊・・・・・82
2009年07月03日
< 不 思 議 な 話 >
一本松の幽霊
わたしの母方の実家は、地元でも少しは名の通った日本そば屋です。
まだ、終戦間もない頃、食糧のない時代にもかかわらず、わたしの祖父は、配給の食料や、祖母の着物を農家に持って行って代わりに分けてもらったジャガイモや、トウモロコシの粉などで、すいとんなどを作り、それでも、何とか商売を続けていました。
そのわずかな食べ物を求めて、店の前には長い列が出来、その列に並ぶことすら出来ない持ち合わせのない人たちは、夜になると、店の裏手にある勝手口へ来ては、売れ残りの蒸かしイモなどを、ただでもらって行ったそうです。その中には、昼間は闇物資を取り締まっていた、若い警察官の姿もあり、「仕事がら、闇米には手を出せず、子供が腹を空かして困っているので、ほんの一つでもいいから、芋を分けてもらいたい」と、涙を流していたそうです。
そんな様子を見かねて、祖母は、「あんたにやるんじゃないよ。子供にくれるんだからね」------そう言って、蒸かしイモと岩塩を少し紙にくるんで、その警察官に持たせたこともあったそうです。
そのそば屋のすぐ隣に、母親とまだ幼い二人の男の子が住む家がありました。その家の父親は、既に戦死し、若い母親は、子供を抱えて必死で他人の家の畑の耕作などを手伝いながら、細々とした給金をもらい、その子たちを育てていました。
わたしの祖父母は、その家族があまりに気の毒で、時々、その家に売れ残りのうどんの玉や、野菜の煮物などを運んでは、「代金はいらないから、子供にいっぱい食べさせてやりなさい」と、渡していたそうです。ところが、しばらくして、その母親が、過労から身体を壊し、寝込む日が多くなりました。
子供たちの世話が出来なくなった母親が、わたしの祖父母に、子供たちにご飯だけでも食べさせてやって欲しいと、頼むので、もともと子だくさんだった祖父母は、別に二人増えたからといっても何のことはないと、二人の息子を家に呼び、朝飯を食べさせ、学校には祖父母の家から通わせ、夕飯を食べさせて、自分の家へ帰すという生活を送らせました。
しかし、そのうちに子供たちの母親の容態はますます悪くなり、地元の開業医の治療もかいなく、とうとう三十半ばの若さで亡くなってしまったのです。お葬式が終わり、引き取り手もなく途方に暮れる子供たちの将来を心配した祖父母は、彼ら二人を手元に引き取り、せめて中学を卒業するまではこの家の子供として育てようと、決めたのです。
そんな、ある日の夜のこと、祖母が家の外へ出た時、近くの畑の真ん中にある一本の松の木の下に、何やらぼうっと薄ぼんやり青白く光る物があることに気付きました。その光の大きさは、ちょうど人間の身体ほどで、よく良く見ると、それは、一人の女性の姿だったそうです。
祖母は、ひどく驚きましたが、さらに間近によって見詰めると、そこに立つ女性は、紛れもなく、数日前に亡くなった二人の息子の母親だったのです。母親は、祖母の方へ顔を向けると、悲しそうな顔をして、黙ったまま何度も何度も深々とお辞儀をするので、祖母は、これは、息子たちのことを頼むと言いたいに相違ないと感じ、
「判っているよ。子供たちのことは、ちゃんと面倒見るから、心配しないでいいよ」
と、声をかけたところ、母親は、嬉しそうに微笑むと、すっとその場から消えてしまったのだそうです。
その後、二人の息子たちは、中学を卒業したのちに、それぞれ会社へ就職し、結婚したそうです。
続きを読む
花園の階段・・・・・66
2009年06月17日
~ 今 日 の 雑 感 ~
花園の階段
わたしの卒業した大学のキャンパスは、ちょうどこの季節、薔薇の花をはじめ色とりどりの花や緑で埋め尽くされ、文字通りの花園となります。
 正門から校舎まで続く長い遊歩道の両脇には、西洋庭園によく見られる石像や、彫像が並び、かぐわしい薔薇の花で彩られたアーチは、正に秘密の花園といった雰囲気を醸し出しています。
正門から校舎まで続く長い遊歩道の両脇には、西洋庭園によく見られる石像や、彫像が並び、かぐわしい薔薇の花で彩られたアーチは、正に秘密の花園といった雰囲気を醸し出しています。そんなキャンパスを、神父様やマスール(シスター)たちが僧服をひるがえしながら闊歩し、いつも学生たちの話し声や笑い声がさざめいていました。
そして、その大学の校舎内の一角には、不思議な階段があったのです。
教授室などが並ぶ棟の三階から二階へ降りる階段で、踊り場のところまで来ると、いきなり、天井から水が落ちて来るような音がするのです。
それも、ピチャッ!------などという可愛らしいものではなくて、思いっ切りバケツで水を浴びせるといった感じのバシャッ!-----と、いう豪快な音なのです。そのことを知らない新入生などは、頭から水をぶっかけられたと思って、慌てて髪の毛を触り、仰天します。
わたしも、始めは何のことか判らずに、本当に驚きました。が、そんなある日、一緒に階段を降りていた友人も、このバシャッ!にびっくりして、再び階段を上って逃げようと焦り、そこに立っていた壁に正面からぶつかったまま、一瞬身動き出来なくなってしまいました。つまり、それに張り付いた格好になってしまったのです。
「〇〇ちゃん!大丈夫?」
わたしも、他の学生の友人たちも、叫んでから今度は思わず込み上げる笑いを抑えるのに必死でした。何故なら、彼女が張り付いていたのは、校舎の壁ではなく、ちょうど教授室から出て来られた、神父様の大きなお腹だったからです。

張り付いた友人は、恥ずかしさで顔面真っ赤でした。
でも、その水音は、必ずいつも聞こえるという訳ではありません。実に気まぐれな音で、聞こえる時と聞こえない時があるものですから、その階段を常に利用しながらも、一度も聞いていないという人もいたのです。
そんな訳で、ある友人は、その音がすると、「ああ、気まぐれ天使が、また、水がめをひっくり返したよ」-----なんて、呆れていました。
あの階段の不思議な水音は、今も聞こえるのでしょうか?
もしかしたら、本当に、天使のいたずらだったのかもしれないと、微笑ましく思い出します。

幽霊電話・・・・・59
2009年06月08日
< 不 思 議 な 話 >
幽 霊 電 話
これは、わたしの従姉が体験した出来事です。
わたしの従姉は、A町とB市の二か所に家を持っていまして、ほぼ毎日のように、自家用車に両親を乗せて、その二軒の自宅を行き来しているのです。
何故、そんな面倒なことをしているのかといいますと、つい最近まで一家はA町の家で暮らしていたのですが、両親の体調が思わしくなくなってからは、大きな病院のあるB市に住んでいた方が、何かと都合がいいということで、そちらの方へ生活の場を移した訳なのです。しかし、もともと温泉場育ちの両親は、お風呂だけは温泉に入りたいというので、従姉は、毎日、両親をその温泉へ入浴させるため、A町へと連れて行かなくてはならなくなったのです。
 その従姉は、未だ独身ということもあり、両親は、一人っ子の彼女に頼りきりで、彼女がいなければ、もはや一日が成り立たないという状態にまでなっているのです。そんなある日のこと、いつものように両親を自動車に乗せて、A町へ行くべく、川沿いの県道を走っていた時でした。かつて、遺体を火葬していた場所で、通称『焼き場』と呼ばれた施設の跡地の前を通り過ぎようとした時のことでした。
その従姉は、未だ独身ということもあり、両親は、一人っ子の彼女に頼りきりで、彼女がいなければ、もはや一日が成り立たないという状態にまでなっているのです。そんなある日のこと、いつものように両親を自動車に乗せて、A町へ行くべく、川沿いの県道を走っていた時でした。かつて、遺体を火葬していた場所で、通称『焼き場』と呼ばれた施設の跡地の前を通り過ぎようとした時のことでした。いきなり、「お~い!」と、いう、男の人の声が聞こえたのだといいます。従姉は、その声に聞き覚えがあったので、何だか奇妙に感じて、後部座席の両親に訊ねました。
「ねえ、今の男の人の声、死んだおじいちゃんに似ていなかった?」
すると、両親も、確かに似ていたような気がすると、言います。三人は、不思議な気持ちで、そこを通り過ぎましたが、おかしなことに、翌日、再び同じ場所へさしかかると、またも、「お~い!」と、呼びかけるような男の人の声を聞いたのでした。
従姉と両親は、何とも奇妙な気持ちになりながらも、A町の自宅へ入り、両親は近所の共同浴場へと出かけ、家には彼女一人が留守番をしていたのでした。すると、しばらくして、二階にある彼女の部屋から、電話のベルが鳴るような音が聞こえてきました。しかし、一階にある電話の親機は、呼び出し音を発してはいません。そのベル音は、二階にある子機のみから聞こえてくるようでした。
「親機が鳴らないのに、子機だけがなるなんて、変なこともあるなァ------?」
と、思いながら、従姉は、二階へ階段を上がり、自室の子機を耳に当てました。すると、受話器の向こうから聞こえて来た声は、
「〇〇か-------?おれが、呼んでいるのに、何で知らん顔して行っちまうんだ?」
その声は、紛れもなく、彼女の亡くなった祖父のものでした。従姉は、思わず子機を放り出し、その場から逃げ出してしまったそうです。
今でも、その場所を通り過ぎる時、ごくたまに、男の人の呼ぶ声が聞こえるのだそうですが、従姉は、その声が聞こえると、「判った、判った、聞こえているよ、おじいちゃん!」と、返事をして行き過ぎるのだと言っていました。
ちょっと、一服・・・・・40
2009年05月14日
~ 今 日 の 雑 感 ~
山道のあんパン
毎度の山シリーズですが、これは、わたしの父親が経験したことです。
わたしの父も山での山菜取りが好きで、若い時分は、よく近くの山へワラビやネマガリダケなどを採りに、何人かの友人たちと出掛けることがあったのですが、その最中、やはり、一度だけ道に迷ってしまったことがあったそうです。
ある時、父は気の合う友人四人と志賀高原へ山菜を採りに出かけたのですが、帰り道を間違え、自分たちがいったい何処を歩いているのかも判らなくなってしまったのだそうです。こうなってしまうと、山道という物は不思議な物で、歩いても歩いても、また、同じような場所に出て来てしまうのです。
父たちの場合は、自分たちの背丈ほどもある草藪の中を何とかかんとか分け出てみると、とても広い綺麗に舗装されている道路が現れるのだそうです。人っ子一人いないその道路をしばらく歩くのですが、やはり、何処へも辿り着かない。そこで、業を煮やし、また、脇道の草藪の中へと踏み行って、下山しようと試みるのですが、出たところが、また、例によって広い道路なのだそうです。
食糧も持たずに来ていた父たちは、既に辺りも日が暮れかけて来たころ、お腹が空いてたまらなくなり、
「まったく、えらいことになったなァ・・・・。昼飯前には帰る予定だったのに、これじゃァ、夕飯にもあり付けねえぞ」
「だれか、お茶ぐらい持っていないのか?」
そう訊ねられても、誰一人、そんなものは持って来ていなかったので、
「自動車の所まで行きつければ、食い物ぐらいあるんだがなァ・・・・。山へなんか来なけりゃよかったなァ・・・・」
そんな気弱なぼやきも出て来た時でした。突然、友人の一人が、その広い道路の上に何かが落ちているのを見付けました。皆がその物の周りへ歩み寄り、よく見てみると、それは、我が家の近所にあるパン屋さんの名前の入った大きな紙袋でした。父たちは、奇妙に思いながらも、そのズシリと重い紙袋を拾い上げ、

「〇〇パン屋のやつだぞ。中に何か入っている-----」
そっと開けてみると、何と、その中には、一つ一つビニール袋に丁寧に包まれた、今焼いたばかりというようなフカフカのあんパンと、缶コーヒーが入っていたのでした。しかも、その数が、ちょうど、あんパン五個に缶コーヒーが五本。
「おい、ちゃんと、人数分あるぞ!すげェ!」
「誰かの落とし物だな。まだ、新しいぞ」
「どうして、こんな場所に、こんな物が落ちているんだ?しかも、ちょうど、おれたちの人数分だなんて、偶然にしても気味が悪いな・・・・」
そんなことを言いながらも、五人は、顔を見合せ、そのあんパンの始末をどう付けようかと考えました。空腹は、既にピークです。
「いいや、おれ、食っちゃうぞ!」
一人があんパンを包むビニール袋を開けてかぶりつくと、残る三人も、袋を開き、パンを食べ始めました。缶コーヒーも飲みながら、うまいうまいと夢中で食べる友人たちを見ながらも、父だけは、どうしてもこの状況に納得がいかず、缶コーヒーは飲んだものの、あんパンには手が付けられなかったといいます。
しかし、これで、少しは空腹が納まったために、父と友人たちは、残りのあんパン一つを入れた紙袋をぶら下げたまま、再び山道を歩き、ようやく、その日のうちに麓まで下山することが出来たのだそうです。
山中に置きっ放しになってしまった自動車は、後日取りに行ったそうですが、その後も、あんパンを食べた四人の体調に別段の変化はなかったそうで、未だに父は、その時の状況が腑に落ちないと言っています。よく昔話にある、キツネに化かされた旅人よろしく、もしや、あれは馬糞ではなかったか------?などと、わたしは思ってしまうのですが、皆さんは、くれぐれも、不審な食べ物は口になさらぬように------。
山道を歩く時は、たとえ近くにホテルや人家があると思っても、必ず、食糧と水分は、携帯しておいた方が、いざという時に便利だと思いますよ。では、お気を付けて、山歩きを楽しんで下さい。
 続きを読む
続きを読むちょっと、一服・・・・・37
2009年05月10日
~ 今 日 の 雑 感 ~
山で道に迷う
皆さんは、登山やハイキングの際に、山道で迷子になったことがありますか?
別に、それほど大袈裟なことではありませんが、わたしは、一度だけ、山で道に迷ったことがあるのです。あれは、まだ二十代も前半の夏のことでしたが、女性の友人と、ぶらりと志賀高原まで出かけたことがあったのです。
山のホテルへチェックインしたのが午後三時頃だったものですから、時間を持て余していたわたしたちは、ちょっとその辺を散歩でもして来ようと、ほんの軽い気持ちで、出かけたのでした。
そして、どうせここまで来たのだから、ハイキングコースでも歩いてみようかと思い立ち、広い国道から外れて林道の方へ入って行ったのが、間違いのもとでした。通常のハイキングコースを歩いているつもりが、いつの間にか、別のルートへ進んでしまっていたらしく、行けども行けども終着点へ辿り着けません。道は次第に険しくなり、大きな岩がゴロゴロしているとてもハイキングコースとは思えない場所を幾つも乗り越えながら、それでも下へ進めばいつかは国道へ出るのではないかと思い、ヘトヘトになるまで歩き続けました。その頃は、携帯電話などもなく、辺りに人影らしきものもまったくなく、たった二人の山中行軍です。
「このまま何処にも出られなかったら、仕方がないから、野宿だね」
「それも、いい思い出じゃァないの」
などと、この期に及んでも、まだ危機感のない会話をしていた時です、不思議なことに、何処からともなくフルートを吹く音色が聞こえて来たのです。静かな木々の間を吹き抜ける風の音に混じって、何とも優しげなそのメロディーは、明らかに、近くに人がいる証拠でした。わたしたちは、一目散にその音の方へと足を速めました。
すると、いきなり視界が開け、出て来たところが広々とした池の縁でした。しかし、そこには誰も人はおらず、ただ一足の男性用の靴が行儀よく揃えられて置いてありました。
「誰が、吹いていたんだろうね?今のフルート・・・・」
「志賀高原では、音楽大学の人が合宿練習をしているから、そんな学生たちの一人だったんじゃない?」
と、話をしていますと、いきなり近くで、木材を伐るチェーンソーの音が響いたので、わたしたちは、今度はそちらへ歩いて行きました。そこには、営林署の職員のおじさんが一人雑木の伐採作業をしておられたので、そのおじさんに国道への行き方を訊ね、わたしたちは、ようやくホテルへと戻ることが出来たのでした。
その間、時間にすれば、わずか三時間ほどのことだったのですが、口では馬鹿なことを言いながらも、内心は、実に不安な体験でした。山に入る時は、やはり、どんなに短い距離を歩くとしても、しっかりと事前のシミュレーションを怠らず、いざという時に必要な登山用具もちゃんと携帯したうえで、行くべきだと痛感した次第です。
それにしても、あのフルートを吹いていた人はいったい誰だったのか?-----あまりのタイミングの良さに、わたしの友人は、
「あたしたちが道に迷っていることを知っていて、あの池のある所まで誘導してくれたみたいだね」
と、言っていました。
山では、時々、不思議なことが起きるものですね・・・・・。
 続きを読む
続きを読むちょっと、一服・・・・・31
2009年05月05日
< 不 思 議 な 話 >
わたしの母方の伯父は、時々、不思議な体験談を色々と話して聞かせてくれます。その中でも、特に変わっているのは、自分の母親、つまりは、わたしの母方の祖母が、嫁に来るところを見ていたという話です。
伯父の話はこうです。「おれは、まだ三歳ぐらいの子供だったが、近所の塀の上に腰を掛けていると、真っ白な綿帽子をかぶった白無垢の打ち掛け姿の若い綺麗なお嫁さんが、仲人さんらしき女の人に手を引かれながら、しずしずとおれの家の中へ入って行くのが見えたんだ。でも、おれには、その時よく判っていた。あのお嫁さんが、おれのお袋になるんだなってことがさ・・・・」
ね?おかしな話ですよね。でも、この前、ある人が話してくれたのですが、そういうことって稀にあるそうなのです。その人の話は、こういうものでした。
小さな少年と飴
ある街の小さな本屋さんに、三十五歳になった陽子(仮名)さんという女性店員が働いていました。陽子さんは、真面目な従業員で、人当たりも良く、周囲の人たちからはとても慕われていたのですが、その年齢になっても未だに特定の恋人などは出来ず、もう半ば結婚は諦めていました。
そんなある日のこと、脚立にのぼり、店の棚の上の方の本を入れ替えていた時のことです。足元の方で何やら動く気配がしたので視線を落とすと、そこには四、五歳の可愛い男の子が一人で立っていました。その男の子は、ニコニコ笑いながら、嬉しそうに陽子さんを見上げているので、彼女は脚立から降りると、男の子の前へ屈み込み、
「坊や、何処から来たの?お父さんか、お母さんは、一緒?」
と、訊ねたのですが、男の子はそれには何も答えず、
「おばちゃん、陽子さんでしょ?ぼく、まこと(仮名)・・・・。これ、おばちゃんにあげる・・・・」
そう言うと、小さな手で、自分のズボンのポケットから可愛らしい模様の紙にくるまれた飴玉を一つ取り出し、陽子さんにくれたのでした。
「ありがとう・・・・・」
不思議な思いで、陽子さんがお礼を言うと、少年は、今度は、店の入り口の方をしきりに気にするそぶりを見せて、
「あのね、おばちゃん、もうすぐここへ男の人が入って来るの。その人が来たら、優しくしてやってね・・・・」
と、言います。陽子さんは、更に、怪訝に感じたものの、
「それが、坊やのパパなの?」
と、訊くと、少年は、ちょっと、小首を傾げて、
「・・・・判んない」
「判んないって、それどういうこと------?」
陽子さんが再び訊ねた時でした。店の入り口に四十歳ぐらいの背の高い男性客が一人現われたので、陽子さんは、その男性客の方へ一瞬目を移し、
「いらっしゃいませ」
と、元気に声を張って立ち上がったのち、もう一度少年の方へ顔を向けると、奇妙なことに、その少年の姿は既に何処にもありませんでした。おかしな子供だったなァ------と、陽子さんは、釈然としないものを感じながらも、その男性客の方へ歩み寄り、
「何かお探しのご本でもおありですか?」
そう声を掛けると、その男性客は、静かな口調で、地元の歴史の専門書を探しているんですが・・・・と、言いますので、陽子さんは、さっき棚の上の方へ入れたばかりの本にそれらしきものがあったことを思い出して、もう一度脚立に上ろうとしました。が、その途端、バランスを崩して、何と、その男性客の上へ落下!男性客は、驚く間もなく、咄嗟に陽子さんの身体を受け止め、事なきを得ましたが、陽子さんは、大赤面で、男性客に向かって、ごめんなさいの連発となってしまいました。
それから半年が過ぎ、陽子さんは、結婚しました。相手は、その時の男性客でした。彼は、地元私立高校の教師で、陽子さんは、ほどなくして妊娠。勤めていた本屋さんも辞めて、翌年には、元気な男の子を出産しました。夫婦で子供の名前を考えている時、夫がふっと思い付いたように、
「きみが、ぼくと初めて出会ったあの日に見たという、その男の子の名前を付けないか?彼は、ぼくたちのキューピッドなんだから」
と、提案するので、陽子さんも異論なく、男の赤ん坊は『誠(まこと)』と、命名されました。
やがて、その誠も、三歳となり、近くの保育園に通うようになると、陽子さんは、再び、以前の本屋さんで働き始めました。すると、それから一年ほど経ったある日のこと、誠が独りで保育園から帰って来るや、陽子さんのいる本屋さんまで来て、ニコニコ笑いながら、
「今日は、お母さんにいいものあげるよ」
と、言うなり、自分の園児服のポケットから何かをつかみだし、陽子さんの掌(てのひら)に載せたのです。それは、可愛い紙に包まれた一つの飴玉でした。俄に、過去の出来事を思い出した陽子さんが、びっくりしながら、
「これって、お母さん前にも・・・・・」
「うん、ちょっと、お祝ね。ぼくが前にお母さんにあげたのはミカン味だったけど、今度のは、イチゴ味なんだよ。だって・・・・」
と、誠は少し言葉を選んでから、胸を張るようにして嬉しそうに言いました。
「だって、今日は、ぼくがお母さんとお父さんを出会わせた日なんだもん」
こんな不思議な話なら、幾つ聞いても楽しいですよね。

ちょっと、一服・・・・・26
2009年04月29日
< 不 思 議 な 話 >
上 条 の 第 二 踏 切
これは、わたしが以前、女性の友人から聞いた話です。
下高井郡山ノ内町の上条という所には、長野電鉄線の二つの踏切があります。
一つ目の踏切は、山ノ内町役場の上にある、通称第一踏切といい、もう一つ目は、それよりも中野市寄りとなる、通称第二踏切といいます。
第二踏切の周辺は、りんご畑や桃畑が一面に広がる農業地域で、北には高社山の悠然たる姿が望め、ちょうどこの春真っ盛りの頃は、一斉に咲き競う菜の花や果樹の花々で辺りは埋め尽くされ、それは見事な景観をおりなす、さながら絵画の世界となるのです。
しかし、その第二踏切には、昔から、ある不思議な話が付きまとい、夜は決して一人ではあの辺りへ行ってはいけないと、子供たちは大人たちから言われていたのだといいます。
ある夏の蒸し暑い夜、一台のタクシーが、その第二踏切に差し掛かった時、その踏切の遮断機のそばに、真っ白なワンピースを着た、髪の長い一人の若い女性が立っていたのだそうです。
「こんな真夜中に、若い女が一人で立っているなんて、誰かと待ち合わせでもしているのかな?」
タクシーの運転手は、不思議に思いながらも、そこを通り過ぎようとした時、その女性がやおら片手を上げて、そのタクシーを停車させようとするのが、ヘッドライトの光の中に浮かび上がったのでした。
タクシーの運転手は、一瞬、不審を感じたのですが、ちょうど乗車予約客もいなかったため、その女性を乗せてもいいと思い、彼女のそばでタクシーを停めました。車のドアを開けると、女性は無言で乗り込んで来て、後部座席でじっと俯いています。 「どちらまで行かれますか?」
タクシー運転手が訊ねると、女性は、長い髪の間に、ほんのわずかにのぞいた蒼白い顔を少し上げ加減に、やっと聞き取れるほどの小声で、
「湯田中駅までお願いします・・・・・」
と、言うので、運転手は、ゆっくりとタクシーを発車させました。運転手は、バックミラーで、時々女性の様子を観察しながら、
「湯田中駅では、どなたかと待ち合わせですか?」
それとなく訊ねたのですが、女性は、返事をしません。ただ、じっと俯いた姿勢のまま、黙って座っているばかりです。
やがて、タクシーは、湯田中駅まで到着したのですが、既に終電が発車した後ですから、駅の構内もすべて電気が落ち、辺りは真っ暗で、こんな所へ若い女性一人を置いたまま帰ってもいいものかと思った運転手が、少々心配顔で、
「ここでいいですか?〇〇円になりますが-----」
と、後部座席を振り返った時、そこには女性の姿はなく、シートが水でも流したかのように、ぐっしょりと濡れていたのだそうです。
このタクシーに乗る幽霊の話は、今でも、この上条地区に住む子供たちの「夏の怪談噺」の定番だということです。
夢に出て来たナガブロガー
もう一つの不思議な話は、ナガブロのあるブロガーさんに関係するお話です。
先日の明け方、わたしは、実に奇妙な夢を見ました。ある一人の女性が、わたしの夢の中に登場したのですが、その人は、何と、ナガブロのブロガーさんだと、夢の中で言うのです。
そのシチュエーションは、こんな感じでした。
春のあるうららかな日に、わたしは、長野電鉄線の通称「赤ガエル」と呼ばれる鈍行電車に揺られていました。
車窓には、春の暖かな日差しがあふれ、何処からか桜の花びらも舞って来ます。車内の横がけの長いシートにのんびりと腰をおろしていたわたしに、やおら、一人の女性が声を掛けて来ました。年齢は、四十代か五十代の垢抜けた感じの人で、花柄のブラウスがとてもよく似合っていました。
でも、不思議なことに、わたしには、初めて会うその人が、何となく「この人、もしかしたらブログを書いているんじゃないかな?」と、直感出来たのです。すると、その女性は、わたしのすぐ隣に腰を下ろし、
「わたし、あなたのこと知っているわ。ちよみさんでしょ?わたしもナガブロでブログを書いているのよ」
と、言います。ああ、やっぱりそうなんだ・・・・。と、わたしが思っていると、その女性は、いきなり、
「わたし、〇〇〇〇よ」
と、ブロガーのハンドルネームを口にし、

「本名はね-------」
と、言い掛けたところで、電車の走行音がその言葉をかき消してしまったので、それは聞けずじまいでしたが、その女性は、次の停車駅で、それじゃァまたねと、にっこり笑って電車を降りて行きました。
わたしは、今までに、ナガブロのブロガーさんたちと直にお会いしたことは、一度もありませんし、電話でお話ししたこともありません。ですから、その夢に出て来たブロガーさんのお顔も、声も、まったく知りませんし、それよりも、ナガブロのサイト内で、コメントを交換したことすらないのです。でも、そのブロガーさんは、確かにサイト内におられます。
夢の中のそのブロガーさんの感じは、アップしたイラストに近いものです。
本当に、不思議な夢を見たものです。(^_^;)
ちょっと、一服・・・・・21
2009年04月12日
< 追いかけて来る男 >
この前、ある人から、「ちよみさんて、スピリチュアルの講演か何かすることがあるの?」と、訊かれまして、何のことかと思っていたのですが、どうやら、「ナガブロ」のあるブロガーさんの記事の中に、「ちよみさんの講演もあります」と、いうような記事があったそうで----。でも、それは、わたしではありません。わたしには、スピリチュアルに関係する講演をするような能力は、これっぽっちもありませんので-----。(^-^)
でも、時々、妙なことを言うなァと、いう体験も無きにしも非ずでして、大学生の時、ある友達から、「ちよみさんて、〇〇大学にも通っているの?」と、変なことを訊かれました。「そんな大学、行ったこともないけど」と、答えますと、「でも、あそこで、あなたを見たっていう人がいるんだけど、人違いだったのかな?」と、言うのです。「何処にでもある顔だから、見間違いでしょ」と、言って笑ってはいましたが、そう言われたのは、実は二度目で、その別の大学には、よほどわたしに似ている学生が通っていたのでしょうね。二つの大学へ、一度に通うことなど出来やしないのに、おかしな噂が立ったものです。
まあ、それはそれとして、今日のお話は、わたしがそんな友人たちの一人から聞いた、少しばかり怖いお話です。
このお話は、その友人の友人------と、ここまで来れば、何処までが真実なのか判らなくなるほどのものなのですが、------その友人の友人が、体験した話だというのです。
この友人の友人、仮に恵子さんとでもしておきましょうか。その恵子さんが、大学の夏休みに、同じ大学のサークル仲間の雅夫、夏美、一郎、善行(いずれも仮名)の五人で、信州のある高原へドライブ旅行へ行こうという、計画を立てたのだそうです。
ところが運悪く、ドライブ旅行の当日、恵子さんは、どうしても実家に戻らなければならない用事が出来てしまい、仲間の四人に、
「少し遅れるけれど、必ずあとから追いかけるから、先に、ホテルへ入っていてね」

と、連絡を入れ、実家の用事を済ませた後で、独り自家用車を運転し、信州へ向かったのです。
そして、仲間と合流するべく、高原のホテルへ赴く山中の国道を自動車で走っていると、途中、交通事故を起こして崖下へ落ち、大破したステーションワゴン車を、崖下から引き上げている最中の、事故処理の現場を目撃したのだそうです。
辺りは、既に薄暗くなって来ていましたが、事故現場には、警察車両や、救急車なども集まっていて、実に物々しい様子だったと、いいます。
しかし、恵子さんは、そんなところで事故処理の様子を眺めて道草を食っている暇もないので、横目で見ただけで、通り過ぎてしまったのですが、しばらく走っていると、恵子さんの運転する自動車の後ろから、猛スピードでやって来るオートバイを、バックミラーで確認したのだそうです。フルフェイスのヘルメットを被っているそのバイカーは、その後、恵子さんの車の後ろへぴったりと車体を付けるようにして、走って来ます。いつまでたっても、そのオートバイは、追走をやめようとしないので、気味が悪くなった恵子さんは、自動車のスピードを上げ、ようやく、目当てのホテルの庭先までやって来た時、そこに、先に来ている夏美、一郎、善行の三人の姿を見付け、慌てて、車を止めると、車外へ飛び出したのでした。
「ああ、よかった!みんな待っていてくれたんだね」
恵子さんは、ほっとして、三人の方へ駆け寄ろうとしました。すると、すぐ後ろから追い付いて来た、そのバイカーが、バイクを止めて、突然大声で叫んだのです。
「恵子!そっちへ行っちゃダメだ!」
それは、雅夫の声でした。雅夫は、フルフェイスのヘルメットを取ると、その顔は傷だらけで、額からは血が垂れています。
「雅夫、その傷どうしたの・・・・?」
驚いた恵子さんが、今度は、雅夫の方へ近付こうとすると、目の前の三人が、
「恵子、それは、雅夫じゃない!雅夫は、おれたちの車が崖へ落ちた時に死んだんだ!そいつは、幽霊なんだよ」
と、言うのです。恐怖におののき、半ばパニック状態になった恵子さんが、自分を手招きする三人の方へ戻ろうとした時、背後から、雅夫が、いきなり彼女の身体へ抱きついて来て、大声で言ったのです。
「恵子、よく見ろ!死んだのは、あの三人の方だ!そっちへは、行っちゃいけない!」
「---------!!」
ショックで、声も出ない恵子さんが、目の前の三人を再び見た時、一郎が一言、
「くそ・・・・!もう少しで、道連れに出来たのに・・・・・」
そういうと、蒼白い顔を悔しげに歪めて、一郎、夏美、善行の三人は、闇に溶けるように姿を消したのだそうです。
そして、改めて、三人が立っていた場所を見た恵子さんは、もう一度、声を失いました。そこは、ホテルの庭先などではなく、断崖の突端だったのでした。
「危なかったな、恵子・・・・」
雅夫は、ようやくほっとした口調で言うと、
「実は、おれも、お前と同じ目に遭わされそうになったんだよ。さっきお前が見たあの交通事故車は、あいつらの乗ったステーションワゴンだったんだ。おれも、あいつらとは、一緒に来ることが出来ずに、あとからオートバイで追い掛けたんだよ。そうしたら、ここへ来る途中の崖へ誘い込まれて、こんな怪我をしてしまった。でも、お前が、車で走って来るのを見て、急いで追い掛けて来たんだよ」
と、説明したのだそうです。
こんな、怖い話が、実際にあるものなのでしょうか?どうも、大半が、その友人の友人という人の、作り話のような気もするのですがね・・・・・・。(^_^;)
ちょっと、一服・・・・・⑰
2009年03月27日
< 学 校 に か か る 電 話 >
これは、わたしの家の近所の女性が、高校生の頃に体験した実話です。
今から約三十年ほど前、彼女は、その頃、長野市内にある、某女子校に通っていました。
その女性の家は、昔から御商売をされているのですが、その家屋部分が庭を含めてかなり広い造りになっているものですから、当時は、その空いている部屋を、下宿として貸し出してもいました。
その彼女が、まだ小学生の時、その貸し部屋に、一人の若い芸者さんが住むことになり、芸者さんは、三味線や踊りの稽古の合間には、よく彼女を部屋に呼び、おはじきをしたり、お絵描きの相手をしたりと、とてもよく面倒をみてくれたのだそうです。
でも、彼女のご両親は、彼女が一人っ子だったこともあり、また、両親が高齢になって出来た娘でもあったため、それこそ目の中に入れても痛くないという可愛がりようで、ほんの短時間でも、自分たちの目の届かないところには置いておきたくないという過保護ぶりもあり、彼女が、芸者さんの所で遊ぶことを、あまり快く思わなかったのでした。
そんな理由もあって、彼女も、小学生、中学生と、成長するにつれて、あまり足繁く芸者さんの部屋へ行くということはなくなって行きました。そして、彼女が高校生になった頃、芸者さんは、当時はほとんど不治の病とされている病気に侵され、お座敷に出ることもかなわなくなり、とうとう病院に入院することになってしまいました。
その病院が、彼女の通う高校の近くにあったことから、彼女は、時々、放課後になると、両親には内緒で、こっそりと芸者さんのお見舞いに行っていたそうです。芸者さんは、その日一日の彼女の学校生活の話を聞くのを、とても楽しみにしていて、自分は、中学卒業と同時に、芸者の置屋(おきや)に奉公に出されたから、学校の話を聞くと、自分も高校生になったような気がすると、とても喜んでいたということでした。
そんなある日、彼女の授業中に、学校の職員室に、その芸者さんからの電話が入り、彼女を呼び出して欲しいというのです。先生の一人が、授業中の彼女の教室まで来て、そのことを伝え、彼女が職員室の電話に出ると、受話器の向こうで、その芸者さんが、「もう元気になったから、今日退院するよ。いままで、お見舞いに来てくれてありがとうね」と、元気な声で言うのだそうです。彼女も、嬉しくなって、「じゃァ、今日家へ帰ったら、退院のお祝いをしなくちゃね」と、答えますと、芸者さんは、何度も「ありがとうね」を繰り返して、電話を切ったのだそうです。
彼女は、既に家には芸者さんが帰って来ているものとばかり思い、喜び勇んで帰宅したところ、家の中の雰囲気が何だかいつもと違うことに気付きました。そこで、従業員の一人に訊いてみたところ、「芸者さん、亡くなったんですってよ、〇〇ちゃん」というので、彼女は、何だか狐にでもつままれているような気がして、「いつ亡くなったの?だって、あたし・・・・」と、途中で言葉を飲み込んだのだとか。それというのも、その従業員が話すには、「〇〇時頃なんだって。病院からの連絡で、〇〇ちゃんのお父さんと置屋のお母さんが、遺体を引き取りに行っているんだよ」と、いうことでした。
その時間は、正しく、彼女が職員室の電話で、芸者さんと話をした時間だったのです。
あの電話は、いったい何だったのか?自分だけが、聞いた空耳などではない。だって、電話を取り次いだ先生だって、それを聞いているんだから・・・・。
彼女は、そのことを、後日両親に話したのですが、両親は、女子高生の絵空事と、取り合おうとはしなかったそうです。
「でも、わたしは間違いなく、あの時、芸者さんと話をしたのよ」-------彼女は、今も、そのことが気になって仕方がないと言います。
これは、わたしの家の近所の女性が、高校生の頃に体験した実話です。
今から約三十年ほど前、彼女は、その頃、長野市内にある、某女子校に通っていました。
その女性の家は、昔から御商売をされているのですが、その家屋部分が庭を含めてかなり広い造りになっているものですから、当時は、その空いている部屋を、下宿として貸し出してもいました。
その彼女が、まだ小学生の時、その貸し部屋に、一人の若い芸者さんが住むことになり、芸者さんは、三味線や踊りの稽古の合間には、よく彼女を部屋に呼び、おはじきをしたり、お絵描きの相手をしたりと、とてもよく面倒をみてくれたのだそうです。
でも、彼女のご両親は、彼女が一人っ子だったこともあり、また、両親が高齢になって出来た娘でもあったため、それこそ目の中に入れても痛くないという可愛がりようで、ほんの短時間でも、自分たちの目の届かないところには置いておきたくないという過保護ぶりもあり、彼女が、芸者さんの所で遊ぶことを、あまり快く思わなかったのでした。

そんな理由もあって、彼女も、小学生、中学生と、成長するにつれて、あまり足繁く芸者さんの部屋へ行くということはなくなって行きました。そして、彼女が高校生になった頃、芸者さんは、当時はほとんど不治の病とされている病気に侵され、お座敷に出ることもかなわなくなり、とうとう病院に入院することになってしまいました。
その病院が、彼女の通う高校の近くにあったことから、彼女は、時々、放課後になると、両親には内緒で、こっそりと芸者さんのお見舞いに行っていたそうです。芸者さんは、その日一日の彼女の学校生活の話を聞くのを、とても楽しみにしていて、自分は、中学卒業と同時に、芸者の置屋(おきや)に奉公に出されたから、学校の話を聞くと、自分も高校生になったような気がすると、とても喜んでいたということでした。
そんなある日、彼女の授業中に、学校の職員室に、その芸者さんからの電話が入り、彼女を呼び出して欲しいというのです。先生の一人が、授業中の彼女の教室まで来て、そのことを伝え、彼女が職員室の電話に出ると、受話器の向こうで、その芸者さんが、「もう元気になったから、今日退院するよ。いままで、お見舞いに来てくれてありがとうね」と、元気な声で言うのだそうです。彼女も、嬉しくなって、「じゃァ、今日家へ帰ったら、退院のお祝いをしなくちゃね」と、答えますと、芸者さんは、何度も「ありがとうね」を繰り返して、電話を切ったのだそうです。
彼女は、既に家には芸者さんが帰って来ているものとばかり思い、喜び勇んで帰宅したところ、家の中の雰囲気が何だかいつもと違うことに気付きました。そこで、従業員の一人に訊いてみたところ、「芸者さん、亡くなったんですってよ、〇〇ちゃん」というので、彼女は、何だか狐にでもつままれているような気がして、「いつ亡くなったの?だって、あたし・・・・」と、途中で言葉を飲み込んだのだとか。それというのも、その従業員が話すには、「〇〇時頃なんだって。病院からの連絡で、〇〇ちゃんのお父さんと置屋のお母さんが、遺体を引き取りに行っているんだよ」と、いうことでした。
その時間は、正しく、彼女が職員室の電話で、芸者さんと話をした時間だったのです。
あの電話は、いったい何だったのか?自分だけが、聞いた空耳などではない。だって、電話を取り次いだ先生だって、それを聞いているんだから・・・・。
彼女は、そのことを、後日両親に話したのですが、両親は、女子高生の絵空事と、取り合おうとはしなかったそうです。
「でも、わたしは間違いなく、あの時、芸者さんと話をしたのよ」-------彼女は、今も、そのことが気になって仕方がないと言います。
ちょっと、一服・・・・・⑮
2009年03月25日
< 書 道 室 の 怪 >
皆さんは、楊貴妃(ようきひ)という女性をご存じでしょうか?世界の三大美女の一人として、エジプトのクレオパトラ、日本の小野小町と、並び称される中国は唐の時代、玄宗帝の寵愛(ちょうあい)を一身に受けた貴妃(皇后の下の位)のことです。
楊貴妃は、その抜群の美貌と、卓越した歌舞の腕前の加えて、大変聡明な女性でもあったということで、十七歳で玄宗の第十八王子寿王の妃となりましたが、玄宗本人が貴妃に惚れ込み、自らの寵妃(ちょうひ・愛人)としてしまったというものです。(一説には、彼女は、中国人と西洋人のハーフだったとも言われています)
その楊貴妃の出世を足掛かりに、楊一族は何人も皇族と縁組をするなど、目を見張るような繁栄を極めて行きますが、七七五年に、楊一族の反目による安禄山(あんろくざん)の大反乱が勃発すると、玄宗帝は楊貴妃を連れて四川に向かって逃れ、この反乱を招く原因となったのが、楊貴妃であるという部下の進言により、玄宗帝は断腸の思いで、路傍の仏堂の中で、楊貴妃を縊死(首をくくること)させたのでした。
正に、美しすぎたが故の悲劇のヒロインという訳です。
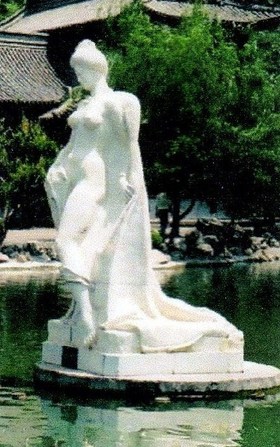
この楊貴妃が、侍女たちに見送られながら、今まさに死出の旅路へ赴こうとしている様を描いた日本画が、わたしの卒業した高校の、通称「書道室」に、額(がく)に入れられ飾られていました。作者の名前は忘れましたが、古き唐の時代の全身をゆったりと覆う背子(からぎぬ)と呼ばれる衣装に身を包んだ侍女たち数名が、丈の長い領巾(ひれ)のような袖を目元に当てて、楊貴妃との別れを惜しんでいるといった、図柄でした。
書道室は、学校内唯一の畳敷きの部屋で、広さは八畳ほどのごく小ぢんまりとした場所でした。わたしが生徒だった当時は、一年生から三年生まで、書道、美術、音楽は、生徒の選択制を採用していて、高校三年の時、わたしは書道を選択していました。書道選択の生徒は、週に二時間ほどこの書道室を利用するのですが、ある時、一緒にこの科目を選択している同級生が、妙はことを言い出したのです。
「あの書道室の額の絵だけど、ちょっと、おかしくない?」
「おかしいって、何が?」
他の生徒が訊き返しますと、その同級生の言うことには、日本画の中に描かれている侍女の人数が、日によって変わるような気がすると、言うのです。それを聞いたわたしたちは、そんな馬鹿なことがある訳ないでしょと、全く取り合わなかったのですが、不思議なことに、しばらくすると、それと同じようなことを他の生徒たちまでもが、噂し始めたのでした。
「いつもは、六人いる侍女が、五人になっている時がある・・・・」
と-------。わたしは、そんな話は気味が悪いので、出来るだけ考えないようにはしていましたし、書道室へ入っても、絶対に絵の人物の人数などは、数えないようにしていました。しかし、ある日、どうしてもそのことを確かめたいという女生徒が現われ、その生徒は、わたしたちがやめるように言うのも構わず、放課後、独りで、誰もいないその部屋へ行ってしまったのです。
その女生徒が、あとでその時のことを同級生たちに語ったのですが、何とも、不思議な出来事が起きたのだそうです。
彼女が、独り書道室内へ入り、壁に掛けてある額の中の絵の女性たちの人数を、一人二人と数えていた時のこと、やはり、人数が、昼間見た時よりも一人足りないと思った瞬間、彼女は、背後に何か人の気配のようなものを感じたのだそうです。そして、背後から首筋の辺りを、何か柔らかな布のようなもので撫でられた気がして、驚いて振り返ると、そこには、何とも恨めしそうな眼をした侍女の一人が立っていたと言うのです。
女生徒は、腰が抜けるほど驚き、そのあとは、どうやって書道室から飛び出したのかもわからぬままに、学生鞄を抱えて、転がるように学校を出たのだということでした。
それからというもの、その女生徒は決して一人では書道室へ行かなくなりました。いいえ、行けなくなってしまったのです。
あの、楊貴妃と侍女たちを描いた日本画は、まだ、あの書道室内に飾ってあるのでしょうか?そして、侍女は、ちゃんと、六人いるのでしょうか?その後、その絵の噂を耳にしたことはありません・・・・・。(^_^;)
**今回は、文章が少し短かったので、行間を開けてみました。如何だったでしょうか? う~ん、すっきりしますねェ。

では、ここで問題です。楊貴妃が好んで食べたと言われる果物は、何だったでしょうか?
答えは、 「茘枝(れいし)」-------ライチ でした。
ちょっと、一服・・・・・⑭
2009年03月17日
< ピ ア ノ 室 の 怪 >
わたしが通っていた高校は、カトリック系のミッションスクールだったという話は、以前の「ちょっと、一服・・・・・」にも書かせて頂きましたが、やはり、そういう宗教関係の学校だったからでしょうか、俗にいう七不思議とまでは行かないまでも、案外、ミステリアスな話題は、校内のあちらこちらに転がっていまして、これからお話しする「ピアノ室」にまつわる不思議な話も、生徒たちの間では、代々語り継がれていたものの一つでした。
こういう、学校の怪談めいた話に興味をお持ちの方は、「ああ、自分の卒業した学校にも、こんな話があったなァ」と、思い出されることでしょう。------では、本日も、最後まで、お付き合いください。

わたしが通っていた高校は、市街地の高台に位置していまして、構内にはカトリックの聖堂もある閑静な趣の建物でした。
そこは、音楽教育にも熱心に取り組んでいる校風でしたので、校舎内には、幾室ものピアノ室も用意されていて、そのピアノ室ごとに、一台のピアノが据えられ、室内は、厚い防音壁で覆われ、生徒は、使用時間を申し出ることで、誰でもそのピアノを利用することが出来ました。
ピアノ室を使う生徒たちの中には、もちろん、音楽大学を目指すような本格的な勉強のためにピアノの練習をする者もいれば、単に授業の合間の気分転換に曲を弾きたいという者もいます。わたしと同じクラスのその女生徒も、どちらかと言えば、後者に当たるものでしたが、ピアノを弾くのが大好きで、時々、そのピアノ室を利用しては、クラシックのピアノ曲を楽しんで弾いていました。
その彼女が、期末試験明けのある日、「ピアノ室へ一緒に行かない?あたしが弾く曲、聞いてみてよ」と、わたしを誘うので、正直、あまり気乗りはしなかったのですが、卒業までに一度くらいは、そのピアノ室なる物を見ておくのも後学のためかと思い、付いて行くことにしました。それというのも、わたしには、ピアノに対する一種の軽いトラウマがあり、何も、学校に来てまでピアノを見ることはないだろうと、思っていたものですから、多分、その時、彼女に誘われなければ、一度も、その場所へは行くことなく終わっていたに違いありません。
使用を申請する時に借りた鍵で扉を開け、ピアノ室の一つへわたしたちが入ると、その女生徒は静かに扉を閉め、おごそかな顔付きでピアノの前へ腰かけて、普段の彼女からは想像できないような力強いタッチで、「乙女の祈り」を、弾き始めました。わたしは、その間彼女の脇に立ち、(これは、『乙女の祈り』というよりも『乙女の絶叫』だなァ・・・・)などと考えながら、それを黙って聴いていたのですが、ふと気が付くと、その部屋の入り口付近の壁にある、何やら、数本の引っかき傷のような物に目が留まりました。
その壁の傷跡は、ちょうど、人間が手の指を広げて爪を立てたような感じのもので、誰かが悪戯に手で引っ掻いたのかとも思っていました。やがて、彼女のピアノ演奏も終わり、「どうだった?」と、自分の腕前の評価を訊ねるので、「うん、とってもよかったよ。〇〇ちゃんは、ピアノ上手なんだね」などと、上手を言ってから、ピアノ室の使用時間も終わりに近付いたので、二人してそこを引き揚げました。
ところが、わたしは、さっき見た壁の傷跡のことが何故か気になって仕方がありません。そこで、教室へ戻る途中で、その女生徒に、そのことをさりげなく話しました。すると、彼女は、にやにや笑いを浮かべ、「やっぱり、気が付いたんだ」と、言います。「あの傷ね、あれは、確かに、人間の引っかき傷なんだって」「誰か、悪戯でもしたの?」と、わたしが訊きますと、「そうじゃないよ。あのピアノ室、ちょっと噂があってさ。今日は、あそこの鍵しか貸してもらえなかったから、仕方なく使ったけれど、普段は、みんなあの部屋は敬遠するんだよ」と、何とも意味深長な言い方をします。わたしが、更に訊きただしますと。「これは、あくまで、先輩から聞いた噂なんだけどね----」と、前置きした後で、「今から十年ぐらい前、あのピアノ室の中で、女子生徒が一人死んだんだって-----。その生徒、夏休みに、ピアノの練習に学校へ来て、練習中に眠り込んでしまい、気が付いたら、部屋には廊下側から鍵がかけられていて、どんなに叫んでも誰も来てくれずに、閉じ込められたまま夏休みが終わって------。みんなが新学期に登校して来た時に、やっと発見されて、その時は、もう、餓死していたんだってさ」と、言います。「じゃァ、もしかして、あの引っ掻き傷って------?」わたしが半信半疑で訊きますと、彼女は、そうと、頷き、「出して欲しいと、必死に爪で引っ掻いた跡なんだって。発見された時は、爪痕があちらこちらにあって、部屋中すごい状態だったそうなんだけど、あとで上から壁紙を張って隠したんだって。でも、どうしても、あそこの一か所だけが、浮き出て来てしまうんだって・・・・」と、真顔で話します。
でも、その生徒がここへピアノの練習に来ていることは、家の人だって知っているはずだから、帰宅しないと判れば、学校へ真っ先に探しに来たんじゃないのかな?と、わたしが言いますと、彼女は、「その子、実家から通っていたんじゃなくて、家の人が借りてくれた市内のアパートで独り暮らしだったんだって。だから、誰も気付いてあげられなかったんじゃないの?」と----。「でね、今でも、夏休み頃になると、誰もいなくなった校舎の中に、ピアノの音が鳴り響くんだってさ」そういった瞬間、その女生徒が、わたしの首を、両手で絞めて来たものですから、「ギャ~ッ!
 」わたしは、大慌てで、そこから駆け出してしまいました。
」わたしは、大慌てで、そこから駆け出してしまいました。でも、本当に、そんなことがあるのでしょうか?どだい、高校生の噂話なんてものは、年数を経るうちに、いつしか尾ひれがついてどんどん膨らんでいくものですから・・・・。真偽のほどは、今もって判りません・・・・。(~_~;)
では、引き続き、「炎の氷壁」を、お読み下さい。
ちょっと、一服・・・・・⑬
2009年03月10日
< 東京大空襲のミステリー >
昭和二十年三月十日の未明、アメリカ軍による、東京の住宅地への絨毯爆撃が行われました。三十二万発もの焼夷弾が投下され、約二時間半の間に十万人の市民が命を落とすという、未曾有の大惨事となりました。これが、いわゆる東京大空襲です。人々は、焼夷弾の炸裂による激しい炎がすさまじい勢いで街を舐めつくす最中を、必死で逃げまどい、熱さに耐えかねて次々に飛び込んだ隅田川は、溺死したおびただしい数の死体で、真っ黒になったそうです。
ところが、東京がそんな大空襲に見舞われているなどという情報は、長野県の片田舎までは、届きませんでした。その時代の全国的な情報収集手段といえばラジオと新聞ぐらいのものでしたので、そのラジオ放送も、すべての番組が軍の統制下に置かれていたため、大本営が情報管理を行っており、日本に不利と思われる放送は、まったく発表されなかったというのが現実のようです。それが証拠に、戦争中に名古屋で起きた大地震で、多くの学徒動員の子供たちが軍事工場の建物の下敷きになって亡くなったことも、決して報道はされませんでした。
そのような訳で、当時、中野農商学校(現在の中野実業高校・この四月からは中野立志館高校)の三年生だった一人の少年は、まさか、自分がこれから専門学校(現在の大学に相当する)の入学試験を受けに行こうとしている東京の地が、そのような有り様になっているなどとは夢にも思わずに、母親が手作りしてくれたキビ餅と蒸(ふ)かしたジャガイモを新聞紙でくるんだ、ささやかな弁当を持って、国鉄長野駅から東京行きの汽車に乗り込んだのでした。
しかし、その汽車も、大宮駅を過ぎた辺りから走り方がひどく遅くなり、やがて、赤羽駅に着いたところで、ついに停まってしまいました。汽車は、もうそこから先は走らないというので、乗客たちは、皆大きな荷物を抱えながら、不安そうに汽車を降りて行きます。少年も、同じように下車したのですが、何せ、初めて来た場所ですから、このようなところで降ろされてしまってはここからどうやって試験会場まで行けばいいのか見当もつきません。しかも、降り立った場所は、何故か見渡す限りの瓦礫の山が連なり、辺り一面が煤けたように黒ずんで、満足な建物一つない有様です。
それもそのはず、なんと、この日は、東京大空襲が行われた翌日だったのですから------。
「いったい、ここは何処なんだ?本当に、東京なのか・・・・?」
少年は、押しつぶされそうな不安に襲われました。でも、ここで躊躇している暇などありません。試験日は、明日なのです。何としてでも、試験会場までたどり着かなくては、期待をかけて自分を送り出してくれた家族に申し訳が立ちません。
辺りは、既に夕闇が覆い始め、寒さも身に沁みる早春の街を、瓦礫を踏み越えながら、歩き始めました。途中、何度か通りすがりの人に会場の住所を訊ねてはみましたが、皆自分自身のことで精一杯で、懇切丁寧になど教えてくれる人はいません。少年が、「もう、明日の試験には間に合わないかもしれないな・・・・」と、半ば諦め掛けた時のことです。はるか遠くの真っ暗な闇の中に、ポツンとほんの小さな灯りが一つ、光っているのが見えました。少年には、その赤い小さな灯りが、何故か、唯一の希望の光のように思えたのです。
「よし、あの灯りを目指して、行くだけ行ってみよう。着いた所が何処でも、それで諦めがつくかもしれない」
少年は、そう気持ちに言い聞かせ、それからは、わき目も振らずにただまっすぐ、その灯り一つを頼りに歩いて行ったのでした。何キロ歩いたのか、足が棒のようになった頃、ようやく、その灯りのある所へとたどり着くと、そこは、二階建ての大きな古びた木造の建物でした。灯りは、そこの玄関灯だったのです。少年は、意を決して、建物の中へと入って行きました。もう身体はクタクタで、廊下の隅でもいいから、一晩休ませてもらいたいと思ったのです。
建物内には、背広姿の一人の若い男の人がいました。少年が事情を話すと、その男の人は、何とも不思議そうな顔をして、
「専門学校の試験を受けに来たって、何処の学校だね?」
と、訊くので、少年が、学校名を答えると、その男の人は突然笑い出し、
「その試験会場なら、この隣の校舎だよ。ここは、別の学校の試験会場だが、よかったら、泊まって行きたまえ。それより、きみ、何か食べる物を持っていないかな?ぼくは、今日は朝から何も口にしていないんだよ」
と、言います。
「・・・・・・・!」
少年は、あまりの偶然に驚きながらも、今朝家を出る時に母親から渡されたキビ餅を、その男の人に渡しました。男の人は、何度も礼を言いながら、そんな粗末な食べ物でも、うまいうまいと言って、頬張るので、少年もつられて、笑ってしまいました。
翌日、少年は、その建物の隣の校舎で、ちゃんと入学試験を受けることが出来、見事に、合格しました。そして、その専門学校卒業後は、明治大学(学部・現在の大学院に相当する)へ進学したそうです。
現在、少年は、八十一歳。この三月十日がやって来ると、その時の奇跡のような出来事を、改めて思い出すのだといいます。
**注釈**
昭和二十年当時の学制は、小学校六年、高等科二年、中野農商学校三年(この少年の場合)、専門学校三年(もしくは、大学の専門部三年)、大学(学部)三年というような進学システムになっていました。その上の進学を希望する者は、大学院というシステムではなく、修士(マスターズコース)、博士(ドクターズコース)と、進む訳です。または、小学校六年卒業ののち、中学校五年(女学校四年)、高等学校三年、大学(学部)という進学の方法もありました。その他にも、中学校卒業後(または、中学在学中)に、陸軍士官学校、海軍兵学校等への進学システムもありました。
では、引き続き、「炎の氷壁」を、お読み下さい。
昭和二十年三月十日の未明、アメリカ軍による、東京の住宅地への絨毯爆撃が行われました。三十二万発もの焼夷弾が投下され、約二時間半の間に十万人の市民が命を落とすという、未曾有の大惨事となりました。これが、いわゆる東京大空襲です。人々は、焼夷弾の炸裂による激しい炎がすさまじい勢いで街を舐めつくす最中を、必死で逃げまどい、熱さに耐えかねて次々に飛び込んだ隅田川は、溺死したおびただしい数の死体で、真っ黒になったそうです。

ところが、東京がそんな大空襲に見舞われているなどという情報は、長野県の片田舎までは、届きませんでした。その時代の全国的な情報収集手段といえばラジオと新聞ぐらいのものでしたので、そのラジオ放送も、すべての番組が軍の統制下に置かれていたため、大本営が情報管理を行っており、日本に不利と思われる放送は、まったく発表されなかったというのが現実のようです。それが証拠に、戦争中に名古屋で起きた大地震で、多くの学徒動員の子供たちが軍事工場の建物の下敷きになって亡くなったことも、決して報道はされませんでした。
そのような訳で、当時、中野農商学校(現在の中野実業高校・この四月からは中野立志館高校)の三年生だった一人の少年は、まさか、自分がこれから専門学校(現在の大学に相当する)の入学試験を受けに行こうとしている東京の地が、そのような有り様になっているなどとは夢にも思わずに、母親が手作りしてくれたキビ餅と蒸(ふ)かしたジャガイモを新聞紙でくるんだ、ささやかな弁当を持って、国鉄長野駅から東京行きの汽車に乗り込んだのでした。
しかし、その汽車も、大宮駅を過ぎた辺りから走り方がひどく遅くなり、やがて、赤羽駅に着いたところで、ついに停まってしまいました。汽車は、もうそこから先は走らないというので、乗客たちは、皆大きな荷物を抱えながら、不安そうに汽車を降りて行きます。少年も、同じように下車したのですが、何せ、初めて来た場所ですから、このようなところで降ろされてしまってはここからどうやって試験会場まで行けばいいのか見当もつきません。しかも、降り立った場所は、何故か見渡す限りの瓦礫の山が連なり、辺り一面が煤けたように黒ずんで、満足な建物一つない有様です。
それもそのはず、なんと、この日は、東京大空襲が行われた翌日だったのですから------。
「いったい、ここは何処なんだ?本当に、東京なのか・・・・?」
少年は、押しつぶされそうな不安に襲われました。でも、ここで躊躇している暇などありません。試験日は、明日なのです。何としてでも、試験会場までたどり着かなくては、期待をかけて自分を送り出してくれた家族に申し訳が立ちません。
辺りは、既に夕闇が覆い始め、寒さも身に沁みる早春の街を、瓦礫を踏み越えながら、歩き始めました。途中、何度か通りすがりの人に会場の住所を訊ねてはみましたが、皆自分自身のことで精一杯で、懇切丁寧になど教えてくれる人はいません。少年が、「もう、明日の試験には間に合わないかもしれないな・・・・」と、半ば諦め掛けた時のことです。はるか遠くの真っ暗な闇の中に、ポツンとほんの小さな灯りが一つ、光っているのが見えました。少年には、その赤い小さな灯りが、何故か、唯一の希望の光のように思えたのです。
「よし、あの灯りを目指して、行くだけ行ってみよう。着いた所が何処でも、それで諦めがつくかもしれない」
少年は、そう気持ちに言い聞かせ、それからは、わき目も振らずにただまっすぐ、その灯り一つを頼りに歩いて行ったのでした。何キロ歩いたのか、足が棒のようになった頃、ようやく、その灯りのある所へとたどり着くと、そこは、二階建ての大きな古びた木造の建物でした。灯りは、そこの玄関灯だったのです。少年は、意を決して、建物の中へと入って行きました。もう身体はクタクタで、廊下の隅でもいいから、一晩休ませてもらいたいと思ったのです。
建物内には、背広姿の一人の若い男の人がいました。少年が事情を話すと、その男の人は、何とも不思議そうな顔をして、
「専門学校の試験を受けに来たって、何処の学校だね?」
と、訊くので、少年が、学校名を答えると、その男の人は突然笑い出し、
「その試験会場なら、この隣の校舎だよ。ここは、別の学校の試験会場だが、よかったら、泊まって行きたまえ。それより、きみ、何か食べる物を持っていないかな?ぼくは、今日は朝から何も口にしていないんだよ」
と、言います。
「・・・・・・・!」
少年は、あまりの偶然に驚きながらも、今朝家を出る時に母親から渡されたキビ餅を、その男の人に渡しました。男の人は、何度も礼を言いながら、そんな粗末な食べ物でも、うまいうまいと言って、頬張るので、少年もつられて、笑ってしまいました。
翌日、少年は、その建物の隣の校舎で、ちゃんと入学試験を受けることが出来、見事に、合格しました。そして、その専門学校卒業後は、明治大学(学部・現在の大学院に相当する)へ進学したそうです。
現在、少年は、八十一歳。この三月十日がやって来ると、その時の奇跡のような出来事を、改めて思い出すのだといいます。
**注釈**
昭和二十年当時の学制は、小学校六年、高等科二年、中野農商学校三年(この少年の場合)、専門学校三年(もしくは、大学の専門部三年)、大学(学部)三年というような進学システムになっていました。その上の進学を希望する者は、大学院というシステムではなく、修士(マスターズコース)、博士(ドクターズコース)と、進む訳です。または、小学校六年卒業ののち、中学校五年(女学校四年)、高等学校三年、大学(学部)という進学の方法もありました。その他にも、中学校卒業後(または、中学在学中)に、陸軍士官学校、海軍兵学校等への進学システムもありました。
では、引き続き、「炎の氷壁」を、お読み下さい。
ちょっと、一服・・・・・⑫
2009年03月05日
< 前 世 の 話 >
皆さんは、前世というものを信じますか?要は、自分は誰かの生まれ変わりかもしれないと、いう話です。学生時代に読んだ英語の本に、イギリスのあるお宅の猫が、突然ピアノの鍵盤を叩きだし、素晴らしいメロディーを奏で始めたため、驚いた飼い主が、そのメロディーを調べたところ、百年も前に死んだ有名な作曲家の未完成の曲だと言うことが判り、猫になって現代へ生まれ変わったその作曲家が、ようやく、曲の続きを完成させたのだったという物語がありました。(題名は、忘れましたが・・・・)
そんな風に、まったく予期しないことで、練習したこともないのに突然何か特殊な技能を発揮したり、覚えてもいない言葉や音楽を口ずさんだりするというような、不思議な経験はありませんか?

実は、わたしには、それがあるのです。(あっ、退かないで下さい!(^_^;))あまりに突拍子もないことを言うなと?いえいえ、これからお話しすることは、別に、そう特別なことではありません。おそらく、皆さんも、一度や二度は体験したことあると思いますよ。そう・・・・・たぶん・・・・・。
わたしが、初めてパソコンなる物に触ったのは、つい昨年の十一月のことでした。何だか、とてつもない物を買ってしまったようで、キーボードを叩くことさえ恐ろしく、近所のパソコン教室へでも通おうかと電話をしてみたのですが、無料の講座は住んでいる自治体が違うということで断られ、断念。仕方がないと、マニュアル本と首っ引きでパソコンとの格闘を始めたのですが、おかしなことに、何故か、文章だけはスラスラと、打ち込むことが出来るのです。確かに、ローマ字を知っていさえすれば、そんなことは簡単だと思われるでしょうが、それとは感じがちょっと違います。文字を打ち込みながら、何だか懐かしささえ覚えるような・・・・。そんな感覚なのです。それで、そのことを従姉(いとこ)に話し、「これって、前世に何か関係があるのかな?」と、訊いたところ、「何言ってんのよ。あんた、昔、アメリカの推理作家に憧れて英文タイプ習ったことがあったじゃないの。パソコンのローマ字配列は、それと一緒なのよ。打てて当然でしょ」との返事。--------そうだった!そのこと、すっかり忘れていました。何のことはない、タネを明かせば不思議でもなんでもないことだったのです。一瞬、「わたしって、天才かも-------。もしや、前世はコンピューター技師か?」なァんて、思ったりもしのですが、「生まれ変わり説」なんて、所詮こんなものなのでしょうね。------ほら、皆さんにも、思い当たる節があったでしょう?
それから、もう一つ。わたしが小学校低学年の頃、音楽の時間に、リコーダーの授業がありまして、クラス全員がパートごとに分かれ、それぞれ種類の違うリコーダーを使うことになったのです。リコーダーの種類は、三種類で、ソプラノ、メゾソプラノ(スタンダード)、アルトがあり、わたしは運悪く、最も大きく丈も長いアルトリコーダーの笛を扱うことになってしまいました。そのうえ、リコーダーなど見るも触るも初めてで、先生が教える吹き方も、ドレミファすら皆目判りません。音階を決める穴を抑えるにも、指が届かないのです。もう、すべてが絶望的で、音楽の時間が来るのが恐怖でした。ところが、ある日、先生が皆に初めて演奏する楽譜を渡し、「今日からは、これを練習するぞ」と、その曲のレコード(CDではありません。念のため)をかけたのです。「ミララシドシラシシドレドシララシドシラシ・・・・」------その何とも物悲しいメロディーを聞いた途端、本当に不思議なことに、わたしは、それまでちんぷんかんぷんだった指の運びをまったく外すことなく、完璧に吹くことが出来たのです。しかも、その曲をレコードで聴いた直後に------。周りのクラスメートは、「何でこの曲が吹けるんだ?知っていた曲なの?」と、驚いていました。いいえ、まったく初めて聴く曲ですし、それが、リコーダーで吹けるなんて、考えてもいませんでした。でも、そのことが一つのきっかけになったのか、それからは、先生の出す課題曲は、ほとんどそつなく演奏することが出来るようになり、その時使ったリコーダーは、今も大事に引き出しの中にしまってあります。
ね、こういう経験は、皆さんにもありますよね・・・・・?え?・・・・これは、ちょっと・・・・違いますか・・・・?

では、引き続き、「炎の氷壁」を、お読み下さい。
ちょっと、一服・・・・・⑨
2009年02月07日
不 思 議 な 話
皆さん、「黒部ダム」はご存知でしょうか。長野県と富山県にまたがる雄大な北アルプス・後立山連峰に懐かれた日本最大の水力発電用のダムです。ダムの高さは186メートル。毎秒10立方メートル以上もの水量を噴き出す観光放水は実に迫力満点です。しかし、このダムを建設するにあたり、こうした極寒の地で、実に多くの貴い人命が犠牲になったこともまた事実なのです。
そうした建設中の事故で失われた人々の御霊を慰めるべく、このダムの上には建設従事者の銅像が慰霊碑として建てられています。修学旅行や遠足等で訪れる小、中、高生たちは、よくこの慰霊碑の前で記念写真を撮るものですが、わたしも中学生の頃、遠足でここを訪れ、集合写真を撮りました。その時、わたしは、最後列の真ん真ん中に立つことになってしまったのです。集合写真を撮る時は、ほとんど前列に並ぶのが常だったわたしが、この時は、何故か一番後ろに並ぶことになってしまい、何となく奇妙な感覚で写真を撮られることになったのです。
そして、後日、その写真が教室で生徒に配られたところ、何故か、みんながざわつき始めました。
「おい、ちょっと見てみろ。これ、変じゃねェか?」
男子の一人が騒ぎ始めると、
「ほんとだ!何なんだ、これ?」
「やだ!こんな所に・・・・。気味が悪い!」
女子も騒ぎ出し、とうとう担任の先生までもが、
「参ったなァ・・・・・」
と、顔をしかめてしまいました。そして、わたしの所まで来て、こう言うのです。
「この写真だけれど、あんまり気にするなよな。きっと、単なる現像ミスだよ」
「はあ・・・・・?」
見ると、何ということか、写真の中のわたしの肩に、人の手らしきものが写り込んでいるのです。わたしは、最後列に立っている訳ですから、その後ろに人がいるはずなどありません。では、この手はいったい-------!?
(ヒエェ~~~~~!?うっそ~~~~~!?)
気にするなという方が無理ですよ!------しかし、先生曰く、
「回収して現像し直すとなると、コストも時間もかかるし、これも思い出の一つだからな・・・・。ハハ・・・・ 」
」
その写真を持って帰宅したわたしが、母親に事情を説明すると、
「バカだねェ、どうして真ん中になんか立ったのよ。昔から言うでしょう。何人かで写真を撮る時は、決して真ん中には立つなって。人数が奇数の時は特に気を付けろってね」
そうなんですか。そんなこと全然知りませんでしたから・・・・・。
と、いう訳で、この写真は、今も我が家のタンスの奥にしっかりと仕舞いこまれています。でも、これって、ただの現像ミスだったのでしょうか?そうです、それしか考えられないと、現在も努めて思い込むようにしています。(~_~;)
そして、これはもう一つの不思議な話。
わたしの知り合いの若い女性が、入院している知人のお見舞いにある病院へ行った時のこと、急にトイレへ行きたくなり、さる病棟の女子用トイレへ駆け込んだのだそうです。トイレは、他に誰も使用しておらず、個室のドアはすべて開け放たれていたため、その中の一つへ飛び込んだのだとか。ところが、しばらくして、彼女が入った個室のドアが激しくノックされたのだそうです。
(いったい誰よ?他の個室があいているんだから、そっちへ入ればいいじゃない!)
そう思いながら、「入っていますよ」と、ノックをし返したのですが、またもドンドンと叩き返してくるのだそうです。しかも無言のままで-------。たぶん、この個室が気に入っていて、どうしてもここへ入りたい人なんだろうなと、思った女性が、大慌てでそこから出てみると、外には誰もおらず、
「------なによ!人騒がせなんだから」
ぶつぶつ文句を言いながら、知人が入院している病室へ戻り、今あったことを話したのだそうです。すると、その知人は、
「ふ~ん、またあったの?よく判らないんだけれど、あそこの個室へ入ると、たまにそういう現象が起きるらしいのよ。でも、別にそれ以上の危害があるっていう訳じゃないから、あんまり気にしない方がいいわよ」
と、言って、笑っていたのだとか・・・・。
「もう、やっだ~~~!」
彼女は、それからは二度とそのトイレには入るまいと思ったそうです。(~_~;)
では、引き続き、「地域医療最前線~七人の外科医~」を、お読みください。
~今日の雑感~
またまた、ブログコメントについて一言、申し上げたいことが・・・・。
これは、わたしが経験したことですが、ある人のブログにコメント(私見ではなく、あくまでも一般論としての意見です)を書き込んだところ、どうもそのブログ管理人と意見が異なっていたらしく、いつまで待ってもコメントの返事がありません。そのうちに、かなり時間がたってから、通りすがりのコメンテーターが、そのブログ管理人のコメント欄に、わたしのコメントに対する反論のコメントを書き込んで来られました。しかし、どうも、そのコメンテーターは、わたしがコメントを書き込んだブログ管理者ご本人のようなのです。つまり、ご自分のニックネームでは面と向かって反論が出来ず、他人になり済まして意思表示をされたようで・・・・。紛らわしいというか、情けないというか・・・・。
きみの意見は常に的確で、筋もとおっていて、正義溢れるものなのだから、もっと勇気を持って下さい!
「今日の一枚」-------『新選組・池田屋』
皆さん、「黒部ダム」はご存知でしょうか。長野県と富山県にまたがる雄大な北アルプス・後立山連峰に懐かれた日本最大の水力発電用のダムです。ダムの高さは186メートル。毎秒10立方メートル以上もの水量を噴き出す観光放水は実に迫力満点です。しかし、このダムを建設するにあたり、こうした極寒の地で、実に多くの貴い人命が犠牲になったこともまた事実なのです。
そうした建設中の事故で失われた人々の御霊を慰めるべく、このダムの上には建設従事者の銅像が慰霊碑として建てられています。修学旅行や遠足等で訪れる小、中、高生たちは、よくこの慰霊碑の前で記念写真を撮るものですが、わたしも中学生の頃、遠足でここを訪れ、集合写真を撮りました。その時、わたしは、最後列の真ん真ん中に立つことになってしまったのです。集合写真を撮る時は、ほとんど前列に並ぶのが常だったわたしが、この時は、何故か一番後ろに並ぶことになってしまい、何となく奇妙な感覚で写真を撮られることになったのです。
そして、後日、その写真が教室で生徒に配られたところ、何故か、みんながざわつき始めました。
「おい、ちょっと見てみろ。これ、変じゃねェか?」
男子の一人が騒ぎ始めると、
「ほんとだ!何なんだ、これ?」
「やだ!こんな所に・・・・。気味が悪い!」
女子も騒ぎ出し、とうとう担任の先生までもが、
「参ったなァ・・・・・」
と、顔をしかめてしまいました。そして、わたしの所まで来て、こう言うのです。
「この写真だけれど、あんまり気にするなよな。きっと、単なる現像ミスだよ」
「はあ・・・・・?」
見ると、何ということか、写真の中のわたしの肩に、人の手らしきものが写り込んでいるのです。わたしは、最後列に立っている訳ですから、その後ろに人がいるはずなどありません。では、この手はいったい-------!?
(ヒエェ~~~~~!?うっそ~~~~~!?)
気にするなという方が無理ですよ!------しかし、先生曰く、
「回収して現像し直すとなると、コストも時間もかかるし、これも思い出の一つだからな・・・・。ハハ・・・・
 」
」その写真を持って帰宅したわたしが、母親に事情を説明すると、
「バカだねェ、どうして真ん中になんか立ったのよ。昔から言うでしょう。何人かで写真を撮る時は、決して真ん中には立つなって。人数が奇数の時は特に気を付けろってね」
そうなんですか。そんなこと全然知りませんでしたから・・・・・。
と、いう訳で、この写真は、今も我が家のタンスの奥にしっかりと仕舞いこまれています。でも、これって、ただの現像ミスだったのでしょうか?そうです、それしか考えられないと、現在も努めて思い込むようにしています。(~_~;)
そして、これはもう一つの不思議な話。
わたしの知り合いの若い女性が、入院している知人のお見舞いにある病院へ行った時のこと、急にトイレへ行きたくなり、さる病棟の女子用トイレへ駆け込んだのだそうです。トイレは、他に誰も使用しておらず、個室のドアはすべて開け放たれていたため、その中の一つへ飛び込んだのだとか。ところが、しばらくして、彼女が入った個室のドアが激しくノックされたのだそうです。
(いったい誰よ?他の個室があいているんだから、そっちへ入ればいいじゃない!)
そう思いながら、「入っていますよ」と、ノックをし返したのですが、またもドンドンと叩き返してくるのだそうです。しかも無言のままで-------。たぶん、この個室が気に入っていて、どうしてもここへ入りたい人なんだろうなと、思った女性が、大慌てでそこから出てみると、外には誰もおらず、
「------なによ!人騒がせなんだから」
ぶつぶつ文句を言いながら、知人が入院している病室へ戻り、今あったことを話したのだそうです。すると、その知人は、
「ふ~ん、またあったの?よく判らないんだけれど、あそこの個室へ入ると、たまにそういう現象が起きるらしいのよ。でも、別にそれ以上の危害があるっていう訳じゃないから、あんまり気にしない方がいいわよ」
と、言って、笑っていたのだとか・・・・。

「もう、やっだ~~~!」
彼女は、それからは二度とそのトイレには入るまいと思ったそうです。(~_~;)
では、引き続き、「地域医療最前線~七人の外科医~」を、お読みください。
~今日の雑感~
またまた、ブログコメントについて一言、申し上げたいことが・・・・。
これは、わたしが経験したことですが、ある人のブログにコメント(私見ではなく、あくまでも一般論としての意見です)を書き込んだところ、どうもそのブログ管理人と意見が異なっていたらしく、いつまで待ってもコメントの返事がありません。そのうちに、かなり時間がたってから、通りすがりのコメンテーターが、そのブログ管理人のコメント欄に、わたしのコメントに対する反論のコメントを書き込んで来られました。しかし、どうも、そのコメンテーターは、わたしがコメントを書き込んだブログ管理者ご本人のようなのです。つまり、ご自分のニックネームでは面と向かって反論が出来ず、他人になり済まして意思表示をされたようで・・・・。紛らわしいというか、情けないというか・・・・。
きみの意見は常に的確で、筋もとおっていて、正義溢れるものなのだから、もっと勇気を持って下さい!
「今日の一枚」-------『新選組・池田屋』
ちょっと、一服・・・・・⑦
2009年01月24日
あ る 外 科 医 の 話
この前も書きましたが、わたし、約一年ほど前に身体の不調で入院しました。あまり、メジャーな病気ではないのでご存じの方はごく少数だと思いますが、「原発性副甲状腺機能亢進症」と、いう病気です。原発と言いましても、別に原子力発電とは何の関係もありません。そこに患部が特化しているという意味だそうです。患者の数はといいますと、これは、ある内科医の先生のお話なんですが、
「たとえば、人口約六万人の市があったとして、その市民のうち女性が半分として、そのうちの約三百人ぐらいが発症する可能性のある病気なんだよ」
とのこと。つまり、女性の発症率が高いようなんですが、男性ももちろん例外ではなく・・・・。つまりは、誰にでもリスクはあるらしいのです。
ところで、「副甲状腺」て、どこにあるの?ということなんですが、皆さん、「甲状腺」は、ご存知ですよね。そうです。首の下の方で、咽喉側にある、ちょうど蝶々が羽を広げたような格好をしている内分泌腺です。その「甲状腺」の蝶々の羽の四隅に、一つずつ、米粒大の小さなものが付いているのですが、この四つが「副甲状腺」というものなのです。「機能亢進症」とは、その「副甲状腺」の一つが腫れて、大きくなり、ホルモンが過剰に分泌され、身体に支障をきたすというものなのです。
そうなると、これを治療するには、現在の医学では、手術で患部を取ってしまうしか手がない訳で、「甲状腺」の治療と違って、薬で抑えるということは、一切選択肢にないのが現状のようです。
-------で、それでも手術を回避したいとういう悪あがきの末、体中の激痛に耐えられず、ついに、覚悟を決めました。(この激痛の理由は、また折を見てお話したいと思います)
前置きが長くなってしまいましたが、本題はその入院中の出来事です。
わたしの執刀医は、三十代半ばの若い男性外科医の先生でした。中肉中背で、いつも医療用マスクをかけたままで、ほとんど素顔を見せたことがありません。看護師さんや薬剤師さんには時々顔を見せるらしいのですが、患者には皆無と言ってもいいほどの徹底ぶりでした。他の先生方は、いつも素顔のままで患者さんに接していましたので、その徹底ぶりが際立っていたのです。必然的に、患者さんたちの間では、その先生の素顔がどのようなものか話題になりました。(なにせ、患者は皆暇をもてあまし気味ですから、そんな他愛もないことが、気晴らしになるもので・・・・)
「ねえ、知っています?〇〇先生って、まだ独身らしいですよ」
「そうなんですか。でも、一度も、あの先生の素顔を見たことありませんねェ」
「わたしもですよ。どうしていつもマスクをしているんでしょうね?」
「退院までには、一度拝見してみたいものですね」
そんな会話を交わしていた次の日です。なんと、その先生がマスクを外して回診に見えたのです。これには、皆びっくりしました。
「どうして、わたしたちの話が判ったんでしょうね?」
「看護師さんが伝えてくれたんじゃないですか?」
「でも、あの時、看護師さんは、この病室にはいませんでしたよ」
「もしや、ナースコールを押しっぱなしだったとか・・・?」
ナースコールの機械は、ボタンを押すと看護師さんの方へ、患者の声が伝わるように出来ています。が、その時は誰もナースコールを押していた人などいません。
「不思議ですねェ・・・・」
先生がマスクを外してきたのは、本当に単なる偶然だったのでしょうか?でも、次の回診からは、またマスクをして来られました。つまり、わたしが、その先生の素顔を見ることが出来たのは、後にも先にも、その一度限りだった訳です。
そして、また、不思議なことが・・・・。
手術前、病気のせいで、わたしの歯はとても弱くなり、固いものは全く食べられない状態でした。でも、麻酔科医の先生に、、
「大丈夫、手術が終われば、また何でもガリガリ食べられるようになりますよ」
と、おっしゃって頂き、正にその通りになりました。
そこで、やはり同じ病室の患者さんに、
「リンゴも食べられるようになったんですよ」
と、何気なく話したところ、翌日、わたしのその担当医の先生が、
「リンゴ、食べられるようになったんですってね。よかったですね」
と、ニコニコ微笑んで(マスクをかけていても、これは判ります)話されるのです。
「・・・・どうして、判ったのかな?」
思わず首を傾げてしまいました。
「ぼく、何処へも行きませんよ・・・・」
先生は、おっしゃっていましたが、結局、それから半年後に、別の病院への転勤が決まり、異動して行かれました。
ところが、不思議なことは、そのあとも続くのです。
その先生が病院を去られてから、しばらくして、わたしは、何度も同じ夢を見るようになりました。夢のシチュエーションはそのつど違うのですが、夢の中で必ず電話がかかってくるのです。
「〇〇先生から電話------」
と、言われて、受話器を取るのですが、相手はいつも無言のままです。そのうちに、また、外来通院の日が来て、病院へ行ったところ、あるスタッフの方が、わたしの所へ来て、
「この前、〇〇先生に会いましたよ。何だか、あなたのことを話していました。急に転勤になってしまったのは、自分にも予想外だったって言っていましたよ」
と、教えて下さいました。その方には、夢の話はしませんでしたが、もしや、そのことを伝えたかったのでしょうか・・・・?
穿ち過ぎかもしれませんが、そんなことを、ふっと、考えました。それから、電話の夢はまったく見ていません。
先生は、今も何処かの病院で、あの不思議な能力(少なくともわたしにはそう思えます)を、発揮されているのでしょうか?
ちょっと、ファンタスティックな外科医との出会いは、とかく暗くなりがちな入院生活を、ちょっぴりミステリアスな愉快な気分で乗り越えさせてくれました。
では、引き続き、「地域医療最前線~七人の外科医~」を、お読みください。
「今日の一枚」-------『都の夢』
この前も書きましたが、わたし、約一年ほど前に身体の不調で入院しました。あまり、メジャーな病気ではないのでご存じの方はごく少数だと思いますが、「原発性副甲状腺機能亢進症」と、いう病気です。原発と言いましても、別に原子力発電とは何の関係もありません。そこに患部が特化しているという意味だそうです。患者の数はといいますと、これは、ある内科医の先生のお話なんですが、
「たとえば、人口約六万人の市があったとして、その市民のうち女性が半分として、そのうちの約三百人ぐらいが発症する可能性のある病気なんだよ」
とのこと。つまり、女性の発症率が高いようなんですが、男性ももちろん例外ではなく・・・・。つまりは、誰にでもリスクはあるらしいのです。
ところで、「副甲状腺」て、どこにあるの?ということなんですが、皆さん、「甲状腺」は、ご存知ですよね。そうです。首の下の方で、咽喉側にある、ちょうど蝶々が羽を広げたような格好をしている内分泌腺です。その「甲状腺」の蝶々の羽の四隅に、一つずつ、米粒大の小さなものが付いているのですが、この四つが「副甲状腺」というものなのです。「機能亢進症」とは、その「副甲状腺」の一つが腫れて、大きくなり、ホルモンが過剰に分泌され、身体に支障をきたすというものなのです。
そうなると、これを治療するには、現在の医学では、手術で患部を取ってしまうしか手がない訳で、「甲状腺」の治療と違って、薬で抑えるということは、一切選択肢にないのが現状のようです。
-------で、それでも手術を回避したいとういう悪あがきの末、体中の激痛に耐えられず、ついに、覚悟を決めました。(この激痛の理由は、また折を見てお話したいと思います)
前置きが長くなってしまいましたが、本題はその入院中の出来事です。
わたしの執刀医は、三十代半ばの若い男性外科医の先生でした。中肉中背で、いつも医療用マスクをかけたままで、ほとんど素顔を見せたことがありません。看護師さんや薬剤師さんには時々顔を見せるらしいのですが、患者には皆無と言ってもいいほどの徹底ぶりでした。他の先生方は、いつも素顔のままで患者さんに接していましたので、その徹底ぶりが際立っていたのです。必然的に、患者さんたちの間では、その先生の素顔がどのようなものか話題になりました。(なにせ、患者は皆暇をもてあまし気味ですから、そんな他愛もないことが、気晴らしになるもので・・・・)
「ねえ、知っています?〇〇先生って、まだ独身らしいですよ」
「そうなんですか。でも、一度も、あの先生の素顔を見たことありませんねェ」
「わたしもですよ。どうしていつもマスクをしているんでしょうね?」
「退院までには、一度拝見してみたいものですね」
そんな会話を交わしていた次の日です。なんと、その先生がマスクを外して回診に見えたのです。これには、皆びっくりしました。
「どうして、わたしたちの話が判ったんでしょうね?」
「看護師さんが伝えてくれたんじゃないですか?」
「でも、あの時、看護師さんは、この病室にはいませんでしたよ」
「もしや、ナースコールを押しっぱなしだったとか・・・?」
ナースコールの機械は、ボタンを押すと看護師さんの方へ、患者の声が伝わるように出来ています。が、その時は誰もナースコールを押していた人などいません。
「不思議ですねェ・・・・」
先生がマスクを外してきたのは、本当に単なる偶然だったのでしょうか?でも、次の回診からは、またマスクをして来られました。つまり、わたしが、その先生の素顔を見ることが出来たのは、後にも先にも、その一度限りだった訳です。
そして、また、不思議なことが・・・・。
手術前、病気のせいで、わたしの歯はとても弱くなり、固いものは全く食べられない状態でした。でも、麻酔科医の先生に、、
「大丈夫、手術が終われば、また何でもガリガリ食べられるようになりますよ」
と、おっしゃって頂き、正にその通りになりました。
そこで、やはり同じ病室の患者さんに、
「リンゴも食べられるようになったんですよ」
と、何気なく話したところ、翌日、わたしのその担当医の先生が、
「リンゴ、食べられるようになったんですってね。よかったですね」
と、ニコニコ微笑んで(マスクをかけていても、これは判ります)話されるのです。
「・・・・どうして、判ったのかな?」
思わず首を傾げてしまいました。
「ぼく、何処へも行きませんよ・・・・」
先生は、おっしゃっていましたが、結局、それから半年後に、別の病院への転勤が決まり、異動して行かれました。
ところが、不思議なことは、そのあとも続くのです。
その先生が病院を去られてから、しばらくして、わたしは、何度も同じ夢を見るようになりました。夢のシチュエーションはそのつど違うのですが、夢の中で必ず電話がかかってくるのです。
「〇〇先生から電話------」
と、言われて、受話器を取るのですが、相手はいつも無言のままです。そのうちに、また、外来通院の日が来て、病院へ行ったところ、あるスタッフの方が、わたしの所へ来て、
「この前、〇〇先生に会いましたよ。何だか、あなたのことを話していました。急に転勤になってしまったのは、自分にも予想外だったって言っていましたよ」
と、教えて下さいました。その方には、夢の話はしませんでしたが、もしや、そのことを伝えたかったのでしょうか・・・・?
穿ち過ぎかもしれませんが、そんなことを、ふっと、考えました。それから、電話の夢はまったく見ていません。
先生は、今も何処かの病院で、あの不思議な能力(少なくともわたしにはそう思えます)を、発揮されているのでしょうか?
ちょっと、ファンタスティックな外科医との出会いは、とかく暗くなりがちな入院生活を、ちょっぴりミステリアスな愉快な気分で乗り越えさせてくれました。
では、引き続き、「地域医療最前線~七人の外科医~」を、お読みください。
「今日の一枚」-------『都の夢』
ちょっと、一服・・・・・⑥
2009年01月17日
< 冬 の 夜 長 の 物 語 >
しんしんと雪が降っています。
白く深い闇の底から延々と、音もなく降りそそいで来る雪を見ていると、かつて山ノ内町の地元のお年寄りから聞いた何とも奇妙な物語を思い出します。
今夜は、そんなお話を二つご紹介しましょう。
き つ ね
あれは、戦後の昭和二十年代、北信濃の片田舎にはまだ自動車などは数えるほどしか走っておらず、たまに長野電鉄のボンネット・バスが、チェーンの音を響かせながら志賀高原へと続く雪深いわだちの坂道を、ゆっくりとのぼっていた時代。
このあたりの人々の移動手段は、もっぱら徒歩という、何とものんびりとした頃のお話です。
やはり、今夜のように雪がしんしんと降り続き、道路につもった雪も、すでに大人の膝丈あたりまでに達していた夜の八時過ぎ、一人若い男が中野町(現在の中野市)にある親戚の家で夕飯をごちそうになった後、平穏村(ひらおむら・現在の山ノ内町)の自宅へと帰ろうとしていました。
「今晩は、こんな大雪だし、家(ここ)へ泊っていけばいい。おめェの寝る部屋も布団も、母ちゃんに用意させるからさ」
親戚の者たちは、口々に若者を引き留めましたが、
「大丈夫だ。酒も入(へえ)っているから、温(のく)てやさ。このまま一気に突っ走れば、すぐ着くから心配いらね」
若者は答えると、ウールのオーバーを頭からすっぽりかぶり、雪の中を帰路についたのだそうです。
兵隊帰りの若者には、雪の夜道など決して怖いものではありません。鼻歌まじりのほろ酔いかげんで、深くつもった雪をかき分けかき分け、ようやく、平穏村の夜間瀬川にかかる橋のたもとまでたどりつくと、
「ここを渡れば、家はすぐ先だ。大したこたァなかったな」
そんな独り言をつぶやきながら、橋を渡り始めたのでした。
しかし、橋を渡り終えたとき、辺りの風景が、何かおかしいのです。
「あれ?-----ここは、さっき渡り始めたところじゃねェか?」
奇妙に思った若者は、
「酔っ払っちまったかな?-----いま、橋を渡ったような気がしたんだが、気のせいだったか・・・」
気を取り直して、もう一度渡り始めました。橋の欄干を確かめながら、足早に渡り終えて、顔を上げると、
「--------!?なんでだ?また、同じ場所じゃねェか!」
若者は、きみが悪くなって、今度は、目をつぶって走るように渡りました。そして、恐る恐る目を開けると、
「うわァ!やっぱり、また元に戻っている!」
心底恐ろしくなった若者は、一度来た道を引き返し、その夜はやはり親戚の家で泊めてもらったのだそうです。
これのことは、のちのち人々の噂にものぼり、
「ありゃァ、キツネに化やかされたに違いない」
と、言われたとか・・・・。
こうした不思議な現象を、このあたりの人々は、今でも「夜間瀬川原のきつね」と、呼ぶそうです。
訪 問 者
信州の北部、山ノ内町の志賀高原へ続く国道の入口ともいう地区に、上林温泉と呼ばれる一帯があります。最近は、「スノー・モンキー」の写真でも世界的に名前の通った「地獄谷野猿公苑」を、背後に控える美しい林道沿いに、数件の旅館やホテル、博物館などが建つ、観光名所の一つです。
しかし、まだ、昭和三十年代の頃は、避暑に訪れる文化人や外国人が長逗留する、ひなびた温泉郷の一つでした。
そんな、ある寒い冬の夜、夕方から降り始めた雪はしだいに本降りとなり、風も加わって吹雪に近い状態となっていました。上林温泉にある一軒の小さな旅館では、この日の泊り客は一人もなく、午後六時を過ぎた頃には、若い女将さんが、玄関の硝子戸を閉めて鍵をかけ、一日の仕事を終えようとしていました。
ところが、女将さんが帳場で台帳の整理をしていた時のこと、にわかに、玄関の硝子戸をガタガタと、たたく音がしました。
「こんな吹雪の中を、いったい誰が来たんだろう?」
訝しがりながらも女将さんが玄関の引き戸を開けると、そこには、薄手のコートらしきものを着て、真っ白に雪をかぶった中年の男性が一人立っていたのです。その男性は、年に二、三度この旅館に湯治に訪れる常連客でした。
「あれまァ、こんな雪の中をよく来なさった。さあさあ、早く座敷へ上ってください。お寒かったでしょう?」
女将さんはその男性を急いで奥の座敷へ通すと、囲炉裏のそばへ座らせました。
「お身体の方はよろしいんですか?この前ご予約をいただのに、体調が良くないからと、奥様から予約の取り消しのお電話があったばかりなんですけど・・・・」
女将が気遣うと、男性は寂しそうな笑みを浮かべ、
「あれは女房の気の回しすぎなんですよ。今日は、どうしてもこの旅館の名物の、女将さんの手作りの『おやき』が食べたくなって、つい来てしまいました」
「それはそれは、ありがとうございます。では、さっそくこしらえますから、存分に召し上がってくださいね」
それから、女将さんは急いで、『おやき』作りに取り掛かり、囲炉裏につるしたホウロクで焼いたあつあつのところを、男性の前に出しました。
「ありがとう・・・・」
男性は、それを手に取ると、そっと一口かじり、突然涙をポロポロと、こぼしたのでした。驚く女将さんに、男性は、
「やっと思いがかないました・・・・」
そう言うなり、一気に『おやき』を二つ平らげると、
「では、今夜はこれで帰ります」
と、腰を上げたので、
「こんな吹雪の中をお帰りになるなんて、無茶ですよ。一晩だけでもお泊りになった方が・・・・。バスも、もう湯田中駅までの最終が出てしまっていますよ」
女将さんは、懸命に引き留めましたが、男性は、明日仕事があるのでと、聞きません。それでは、今日のお代は結構ですから、ハイヤーを呼びましょうと、電話をかけ、運転手には上林温泉の入口あたりで待っていてくれるように頼みました。
男性は、丁寧に礼を言うと、女将さんに見送られながらあたり一面真っ白な雪の中を去って行きました。
すると、しばらくして旅館にハイヤーの運転手が雪だらけになりながら入ってきたのです。
「どうしたの、観光さん(ハイヤー会社の通称)?お客さんは、とっくにここを出て行ったんだけど・・・」
「いつまで待っていても、上林温泉入口へお客さんが現れないから、まだ旅館かと思って来てみたんだよ。まさか、道に迷ったんじゃないだろうね?」
「そんなこと・・・・」
もしや、遭難-------?おかみさんの頭の中をいやな予感が駆け巡った時でした。突然、帳場の電話のベルが鳴り、女将さんが受話器を取ってみると、相手は、今帰ったばかりの男性客の奥さんでした。
「〇〇旅館さんですか?わたし、〇〇の家内です。いつも主人がお世話になりまして、ありがとうございました。主人、たった今、病院で息を引き取りました。生前、〇〇旅館さんには、礼を言っておいてくれと申しておりましたので、こうしてご連絡を差し上げた訳でして・・・・」
「-------------!!」
女将さんの受話器を握る手が、思わず震えました。そして、相手の話に耳を傾けながら、何気なく、そこから見える座敷の、さっき男性客の食べていた『おやき』をのせた皿に目をやります。と、空になっていたはずの皿の上に、まだ『おやき』が二つ手つかずのままに残されているではありませんか。電話の声は、さらにこう続けました。
「実は、主人、亡くなる直前まで、そちらの『おやき』をもう一遍だけ食べたかったなァと、申しておりまして・・・。それで、わたし、近いうちにそちらさまへ伺わせていただきたいと思いますので、その節は、主人の大好きだった『おやき』を、作って頂きたいのですが、よろしくお願いいたします」
女将さんは、その言葉が終らぬうちに、受話器を持ったまま、とうとうその場にへたり込んでしまったのだそうです。
如何でしたか?------雪の夜には、時に思わぬ不思議と出会うことがあるそうです。あなたのお隣にいる人は、本当に、ご本人でしょうか?明日、お出かけから戻られる時は、決して、ご油断なさらぬように・・・・・。何処かで、キツネが見ているかもしれません。
では、おやすみなさいませ。
引き続き、「地域医療最前線~七人の外科医~」を、お読みください。
*訂正*
これのことは、------- このことは、 の間違いです。
この前ご予約をいただのに、------- この前ご予約をいただいたのに、 の間違いです。
しんしんと雪が降っています。
白く深い闇の底から延々と、音もなく降りそそいで来る雪を見ていると、かつて山ノ内町の地元のお年寄りから聞いた何とも奇妙な物語を思い出します。
今夜は、そんなお話を二つご紹介しましょう。
き つ ね

あれは、戦後の昭和二十年代、北信濃の片田舎にはまだ自動車などは数えるほどしか走っておらず、たまに長野電鉄のボンネット・バスが、チェーンの音を響かせながら志賀高原へと続く雪深いわだちの坂道を、ゆっくりとのぼっていた時代。
このあたりの人々の移動手段は、もっぱら徒歩という、何とものんびりとした頃のお話です。
やはり、今夜のように雪がしんしんと降り続き、道路につもった雪も、すでに大人の膝丈あたりまでに達していた夜の八時過ぎ、一人若い男が中野町(現在の中野市)にある親戚の家で夕飯をごちそうになった後、平穏村(ひらおむら・現在の山ノ内町)の自宅へと帰ろうとしていました。
「今晩は、こんな大雪だし、家(ここ)へ泊っていけばいい。おめェの寝る部屋も布団も、母ちゃんに用意させるからさ」
親戚の者たちは、口々に若者を引き留めましたが、
「大丈夫だ。酒も入(へえ)っているから、温(のく)てやさ。このまま一気に突っ走れば、すぐ着くから心配いらね」
若者は答えると、ウールのオーバーを頭からすっぽりかぶり、雪の中を帰路についたのだそうです。
兵隊帰りの若者には、雪の夜道など決して怖いものではありません。鼻歌まじりのほろ酔いかげんで、深くつもった雪をかき分けかき分け、ようやく、平穏村の夜間瀬川にかかる橋のたもとまでたどりつくと、
「ここを渡れば、家はすぐ先だ。大したこたァなかったな」
そんな独り言をつぶやきながら、橋を渡り始めたのでした。
しかし、橋を渡り終えたとき、辺りの風景が、何かおかしいのです。
「あれ?-----ここは、さっき渡り始めたところじゃねェか?」
奇妙に思った若者は、
「酔っ払っちまったかな?-----いま、橋を渡ったような気がしたんだが、気のせいだったか・・・」
気を取り直して、もう一度渡り始めました。橋の欄干を確かめながら、足早に渡り終えて、顔を上げると、
「--------!?なんでだ?また、同じ場所じゃねェか!」
若者は、きみが悪くなって、今度は、目をつぶって走るように渡りました。そして、恐る恐る目を開けると、
「うわァ!やっぱり、また元に戻っている!」
心底恐ろしくなった若者は、一度来た道を引き返し、その夜はやはり親戚の家で泊めてもらったのだそうです。
これのことは、のちのち人々の噂にものぼり、
「ありゃァ、キツネに化やかされたに違いない」
と、言われたとか・・・・。
こうした不思議な現象を、このあたりの人々は、今でも「夜間瀬川原のきつね」と、呼ぶそうです。
訪 問 者

信州の北部、山ノ内町の志賀高原へ続く国道の入口ともいう地区に、上林温泉と呼ばれる一帯があります。最近は、「スノー・モンキー」の写真でも世界的に名前の通った「地獄谷野猿公苑」を、背後に控える美しい林道沿いに、数件の旅館やホテル、博物館などが建つ、観光名所の一つです。
しかし、まだ、昭和三十年代の頃は、避暑に訪れる文化人や外国人が長逗留する、ひなびた温泉郷の一つでした。
そんな、ある寒い冬の夜、夕方から降り始めた雪はしだいに本降りとなり、風も加わって吹雪に近い状態となっていました。上林温泉にある一軒の小さな旅館では、この日の泊り客は一人もなく、午後六時を過ぎた頃には、若い女将さんが、玄関の硝子戸を閉めて鍵をかけ、一日の仕事を終えようとしていました。
ところが、女将さんが帳場で台帳の整理をしていた時のこと、にわかに、玄関の硝子戸をガタガタと、たたく音がしました。
「こんな吹雪の中を、いったい誰が来たんだろう?」
訝しがりながらも女将さんが玄関の引き戸を開けると、そこには、薄手のコートらしきものを着て、真っ白に雪をかぶった中年の男性が一人立っていたのです。その男性は、年に二、三度この旅館に湯治に訪れる常連客でした。
「あれまァ、こんな雪の中をよく来なさった。さあさあ、早く座敷へ上ってください。お寒かったでしょう?」
女将さんはその男性を急いで奥の座敷へ通すと、囲炉裏のそばへ座らせました。
「お身体の方はよろしいんですか?この前ご予約をいただのに、体調が良くないからと、奥様から予約の取り消しのお電話があったばかりなんですけど・・・・」
女将が気遣うと、男性は寂しそうな笑みを浮かべ、
「あれは女房の気の回しすぎなんですよ。今日は、どうしてもこの旅館の名物の、女将さんの手作りの『おやき』が食べたくなって、つい来てしまいました」
「それはそれは、ありがとうございます。では、さっそくこしらえますから、存分に召し上がってくださいね」
それから、女将さんは急いで、『おやき』作りに取り掛かり、囲炉裏につるしたホウロクで焼いたあつあつのところを、男性の前に出しました。
「ありがとう・・・・」
男性は、それを手に取ると、そっと一口かじり、突然涙をポロポロと、こぼしたのでした。驚く女将さんに、男性は、
「やっと思いがかないました・・・・」
そう言うなり、一気に『おやき』を二つ平らげると、
「では、今夜はこれで帰ります」
と、腰を上げたので、
「こんな吹雪の中をお帰りになるなんて、無茶ですよ。一晩だけでもお泊りになった方が・・・・。バスも、もう湯田中駅までの最終が出てしまっていますよ」
女将さんは、懸命に引き留めましたが、男性は、明日仕事があるのでと、聞きません。それでは、今日のお代は結構ですから、ハイヤーを呼びましょうと、電話をかけ、運転手には上林温泉の入口あたりで待っていてくれるように頼みました。
男性は、丁寧に礼を言うと、女将さんに見送られながらあたり一面真っ白な雪の中を去って行きました。
すると、しばらくして旅館にハイヤーの運転手が雪だらけになりながら入ってきたのです。
「どうしたの、観光さん(ハイヤー会社の通称)?お客さんは、とっくにここを出て行ったんだけど・・・」
「いつまで待っていても、上林温泉入口へお客さんが現れないから、まだ旅館かと思って来てみたんだよ。まさか、道に迷ったんじゃないだろうね?」
「そんなこと・・・・」
もしや、遭難-------?おかみさんの頭の中をいやな予感が駆け巡った時でした。突然、帳場の電話のベルが鳴り、女将さんが受話器を取ってみると、相手は、今帰ったばかりの男性客の奥さんでした。
「〇〇旅館さんですか?わたし、〇〇の家内です。いつも主人がお世話になりまして、ありがとうございました。主人、たった今、病院で息を引き取りました。生前、〇〇旅館さんには、礼を言っておいてくれと申しておりましたので、こうしてご連絡を差し上げた訳でして・・・・」
「-------------!!」
女将さんの受話器を握る手が、思わず震えました。そして、相手の話に耳を傾けながら、何気なく、そこから見える座敷の、さっき男性客の食べていた『おやき』をのせた皿に目をやります。と、空になっていたはずの皿の上に、まだ『おやき』が二つ手つかずのままに残されているではありませんか。電話の声は、さらにこう続けました。
「実は、主人、亡くなる直前まで、そちらの『おやき』をもう一遍だけ食べたかったなァと、申しておりまして・・・。それで、わたし、近いうちにそちらさまへ伺わせていただきたいと思いますので、その節は、主人の大好きだった『おやき』を、作って頂きたいのですが、よろしくお願いいたします」
女将さんは、その言葉が終らぬうちに、受話器を持ったまま、とうとうその場にへたり込んでしまったのだそうです。
如何でしたか?------雪の夜には、時に思わぬ不思議と出会うことがあるそうです。あなたのお隣にいる人は、本当に、ご本人でしょうか?明日、お出かけから戻られる時は、決して、ご油断なさらぬように・・・・・。何処かで、キツネが見ているかもしれません。
では、おやすみなさいませ。
引き続き、「地域医療最前線~七人の外科医~」を、お読みください。
*訂正*
これのことは、------- このことは、 の間違いです。
この前ご予約をいただのに、------- この前ご予約をいただいたのに、 の間違いです。
ちょっと、一服・・・・・③
2008年12月27日

ところで、アクセサリーというものには、持ち主や贈り手の思いなり人生模様なりが如実に宿ることがあるといわれていますよね。持ち主の心情や生き様が波乱に満ちていればいるほど、それらにまつわる逸話の類も彩りを増すというものなのでしょう。
それほど大それた話ではないのですが、つい過日、わたしにも一つのキーホルダーにかかわるちょっと不思議な出来事がありました。わたしは、昨年秋に患った病気のために時々病院通いをしているのですが、その病院でのことです。
わたしは、いつも持ち歩いているデニム地のショッピングバッグに、その日たまたま、以前に甥からもらった修学旅行土産のキーホルダーをつけて行ったのです。わたしが新選組や幕末ものが好きなことを知っている甥が、修学旅行先の京都から買ってきてくれたもので、私の気に入りの一つでした。透明なプラスティックの中に副長・土方歳三(と、勝手に思っているのですが)らしき新選組隊士が一人刀をさして佇んでおり、『新選組』の文字が入っている小さなキーホルダーです。
診察までにまだ少し時間があったため、病院の中を歩き回っているうちに、いつの間にかそれを紛失してしまっていたのです。何処で落としたのか判らず、焦りました。せっかく京都から買ってきた甥の気持ちを考えると、
「なくしちゃった-------」
では、済みそうにもありません。実に、困りました。もしかしたら、バッグの中に落ちているのかも・・・・?とも思い、中身をすべて放り出して確かめましたが、やはり見つからず・・・・・。どうにも仕方がないと、腹をくくってあきらめることにしました。
それから、約一月がたち、また診察日がきて、通院から帰って来たときです。何気なく手を入れたショッピングバッグの中に、何かキラリと光るものがあります。
「-----------?」
まさか!?--------と、思い、それを取り出してみると、何と、あのキーホルダーです。それも、一番目につきやすい内ポケットの中に・・・・・。ちょっこりと、鎮座ましましていたのですから、まったく目を疑いました。わたしの探し方が足りなかったのでしょうか・・・・?いえいえ、家人にも、友人にも探してもらったのですから、そんなことはないと・・・・。それでは、いったい何処から現れたのでしょうか?いいえ、帰ってきたのでしょうか・・・・?病院で拾った方が、親切にも、わたしの知らないうちにこっそりとバッグの中に入れておいて下さったのでしょうか?
不可思議でなりません。
アクセサリーには、やはり、何かしら凡人には解明し難い不思議がつきものなのかもしれませんね。(--〆)
では、引き続き「地域医療最前線~七人の外科医~」をお読みください。
ちょっと、一服・・・・・
2008年12月13日
実は、わたし、ちょうど一年前少し大きな病気をしましてある病院に入院しました。そこで、同じ病室にいた患者さんのお一人から、不思議な話を聞きました。その人が入院する前、二匹の飼い犬が立て続けに死んだというのです。それまでは、本当に元気に庭を走り回っていた犬たちが、何の前触れもなくあっさりと逝ってしまったのだとか・・・・。その患者さんは、一人暮らしで、その人が入院してしまったら犬たちの面倒を見る人間がいなくなってしまう訳で・・・・、彼らは、そのことを察知して飼い主に迷惑をかけまいと、自らの始末をつけたのかもしれないと、話しておられました。
それと似たようなことが、わたしにもあったのです。入院する前、まだそんなことになるとは思ってもみなかった昨秋のこと、実家の家庭菜園の作物が全滅してしまったのです。これまでは、毎年豊作だったさつまいもなどは、まったくというほどものにならず、まるで、収穫の手間を省いてやると言わんばかりのようでした。でも、今年は、さつまいもも、大根も、かぼちゃも、玉ねぎも大豊作!本当に不思議です。
それと、これは十年ほど前の話ですけれど、お隣の元近衛兵だったおじいさんからイチジクの苗を頂き、毎年大きな実をつけて、その甘くておいしい味を堪能していました。ところが、おじいさんが亡くなると同時に、そのイチジクは、瞬く間に枯れ果ててしまったのです。
「もう、私の役目は終わりました」
とでも言うかのような朽ち方に、植物にも魂があるのでは・・・・?と、思われるほどでした。
みなさんも、時々身の周りの変化に気をつけてご覧になられたらいかがでしょう。昨日までとちょっと違うな?と、思われることの中に、これからご自身に起きるであろう何かの兆候がかくれているかもしれませんから・・・・・・(;一_一)
では、また、小説の続きをお読み下さい。





