噂を信じやすい人とは・・・
2012年05月11日
噂を信じやすい人とは・・・

専業主婦のAさんとBさんはカルチャースクールで知り合いそこそこの仲良しだったが、そんな二人の前にある時OLのCさんが現われて、今度は三人で食事をしたりショッピングを楽しんだりと親しく付き合うようになった。
ところが、ある日を境に、何故かAさんがBさんを避けるようになる。
戸惑うBさんは、直接そのわけをAさんに訊く勇気がないので、Cさんに相談を持ちかけた。
すると、Cさんが言うには、「Aさんは、『最近のBさんは自分に隠し事をしているみたいで不愉快だ』と思っているらしい」とのことなので、驚いたBさんは、「そんなことはAさんの誤解だ。わたしはAさんに隠し事などしてはいないと伝えて欲しい」と、Cさんに頼んだ。
ところが、その後もAさんがBさんを避ける態度は変わらず、ついに二人は仲たがいをすることに----。
Bさんは、Aさんと顔を合わせるのが嫌になり、カルチャースクールもやめた。
やがて、Cさんが家族の都合でその土地から引っ越して行くと、AさんとBさんは、偶然、街で一年ぶりに顔を合わせた。
Bさんは、勇気を振り絞ってAさんに話しかけ、一年前にどうして自分を避けるようになったのかと、そのわけを質した。
Aさんの答えは、「だって、Cさんが教えてくれたんだけれど、Bさんがわたしのことを隠し事の多い人だと言って嫌っているというから・・・。嫌われながら付き合うこともないだろうと思ったのよ」と、いうものだった。
そこでAさんとBさんは、Cさんがそれぞれに言いふらした、まったくありもしない情報に踊らされて互いに嫌悪感を抱き合っていたということに気付いたのである。
そして、Cさんが、そうやって二人の間を切り離し、自分だけがAさん、Bさん各々の相談相手となることに快感を感じていたのだということを知ったのだった。
こうした「生じるはずのない誤解」が、噂とか伝聞によって生じることは、とかく日常の人間関係の中で時として起こり得ることである。
では、何故、AさんもBさんも、Cさんが与える間違った情報を鵜呑みにしてしまったのであろうか?
確かにAさんとBさんが、頻繁に情報交換をするほど親しい間柄ではなかったということもあるが、噂や伝聞では殊に肯定的な情報よりも否定的な情報の方が伝わりやすいという特徴があるのだという。
伝わりやすいとは、信じられやすいということでもあるため、悪口や陰口の類ほど広まりやすいということにもなるのである。
また、固定観念や先入観が強く、多数の意見に同調しやすい、また他人と自分を同一視しやすい人ほどこうした噂を信じやすいのだそうだ。
AさんとBさんは同じカルチャースクールへ通う者同士でもあったため、共通の友人であるCさんの言葉を容易に信じてしまう同調化しやすい要素を多分に持っていたともいえるようである。
もしも、AさんとBさんが、趣味も立場も異なる者同士であったならば、Cさんの言葉の受け取り方も微妙に違ったのではないかと思われる。
いずれにせよ、噂や伝聞による情報はとかく歪曲化されたり誇張されやすいものであるから、「これは少し変だぞ」と、思った時は、やはり直接相手に真偽のほどを訊ねてみることが大切なように思われる。
 続きを読む
続きを読む自分が嫌いな人は・・・
2012年05月10日
自分が嫌いな人は・・・

自分が嫌いな人は、自分に自信がない人である。
自分に自信がない人は、他人の好意を素直に受け入れられない人でもある。
何故なら、そういう人は、「自分は他人から好かれるような人間ではないはずだ」と、思い込んでいるために、好意を寄せてくれる相手が自分をバカにしているようにしか思えないからである。
つまり、他人を信じられない人でもあるのだ。
そういう人が組織のトップに祭り上げられてしまった時、一体どうなるか?
トップにいることが苦痛でたまらなくなるはずである。
やがて、他人の好意や親切が逆に敵意にさえも感じられて来る。
「自分は、トップになどふさわしくない」と、内心自覚しているために、辛くて苦しくてならないのだ。
自分を持ち上げてくれる周囲が、本当は自分を嫌っているに違いないとも思うために、組織から孤立し、次第に自分自身の殻に閉じこもってしまうことになる。
「トップは孤独だ」と、思ったとしたら、それは、自分自身がその地位にふさわしくない人間なのだと認めているようなものなのである。
その反対に、盲目的に自分が大好きな人は、トップでいることが楽しくて快感で仕方がないという人である。
こういう人はトップの重責など、正直どうでもいいと思っている。
実に、「神輿は軽いに限る」の典型である。
仕事は、皆、下々の者がやってくれるから、自分は常に高みの見物をしていればそれでいいと何も考えずにふんぞり返っているおめでたい人でもあるのだ。
そして、こういう人は得てして周囲からは大して評価されない。
自分が嫌いな人は、奥ゆかしさ故に周囲には好かれるが、その好意を信じられない。
自分が大好きな人は、周囲からは愚か者呼ばわりされるが、そうした周囲の反応に気が向かない。
要するに、トップに最もふさわしい人というのは、自分のことは好きだが、自分の欠点も熟知している人間で、周囲の人々の言葉にも素直に耳を傾けられる気持ちに余裕を持っている人物----と、いうことになるのではないだろうか。

続きを読む
人が心身を病む時・・・
2012年05月10日
人が心身を病む時・・・

あなたが今している仕事は、本当に自分がしたいと思ってしているものなのだろうか?
あなたが好きだと思っている人は、本当にあなた自身が好きだと思っている人なのだろうか?
本当は、それは、あなた自身がやりたい仕事だったのではなく、誰か別の人がそれをして欲しいと願っていたことを、あなた自身がしたいことなのだと、思いをすり替えて行なっているのではないだろうか?
そして、あなた自身はその人のことをそれほど好きではなかったのだが、あなたがその人を好きになることで、誰か他の人が喜ぶから、あなたも好きになったように錯覚しているだけなのではないだろうか?
現代人が心や体を病むのは、時にこうした「両立し得ない納得」を強引に心の中に仕舞い込んでいる場合が多いという。
つまり、「こんな仕事はやりたくない」と思いながら嫌々しているのではなく、本来は心が拒否しているにもかかわらず、誰かが喜ぶからという理由で、自身もやりたいからしているのだと信じて疑わないところに、こうした問題の根深さがあるのだそうだ。
職場に行くと、何となく気持ちが落ち着かない。
あの人と会ったあとは、いつも体調が悪くなる。
そんなことが頻繁に起きる場合は、あなた自身が自分の本当の気持ちに気付いていない証拠なのかもしれないという。
しかし、もしも本当に自分の思うがままに行動すれば、あなたに期待してくれている誰かを落胆させたり立腹させることにもなるので、それは出来ない。
だから、仕事で失敗したり、相手に対して不満を感じたりした時、その怒りの矛先はどうしてもあなた自身に向いてしまうのである。
意味の判らない苛立ちや憤慨は、本来ならばあなたをそんな風に思わせている他の誰かに向けなければならないものであるにもかかわらず、それに気が付かないあなたは、自分自身を責めてしまうのである。
そのように、どうしても自分自身への苛立ちが治まらない時は、他に原因があるのではないかと考えてみるのも手だそうだ。
意外に、その原因があなたの最も身近にいる家族である可能性も捨てきれないのだから・・・。
続きを読む
(笑)の考察
2012年05月09日
(笑)の考察

皆さんは、文章の終わりに(笑)を付けることがあるだろうか?
この(笑)という書き方だが、一つ置き方を間違えると、とんでもなく相手の気分を害させてしまう言葉の凶器でもあるのだ。
たとえば、今から二年ほど前の信濃毎日新聞の記事にこんなものがあった。
あるフランス料理のシェフが書いた文章中のくだりである。
「長野電鉄の須坂駅の構内に、地元の生産者のみなさんが持ち寄った新鮮な農産物を販売する、無人の青空市場風の売店を発見し思わず足を止めて、見入ってしまいました。----何といってもカボチャの種類の多さにびっくりしました。----黄色やオレンジのものまで色とりどり。形や大きさも、丸いものから長細いものまで、大小さまざまで----『ここはヨーロッパの市場かな?』と錯覚しそうでした(笑)。」
この文章を読んだ時、わたしは、この(笑)の使い方に疑問を感じたのである。
これは、ヨーロッパ各地を旅行したことのある著名な筆者が、須坂駅構内の無人青空市場風の売店に売られているカボチャの種類の豊富さに驚いた----ということなのであろうが、『ヨーロッパの市場かな?』と錯覚しそうになったというあとに(笑)を付けたことによって、「そんな訳ないでしょ。冗談だよ。たかだか田舎の無人販売所が、そんな風に見えるわけないだろう」と、いう筆者の高慢さが読みとれたのであった。
もしも、そうした感想を聞けば、「そんなつもりはなかった」と、おそらく筆者は答えるだろうが、読み手の側に田舎コンプレックスがあったとすれば、そう受け取られても仕方がない書き方なのである。
また、こういう例もある。
相手に何かを頼もうとした文章のあとに(笑)を付けた場合である。
「今度、〇〇をお願いしますね。(笑)」
これも、相手の機嫌を損ねるには十分な書き方である。
この(笑)は、相手に対しての親しみを表現していると書き手はいうだろうが、それほどお互いが親しい間柄ではない場合は、やはり、「〇〇をお願いするつもりなんかさらさらないよ。本気にするなよ、冗談なんだからさ」と、いう意味として相手には伝わる可能性が大なのだ。
しかし、この(笑)という表記は、自虐的な文章には有効な書き方かもしれない。
「この間、何もない道で突然転んで、子供に不思議な目で見られたよ。(笑)」
こんな場合なら、読む側も素直に笑えるだろう。
しかし、書く場所によっては、相手を軽蔑したり軽んじたりする文章となるために、読む側に多大な不快感を与えることにもなり兼ねないのである。
たかが(笑)だが、されど(笑)でもあることを、忘れて欲しくはないものである。
続きを読む
仲良しグループほど脆い
2012年05月08日
仲良しグループほど脆い

「〇〇ちゃんと遊ぶなら、あたしたちのグループには入れさせない!」
小、中学生の仲良しグループには、よくある話である。
そういう仲良しグループの結束はとても強い----と、その子供たちは思っている。
こうした例は、何も子供たちだけのこととは限らない。大の大人同士の職場や地域社会などでも良く見られる光景だ。
では、そうしたグループに属する人々は、本当に仲が良いのだろうか?
その前に、どうして彼らはそうしたグループを作らねばならないのだろうか?
専門家が説くには、彼らは決してお互いを好きなわけではなく、そのグループ内にいると自分に対する褒め言葉やお世辞を聞くことが出来て心地よいからだけに他ならない----と、いうことのようである。
そうした共生関係は、真の友情とはまったく異質なものであり、お互いに対して上辺だけを気を使いながらそっと撫で合っているに過ぎない実に脆いものなのだということである。
それが証拠に、そうしたグループ内に波風を立てることなど容易にできる。
仲間の一人が、一言本音を漏らせばいいのである。
本音で付き合うことを知らない彼らは、それだけでお互いに疑心暗鬼を募らせて、グループ内の結束は一気に崩壊する。
もしも、彼らに真の友情や信頼関係があるのなら、お互いの欠点や意見の相違を忌憚なくぶつけ合ったところで、簡単にその結束が揺るぐはずはなく、また、グループ外の者たちと誰が付き合おうと、それに対して反感を持つ者などいないはずなのだ。
共生関係にある仲間同士の世界はとにかく狭いのが普通で、お互いが神経症的依存関係にあるためその中の誰か一人が離脱しただけでも、グループはバランスを欠き崩壊してしまうのが落ちなのだそうである。
本当に人間が好きならば、どんな人とでも満遍なく付き合えるはずであり、もしも相手と気が合わないならば自らが身を引けばいいだけのことである。
つまり、何もグループや派閥を構成する必要などないのである。
では、自分のグループをさらに拡大しようと触手を伸ばすような行動に出る者の心理状態とはどういうものなのだろうか?
そういう人物こそ、実は共生関係なくしては生きられない特に他者への依存度の強い者だといえるそうで、万が一にも自分を裏切る仲間が出た時のストックのために常に仲間を増やしておかなければ気が気ではないという、幼児性を捨てきれずにいる可能性が高いのだそうである。

続きを読む
こういう女性には要注意!
2012年05月08日
こういう女性には要注意!

独身男性に訊きたいのだが、ここに二人の独身女性がいるとして、彼女たちを食事に誘ったとする。
さて、あなたは、どちらの女性と付き合いたいと思うだろうか?
あなたは、会社でも評判の美人OLのA子と二人でレストランへ食事に出かけた。
あなたが「何食べたい?」と、彼女に訊く。すると、A子はこんな返事をする。
「あなたの好きなものでいいわ。あなたと同じ物をお願いします」
その翌日、今度は容姿はそこそこだがしっかり者で仕事も出来るB子と同じレストランで昼食をともにすることになった。
あなたは「何食べようか?」と、B子に訊ねる。
すると、B子はしばらくメニューを眺めていたが、やがてはっきりと、「ナポリタンにする。それと季節のサラダでいいわ」と、答えた。
この二人の女性の返事の仕方の違いを見て、たいていの男性は、おそらくA子の方を奥ゆかしくて男性を立てることの出来る優しい女性のように思うだろう。
その反対に自分の意見をしっかりと持っていて男性の前でも臆面なくそれを主張できるB子は、何だか女性にしては逞しすぎて、ややとっつきにくい感が否めないと思うのではないだろうか?
しかし、心理学者の目線から見ると、この二人の女性のうちで男性を常に自分の目の届くところに置いておかなくては気が済まない依存性の高い女性は、間違いなくA子の方なのだそうである。
しかも、A子はかなり嫉妬深い性格だともいえるのだそうで、「あなたの好きなものでいいわ」という、他人任せの答え方にこそ、その証拠は如実に表われているといえるのだそうだ。
「あなたの好きな物でいいわ」ということは、裏を返せば、「あたしは、あなたの言うように従うから、だからあなたもわたしの方をずっと見ていてね。わたしに優しくして、わたしだけのあなたでいてね」ということに他ならないのだという。
つまり、それは、「あなたは、わたしの言うことに従いなさい。わたしを裏切ったら承知しないから・・・」との無意識下の束縛であるともいえるのだそうだ。
この手の女性を妻にしたら、結婚生活は大変なことになるかもしれないと想像されるそうで、まず妻は仕事をやめて専業主婦となるが、家事育児はそっちのけで夫がいなければ何も出来ないような自立心の欠如した女性の本性を現わすことさえもあり得るということである。
いくら女性でも、自分の趣味趣向ぐらいは自分で決められることこそが、大人の証である----ということなのだ。
自身の意見をしっかりと持っている女性を、とかく男性は生意気だとか気丈だとか言って敬遠する節がある。
だが、いざ生活を共にする場合は、そういう自分の意思というものをちゃんと持っている女性こそが実際頼りになる存在なのではないだろうか?
しかし、気を付けなければならないこともある。
自分の意思を持っている大人の女性と、単なる我がまま女性を見分ける目も男性には必要だということである。
自己主張をするのも時と場合によりけりで、いつもいつも自分の我を通してばかりで相手を立てる術を知らない女性は、ただ幼児性の強い癇癪持ちでしかない。
それを可愛いと思ってしまう男性も中にはいるだろうが、そういう段階になればもはやマニアの域に入ってしまうので、わたしなどは何をか言わんや----である。
続きを読む
宿泊客の秘密
2012年05月07日
宿泊客の秘密

守秘義務----を辞書で調べると、「公務員に課せられた職務上の秘密を守る義務」と、書かれている。
でも、こうした職務上の秘密を守る責任は、何も公務員に限らず医師でも弁護士でも教師でも飲食店の経営者でも、仕事を持っている人は誰しもが負わねばならないものだと思う。
しかし、そうした仕事上知り得た情報を、ふとしたことから単なる不注意で第三者に漏らしてしまい、周囲の人たちに大変な迷惑をかけてしまったという、ある女性の話を耳にした。
それは、もう今から数十年も前の出来事である。
地元のある旅館に、毎年夏になると避暑を兼ねて約一月ほども滞在する年配男性がいたそうだ。
男性は、東京の大きな商店の経営者で、その旅館にはいつも奥さま連れでやって来ていたのだという。
その年の夏も男性は奥さまとともに旅館に長逗留したのち、女将さんや仲居さんたちに丁寧にお礼を述べて帰って行った。
その後、旅館の女将さんは、その男性宛てに改めてお礼状を出すことを思いついた。
「いつも当館へのご宿泊を頂きまして、誠にありがとうございます。----奥さまにもよろしくお伝え下さいませ」
ところが、後日、この手紙を受け取った男性から怒りの電話が旅館へかってきたそうで、そのわけを聞くと、男性が旅館へ連れて来ていたのは妻ではなく、実は愛人だったということが判ったのだった。
しかも、女将さんが出した手紙が奥さまの目に触れて、すべてがばれてしまったということであった。
そんなことがあってから、その男性は二度とその旅館を訪ねることはなかったのだそうである。
まあ、これはかなり昔の話なので、悪気のない不注意とはいうものの、手紙が客の秘密を暴露するための手段に使われてしまった例だが、今ならさしずめブログやツイッター、メールがそうした守秘義務違反の媒体に使われる可能性もあるということになるだろう。
ネット社会の現代においては、こうした守秘義務違反のような問題は、ますます日常的に注意する必要があるように思われる。
つい何の気なしに書き込んだ他愛もない顧客情報が、後にとんでもない結果をもたらす可能性もあることを念頭に入れた上で、インターネットは慎重に使用しなければならないと、そんな世間話を聞きながら改めて考えた次第である。
続きを読む
独身アラサー女子の悩み
2012年05月07日
独身アラサー女子の悩み

30歳前後のいわゆる独身アラサー女子の大半が悩むこと。それは、
「自分には、まだまだやりたいことがたくさんあるのに、どうして世間は結婚ばかりを焦らせるのか」
----だそうである。
家族も親戚も、寄るとさわるとその話になるそうで----。
「同級生の〇〇ちゃんは、結婚して子供も生まれたっていうのに、うちの子ときたら全然結婚に興味がなくて・・・」
「〇〇さんちの〇〇くんなんてどうかしら?一応、勤めている会社も一流だし・・・」
本人の気持ちなどお構いなしに、勝手な結婚話に花を咲かせて楽しんでいる様子を見るにつけても、「人を何だと思っているんだ。犬や猫じゃないんだぞ!」と、立腹する女性も少なからずいるはずだという。
また、それと同時に、彼女たちには「自分がいつまで経ってもこの家にいるのが、そんなに世間体が悪いのか?さっさと片付けというつもりなのか?」----などの家族不信も生まれて来るそうだ。
しかも、
「結婚なんかしたくない!」
と言えば、本心ではなく強がりだと勝手に解釈され、ますます可哀そうな女子だと誤解される。
アラサーといっても、今の時代はそう結婚に焦る必要もないとは思うのだが、もう20代前半のような華やかな若さはないという思い込みもあって、彼女たちの気持ちは実に複雑である。
ところが、年齢を重ねるうちに、女性の男性に対する理想はますます高くなるのが普通で、「教養も経済力もある程度持つ自分が、なまじっかな男性で手を打てるはずがないのだ」とのプライドが、さらに結婚に対するハードルを高くさせるのだともいわれる。
では、彼女たちの相手となるべき男性たちはどう考えているのかといえば、はっきりいって、「出来すぎる女性は敷居が高い」ということになるらしい。
今の独身男性たちは、とかく自分に自信がない者が多いということで、自分と同年代の女性は自分よりも何もかもが上のように思えて、正直怖いのだという。
気兼ねなく男の強さや賢さをアピール出来るのは、やはり自分よりも世間慣れしていない若い女性ということになるのだろう。
つまり、アラサーという年齢は、もっとも恋愛や結婚を考える上で難しく辛い年頃ということになるのかもしれない。
だからといって、そう悲観ばかりすることもない。
そんな彼女たちでも40歳まで独身を通せば、世の中は俄然自由になるはずだ。
40歳を過ぎた女性に結婚を促すような言葉をかける人はほとんどいなくなるからだ。
要するに、そこまで独身を通した女性は、結婚したいが出来なかったいわゆる「売れ残り」ではなく、独身はその人の主義主張ということになり、自ら選んだ「積極的非婚」になるわけだという。
そういえば、この間のテレビ番組でも女性、男性問わず、かなり独身者が増えたと報じていた。
自分に自信があり過ぎる女性と、自信喪失気味の男性が、現代社会の婚活ミスマッチを生み出しているのかもしれない。
続きを読む
男の逃げ口上
2012年05月06日
男の逃げ口上

心理学者が説くには、男性が女性に対して、「きみとはもう別れたい」と、思った時の逃げ口上にはいくつかのパターンがあるということだ。
まずは、自罰的言い訳----「ぼくは、きみにふさわしい男じゃない。きみのことを大切に思うからこそ、別れるんだ」
これは、もっとも女性を傷付けまいとする優しい言い訳であるが、この言葉の裏を読めば、「心底大切に思う女性から、あえて別れようとする男などいるわけない」と、いうことになる。
「ぼくは、きみにふさわしい男じゃない」ということの本心は、「きみは、ぼくにふさわしい女性じゃない」と、いうことだと気付くべきである----と、学者は言うのである。
次に、自己保身的言い訳----「今度、こっちから連絡するよ。そのうちに飯でも食おう」
「今度、こっちから連絡するよ」は、「きみから連絡することはやめて欲しい。気が向いたらおれの方からメールするけど、たぶん、そういう時はもう来ないよ」という意味であり、「そのうちに----」とは、日にちを決めていないことで「今後一生ご飯を共にすることはない」という意味なのだ。
そして、他罰的言い訳----「実は、母がきみのことをあまり良く思っていないんだ。ぼくはきみが大好きなんだけれど・・・。でも結婚というのは、家族の祝福が大事だろう?無理して一緒になっても、あとで困るのはきみだから・・・」
つまり、「悪いのはすべて母親であり、被害者になるのはきみだ」という、我関せず型の逃げ口上である。
また、音信不通型言い訳----これは文字通りの音信不通で、彼女の送るメールや電話は一切拒否。「さよなら」の一言も告げないままに、いつの間にか姿を消すという去り方である。
まあ、この他にもさまざまな男性からの別れ方があるのだが、とにもかくにも、男性側がこれまでの具体的会話をあいまいな内容にシフトし始めたら、それは女性から興味がなくなって来ているか、もともと大して興味がなかったかの意味だと理解するべきだそうである。
男性が未婚だろうが既婚だろうが、はたまたバツイチだろうが、本当に好きな女性が現われれば、決して上記のような台詞は口にしないものだそうで、人の好き嫌いは時が経てば何とかなるなどという甘いものではない----と、いうのが学者の理論のようだ。
とはいえ、すべてがこうした理屈で割り切れるものではないだろうけれど・・・ね。
一応、ご参考までに----。

続きを読む
花束をもらう夢を見たら・・・
2012年05月06日
花束をもらう夢を見たら・・・

今日は、朝から何となくバタバタしていました。
そんなわけで、昼食も夕飯もコンビニ弁当で済ませてしまいました。(塩分、ちょっと多めに摂った・・・かも)
でも、最近のコンビニ弁当は、以前に比べてかなりおいしくなったように思いますね。

ところで、あなたは夢の中で誰かに花や花束をもらった----ということはないだろうか?
しかも、異性からのプレゼントで。
これは、夢占いからすると、もしもその異性が知り合いだった時は、その人があなたに少なからず好意を持っている暗示だそうである。
また、その異性が知らない人だったとしても、それはあなたにもうすぐラブチャンスが巡って来るかもしれないという意味だとか・・・。
もらった花束が美しければ美しいほど、そのチャンスは大きくなるそうである。
ただ、その花束がドライフラワーや造花だった場合は、かなり意味合いが変わって来る。
新しい恋愛に踏み出す勇気が出ないとか、心の何処かで過去の恋人を引きずっているということになるらしい。
そして、もしも新しい恋を手に入れても、それはあまり長続きしないということの暗示でもあるそうだ。
因みに、知り合いの同性から枯れたりしおれた花を贈られた夢は、その人があなたに敵意を懐いている証拠でもあるそうなので、要注意だという。
また、逆にあなたが誰かに花や花束をプレゼントするような夢は、どんな意味を持つのだろうか?
その時、あなたの気持ちがウキウキしているとか、穏やかならば、それは何らかの形で友人や知り合いとこれからも良い関係を築ける証だそうだが、もしも、あなたがその花をいやいや相手にくれるような夢ならば、それはあなたの大切な物が他人に奪われる暗示でもあるそうなので、最近急に接近して来たな・・・と、思う相手には極力用心した方が良いということのようだ。
もしも、夢の中に花や花束が出て来たら、その花自体にも強いメッセージ性が隠れているらしいので、注意して覚えておくことも近い将来の参考になるかもしれないということである。
続きを読む
オンリーワン・ブーム
2012年05月05日
オンリーワン・ブーム

テレビを観ていたら、ある番組で、「近頃は、何でもかんでもオンリーワン・ブームだ」という話題を取り上げていた。
他の誰ともかぶらない、自分だけの飾り付け(デコレーション)をした携帯電話の「デコ電」や、味気のない普通の乳母車をやたらめったら装飾する「デコ・バギー」なども、そのオンリーワン・ブームに乗っかった女性たちの間で人気だということだった。
「デコ・バギー」などは、ぬいぐるみや造花が乳母車を覆うように飾られていて、肝心の赤ん坊がうっとうしいのではないかと思われるくらいだ。
また、市販の家具に飽き足らず、自分たちの趣味に合わせて作り替えてしまおうという「日曜大工女子」なる者も増殖中だという。
彼女たちの手にかかれば、何の変哲もないカラーボックスが、腰をかけることも出来るおしゃれな収納椅子に変身してしまうのだから、アイデアの豊富さに驚かされるばかりだ。
さらに、彼女たちは傷がついた床や壁なども、主婦ならではのアイテムであるキッチン用品などを駆使して、職人顔負けの手際の良さで修復してしまう技術さえ身に付けている。
そして、やはり女性の趣味としては定番の裁縫では、今や市販の洋服を自分なりにアレンジした世界に一つだけの洋服を手作りするのは当たり前で、最近は「ミシン・カフェ」なる喫茶店も登場するなど、お茶のついでに簡単な服やバッグなどを喫茶店内に設けられた裁縫コーナーで製作してしまおうという女性たちも増えているそうである。
しかも、この「ミシン・カフェ」は、デザイナー志望の男性たちにもかなりの人気だという。
とはいえ、こうした一品物ブームというようなものは、実はこれまでにもないわけではなかった。ただ、かつてのそれに比べて、現在のものが明らかに様相を違えるのは、作った物を自分一人で楽しむためのアイテムとはしていないことだという。
つまり、彼女たちは自作の物を、必ず誰かに見てもらわなければ製作した満足感や達成感を得られないというのである。
そこで、作品をフリーマーケットに出品したり、ブログに写真で発表したりして評価し合うのである。
要するに、現在の「オンリーワン・ブーム」とは、正に自己表現したい女性たちが巻き起こしている作品発表社会といっても過言ではないようである。
かつては、ファッションにしてもヘア・スタイルにしても誰もが同じという横並びが世間の風潮だった。そこから逸脱することを、若者たちは「ダサい」と呼んでいたわけである。
ところが、今の時代は、むしろ人とは違う物がカッコいいといわれるように世の中の流れが変化してきている。
自分だけは他人とは違う人間で、特別な存在なのだ----と、皆が信じたいと考えるようになって来ているらしい。
それが良いことか悪いことかは判らないが、日本人の美徳とされて来た協調性や調和が薄れ始め、明らかに人々の感覚が個性重視、自己開示重視の方向へシフトし始めたようである。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」から、「赤信号、みんなは止まれ、おれ渡る」の時代に突入しつつあるのかもしれないな。
 続きを読む
続きを読む大げさなお世辞の裏側
2012年05月05日
大げさなお世辞の裏側

あなたは、お世辞を言われるとつい嬉しくなってしまう方だろうか?
それとも、相手に何か下心があるに違いないと疑ってかかる方だろうか?
まあ、それもこれも相手のお世辞の内容によっても捉え方は異なるだろうが、どう考えてもそこまで褒めそやされる理由が自分に見当たらないと思うほどのお世辞を言う人が周囲にいたとしたら、その人の本心はいったいどういうものなのだろうか?
たとえば、あなたが子供のために用意したどう見ても素人作り丸出しのキャラ弁を、異常なほどにほめたママ友がいたとする。
「すごい!!まるで、アニメの作者本人が作ったみたいなキャラ弁ね。〇〇さんは本当に器用でらっしゃるから、お子さんもお幸せだわ。わたしも〇〇さんにキャラ弁作りの手ほどきを受けたいくらいよ。素晴らしいわ」
歯の浮くように大げさなお世辞である。
さて、言われたあなたの気持ちはどうだろうか?
わたしなら、きっとこう思う。
「おいおい、今度の遠足にお前の子供に持たせる弁当を、わたしに作れとでもいう気じゃァないだろうな。冗談じゃないぞ」
こんな反応を示すようならば、あなたは相手の本心をよく理解しているといえるのだそうである。
どう考えても言い過ぎだろうと思うほど大げさなお世辞を述べる人は、褒めそやす相手のことを実際はそれほど好きではないことが大半なのだそうだ。
好きではないからこそ、平気で本心を偽れるのである。
人は、本当に好きな人に対しては本心を偽れないというのが普通で、お世辞は言えてもここまでのあからさまな言い方は恥ずかしさや罪悪感さえ覚えてしまい、容易くは出来ないのが人情というものなのだそうである。
ある心理学者は、「これをあなた自身の経験に置き換えて考えてみると良い」という。
心にもないお世辞を言ったあとには、何となくすっきりしない不快感が残りはしないかと・・・。
とはいえ、あなたが本心から尊敬する人物が、本当に素晴らしい功績を上げたり、衆目が認める才能の持ち主だった場合ももちろんあるわけなのだから、そういう時は思いっきり褒めそやして構わないだろう。
それほどの功績ならば褒められた相手もそれを当然のことだと認識しているわけだから、あなたの言葉を殊更に裏読みすることはないはずである。
続きを読む
魅力を感じられない人
2012年05月04日
魅力を感じられない人

「お友達でいましょうね」
そう言われて、実質、異性からフラれた経験があるという人も多いだろう。
「お互いあんなに楽しくおしゃべりしていたのに、わたしの家族の話や過去に付き合った人のことまで正直に話して、あなたもちゃんと納得してくれたのに・・・。どうして、わたしが彼女(彼氏)じゃダメなの?」
確かに、いざ結婚相手を探すとなれば、相手の家族構成や病歴、過去に付き合った人のことに至るまで、何もかも知っておきたいのが人情というものである。
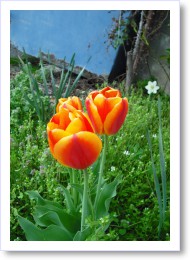
しかし、それは二人の間にしっかりとした恋人関係が築けた後の問題で、付き合って間もなくの頃に、既に相手のすべてが判ってしまうのは、むしろ互いの思いの盛り上がりにはマイナスに作用するものなのだと、専門家は説く。
つまり、知り過ぎてしまった異性には、まったく自分勝手な想像の余地がないのだという。
恋愛感情というものは、早い話が「楽しい誤解」に他ならない。
想像や誤解が入り込めないほどに正確な情報を、まだ知り合って間もなくにして教えられてしまったのでは、相手へ対する好意の盛り上がりようがないのである。
以前もこのブログに書いたが、ストーリー性のない女性は異性から興味を持たれにくいというのもその理由からで、判り切っている相手には安心感はあるものの、魅力という点においてはかなりの減点がなされてしまうという事実もあるのだ。
先日書いた「赤裸々女」も、言わばそうした女性の典型でもある。
「何も、そこまで本当のことを話さなくても・・・」
と、男性は引いてしまうのが常なのだという。
ならば、何でもかんでも秘密主義にしておいた方がモテるのか?----と、いえば、それがそうでもないらしい。
やはり、あまりにも神秘が度を超すと、それは単なる「得体のしれない気味の悪い人」になってしまう。
つまり、人の気を惹くということは、その辺の兼ね合いが難しいのである。
相手には自分という人間を教え過ぎてはいけない。
だが、秘密を作り過ぎてもいけない。
ほどほどの神秘性が大事なのだということのようである。
続きを読む
真の大人は頑張らない
2012年05月04日
真の大人は頑張らない

普通の社会通念からすれば、頑張るとか努力するとかいうことは、基本的に立派なことだと位置づけられているが、その頑張りや努力を人に認めて欲しいという思いで行なっている人は、実はかなり幼児性の強い人だといえるのだそうである。
何事にも一生懸命に取り組んで、自分にも他人にも厳しいというような人がよくいるが、これはすなわち「自分がこんなに頑張っているのに、どうしてお前たちはおれの気持ちが判らないんだ」という、依存度の高い人なのだそうである。
また、「こうすればいい」「こうするべきだ」「こうしなさい」が口癖の人も、結局は他人を自分の意のままにコントロールしたいと考える、幼児性の強い我執人間であるというのが心理学の考え方らしい。
「彼は、人知れず努力していて本当に偉い」
と、周囲が評価する人物も、そう言われた時点で既にその努力は人に知られているわけで、真に努力を楽しんでいる大人なのか否かは疑わしいといえるのだ。
裏を返せば、真の大人とは他人に自分が頑張っているようには思わせない人ということになる。
ましてや、自分の口から二言目には、「わたしは頑張っている」などという台詞は、間違っても吐かない人間なのである。
誰かに認められたいとか、知ってもらいたいなどという欲求があるうちは、自分もまだまだだなァ・・・と、思うべきなのだそうだ。
他人に心が縛られているからこそ、そうした欲求が生まれるのであって、他人がどう評価しようとまったく自分とは関係ないと達観出来た時、人は真の大人になれるのだという。
良く親が子供に向かって言う言葉に、「みんな、あなたのためなのよ」というものがあるが、これもある意味子供への依存心が言わせる言葉であり、真実は、「あなたがそうしてくれないと、ママが困るのよ」なのだという。
そう言われると、夢や希望に向かって頑張る人は、皆、精神的に子供なのだという理屈になる。
要するに、ある意味、真の大人とは、自分のことはもとより他人のことにもさほど執着がなく、自らの成長や向上にすでに満足しきってしまった人間ということなのかもしれない。

続きを読む
好意が生まれる条件
2012年05月03日
好意が生まれる条件

この間、あるテレビ番組で、アメリカで放送された独身男女カップル成立を目指すサバイバルゲーム・バラエティーを紹介していた。
これは番組収録のために出会ったばかりの独身男女数名が急ごしらえのカップルとなり、協力して知恵と体力の限界に挑みつつ、かなりの危険も伴うようなゲームをやり遂げながらお互いを理解し愛を芽生えさせて行くという、日本ではちょっと考えられないような過激な内容の恋人探し番組であった。
もちろん、急ごしらえのカップル同士の気が合わない場合は、途中で別のパートナーを選んでも構わないというルールだ。
しかも、このサバイバル・ゲームの中には、参加した男女の気持ちを恋愛感情が芽生えるようにコントロールして行く心理学的手法が、実に上手に組み入れられているように思えた。
まずは、雄大な自然の中で男女二人が協力し合いながら一つの目標に向かって頑張るということ。
次に、参加者に与えられるゲームが必ず知力と体力のどちらも必要とするものであること。
そして、そのゲームにはある程度の恐怖感が伴うと同時に、参加者の勇気や決断力までもが試されるということ。
最後に、ゲームをやり遂げるためには、必然的に男女が短時間でも身体を接触させる場面(キスするとか手をつなぐなど)が出て来るということである。
こうした行為は、すべて人が人を意識するために不可欠な条件となるものだそうで、人は互いが同じ目的のために尽力する時、必ず協調関係を意識せずにはいられないものなのだという。
また、人によっては知識には自信があるが体力はイマイチとか、その逆の場合もあるわけで、この番組は誰もが何かしらの得意分野をアピール出来るようなゲーム内容になっているのだ。
そして、パートナーの男女が二人で高所から飛び下りなければならないなどの恐怖体験も加味されており、こうした恋愛感情をあおりやすい吊り橋効果もしっかりと押さえられている。
さらに、単純接触という、お互いがより親近感を懐きやすいシチュエーションまでもが盛り込まれているのである。
とはいえ、まさかこの日本国内で一般人を対象に背後から爆風に襲われるような過激ゲームが行なえるはずもない。
となると、開放感に満ちた場所で、知力、体力を駆使しつつも独身男女が無理なく好意を育めるものは何なのか?----と、考えた時、思い付くのは野山や高原でのハイキングやトレッキングではなかろうか。
山菜採りや宝探しゲームなどをそのハイキング・コースに組み入れても面白いかもしれない。
お互いの魅力に気付くだけでなく、意外に自分自身の隠れた能力を新発見することもあり得るはずだ。

続きを読む
何故、女性は騙されるのか?
2012年05月03日
何故、女性は騙されるのか?

「あたしのこと、好き?」
彼氏に向かって絶えずこんなことを言い続ける女性がいるそうだが、どうして彼女はこうも頻繁に彼の愛を確かめなければ気が済まないのか?
彼が誰か他の女性に心を奪われるかもしれないことを警戒しての質問なのか?
彼女は子供の頃も、親に向かっていつもこれと同じことをしょっちゅう訊ねていたはずである。
「ママ、あたしのこと好き?」「ママ、あたし、可愛い?」
母親はこれに対して必ずこう答える。
「もちろんよ。ママは可愛い〇〇ちゃんが大好きよ」
この一言で、子供の気持ちは穏やかになるのだそうである。だから、大人になっても彼女は彼氏に同じ答えを求める。
そうすることで、彼の愛を確かめるのである。
しかし、彼女に対して包容力という大人の恋愛感情を懐く彼氏にとっては、この質問は次第に煩わしいものとなって来る。
「どうして、いちいちそんなことを訊いて来るんだ?おれの愛情を疑っているのか?」
彼女は、別に彼の愛情を疑っているわけではないのだが、自分へのほめ言葉やプレゼントなどの好意を示す具体的なものがないと愛情そのものを実感できないのである。
これこそが彼女の中の幼児性であり依存性なのだという。
やがて彼女は、ほめ言葉もかけてくれない彼氏に物足りなさを感じ始める。そこへ偶然にも、彼女をべた褒めする別の男性が現われたりすれば、途端に彼女はそちらの男性へと気持ちを移してしまうことなど、容易にあり得る話なのである。
べた褒めしてくれる男性が本心から褒めている場合は、それもいいだろうが、初対面から会釈もなく女性の機嫌をとりまくるような男性の中には、当然遊び感覚で女性をひっかけようと思っている者も少なからずいる。
だから、そういうご機嫌とり男性を運命の人だと勘違いしてしまった女性は、男性に去られたあとで、「騙された!」と、思うのだ。
つまり、ほめ言葉でしか相手の愛情を確信できない女性は、騙されやすい女性ということになる。
あなたは、自分をチヤホヤしてくれた相手に、簡単に気を許してはいないだろうか?
もしも、あなたに対して必要以上のほめ言葉を並べる相手がいたら、一度じっくりとわが身を振り返ることも必要だ。
「自分は本当に、そこまで褒めそやされるほどの人間なのだろうか?」
と----。
続きを読む
モテ男の条件
2012年05月02日
モテ男の条件

あなたの周りに、「何で、大して男前でもないのに、あいつばかり女性から人気があるんだろう?」と、首を傾げられるような男性はいないだろうか?
そんな「モテ男」とあなたの違いは何処にあるのか?
簡単にいえば、女性に対しての心遣いがマメか、そうではないかの違いぐらいなものなのである。
「え?----だって、おれも意中の女性が出来れば、かなりマメに連絡したりしているんだけれどなァ・・・」
でも、結局、二人の仲が長続きすることはない。
その理由の一つに、あなたの記憶力と気配り力が大きく関係しているともいわれる。
元総理大臣の田中角栄氏は、「人たらし」と呼ばれるほどに支援者はもちろん、地元選挙区の住民たちから慕われていたが、その記憶力はけた違いにすごかったという。
一度会った人の顔や名前は確実に覚えていたそうで、その人のことだけでなく、その人にどんな家族がいてどういう経歴を持っているのかまでもしっかりと記憶していたのだとか・・・。
そして、数ヵ月ぶりにその人が田中氏を訪ねた時には、「その後、お母さんの具合はどうだね?」などと、友達でも忘れているようなことを気遣う心配りがあったのだそうである。
人は、相手が自分のことを覚えていてくれると、ことのほか嬉しいものである。
元国会議員の杉村太蔵氏も、「自分の欠点は、他人の顔と名前がどうしても一致しないことだ」と、悩んでいた。つまり、記憶力こそが人を惹きつける原点だといっても過言ではないのである。
特に、女性は男性に比べて記憶力が勝っているといわれる。
運よくあなたが意中の女性とデートまでこぎつけたとしよう。そして、その際、彼女が着ていたワンピースのデザインをほめたとしよう。
すると、彼女はたぶんあなたがほめてくれたことが嬉しくて、次のデートにも同じワンピースを着て行くだろう。が、そこでもしも、その事実にあなたがまったく気付かなかったとしたら・・・。
おそらく、彼女はあなたに対して少なからず不信感を懐くはずである。
「な~~んだ。服をほめてくれたのも口先だけだったんだよね」
ましてや、彼女の名前までうろ覚えで、つい呼び間違えでもしたら、もうそれ以上の発展はありえないと覚悟した方が良い。
だが、いわゆる「モテ男」は、そういうポカは決してしない。そして、そういう気配りが特別に苦労なく出来るのである。
もしも、あなたに振り向かせたい女性がいるとしたら、まずは記憶力を鍛えることをお勧めする。
女性は、もしも自分があなたにとって特別な人間なら、絶対に自分の細かい身の回りのことについても覚えていてくれるはずだと期待するものだからだ。

続きを読む
人が人を好きになるということは?
2012年05月01日
人が人を好きになるということは?

「もしも、あなたが誰かを好きになった時、その誰かが同性でも異性でも、その誰かから何かをしてもらったから好きになったわけではないはずだ」
と、いうのが心理学者の理屈だそうだ。
そう言われてみれば、確かにそうである。
テレビでいつも目にしているイケメン俳優を好きになってファンになった人も、別にそのイケメン俳優から個人的に声をかけられたわけではない。
そのイケメン俳優の顔や仕草や時には生い立ちなどが、自分の想像を刺激したり好みに合っていたということのみに他ならないのだ。
故に、もしも、あなたが特定の異性から好意を持たれたとしても、それはその特定の異性に嫌われないために何か特別な親切をしてあげようなどと頑張る必要はない----と、いうことになる。
好かれているということは、好いている相手からしてみれば、早い話があなたと一緒にいるだけで満ち足りているということになるのだ。
良くドラマのセリフなどである、「きみは、きみのままでいいんだよ」というのは、そういう意味だという。
つまり、「そばにいてくれるだけで、こっちが勝手に想像を膨らませて好きになるから、気にしないでくれ」というのが、本来人を好きになるということであるらしい。
時々、相手の男性がせっかく好意を感じて付き合おうと言ってくれたのに、最終的には「重い・・・」と、言われて男性に去られてしまう女性がいるが、これはどうやら女性が男性に嫌われたくないとばかりにあまりに頑張りすぎて、あれこれと男性の世話を焼きすぎてしまうためだという説もある。
人が人を好きになるのは、理屈ではない。
逆を言えば、どんなに好かれたいと思って手を変え品を変え接近したところで、興味がわかない相手には悪意も感じないかわりに、決して好意も懐けないのが人なのである。
続きを読む
ちょ~簡単、茶碗蒸し
2012年05月01日
ちょ~簡単、茶碗蒸し

今日、「七人の敵がいる」を観ていて、有森也実の夫役の俳優が登場した時、一瞬「え?」と、思った。
どうして、ここにあの「白い巨塔」主演の田宮二郎がいるんだろうか?

あまりに似ているので、インターネットで検索してみると、何と、彼は田宮二郎の次男の田宮五郎だということが判った。
本名は、柴田英晃。
過去にニュースキャスターも務め、現在は舞台関係の仕事に就いている柴田光太郎の弟だそうだ。
それにしても、仕草といい、顔形といい、186センチ(らしい)の長身も相まって本当に父親に瓜二つである。
このドラマを観る楽しみが、また一つ増えた。

で、ちょ~簡単に出来る茶碗蒸しだが、これを茶わん蒸しと言ってもいいのか・・・少々疑問だが、とにかく似たような物である。
小学一年生にでも出来る料理だから、独り暮らしの大学生などは覚えておくとかなり便利かもしれない。
まず、電子レンジ可の大きめの器の中へ卵を二つ割り入れる。
これをしっかりとかき混ぜてから、そこへ砂糖(適宜)、麺つゆ(しょっぱくならない程度)、水を入れる。
水は、器の半分ほどまで液体が来るくらいまで入れる。
これらをまたしっかりとかき混ぜて、ラップはせずに電子レンジへ入れ、「あたため」でチンする。
器の液体がドーム状に盛り上がる様子を電子レンジの窓から観察しつつ、盛り上がり切ったところで電子レンジから取り出す。
まあ、器の大きさにもよるが水気が多いと思ったら、卵をもう一つ入れるとよい。
電子レンジへ入れる時間は、3~5分ほどで良いと思う。
これで、出来上がり。
使う器も一つだけ。食器洗いの手間も省ける。
もしも、具を入れたかったら、器を電子レンジへ入れる前にタケノコの水煮や銀杏の水煮、熱が通りやすいキノコなどを入れてチンしてもいいと思う。
ところどころ空気の穴が出来て見栄えはあまり良くないが、味はしっかりとプルプルの茶碗蒸しである。


続きを読む
親のエゴは子供の敵
2012年04月30日
親のエゴは子供の敵

この間、知り合いの女性と、いわゆる「ママ友バトル」の話題になった。
同じような年齢の子供を持つ親同士は、一見結束が固いようだが、その結束の仕方には従順型、しもべ型、友情型など色々なパターンがあるという。
そして、こうした団結は、えてして外敵である外集団を作ることでより強まるのが普通である。
これを内集団の団結と心理学では言うらしい。
しかし、こうした内集団VS外集団の対決で真に犠牲になるのは、常に子供たちである。
親は、我が子可愛さのために気の合う親同士で結束するのだが、子供の世界は親のそれとはまったく異なり、外集団の親を持つ子供たちも内集団の親を持つ子供たちと友だちであることには変わりないのだ。
そして、もちろん子供たちはその地域で大人になって行く。
学校を卒業していざ就職となった時、子供の頃の親同士の確執が原因で、いがみ合った相手の親が関わっている職業に就きたくても就けないなどということも十分にあり得るのである。
その時になって、「どうして、昔、〇〇くんのお母さんとケンカなんかしたんだよ」と、子供に責められてもあとの祭りなのだ。
親は、何があっても決して子供の将来の選択肢を減らしてはいけない。
そのためには、親同士はお互いに自身のエゴを捨てることが大事なのだと、知り合いの女性は話す。
バトルをしている本人たちはそれでもいいのかもしれないが、その犠牲になる子供はたまったものではない。
これは一例だが、かつて母親同士が争っていたことで、その一方の母親の夫が勤めている会社に相手側の子供が就職試験を受けに来たが、その夫が不快感を示して面接で落とされたというケースもあったそうだ。
子供は将来どんな道を歩むことになるか、それは誰にも判らない。
だから、親は自分の思いはさておいても、子供の未来を阻むことになるかもしれない可能性は、出来るだけ排除しておいてやるべきなのではなかろうか。

続きを読む





