人見知りの正体
2012年08月03日
人見知りの正体

人見知りしやすい性格といっても、その人が世の中すべての人を苦手なわけではない。
気を許せる相手も必ずいるのである。
そうした人見知りしやすい人が、気を許せる相手とは、どういう人なのだろうか?
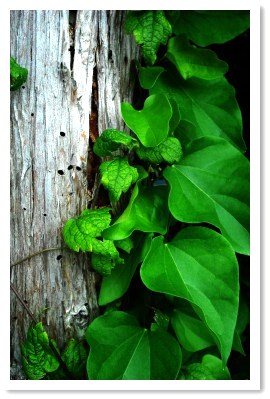 それは、一言で言って、不安や焦燥を感じない相手ということなのである。
それは、一言で言って、不安や焦燥を感じない相手ということなのである。相手から何か攻撃を受けるのではないかという不安が、人見知りをさせるのだが、それは自分自身に攻撃を受けるに足る要素があると思い込んでいるから生じる不安なのだ。
つまり、自分が相手を敵視したり嫌悪している感情の灯影が、相手を歪んだものに見せてしまうのだという。
ところが、自分がまったく敵意や焦燥を感じない相手もいる。
そういう相手は、自分とほとんど共通点や利害関係を持たない相手でもある。
たとえば、まだ幼い子供たちは、男の子も女の子も関係なく掴み合いのケンカをする。それは、幼い頃はまだ男女の力の差がほとんどないからなのである。
そのため、男の子も女の子もお互いをライバルと思うことが出来るので、派手なケンカもするのだが、これが20歳を過ぎる頃になると、男女が取っ組み合いのケンカをするようなことはほとんどなくなる。
力の差が歴然としてくるために、女子が男子をライバル視する意味がなくなるからである。お互いを比べ合う必要を見出せなくなった時、ようやく人は相手に対する不安や焦燥を考えずに済むようになるのだ。
(この場合の不安や焦燥とは、不審人物に対するそれとは意味が違う)
大人になればなるほど、人はそれぞれ職業も生活環境も変わって来るために、互いの共通点を見出せなくなってくる。
ために、ライバル心も薄れてくるので、人見知りする性格も和らいでくるのだという。
さまざまな問題で力関係が同等もしくは近い相手には、人はどうしても警戒心を懐きやすくなるために、簡単には気持ちを許すことが出来ないのだが、互いを比較する意味がない場合は、案外容易に心を開き合うことも可能なのである。
「この人、何か気に障るな」
と、感じた時は、たぶん、あなたはその相手の中に、無意識ではあっても自分に似ている点を見付け出しているのである。
そして、心の奥で、「こんな奴に負けるものか」というライバル心を燃やし始めた証拠なのだそうである。
続きを読む
不思議なペット事情
2012年08月03日
不思議なペット事情

ヤフー知恵袋に何ともユニークな質問があった。
「ペットの犬が死んだという同僚が三日間の喪中休暇をとり、それだけでも他の社員たちは呆れていたのに、死んだ犬の葬式に出席して欲しいという告別式案内状が社員全員に届いた。
犬の葬式に花代や香典を包むなど考えられないということで、皆、他に用事があるとの理由で、葬式への列席は断わった。
すると、この同僚は、「死んだ犬は家族同然なのに!」と、激怒。
しかし、犬の葬式に香典を包めば、金魚が死んだ、鈴虫が死んだというだけでお金を包まねばならなくなる。
それでも、ペットの葬式に出席しなければいけないのか?わたしには、絶対にそんなことは出来ない」
これに対する回答者の意見は、「確かに、愛犬が死んで悲しいのは判るが、その悲しみを他人にまで強要する必要はない。この社員は特殊な人です」と、いうものが多かった。
それにもう一つ。
「身内が亡くなって悲しんでいる人に対して、『判るわ。わたしも〇〇ちゃん(犬の名前)が死んだ時は、本当に辛かった』と、人間の死と犬の死を同レベルで悲しむ人の神経はどうなっているのか?実に、不謹慎だ」
と、いう質問もあった。
これについても、回答者たちの答えは、「犬の死と人の死を混同するなどおかしい。犬はあくまでペットであり、人間の価値と同じレベルで考えるのは間違っている」というものが大半で、日本人の意識は、まだまだ健在であることが判りほっとした。
しかしながら、上記の質問のような、「ペットは家族以上の存在」と、考える飼い主が増えているのも事実である。
飼い犬を「ちゃん」付けで呼ばなかったというだけで、烈火のごとく怒る飼い主もいる。
回答者の中には、「自分も飼い犬を溺愛してはいるが、他人さまに対してまでそうしろというようなつもりはない。犬を飼っていない人に話す時は、『うちの犬』というように呼び方を替えている」と、いう常識人もいた。
「本当に犬嫌いの人に、愛犬を『犬畜生』と、呼ばれて腹が立ったが、犬は犬なので仕方がない」と、いう回答者もいた。
ペットの葬儀で思い出したが、昔、ご近所に飼い猫の葬式をした人がいた。
まだ、ペットの葬儀が珍しい頃だったので、近所でもかなり話題になった。
そこへ参列した飼い主と友人のある主婦が、その時の会場の雰囲気をこんな風に話してくれた。
「ちゃんと、人間のお葬式のように庵主さんが来られて、『猫ちゃん、猫ちゃん』って、お経をあげるんでびっくりしたわよ」
でも、その風景を想像すると、何となく微笑ましくさえ思えた。
おそらく、その猫の飼い主が、猫が生きている頃はおよそ猫を溺愛しているようには見えなかったからであろう。
猫は、特段、家族といった具合ではなく、ただの飼い猫として一生を過ごしたのだが、その葬儀を執り行ったことで、猫に対する飼い主の愛情が垣間見えたからである。
参列した飼い主の友人たちも、香典などを持ち寄ることもなく、葬儀の後も和気藹々とした他愛もないおしゃべりをするお茶会で過ごしたという。
もしも、質問中の同僚社員が、告別式案内状を郵送するような仰々しいことなどせずに、ペットを失った自分の寂しさを癒すために近しい人たちに集って欲しいというだけの、そんな簡素なほのぼのとした葬式なら、社員たちも違和感を覚えることなく出席してくれたのではないだろうか。
続きを読む





