犬の記憶力・・・・・895
2011年01月18日
~ 今 日 の 雑 感 ~
犬の記憶力

犬の記憶力って、バカに出来ないなァ・・・と、思うことがありました。
先日、ご近所のシバ犬の雑種のジョン(オス)が、何とも切なげな鳴き方をしていたのです。
何かを怖がるような、訴えるような、ウォ~~~ン、ウォ~~~ンというおかしな吠え声を長々と出していたので、
「もう、年寄りだから、心細くなっているのかな?」
なんて、勝手に思っていたのですが、その後、鳴き声の訳を飼い主の人に聞いてびっくりしました。
実は、ジョンは、生まれて二ヶ月ぐらいの時にそのお宅へもらわれて来たのですが、その前は、別の飼い主の家にいたのだそうです。
その時、そこの飼い主に、思い切りコウモリ傘で、頭をたたかれたことがあったのだとか・・・。
まだ、赤ん坊だったジョンの記憶には、その時の恐怖感がしっかりと刻まれてしまった訳で・・・。
それが、あの奇妙な鳴き声を出していた日、昔の飼い主の男性が、珍しく近くまで用事に来ていたのだそうです。
ジョンは、その男性が、用事を済ませるまでの間、仔犬の時の恐怖感をよみがえらせ、鳴き続けていたのでした。
「あいつが来た。また殴られるかもしれない・・・。怖いよ・・・」
そんな気持ちだったのでしょう。
もう、十年以上も前の出来事にもかかわらず、しっかりと覚えていたのです。
犬の記憶力は、すごいものがあると驚きました。
そういえば、盲導犬も利用者の家に飼われている時は、「ここは、仕事場」という意識で働いているのだとか・・・。
老体になり、また仔犬の時に預けられていたパピーウォーカーの家へ戻ってきた時の喜びようは、ひとしおだと聞いたことがありますし、当時使っていたおもちゃのある場所をしっかりと覚えていて、その戸棚からおもちゃを取り出すと、赤ん坊に返ったかのようにはしゃぎまわるそうです。
そう考えると、犬も犬の人生----犬生をしっかりと背負いながら生きているんだなァ・・・と、感慨深いものがありました。
続きを読む
難しいB ・Bカップル・・・・・894
2011年01月17日
~ 今 日 の 雑 感 ~
難しいB ・Bカップル
今朝の積雪は、すさまじかったですね~~~。

今日もまた、通院日でしたから、駐車場にとめてある自動車を雪の中から掘り出すのだけでも四苦八苦でした。
何せ、身体が本調子ではないので、ほとんど父親がやったんですけれど・・・。(~_~;)
先ほど、ちょっと薄日が差したので、これで雪もやむかと思いましたが、また降り始めました。
まだ、積もりそうですね。
では、本題です。
一点集中型のB型同士のカップル。
一見、相性抜群のベタベタカップルのように見えるのですが、それは、二人の趣味や興味が同じ場合だけ。
どちらかといえば、自分のこと以外には、ほとんど関心がない血液型B型は、相手がどんなに思いやりを見せても、それがその時の自分の気分やタイミングにそぐわないと、
「余計なことをして!」
と、ムカついてしまうのです。
たとえば、冬の寒空の下、夫が健康のための日課であるウォーキングをして帰ってきた時、妻が気を利かせて部屋の中を暖めておいたとします。
しかし、ウォーキングで身体中ポカポカになり汗までかいている夫は、妻の好意を有難迷惑としかとらず、
「おれが、こんなに暑がっているのに、ストーブを焚くなんて嫌がらせのつもりか!?」
ということになってしまうのです。
そうなれば、妻も面白くありません。
「わたしの思いやりにケチを付けるなんて許さない!」
と、なって夫婦の仲もぎくしゃくし始めてしまうという訳です。
また、夫が妻のために良かれと思い夫婦で行く温泉旅行を計画しても、妻は、ご近所の奥さま同士で行なうボランティアに夢中で、「わたしが今忙しいの判るでしょ。旅行になんか行っている暇があるわけないじゃない!」と、立腹してしまうなどというケースもあります。
B型夫婦は、お互いの気持ちを思いやっているつもりが、自分中心でしか物事を考えられないために、本当の相手の気持ちを把握しきれないのです。
お互いに自分に同調して欲しいと望むのがB型カップルの特徴ですから、この関係が崩れると悲惨です。
つまり、B型カップルがうまくやって行く秘訣は、相手に自分の趣味を押し付けたり、興味を共有することを無理強いしないことです。
二人の価値観はもともと違う物----という気持ちで、過度の干渉をせずに付き合うことがコツだと言えるでしょう。
続きを読む
嫌な記憶は残りにくい・・・・・893
2011年01月16日
~ 今 日 の 雑 感 ~
嫌な記憶は残りにくい
これは、わたしの伯母の話だが、伯母は、今から十年ほど前にある大きな手術をした。
別に、命にかかわるという病気ではなかったのだが、とにかく、生活がしにくいと言うので思案した揚句、決意したのである。
しかし、手術など出来ればやりたくはないのが人情だから、とにかく、恐怖心が先に立ち、入院当日、その不安と緊張のせいか、物干し台で洗濯物を取り込んでいて階段を踏み外し、50センチほど下の部屋の中へお尻から落ちたのである。
伯母は、あまりの痛さに立ちあがることが出来ず、「入院はしない」と、言いだしたのだが、伯父と娘であるわたしの従姉が必死で説得して病院へ連れて行った。
ところが、病室へ入っても、「腰が痛い、腰が痛い」と訴え続けるので、整形外科でレントゲンを撮ってもらった。が、何処にも異常なし。
翌日、手術室へ入るはずだったのだが、伯母はものすごく太っているところへ持って来て、さらに腰が痛むと言うので、搬送用のベッドへ乗り移ることが出来ずに、その日は手術を断念せざるを得なかった。
仕方なく、それから入院したままで、一週間が経過。
改めて、手術日を決め、ようやく、手術出来たのであった。
その時のことについて、ごく最近になってから伯母と話をしたのだが、何と伯母は、「あの時は、入院した翌日に手術してね」と、言う。わたしが、そうじゃなくて一週間後だったでしょうと、言っても、その一週間のことは、まったく記憶にないようなのだ。
しかし、手術後のことは、克明に記憶しているので、まるで、その一週間だけが記憶からスッポリと抜け落ちているようである。
心理学者のマリーゴールド・リントンは、人の記憶の傾向を調べるために、自分のしたことを喜怒哀楽の強さや刺激的な出来事を、五段階の強弱に分けて書き記し、一ヶ月後にその記憶がどれだけ残っているかを確かめるという実験をした。
すると、楽しいことや自分にとって有益になったことはすんなりと思いだせたのだが、自動車が故障した、苦情を言われたなどの不快な記憶は、思い出すのに時間がかかったという。
つまり、人間は、自分にとって不利だったり不快であったりした記憶は、自然と意識下にしまいこもうとする習性を持っていることが判ったのである。
その逆に、自分にとって嬉しかったり、楽しかったり、快感に結びつく記憶は、繰り返し回想して行くうちに次第に美化され、ドラマティックな出来事として記憶されてしまうことも判ったのだった。
嫌な記憶、不快な記憶を、無意識のうちに封印することで、人間は、自分自身の精神を守ろうとしているのではないかと思われる。 続きを読む
「ちょっと、トイレへ・・・」の裏・・・・・892
2011年01月15日
~ 今 日 の 雑 感 ~
「ちょっと、トイレへ・・・」の裏
あなたは、初対面の人と商談をしています。
20分ほどした時、相手の人が、「すみません。ちょっと、トイレへ行ってきます」と言って、席を立ったらどうしますか?
その人がトイレから戻って来て、同じ調子で話を進めても、おそらくその商談はうまく運ばないものと思います。ですから、日を改めて、また話をするか、その人との契約を諦めるしかないでしょう。
何故なら、そういう短時間で腰を上げるということは、相手がその話題にほとんど乗り気でないということを意味するからだそうです。
そんな相手の態度を観察すると、たぶん、以下のようなことに気付いたはずです。
一つは、相手の体の向きです。
相手が、あなたの方へ顔を向けて、前かがみになるような姿勢で話を聞いている場合は、これは、相手もあなたの提案に興味を示している証拠なのですが、もしも、その身体が、斜めを向いていたり、あなたに視線を合わせない場合は、明らかに、話しに飽きていることになるのです。
続いて、咳払いをする、腕時計に目を落とす、貧乏ゆすりをする、「はい、はい」などの生返事を繰り返すなどの場合も、相手が乗り気でない証しになります。
やがて、相手が出されたコーヒーなどを飲み干すとか、椅子の肘かけをつかんで体を浮かしかけるなどした時は、「もう、やめてくれ!」の積極的アプローチと見て間違いがありません。
そして、ついに、「ちょっと、トイレへ・・・」とか「会社へ電話をかけたいので、席を外します」という、直接行動に出る訳です。
そうなったら、即刻話を打ち切りましょう。
そんな相手に、それ以上無理に話を聞かせれば、怒りを買うばかりではなく、その後の関係もこじらせてしまいかねませんから。
しかし、案外、人は、このタイミングを見逃してしまいがちなのです。
これらの態度を相手が取り始めたら、どれほど愛想良く話に乗って来たとしても、その顔色に関係なく即断即決、出来るだけ短時間で話を切り上げることをお勧めします。
続きを読む
相手の共感を確かめる方法・・・・・891
2011年01月14日
~ 今 日 の 雑 感 ~
相手の共感を確かめる方法
かなり昔のテレビコマーシャルに、若い女性が喫茶店の席に座っていて、前のテーブルにいる中学生ぐらいの男の子を、ちょっとくすぐったそうに眺めながら、グラスに注がれているジュースを飲むという、おしゃれなシーンがありました。
その時、女性は、添えられているストローをわざと取り出し、直接グラスに口を付けてジュースを飲むのです。
すると、前のテーブルの中学生もまた、同じように自分のグラスのストローを取り出して、恥ずかしそうな素振りで、グラスに口を付けて飲みます。
この時、二人は何も言葉を交わす訳ではないのですが、綺麗なお姉さんに淡い恋心を懐く男子中学生の心理が見事に表現された、実にうまい場面構成でした。
このように、たとえ何も言葉にしなくても、好意を持つ者同士というのは、知らず知らずのうちに、相手と同じ動作をするという心理学的法則があるのだそうです。
これを「姿勢反響」といいます。
友人同士のグループで、意見が真っ二つに分かれた時など、この姿勢反響に気を付けて観察すると、その中の誰と誰の意見が同じで共感しあっているのかがよく判るとか・・・。
つまり、同じ意見の者は、発言者の言葉に、ほぼ同じタイミングで頷いたり、前かがみになって集中していることが多いのです。
このように喫茶店などで意見が一致したり話が盛り上がっているグループなどを見ると、誰かがティーカップに手を伸ばせば、必ずというほど、皆が同じようにティーカップに手を伸ばしていることが判るのです。
そして、誰かが足を組めば、他の者も足を組み、顔を触れば、他の者も触る----こんなシンクロした場面を見ることが出来るのです。
こうした「姿勢反響」は、親しい人同士では、さらに頻度が高くなるそうですから、これを観察することで、相手が本音を漏らしても良い人間かどうかが、ある程度把握できるとも言います。
ただ、この「姿勢反響」で気を付けなければならないのは、見ず知らずの初対面にもかかわらず、やたらに終始、同調行動を見せる人間がいることです。
相手の意見に決して反論せず、常に仕草を真似るような態度をとる人が稀にいるのですが、こういう人は、そうした行動をとることで、わざと相手の共感を得ようとしている場合があるのです。
こうした人に会った時は、何か下心があると解釈して、安易に信用しないことが大事です。
あなたの友人や恋人が、食事の最中などに「姿勢反響」してくれた場合は、あなたに共感し、気持ちを許している証拠です。しかし、その気配すら見えない時は、その人物に腹話をすることはあまりお勧めできません。
「この人、本当にわたしに関心があるのかしら?」
と、悩むような時は、こんなことも、相手を知る上で少しばかり参考にしてみると良いでしょう。
続きを読む
恋人の短所は見えない・・・・・890
2011年01月12日
~ 今 日 の 雑 感 ~
恋人の短所は見えない
わたしは、昔から友人の間では有名なイケメン好みだった。

気に入りの俳優やタレントにも、イマイチな男性は一人もいなかった。
ところが、ここ数年前から、その好みがぐらついて来た。遅まきながら、「男は顔じゃない。人格や才能だ」----と、思えるようになったのだ。
まあ、それにはちゃんとした理由があるのだが、ここでは置いておくとして・・・。
たとえば、「恋をすると、あばたもえくぼ」と、俗に言うが、恋人に限らず、自分が好意を持っている人のことは、あまり悪く思いたくないというのが人情だろう。
しかし、どんな人間にも短所もあれば、長所もあるものなのだ。
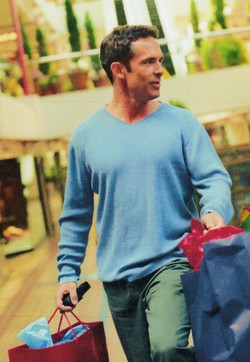
ところが、好意を持つ相手に対しては、人は無意識のうちに長所ばかりを探してしまうという習性があるらしい。
好意とは、大抵において意見が合うというところから始まるので、共感出来るだけで、その相手を良い人に違いないと思い込むのである。
そうなると、その人の容姿や態度にも好感が持てるようになり、どんなにイマイチな容貌であったにせよ、それすら魅力的に感じてしまうのである。
その反対に、意見が合わない人に対しては、人は、少なからず嫌悪感を懐く。ブログなどもそのよい例だが、特に書き手の顔の見えないブログ上での意見の相違は、敵意に発展することさえあるのだ。
一度、自分の意見と合わない記事をアップしたブロガーの書くことは、どれほど含蓄のあるためになることでも、細部までけなしたくなるのである。
また、それはブログに限らず、リアルな日常生活でも、同じことが言える。
皆さんにも、最初は好意を寄せていた人物でも、その後、嫌いになると、今度は、それまで素敵だと思っていた相手の部分まで、欠点にしか見えなくなったという経験があるだろう。
人気絶頂だったタレントが、ちょっとした失言をきっかけに、芸能界から姿を消す破目になるのも、そうした理由からなのである。
好感を持つ人と話をする時は、大して興味のない話題でも、楽しいと感じるが、嫌いな人と同じ話題で話をしても、少しも面白いと感じないのも、そういうことが関係するからなのだという。
よく仲の良い夫婦は同じ趣味を持つといわれるが、これにも、こうした認知の錯誤がかかわっていて、夫のことが大好きな妻が、夫の趣味までも好きだと勘違いして、知らず知らずのうちに夫の趣味に付き合わされてしまっている例も少なくないのが実情なのだ。
特に、女性にはこの認知の錯誤の傾向が強い。
「あの人が好きだから、あの人のすることなら何でも好き」
これは、ある意味幸せなことなのかもしれないが、いざ、裏切られた時の心構えも必要であると、心理学者は説いている。
続きを読む
中二病って、何?・・・・・889
2011年01月11日
~ 今 日 の 雑 感 ~
中二病って、何?
巷に浸透しつつある「中二病」なるもの----。
実は、わたしは、ごく最近この言葉を知りました。
語源が何処にあるのか少し調べたところ、タレントの伊集院光さんが、今から十年ほど前に、パーソナリティーを務めるラジオ番組で使用した造語なのだとか・・・。
でも、伊集院さんが生みだした時は、今のような使われ方ではなく、もっと広い意味で「中学二年生の頃、夢中になっていたり、考えていた、ちょっとおバカなこと」のような意味合いで使われていたようです。
しかし、今は、その中二病の定義が固まり、ほぼ3つに分類されているのだそうで、
DQN系 わざと反社会的な行動をとる。しかし、根は真面目なので、それが通常でないと認識している。
サブカル系 流行になど流されない。人と同じことを嫌い、自分は特別だと思う。
邪気眼系 いわゆる不思議ちゃん。スピリチュアルなことや超常現象系にはまり、未知なる力に憧れる。
と、こんな具合になるのだそうです。
まあ、もっと別の解釈もあるのかもしれませんが・・・。
これ以上調べるのは、面倒なのでしません。興味のある方は、自力でお調べ下さい。(笑)
ただ、これを見て思うのですが、確かに中学二年生の頃は、すさまじいほどのエネルギーと集中力で何かに凝っている生徒が多いものですよね。
そして、その世界に没頭するあまり、格好や持ち物も興味の対象と同じようにしたがるものです。
言葉遣いやヘアスタイル、顔つきまで、好きな小説の主人公や漫画のヒーローと同じにしなければ気が済まない子供もいます。
本当は、素直になりたいのに、何か世の中に反発することが格好いいと勘違いをして、わざと校則を破ってみたり、だらしない制服の着方をしたり----と、まるで、バンクーバー冬季五輪の某スノーボードHP選手のような抵抗を示すこともあるのです。
実は、わたしの大学時代の友人にも、自分のことを「ぼく」と、言っていた女性がいたり、男性名で呼んで欲しいと、頼んできた女子学生もいました。
かくいう、わたし自身も、中学生の頃は、新選組にどっぷりとつかり込み、彼らに関する小説や資料を手当たり次第に読み漁ったものでした。
一口に「中二病」と言いますが、これは、ちょうどその頃そうしたある意味狂信的な趣味のジャンルに目覚めるという意味で、その趣味志向は、その後も強弱の差はあっても、案外、一生続くのかもしれません。
要するに、中二の頃に、人間の性格がほぼ形成を終わるということなのでしょう。
その後は、周りに自分を合わせるために、演技をしながら大人としての社会生活を営むわけです。
他人を変えられないのなら、自分が変わるしかない----と、説くカウンセラーなどもいますが、それは、おそらく、根本的な性格から変えろというのではなく、表面だけでも変わったふりをしておけと、いうことなのだと思います。
でも、これは、かなりのストレスが溜まりますよね。
何故なら、老いて認知症などになった時、やはり、これまで取り繕って来た仮面が取れ、本当のその人の性格が現われるからです。
認知症発症後、結婚以来、夫や夫の両親に遠慮して一度も弾いたことのなかったピアノを、突然弾き出して子供たちを驚かせたという女性もいるそうですから・・・。
中二病は、誰もが一度はかかる麻疹のような存在なのかもしれませんが、治ったあとも、そのウイルスは、きっと一生その人の中にそっと潜み続けるのだと思います。
そう考えると、「中二病」も侮りがたいものですね。

続きを読む
柔軟な発想は正しい理解から・・・・・888
2011年01月11日
~ 今 日 の 雑 感 ~
柔軟な発想は正しい理解から
これから、ある心理学の本に書かれていた質問をします。
「友人とゴルフを楽しんでいたあなたは、日ごろの練習の成果を発揮し、ドライバーでフェアウェー中央へ飛ばした。ところがボールは、そこに落ちていた紙袋の中へ転がり込んでしまった。
紙袋を拾ってボールを取り出した場合は、ペナルティを取られてしまう。かといって、紙袋ごと打つ訳にも行かない。そんな時、どうすればいいだろうか?」
これを読んで、三分以内に答えを見つけて下さい。
因みに、この問題を74人の被験者に答えさせたところ、柔軟な発想で回答できたのは39人で、回答者の53%でした。
その答えとは、「その場で紙袋を、ライターの火で燃やしてしまう」でした。
この問題を解決するために、何を真っ先に考えたかを74人に訊いたところ、57%の人が「どうやったら第二打をうまく打つことが出来るか?」ということで、残り半数近くの人は、「どうやったらペナルティを取られないで済むか?」「どうしたら友人に勝つことが出来るか?」という二次的なことだったそうです。
この問題解決のための柔軟回答が出来た人たちは、次の手順で回答にたどり着いたのでした。
1) うまく打つためにはどうしたらよいか?
2) ペナルティを取られない方法で障害を取り除かねばならない。
3) ここで障害となるのは、紙袋である。
4) 紙は燃えるので、ライターの火で燃やしてしまえばボールが出て来る。
人間は、日常生活でいつも何らかの問題にぶつかっている訳で、その問題を解決するためには、今実際に何が起きていて、それを解決するためには何が必要なのかを自然と認識し、解決方法を的確に選択しているのです。
かつて、週刊誌で読んだのですが、現代人はそういう柔軟な解決のための発想が出来なくなっているということで、ある若い母親が、自分の赤ん坊の寝顔に蚊がとまったのを見て、慌てて赤ん坊の顔に向かって殺虫剤を噴霧してしまったというのです。
つまり、母親の頭の中には「蚊がとまった」「刺されたら困る」「蚊を殺そう」という発想しか浮かばなかったので、その時点で蚊がとまっている場所が我が子の顔だという事実を見落としてしまったのです。
発想の柔軟性とは、今起きていることを多方面から正確に把握、理解し、最善の策を講ずるということなのです。
しかし、これが簡単なようで実に難しいのです。
特に、こと相手が他人となれば、その正しい発想がむしろ裏目に出ることも無きにしも非ずなので、解決方法が判っているにもかかわらず、あえてしないという場合もあるのです。
とはいえ、問題自体に気付かないよりも、やはり、気付いていた方が解決のしようがある訳ですから、常に問題意識は持ち続けているべきだと思います。

続きを読む
重ね着の「?」はてな・・・・・887
2011年01月10日
~ 今 日 の 雑 感 ~
重ね着の「?」はてな
今風のファッションは、重ね着が主流だそうですね。
真冬なのにノースリーブのカットソーを着た上にフェイクファーのボレロをはおり、ストールを巻く。ミニスカ-トの下にはレギンスを履き、足元はブーツ。
だったら、タートルネックのセーターにカーディガン、そしてジーパンを履いた方が、効率よく温かさを保てるのでは?----と、思ってしまいますが、それは、ダサいのだそうです。
もしも、ズボンを履くなら、ひざ丈くらいの短めの物を履いて、わざとブーツを見せるようにするのだとか・・・。
意味が判りません。ズボンも長めの物を履いた方が、ブーツと二重になって温かさが増すと思うのですが、今のファッションは、常に20度以上の室内にいることを想定して作られているように思えるのです。
それだけ、贅沢な生活が当たり前になってしまった人たちが考え出しているものなのでしょうね。
コートの前をわざと開けて歩くのも、格好がいいのだとか・・・。つまり、身体に縦長のラインを取ることで、細身効果があるのだそうです。
しかし、信州の真冬にいくら格好が良いからと言って、コートの前を開けて歩けばどんな状態になるのか判りそうなものです。
こういう着方をする人を、昔の人は方言で「りこうもん」と、言いました。
ヒールの高いブーツを履いて、凍った道を歩いてみて下さい。わたしは、どんなに頼まれても、ご免こうむります。
あなたが持っているクローゼット・ワードローブ(アクセサリーや小物類までも含めた身に着けるためのアイテム)を考えてみても、実際のところは季節によって分けられているのが普通ではないでしょうか。
つまり、頭が固い柔らかいの話しではないのです。もっと言えば、信州に暮らしている以上、ファッションは命とも直結している大切な問題なのです。
しかも、これらは少なくとも中肉中背から痩せ型の人に合わせたコーディネートです。太めの人に重ね着は拷問に等しいものがあります。
ファッション関係の仕事をしている人は、一時の流行ばかりを追うのではなく、その地域地域の気候や習慣に即したファッション性を重視し、研究して欲しいものだと思うのです。
続きを読む
「戦前女」は、褒め言葉?・・・・・886
2011年01月09日
~ 今 日 の 雑 感 ~
「戦前女」は、褒め言葉?
ネットの悩み相談コーナーを読んでいたら、二十代の女性からの質問で、
「友人の結婚披露宴に振袖を着て行ったら、会場に来ていた招待客の30代の男性たちから、『昭和の女って感じ・・』『それも、戦前・・・?』と言われ、凹んでいます。これって、褒め言葉なんでしょうか?それとも、けなされているのでしょうか?」
と、いうのがあった。
彼女は、着物も渋めの色の物を着ていたらしく、普段も年上に見られることが多いとか・・・。
身長は162センチぐらいだが、体重があり、少し太めなのだと書かれてあった。
これに対してのベストアンサーは、「あまり気にしないこと。褒め言葉だと思っていればいい。本当にけなすつもりなら陰で言うはず。年上に見られてもまだ二十代ならそんなに気に病む必要はない」というものだったが、他の意見には、「戦前・・・?」というのは、やはり失礼だというものもあった。
最近は、自分のことは棚にあげ、人を客観的に評価することがやたらに多くなって来ているが、褒め言葉の使い方も判らないくせに、安易に口を開くなと言いたい場合がよくある。
この女性への言葉も、「着物が似合うね。落ち着きがあって昭和の女性の雰囲気があるよ。大人っぽくて素敵だね」と。言えば、何のことはないのに、戦前の女がどんなものかも判らない若造が、「戦前・・・?」なんて知ったかぶった言い方をするから、いらぬ不快感を与える破目になってしまったのである。
本当に、口は災いの元だ。適切な褒め言葉が判らないのなら、しゃべるなと言いたい。
まあ、あえてバカにするつもりで言った言葉なら、それは、論外であるが、おそらくはこの男性たちは、「古風な感じが良いね」と、言いたかったのだと察する。
実は、わたしにも似たようなエピソードがある。
わたしは大学生の頃、教育実習で母校へ行った時、古典の授業を担当した。
すると、生徒から「先生は、平安美人ですね」と、言われたことがあった。平安美人の典型は、色白、しもぶくれの麻呂眉、目細、鉤鼻、おちょぼ口だから、現代の感覚からすれば美人の定義には程遠いと思われるが、わたしは、彼女の言葉を褒め言葉と受け取った。
いずれにしても、どんな時代でも、美人は美人であるし、紫式部や清少納言、ましてや小野小町と同等に思われたのなら、こんなに嬉しいことはないからだ。
その生徒も平安時代が好きな女子だったので、たぶん、その頃の女性に憧れを懐いていたのだろう。
だから、その悩み多き二十代の女性にあえて言いたい。
戦前の女----と、いう表現に引っかかっているのだと思うが、戦前の女性は、今の女性たちに比べて決して劣るものではない。むしろ、今の若い女性たちよりも遥かに品が良く、清楚で、心身ともに美しい人が多かったのだ。
だからこそ、あのような貧しく苦しい時代を逞しく生き延びることが出来たのだと思う。
決して、自身の容姿を卑下する必要などないのである。
続きを読む
スーパー特急の男の子・・・・・885
2011年01月08日
< 不 思 議 な 話 >
スーパー特急の男の子
JR東日本で勤務する車掌のわたしは、その日、C線のスーパー特急に乗務していました。
車内検札で車両内を歩いて行くと、二両目の指定の窓際席に三歳ぐらいの小さな男の子が一人、腰かけていたのです。
そばには親と思われる人の姿もなく、他の乗客もまばらな車内にポツンと座っている男の子の存在は、実に奇妙でもありました。
男の子は、移り変わる窓の外の景色に夢中で、ニコニコ笑いながらとても楽しそうに足をブラブラさせ身体を揺らしています。
「一緒に乗っている親は、トイレへでも行っているんだろうな・・・」
男の子の座る指定席の利用客は、既に手前の駅で降車していたので、わたしは黙認したまま次の車両へと通り過ぎて行きました。
やがて、再び二両目へ戻って来た時、男の子はまだ一人で車窓の風景を楽しんでいます。少し不審に思ったわたしは、男の子に声をかけました。
「ねえ、ぼく、お母さんかお父さんが一緒に乗っているんだよね。何処にいるのかな?」
すると、男の子は、キョトンとした顔を向け、わたしを見上げると、大きく頭を振ります。
「お母さんもお父さんも、おうち・・・」
「おうちにいるの?それじゃァ、おばあちゃんと一緒に乗っているのかな?」
「ううん、おばあちゃんもおじいちゃんも、おうちだよ・・・」
「それじゃ、ぼくは一人でこの電車に乗っているの?」
半信半疑で訊ねるわたしの目をまっすぐに見て、男の子は、うん----と、大きく頷いたのでした。
これは、大変なことになった。こんな幼い子供がたった一人で乗車するなど、尋常なことではないと焦ったわたしは、それでも何処かに付き添いの大人がいるのではないかという思いで、車内を探そうと、ちょうどそこへカートを押しながらやって来た車内販売の女性スタッフに、男の子を見ていて欲しいと頼んだのです。
しかし、その女性スタッフは、怪訝な表情でわたしを見詰めると、
「男の子って、何処にいるんですか?」
「何処にいるって、ここに座って・・・・」
窓際の指定席を振り返ったわたしは、驚きました。その席には今しがた腰かけていたはずの男の子の姿は影も形もなかったのです。
まるで、きつねにでもつままれたような気持ちで立ち尽くすと、女性スタッフは、
「やだ~、しっかりして下さいよ」
笑いながらカートを押して行ってしまいました。
やがて、特急列車はトンネルへ入ります。そして、釈然としない気分のままに車掌室へ戻ったわたしが、何気なく窓外に目をやると、そのトンネルを出た直後の線路際にささやかな花束が供えられている光景を、一瞬目の当たりにしたのです。
その後、同僚の車掌から聞いた話では、十数年前、トンネルの入り口付近に住む家族の三歳の男の子が、列車見たさに線路内へ入り、運転士は慌てて非常汽笛を鳴らしてブレーキをかけたが間に合わず、列車にはねられて死亡したという痛ましい事故があったのだそうです。
きっと、その男の子がどうしても列車に乗りたくて、あの日、偶然わたしの乗務する車両に現われたのかもしれないと、同僚は話しました。
わたしは、今もC線の車両に乗務するたびに、あの小さな男の子がまた乗っているのではないかと、車内を探してしまうのです。
*** この物語はフィクションです。
続きを読む
混ざり合う記憶・・・・・884
2011年01月04日
~ 今 日 の 雑 感 ~
混ざり合う記憶
人の記憶ほど曖昧なものはない。
「思い込み」ということは、よくある話で、実際は別々の場所や日にちに起きたことが、一年も経つと一つの出来事のように思い込んでしまうというのも、珍しくはない。
わたしの知り合いに、アメリカの独立戦争と南北戦争がごっちゃになっていて、未だに同じことだと認識している者もいる。まあ、これは、単に世界史の勉強不足だと言われても仕方がないのだが、自分にとってあまり関係がない出来事については、殊にこういう記憶の混同が起きやすいのである。
もっと、すごい記憶の混同に、他人の記憶を自分の物として認識してしまうという場合もある。
こういうすさまじい記憶の混同を起こすのは、血液型B型の人に多い。
B型は一点集中型といい、一つのことに対しては極めて強い集中力を発揮するタイプなのだが、相手の話にあまりに集中し過ぎて、その話の内容があたかも自分自身が体験したことのように錯覚してしまうことがあるのだ。
わたしの伯母がこの典型で、野沢温泉に行った伯父の記憶を、しっかり自分自身の記憶だと思い込んでしまっていたことがあった。たぶん、伯父が話したことを自分の体験として受け止めてしまったのだと思うのだが、雪が降っていたことや朝食でバイキング料理を食べたことなど、実に詳細に説明するので、
「伯母さんも、伯父さんと一緒に行ったの?」
と、わたしが訊ねたところ、「行ったような気がする」というので、泊まったホテルは何処で、どんな部屋だったのかと更に訊ねると、そこの記憶はあいまいで、結局自分自身は行っていなかったことが判明した。
それにしても、何故、こんな記憶の混同が起きてしまうのだろうか?
心理学者のフレデリック・バートレットは、人の記憶には矛盾や不可解なことが多くあることから、「記憶再構成説」を唱え、記憶はよみがえるのではなく、再構成されるのだと考えたのである。
では、記憶はどうして変わってしまうのか?
心理学者のロフタスは、こんな実験をした。
大学生を二つのグループに分け、自動車事故の光景が移っている短い映画を観せたのち、違った言い方で質問をしたのである。
Aグループ 「フィルムに映っていた自動車は、ぶつかった瞬間、どのくらいのスピードを出していたと思うか?」
Bグループ 「フィルムに映っていた自動車は、激突した瞬間、どのくらいのスピードを出していたと思うか?」
すると、両グループとも観ていた映像は同じにもかかわらず、Bグループの学生たちの方が、Aグループの学生たちに比べて、自動車のスピードをより速いものと認識していたことが判った。
つまり、「ぶつかる」という言葉よりも、「激突」という言葉の方に、学生たちはよりスピードを感じていたことが判ったのだ。
また、それから一週間後、「映像の中でガラスの破片が飛び散っているのを観たか?」と質問したところ、Bグループの学生たちの中に「観た」と答えた者が多かった。映像にはガラスの破片など映っていなかったにもかかわらずである。
これにより、記憶には、最初に与えられたインパクトだけで構築される一次情報と、その後、色々なシチュエーションにより提供された諸々のインパクトによって形作られて行く二次情報があることが判るのだ。
二つの情報は時間の経過に合わせて次第に混ざり合い、元からあった記憶として、すり替わってしまうのである。
しかも、人には、自分に都合が悪い記憶は無意識に美化したり忘れたりする傾向があるので、同じ体験でも人によってあからさまな記憶違いということも起きるのである。
続きを読む
怒りは命を縮める?
2011年01月03日
~ 今 日 の 雑 感 ~
怒りは命を縮める?
いつも怒っている人は、心臓の収縮期圧と拡張期圧が高いそうで、平たく言えば、血圧が高いのだそうです。
特に、怒り、敵意、攻撃性と三拍子そろっている人は、この傾向が顕著だったと言います。
また、別の研究によれば、怒りっぽい人が心筋梗塞にかかる確率は、そうでない人の二倍だったとか・・・。五十歳前後で亡くなる確率も普通の人の5倍にはねあがるそうです。
ただ、わたしの場合、怒りは自分自身の気持ちを守る最大の防御でもあるのです。辛さや苦しさを感じた時は、とにかく怒ることでそうした知覚を打ち消すことが出来るからです。
徳川家康の言葉に「怒りは敵と思え」というのがあるそうですが、単に怒りを我慢したのでは、更に逆効果ともなりますから、その点は注意が必要です。
まあ、もしも、異常に腹が立った時は、自分の中で嬉しいことや楽しいことを膨らませて、怒りをコントロールすることが必要だと思います。
たとえば、大好きなペットのことを考えるとか、恋人との楽しいデートを思い出すとか、休日の旅行のスケジュールを思い描くなど、怒りのはけ口を見付けることも良いでしょう。
しかし、そんな楽しいことなど皆無だという人は、やはりコントロールも難しいと思います。そういう人は、マットレスや枕を思い切り殴りつけるとか、大声でうっ憤晴らしをするなどして、短時間で怒りを放出してしまうことも良いかもしれませんね。
とにかく、いつまでもイジイジと怒りをくすぶり続けさせないことがストレスを溜めない秘訣だとも言われます。
では、あなたは、次の項目に幾つ当てはまりますか?
1) 他の人と良く意見が対立する。
2) 自分の権利は遠慮なく主張する。
3) 怒鳴る相手には、怒鳴り返す。
4) 時に、脅し文句を使うことがある。
5) 言い合いになると声が大きくなる。
これは、アメリカの心理学者バスが考案した「言語的攻撃尺度」からの抜粋ですが、ここにあげた全項目が攻撃的反応です。そして、三項目以上が当てはまる場合は、「攻撃的人間」だと言えます。
これで見る限り、わたしも筋金入りの「攻撃人間」ですね。(笑)
ただ、攻撃的人間にも三つのタイプがあるそうです。
A 攻撃を道具として利用し、物事を自分の有利な方向へ導こうとするタイプ。(恫喝型)
B 攻撃によって、自分の怒りを爆発させ、他者を傷つけることで権力や支配を得ようとするタイプ。(独裁者型)
C 攻撃して相手を困らせることだけを楽しむタイプ。(幼児性快感型)
最近は、Cのタイプの「幼児性快感型攻撃人間」が世の中に増殖しているように思います。
でも、わたしの場合は、もう一つ、Dを付け加えて、攻撃して怒りを爆発させ、身体の痛みや辛さを回避するタイプ---と、いったところでしょうか。これを称して、(苦痛回避型)とでも名付けようと思います。
皆さんも、怒りとうまく付き合いながら、心のガス抜きをして下さいね。

仲間が増えると手抜きする・・・・・883
2011年01月02日
~ 今 日 の 雑 感 ~
仲間が増えると手抜きする
ドイツの心理学者・リンゲルマンは、「人間は集団で作業すると、独りで作業した場合に比べて働かなくなる」という説を立てたそうです。
たとえば、綱を引っ張る時の人間一人の力を100%とすると、二人で綱を引っ張った時は、一人が93%の力しか出していないことが判ったのだそうです。
これは「リンゲルマン効果」とか「社会的手抜き」というそうですが、同じような立場の人が同時に作業をする場合、参加人数が増えれば増えるほど、その課題を遂行しなければならないという精神的な圧力が分散してしまう傾向があるのです。
とはいえ、スポーツなどで勝ったチームのキャプテンが、「チームワークの勝利です」などと発言していることがありますよね。これは、上記に矛盾するのではないか?と、思いますが、上に書いた精神的圧力の分散は、あくまでも赤の他人の寄り集まりが行なった実験に限るのです。
ところが、いざ、チームということになると、チームメート同士はお互いの気心も知れ、同じ釜の飯を食い、時には同じ屋根の下で寝起きし、目を見交わしただけでも相手の気持ちが読みとれるような間柄とも考えられます。
こうなると、一つの試合に臨む気持ちの分散は最小限にとどめられます。
こうした緊密感の強い集団に属している場合は、集団の力が個人の力に匹敵するほど集約されることが考えられるのです。正に、毛利元就が息子たちに諭した「三本の矢」の逸話と同じになる訳です。
ですから、何かことを成し遂げようとした時、人数ばかりを集めて「さあ、みんなで頑張ろう!」などと発破をかけても、それはすなわち「さあ、みんなで手抜きをしよう」と、言っているのと同じことになるのです。
こういう時は、全員に何か共通する精神を自覚させる必要があるので、一緒に同じ歌を歌うなど、結束を強めるための何らかのテクニックを使うことが不可欠なのです。
そして、一人一人の役割を決めて、責任を持たせるようにします。そうすることで、一人一人がしっかりと100%の力を発揮することが出来るのです。
続きを読む
血液型で見る相性・・・・・882
2011年01月01日
~ 今 日 の 雑 感 ~
血液型で見る相性
女性も男性も、恋をするたびに好きになる人のタイプは、何故かほぼ同じだと言いますよね。
「何で、いつもいつも似たような性格の人間ばかり好きになるの?あんたも懲りない人だね」
なんて、友人に呆れられることありませんか?
でも、これって、ある意味仕方がないことなのだそうです。あなたの血液型がそういうタイプの人を好きになるようにインプットされているのだそうですから。
ですから、これまでに好きになった相手の血液型を調べてみて下さい。おそらく、ほとんど同じなのではないでしょうか?
血液型には、相性というものがあるのです。
どんなに、いい人でも、血液型によってはまったく魅力を感じない場合もある訳で、男女の仲が一筋縄ではいかないのも、そういう理由があるからなのだとか・・・。
では、魅力を感じるか否かということは別にして、本当に相性のいい血液型同士とはどういうものなのかを、考えてみたいと思います。

 血液型の中で、最強の相性と言われるのが、O型男性とA型女性のカップルだそうです。この二人は、いつも本音で話し合える間柄でありながら、ケンカすることも少なく、常にリラックスして付き合えるということで、波乱万丈な生活は望めませんが、穏やかに暮らせる最良カップルなのだそうです。
血液型の中で、最強の相性と言われるのが、O型男性とA型女性のカップルだそうです。この二人は、いつも本音で話し合える間柄でありながら、ケンカすることも少なく、常にリラックスして付き合えるということで、波乱万丈な生活は望めませんが、穏やかに暮らせる最良カップルなのだそうです。ただ、A型女性のこまごまとした注文や愚痴を、O型男性がウザったく思い始めた時が危険なので、O型男性は、A型女性の言葉をBGMのように聞き流す術を学びましょう。
次に相性として良いのは、B型男性とA型女性。O型男性とB型女性。A型男性とO型女性。O型男性とAB型女性。AB型男性とO型女性のカップルです。
これらのカップルたちは、少しの我慢は必要ですが、それでも穏やかな関係を保てる間柄です。
 B型男性とA型女性のカップルは、B型男性がドンドン前を進み、A型女性がそれについて行くという古風なカップルのパターンになります。亭主関白に見えるカップルですが、女性はそれをあまり苦とは感じません。二人で共通の話題や趣味を見付けることで、より親密になれるのです。
B型男性とA型女性のカップルは、B型男性がドンドン前を進み、A型女性がそれについて行くという古風なカップルのパターンになります。亭主関白に見えるカップルですが、女性はそれをあまり苦とは感じません。二人で共通の話題や趣味を見付けることで、より親密になれるのです。 O型男性とB型女性のカップルは、B型女性にとって最も相性がいいのがO型男性なのです。O型男性はいつも穏やかで優しい存在なので、B型女性があまり無理難題を言い始めない限り二人はうまく行きます。
O型男性とB型女性のカップルは、B型女性にとって最も相性がいいのがO型男性なのです。O型男性はいつも穏やかで優しい存在なので、B型女性があまり無理難題を言い始めない限り二人はうまく行きます。 A型男性とO型女性のカップルは、筋金入りの頑固さを持つO型女性ですが、その頑固さをA型男性はむしろ頼もしく感じます。ケンカになっても、忍耐強いA型男性がO型女性の気持ちを上手に緩和させることが出来るので、この二人も意外にうまく行くのです。
A型男性とO型女性のカップルは、筋金入りの頑固さを持つO型女性ですが、その頑固さをA型男性はむしろ頼もしく感じます。ケンカになっても、忍耐強いA型男性がO型女性の気持ちを上手に緩和させることが出来るので、この二人も意外にうまく行くのです。 O型男性とAB型女性のカップルですが、いつも自由でいたいAB型女性には大らかでザックリとした性格のO型男性は、最も相性のいいパートナーになります。気まぐれなAB型女性が突然姿を消して、再び戻って来ても、「終わり良ければすべてよし」と、受け入れてしまう度量の広さをO型男性は持っているのです。
O型男性とAB型女性のカップルですが、いつも自由でいたいAB型女性には大らかでザックリとした性格のO型男性は、最も相性のいいパートナーになります。気まぐれなAB型女性が突然姿を消して、再び戻って来ても、「終わり良ければすべてよし」と、受け入れてしまう度量の広さをO型男性は持っているのです。 AB型男性とO型女性のカップルは、O型女性のパワーにAB型男性が押し切られても、転換の早いAB型男性は、「ま、それもありだな」と、納得して、O型女性を許してしまうところがありますから、この二人も意外にうまく行くのです。また、ドンブリ勘定のO型女性は、頭の切れるAB型男性を尊敬もしますから、割れ鍋に綴蓋タイプのカップルになるでしょう。
AB型男性とO型女性のカップルは、O型女性のパワーにAB型男性が押し切られても、転換の早いAB型男性は、「ま、それもありだな」と、納得して、O型女性を許してしまうところがありますから、この二人も意外にうまく行くのです。また、ドンブリ勘定のO型女性は、頭の切れるAB型男性を尊敬もしますから、割れ鍋に綴蓋タイプのカップルになるでしょう。ここにあげられていない血液型同士のカップルも、それなりにうまくはやって行けますが、お互いの努力が上に書いた血液型同士よりは、少し多めに必要となるそうです。
 しかし、そんな中でも特に努力が必要なのは、AB型男性とB型女性のカップルです。AB型男性のささいな気持ちの変化に、B型女性が不満を募らせ疲れてしまうのです。しかし、そのB型女性の方が実際は気持ちの変化が激しいのですが、それを自覚していないために、「どうして、彼はわたしに合わせてくれないのかしら?」と、イライラ感がつのるのです。
しかし、そんな中でも特に努力が必要なのは、AB型男性とB型女性のカップルです。AB型男性のささいな気持ちの変化に、B型女性が不満を募らせ疲れてしまうのです。しかし、そのB型女性の方が実際は気持ちの変化が激しいのですが、それを自覚していないために、「どうして、彼はわたしに合わせてくれないのかしら?」と、イライラ感がつのるのです。とにかく、どんなカップルでも、腹を割って話が出来ないようでは相性がいいとは言えません。
上辺だけで付き合うのなら赤の他人と同じです。せめて恋愛感情を共有する間柄なのでしたら、相手に理想だけを期待するのはやめましょう。
では、本日は、ここまで。
続きを読む







