スーパー閉店
2012年08月08日
スーパー閉店

先日、「買い物難民」の記事を書いたが、今日、この地域でまた一軒スーパーが8月いっぱいをもって閉店することが判った。
このスーパーは、この地域では正に中核商店といってもいい店舗で、創業50年ほどになる。
それほどの大型店ではないが、地域住民の食卓を長年支え続けてくれた店舗で、今は閉店してしまったが、近くに大型チェーンスーパーが出店した際も、地域密着の独自色を打ち出しながら頑張って営業を継続して来た。
その店が閉じるというのは、よほどのことだと、近所の主婦たちは心配する。
つまり、それだけ不景気のレベルがひどいということなのだ。
この夏、街の中には観光客の姿はほとんど見えない。
そのスーパーも、近くのホテルや旅館の宿泊客が買い物に訪れるような気さくな店だったのだが、その宿泊客数がここに来て急激に落ち込んだのも閉店を余儀なくされた原因の一つだそうだ。
このスーパーが閉店してしまったら、一番に打撃を受けるのは近隣のお年寄りたちである。
「今度は、何処へ買い物に行けばいいのか判らない」
「買い物に行きたくても、他の店までは遠すぎて歩けない」
観光客も激減し、中核スーパーも閉店----いったい、町は何を考えているのだろうか?
消費増税が可決されたことで、景気は一気に冷え込んだ。
東京の大学生に地域活性化のアイデアを出してもらい、何やらイベントを行なっている温泉場もあるようだが、そんなものは何の好影響も及ぼしはしない。
町住民のほとんどがそのイベント自体さえも知らない。
一部地域だけで自己満足的に浮かれるのは、もはや大概にして欲しいものである。
町民が抱えている困窮は、そんな子供だましの景気回復ごっこなどでは解決できないほど、待ったなしの深刻な問題なのだ。
続きを読む
投げつけられたペットボトル
2012年08月07日
投げつけられたペットボトル

ジャマイカのウサイン・ボルト(Usain Bolt)らが出場したロンドン五輪、陸上男子100メートル決勝でスタート時に選手たちに向かってペットボトルを投げつけた観客に、柔道女子70キロ級で銅メダルを獲得したオランダのエディト・ボッシュ(Edith Bosch)選手(32)が「平手打ち」をくらわせた。
当時、ボッシュ選手はロンドンのオリンピックスタジアム(Olympic Stadium)でレースを観戦していた。審判員が「セット(用意)」と言ったところで、前に座っていた男性がやじを飛ばし、さらに出場中の陸上選手たちに向かってペットボトルを投げつけたという。投げられたボトルは、第5コースの後ろに落ちた。テレビ映像にも選手たちの後ろでバウンドする緑色のペットボトルがはっきりと写っている。
このレースで金メダルのボルト選手に次ぎ銀メダルを獲得した同じジャマイカのヨハン・ブレイク(Yohan Blake)選手からは数メートルしか離れていなかった。
これを見て怒り心頭に達したのが、柔道世界選手権でチャンピオンになったこともあるボッシュ選手。オランダのテレビ局NOSに対し「その男はずっと『ノー、ウサイン・ボルト、ノー』と叫んでいて、まったくリスペクトに欠けていた。私の真ん前に立っていたけれど、ボトルを投げたのは止められなかった。『何事?』って思ったわ。頭に来たので、後ろから思い切りひっぱたいたのよ」と語った。その後、警備員に取り押さえられた男性は警察に逮捕されたという。
おかげでボッシュ選手は、ウサイン・ボルト選手が五輪新記録を出して優勝したレースそのものを見逃してしまい、それを何よりも悔しがっているようだ。【8月7日 AFP】
このシーン、わたしも観ましたが、ホント、ビックリでしたね。

レースがやり直しにならなかったのが不思議なくらいでした。
選手たちは、まったく気付かなかったのだそうですが、間違って選手にぶつかりでもしていたら大変でした。
あのバウンドの仕方では、ペットボトルの中は、空ではなかったように思えます。
それにしても、このペットボトルを投げつけた男は、どうしてそこまでボルト選手を憎んでいたのでしょうか?
他のひいき選手を勝たせたかったのでしょうか?
それとも何かもっと個人的な理由でもあったのか?
ただ、この会場にはペットボトルの持ち込みが禁止されていなかったんですね。
普通、オリンピックの競技観戦の時は、飲み物はすべて紙コップに移さなければならないものだと思っていたのですが・・・。
その辺の警備も少し甘かったのかな?
*** 時に、気付いたのですが、上記の「これを見て怒り心頭に達したのが」は、「怒り心頭に発したのが」の間違いですよね。この記事を書いた記者は、勘違いをしているようですね。
続きを読む
うつになりやすい人の特徴
2012年08月07日
うつになりやすい人の特徴

うつになった人の周囲からの評価には、
「あんなにしっかりしていた人がねェ・・・」
と、いうものが多いそうである。
要するに、自分を懸命に操作しながら、立派な自分や愛される自分を作って来た人が多いという。
自分は、決して間違ったことが出来ない。
人前では、絶対に弱みを見せない。
醜態をさらすくらいなら、死んだ方がましだ。
そして、いつも周りから愛される存在でなくてはならない。
こんな規範を自らに課すことで、必死で本当の自分と戦って来た人なのである。
心理学者は、「そういうイメージの自分にしがみついて来ただけである」と、語る。
しかし、本当の自分は、間違いも犯すし、弱虫の小心者で、頼りがいのない、みっともない自分なのである。
が、それを認めたくないがために、突っ張り続けているうちに、いつしか神経がすり減って行ってしまうのだそうだ。
そして、これは立派な自分を演じることだけで起きるものではない。
明るい自分、元気な自分を演じることでも起きる場合がある。
つまり、本物の自分でない自分を作り上げるということが、どれほど精神的にキツイものかということの証明でもあるのだ。
もしも、あなたが誰かから嫌がらせをされたとして、その人に素直に怒りをぶつけられるならば、それは本当の自分をさらけ出していると言っていいだろう。
でも、ほとんどの人は、そこで相手の挑発に乗って怒り狂ったら、きっと世間はわたしを「愚か者」と、思うだろう----などという理性という名のブレーキをかけてしまう。
とはいえ、そんなほとんどの人には、その悔しさや怒りを消化する術が何かしらあるものだ。怒りを共有して愚痴を聞いてくれる友だちがいるとか、趣味に没頭することで嫌なことは忘れるとか・・・。
だが、一切そういう術を持たない人がたまにいるのである。
いや、持てない人というべきか・・・。
そういう人こそ、要注意なのだそうである。
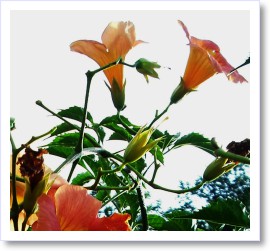
続きを読む
トップアスリートと偏食
2012年08月06日
トップアスリートと偏食

この五輪で金メダルをとった体操男子の内村航平選手(23)や、柔道女子の松本薫選手(24)は、実はかなりの偏食家だそうである。
ことに内村選手の偏食は有名で、前回の北京五輪で「好きな食べ物はチョコとバナナ」「野菜は見るのもイヤ」と、語っていたそうだ。
今回も大好きなチョコ、「ブラックサンダー(有楽製菓が製造しているチョコレート菓子)」を3箱(計60個)持参し、選手村の食事にはほとんど手をつけず、「北京に続きマクドナルドのお世話になっている」「体調はバッチリ」と笑顔で話していたという。
しかも、昨年4月にコナミに入社し、夜だけは栄養士が作る食事を取っているのだが、朝と昼はジャンクフードやカップラーメン、お菓子が中心。たばこもかなり吸うというのだから恐れ入るしかない。
松本薫選手もアイスクリームやポテトチップス、空揚げが大好きで、見かねた栄養士の父親が3年前から冷凍した料理を送り、少しは改善されたが、自炊はほとんどせず、息抜きのお菓子は欠かさなかったそうである。
しっかりと計算された食事をきちんと取っていた選手より、偏食大好きの2人が金メダルとは、何とも不思議な話だが、あのメジャーリーグのイチロー選手も野菜嫌いで有名だという。
「ストイックで厳しい練習をする選手には、息抜きが必要です。毎日の食事やお菓子はとても重要。しかし好きなモノが食べられず、上から『これを食べろ』と管理されると、ストレスで潰れたり、練習に身が入らなくなる。特に今の若い子はその傾向が強い。ある程度、自由を与えられた選手の方が伸びていくのは、当然といえば当然です」とも、スポーツに詳しい心理学者の関修氏は語っている。
「管理された食事ばかり食べていると自主性が芽生えず、試合で予想外のことが起きても臨機応変に対応できないというデメリットがあります。マラソンなど持久力を必要とするスポーツ以外は、多少偏食でもビタミン剤などで補えるし、若いうちはそれほど問題にはならないでしょう」
プロ野球選手や五輪代表選手を指導するメンタルトレーナーの高畑好秀氏もこう言っている。
トップアスリートのように、日々かなりの運動量をこなす場合、むしろ自分の食べたい物を食べるという方が、精神面でリラックスが出来、ストレスを溜めにくい身体になるのだろう。
しかし、これはあくまで代謝の促進が順調な若いうちに限る話であり、いくらトップアスリートでも、年齢を重ねるにつれて偏食は間違いなく体調に悪影響をもたらすと思われる。
偏食でも好成績が残せるのは、せいぜい30代まで。
40代以降は、食事の管理もしっかりと行わなければ、その後の選手生命を脅かすことは間違いがないらしい。
確かに、今回の金メダルは、2人がまだ20代前半の若い選手たちだからこそ、極度の偏食でも成し遂げられた偉業であるといえよう。

続きを読む
都 市 伝 説
2012年08月05日
都 市 伝 説

都市伝説ばかりを取り上げたテレビ番組を観た。
伊勢神宮とユダヤ教が関係あるとか、株価は満月に落ちて新月に上がるとか、面白い話が多かった。
そういえば、以前、こんな都市伝説を聞いたことがある。
ある女性が耳たぶにピアスの穴を開けていたところ、ある日その穴から糸のようなものがのぞいていた。
何だろうと思って、その糸をどんどん引っ張り出してみたら、あるところでプツンと音がして、その瞬間目の前が真っ暗になり、そのまま目が見えなくなってしまったという話だった。
おかしな話である。
また、こんな話も聞いた。
男子高校生が毎日の登校途中に見るある古いマンションの一室の窓から、いつも彼を見下ろす少女がいた。
少女は白いネグリジェのような物を着ていて、元気に学校へ通う男子高校生の姿を羨ましそうに見詰めていた。
男子高校生は、この少女のことを勝手にこんな風に想像した。
「きっと、病気で学校に通うことが出来ないんだな。いつかお見舞いに行ってやろう」
男子高校生は、卒業を目前にしたある日、意を決して彼女のために見舞いの花束を買い、そのマンションへ向かった。
建物内はやけに静かで、人影も見えない。
階段を上り、少女がいるはずの部屋のドアをノックしても返事がないので、ノブを回して中へ入ると、室内はまるで廃屋同然であった。
もちろん、住人などいるはずもない。
男子高校生は気味が悪くなって、慌ててマンションから飛び出した。
また、こんな話もある。
一人の女子大生が、ある夜、同じ大学に通う女友だちのアパートの部屋を訪ねた。
ひとしきり二人で他愛もないおしゃべりをしたあとで、友だちがベッドの上へ座りながらこんなことを言い出した。
「ねえ、知っている?あたしの知り合いの一人暮らしの女の子が、この間実家の法事で数日帰省してからアパートへ戻ったら、何か部屋の中の様子がいつもと違うような気がしたんだって。
でも、別に何かが盗まれているというわけでもないので、ただの気のせいかと思って、疲れもあったのでそのままベッドで眠ってしまったんだって。
すると、夜中に何か嫌な胸騒ぎがして眠れなくなってしまったので、台所へ行って水を飲もうとベッドから出て、水道でコップに水を汲んで飲みながら何気なく部屋のベッドの方を見たら、そのベッドの下に男が一人横になってじっと彼女を見ていたんだって」
これを聞いた女子大生は、
「それって、都市伝説ってやつでしょ」
バカバカしいと笑ってから、飲み物が足りなくなったので、コンビニまで行って来ると言って友人の部屋を出た。
コンビニで買い物を済ませた彼女が友人が待つアパートの部屋へ戻ると、飲み物をテーブルの上へ置こうとした時、何とはなしにベッドの下の空間が目に入った。
すると、そこに見知らぬ男が一人潜んでいるのを見て仰天し、友人に、
「ねえ、ちょっと一緒にもう一度コンビニへ行ってくれない。買い忘れたものがあるんだけれど・・・」
そう言いながら友人を連れ出すと、その足で二人は近くの交番へ息も絶え絶えに駆け込んだ。
と、いう具合に都市伝説には、SFのようなものから、ホラーのようなもの、実際に起きそうな事件のようなものなどいろいろある。
これもまた一つの夏の風物詩だ。
続きを読む
人選は満遍なく
2012年08月05日
人選は満遍なく

信濃毎日新聞に掲載されている「のびのび育児 信州はなし隊」を毎回興味深く読ませて頂いている。
若い父親や母親たちが、暗中模索しつつも子育てを頑張っている姿が彷彿として、なかなか楽しめる紙面座談会である。
その記事に、「雨の休日の過ごし方」という回があった。

「雨の休日を家族でどう過ごしますか?」との質問に、ジンヤ、はつね、みかん、百花、ジャスミン、コウタロウ、新司といったパパ、ママたちが、我が子との雨の休日について、独自の過ごし方を発表し合っているのである。
ある父親は、「子供が小さい頃は、よく相撲をした」と語り、また別の父親は、「旅行に行って家族みんなで楽しんだ」と話す。
また、別の父親は、「子供が小さい頃は、家で布団の上で遊んだ」と、言っていた。
そして、一人の父親がそれに対して、「休日は何処かに行かないともったいない気がしてしまうけど、家で過ごすのもいいですね」と、応えていた。
ここまで読み進めていて、わたしは、小さな違和感を持った。
「休日って、わたしの家には、そんなものはなかったな・・・」
そうなのである。この座談会に出席している父親たちは、おそらく全員が勤め人なのだ。
わたしの家は、商売をしているので、未だに休日も平日もない。
もしも、この座談会に、休日なしの商店経営や旅館経営などの父親や母親が入っていたら、この会話はどうなったであろうか?
おそらく、雨の日だからと言って、子供と遊んでいる時間など決してとれないのではないだろうか。
最近のアニメや漫画に生活感がなくなってきたのは、登場する子供たちがほとんどサラリーマン家庭の子供たちだからなのである。
しかし、世の中はそんな勤め人だけで構成されている訳ではない。
酒店、精肉店、雑貨店、鮮魚店、洋品店、宿泊業、飲食店、俳優、芸術家、新聞店などなど、千差万別の職業人がいるのである。
座談会形式の記事を考えるならば、そんな休日などとはほとんど無縁の人たちの声も拾う方が内容に深みや現実感が出たのではないだろうか。
この辺りで、紙面座談会の人選を一考してみるのも良いのではないかと思った。
続きを読む
矛盾だらけの人々
2012年08月04日
矛盾だらけの人々

「ギャルママ」モデルの益若つばささん(26)がブログに自分のネイル写真を掲載したところ、ネットで「そんな爪で家事ができるのか」といった声が挙がり、議論が起きている。今のネイルは昔より丈夫だというが、実際どうなのか。(YAHOO!ニュース)
ネイルアートをしたままで家事が出来るのか?
この疑問や批判は、年齢層によってもさまざまだと思うが、わたし自身は、酢の物をネイルアートをした爪のままの素手で揉んでは欲しくないというのが本音だ。
ただ、そういう人が作った料理でも違和感なく食べることが出来るという人ならば、別にその手で料理をしてもらっても構わないのではないだろうか。
それにしても、そういうネイルアートを施した爪のままでといだコメを炊いたご飯は食べられても、他人が素手で握ったおにぎりは食べられないという人も世の中にはいるらしい。
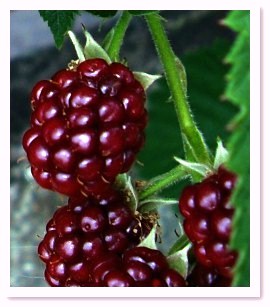
「母親やおばあちゃんが素手で握ったおにぎりだけはOKなんだけれど、友だちや親戚のおばさんが握ったのは、どうしても不潔な気がして食べられない」
と、いう若い女性もいるという。
年配の人たちに言わせれば、「あなたのネイルアートの隙間に入っているゴミや雑菌の方がよっぽど不潔よ」と、いう反応になるのだろうが、要は、その人その人の価値観の相違であろう。
ある女子高生は、
「毎日朝シャンをしないと気持ち悪くて一日過ごせないが、お風呂へ入るのは三日に一遍でも平気」
だそうだ。
また、トイレから出たあとはたいていの人は手を洗うが、
「本当の手の汚さはトイレへ入る前の方が汚いはずだから、自分は入る前に手を洗って、入ったあとは洗わない」
と、半ば信念をもって言い切る女性もいた。
では、その手のままで食事をするのかと、こちらは不安に思うのだが、
「汚い手のままでトイレットペーパーを使う方が、よほど身体には悪いはずだ。尿に大腸菌はいない」
と、女性は言うのである。
しかし、トイレでたす用は、小水ばかりではないはずなのだが・・・。
まあ、清潔、不潔の感覚は、正に人それぞれということなのだろう。
今日の信濃毎日新聞の記事に、こんな言葉が書かれてあった。
「常識の別の言い方は、偏見である」
そうはいっても、世の中には常識がなければ、社会秩序の基準というものがなくなってしまう。
ネイルアートをしながら料理をするギャルママたちも、徹底してそのスタイルを貫くなら、社会には彼女たちだけの世代が生活をしている訳ではないことを理解した上で、たとえ風当たりは強くても、胸を張って常識に立ち向かって欲しいものである。
きっと、若かりし頃の思い出の一ページにはなるだろうから----。

続きを読む
人見知りの正体
2012年08月03日
人見知りの正体

人見知りしやすい性格といっても、その人が世の中すべての人を苦手なわけではない。
気を許せる相手も必ずいるのである。
そうした人見知りしやすい人が、気を許せる相手とは、どういう人なのだろうか?
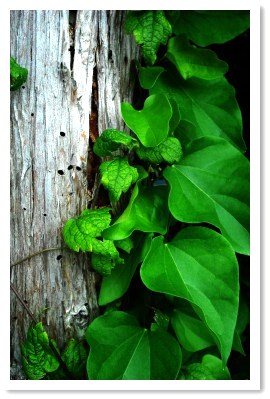 それは、一言で言って、不安や焦燥を感じない相手ということなのである。
それは、一言で言って、不安や焦燥を感じない相手ということなのである。相手から何か攻撃を受けるのではないかという不安が、人見知りをさせるのだが、それは自分自身に攻撃を受けるに足る要素があると思い込んでいるから生じる不安なのだ。
つまり、自分が相手を敵視したり嫌悪している感情の灯影が、相手を歪んだものに見せてしまうのだという。
ところが、自分がまったく敵意や焦燥を感じない相手もいる。
そういう相手は、自分とほとんど共通点や利害関係を持たない相手でもある。
たとえば、まだ幼い子供たちは、男の子も女の子も関係なく掴み合いのケンカをする。それは、幼い頃はまだ男女の力の差がほとんどないからなのである。
そのため、男の子も女の子もお互いをライバルと思うことが出来るので、派手なケンカもするのだが、これが20歳を過ぎる頃になると、男女が取っ組み合いのケンカをするようなことはほとんどなくなる。
力の差が歴然としてくるために、女子が男子をライバル視する意味がなくなるからである。お互いを比べ合う必要を見出せなくなった時、ようやく人は相手に対する不安や焦燥を考えずに済むようになるのだ。
(この場合の不安や焦燥とは、不審人物に対するそれとは意味が違う)
大人になればなるほど、人はそれぞれ職業も生活環境も変わって来るために、互いの共通点を見出せなくなってくる。
ために、ライバル心も薄れてくるので、人見知りする性格も和らいでくるのだという。
さまざまな問題で力関係が同等もしくは近い相手には、人はどうしても警戒心を懐きやすくなるために、簡単には気持ちを許すことが出来ないのだが、互いを比較する意味がない場合は、案外容易に心を開き合うことも可能なのである。
「この人、何か気に障るな」
と、感じた時は、たぶん、あなたはその相手の中に、無意識ではあっても自分に似ている点を見付け出しているのである。
そして、心の奥で、「こんな奴に負けるものか」というライバル心を燃やし始めた証拠なのだそうである。
続きを読む
不思議なペット事情
2012年08月03日
不思議なペット事情

ヤフー知恵袋に何ともユニークな質問があった。
「ペットの犬が死んだという同僚が三日間の喪中休暇をとり、それだけでも他の社員たちは呆れていたのに、死んだ犬の葬式に出席して欲しいという告別式案内状が社員全員に届いた。
犬の葬式に花代や香典を包むなど考えられないということで、皆、他に用事があるとの理由で、葬式への列席は断わった。
すると、この同僚は、「死んだ犬は家族同然なのに!」と、激怒。
しかし、犬の葬式に香典を包めば、金魚が死んだ、鈴虫が死んだというだけでお金を包まねばならなくなる。
それでも、ペットの葬式に出席しなければいけないのか?わたしには、絶対にそんなことは出来ない」
これに対する回答者の意見は、「確かに、愛犬が死んで悲しいのは判るが、その悲しみを他人にまで強要する必要はない。この社員は特殊な人です」と、いうものが多かった。
それにもう一つ。
「身内が亡くなって悲しんでいる人に対して、『判るわ。わたしも〇〇ちゃん(犬の名前)が死んだ時は、本当に辛かった』と、人間の死と犬の死を同レベルで悲しむ人の神経はどうなっているのか?実に、不謹慎だ」
と、いう質問もあった。
これについても、回答者たちの答えは、「犬の死と人の死を混同するなどおかしい。犬はあくまでペットであり、人間の価値と同じレベルで考えるのは間違っている」というものが大半で、日本人の意識は、まだまだ健在であることが判りほっとした。
しかしながら、上記の質問のような、「ペットは家族以上の存在」と、考える飼い主が増えているのも事実である。
飼い犬を「ちゃん」付けで呼ばなかったというだけで、烈火のごとく怒る飼い主もいる。
回答者の中には、「自分も飼い犬を溺愛してはいるが、他人さまに対してまでそうしろというようなつもりはない。犬を飼っていない人に話す時は、『うちの犬』というように呼び方を替えている」と、いう常識人もいた。
「本当に犬嫌いの人に、愛犬を『犬畜生』と、呼ばれて腹が立ったが、犬は犬なので仕方がない」と、いう回答者もいた。
ペットの葬儀で思い出したが、昔、ご近所に飼い猫の葬式をした人がいた。
まだ、ペットの葬儀が珍しい頃だったので、近所でもかなり話題になった。
そこへ参列した飼い主と友人のある主婦が、その時の会場の雰囲気をこんな風に話してくれた。
「ちゃんと、人間のお葬式のように庵主さんが来られて、『猫ちゃん、猫ちゃん』って、お経をあげるんでびっくりしたわよ」
でも、その風景を想像すると、何となく微笑ましくさえ思えた。
おそらく、その猫の飼い主が、猫が生きている頃はおよそ猫を溺愛しているようには見えなかったからであろう。
猫は、特段、家族といった具合ではなく、ただの飼い猫として一生を過ごしたのだが、その葬儀を執り行ったことで、猫に対する飼い主の愛情が垣間見えたからである。
参列した飼い主の友人たちも、香典などを持ち寄ることもなく、葬儀の後も和気藹々とした他愛もないおしゃべりをするお茶会で過ごしたという。
もしも、質問中の同僚社員が、告別式案内状を郵送するような仰々しいことなどせずに、ペットを失った自分の寂しさを癒すために近しい人たちに集って欲しいというだけの、そんな簡素なほのぼのとした葬式なら、社員たちも違和感を覚えることなく出席してくれたのではないだろうか。
続きを読む
信頼される人間になりたいなら
2012年08月02日
信頼される人間になりたいなら

「あの人は、信頼出来る人だ」
そんな評価を受ける人に共通する点は、とにかく言動がブレないということのようです。
一度自分の考えを決めたら、周囲の意見に惑わされることなく、たとえ自分の立場が不利になろうとも、それを貫く意志を持っているということが大事なのだとか。
ところが、人はとかく親しい人や利害関係のある人などの意見に引きずられて、簡単に最初の意見を翻してしまうものなのです。
「さっきは、そう思ったんだけれど、やっぱりそれだけじゃないような気がして・・・」
度々こんなことばかり言われたのでは、最初にあなたの意見に賛同してくれた人の立場がありません。
こんなことがたび重なると、
「ああ、この人はなんて優柔不断なんだ。今日はいいとしても、明日になれば何を考え出すか判らないぞ」
と、周りは自然とその人を避けるようになってしまいます。
最初に口から出したことを最後まで貫くのは、身近な人を敵に回す可能性もあり、確かに気力のいるものですが、そんなことでその人を敵視するような人ならば、初めから敵視する人とは縁がなかったものと悟るべきです。
この間まで放送していた「七人の敵がいる」ではありませんが、敵が七人いても、必ず三人は味方がいるものです。
七人があなたの考え方に反対でも、三人が賛成してくれるなら大収穫です。
もう二年ほど前になりますが、わたしはあるブロガーさんのコメント欄に、そのブロガーさんの意見に賛成したコメントを書き込んだことがありました。
ところが、それに対する返事は、「そこまでは考えていない」というような曖昧なものだったので、「一度ブログに書いた意見を曲げないで欲しい。その程度のフラフラ意見なら、ブログになどアップするべきではない」と、苦言を呈したことがありました。
ブログに限らず同調者は、あなたを信頼しようとしているのです。
それを裏切るような真似は、あなた自身の人間性までも疑わしいものにしてしまいます。
あなたは、自身が他人から信頼されるに足る人間だと思いますか?
続きを読む
自信満々な人々
2012年08月01日
自信満々な人々

最近の若い人たちの中には、とにかく自分に自信満々な人が多いように見受けられる。
こんな現象は、わたしたちが若い頃には考えられないことであった。
たとえば、文筆家にしても、若くして世間にのし上がろうとするなら、親子の縁を切り、羞恥心さえかなぐり捨てたような下品な文章でも書かなければ注目を集められなかったものである。
しかし、今は20代、30代でも一人前の文筆家や事業家として、堂々と会場を借りて講習会を開く人までいるそうだ。
単にブログやツイッター等で、ささやかに独自のアイデアや経験談を語ったり、ご近所同士や親しい仲間内で、和気藹々と漬物のつけ方や料理の作り方を教え合うのとは訳が違う。
わたしたちのような常に年配者に従って来た世代の者たちにしてみれば、冒険心があると言うのか、怖い物知らずと言うのか、大した度胸だと舌を巻かざるを得ない。
わたしなど、未だに自分の書いている物が本当に人さまの目に触れてよいものか否か、思考錯誤の連続である。
かつて、英会話学校の先生から華道教授として指南して欲しいと頼まれた時も、自分の実力がどれほどのものか判っているので、丁重にお断りした。
若くしてそういう講義や講演が出来る人というのは、どれだけの知識や経験を持っているのであろうか?
年配者は、たとえ知っていても知識や教養をひけらかすようなことはしない。
若い人たちが訳知り顔に話すことも、たいていの年配者は既に知っていることばかりなのだ。
だが、年配者は、相手を立てる術を子供の頃からしつけられているので、決してそのようなことは口にせず、
「若いのに大したものだね」
と、わざと驚嘆してみせたりもする。
だが、自分を過信している若手の文筆家や事業家には、そうした大人の思いやりはほとんど伝わらない。
だから、わたしは、そういう人たちにあえて問いたい。
「あなたは、人さまに何かを教えることが出来るほど、知識や教養のある経験豊かな人物なのですか?」
と-----。
他人に物事を教えるということは、それほど単純なことではないはずなのだが・・・。
近頃は、にわか教授が多すぎるような気がする。
続きを読む






